確定申告後の書類の保存期間は何年?個人事業主の場合を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新
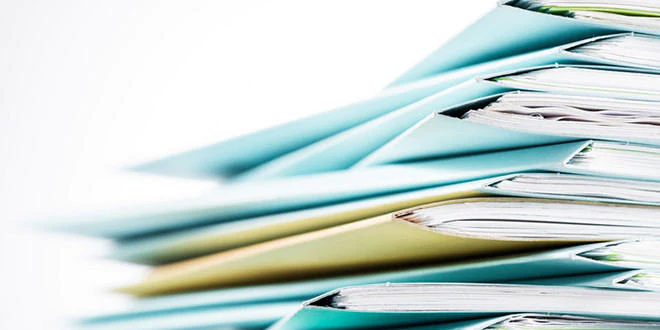
確定申告に必要な帳簿や領収書、請求書などは、申告が終わった後も一定期間保存することが義務付けられています。また、書類によって保存期間に違いがあるため、どの種類をどれくらい保存するかを知って管理することが大切です。
ここでは、個人事業主が保存しなければいけない確定申告書類の種類とそれぞれの保存期間、保存方法について解説します。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

確定申告書類の保存期間は青色申告と白色申告で異なる
個人事業主が確定申告の際に必要な帳簿や決算関係書類といった書類については、所得税法で一定期間の保存が義務付けられています。青色申告と白色申告では、書類の分類方法と保存期間に以下の表のような違いがあります。
青色申告で保存が必要な書類
| 書類の分類 | 書類名 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳など | 7年間 |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表など | 7年間 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収書、預金通帳など | 7年間(※) |
| その他の書類 | 請求書、契約書、納品書など | 5年間 |
- ※前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の人は5年間
-
※国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告
」
白色申告で保存が必要な書類
| 書類の分類 | 書類名 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年間 |
| 業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿 | 5年間 | |
| その他の書類 | 決済に関して作成した棚卸表など | 5年間 |
| 請求書、領収書など、業務に関して作成または受領したもの | 5年間 |
-
※国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告
」
なお、確定申告書の控えは、所得税法で保存が義務付けられているわけではありませんが、住宅ローンや自動車ローン、奨学金などの申請に必要となります。お子さんがいる場合は、学童保育などの申し込み手続きに必要になることもあります。控えだからといって放置することなく、しっかりと保存しておきましょう。
2025年以降、税務署は収受日付印の押なつが廃止されたため、提出は不要ですが自身で作成をして保存するとよいでしょう。できれば、e-Taxで電子申告して提出証明書類を取得することをおすすめします。
確定申告書の控えについて、以下の記事で詳しく解説していますので参照ください。
【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト
請求書など証憑書類の保存期間
見積書・納品書・請求書などは、保存しておかなければなりません。これらは「証憑(しょうひょう)書類」と呼ばれており、所得税法、消費税法、法人税法などで保存期間が定められています。
個人か法人かで保存するべき期間が異なりますが、ここでは、主に個人事業主の情報をご紹介します。法人の場合も参考まで記載しています。
証憑書類は原則5年間保存する
証憑書類の保存期間は、青色申告でも白色申告でも、原則として5年間です。保存期間の起点は、「その年の確定申告書の提出期限の翌日」となります。例えば、2025年分の確定申告の証憑となる請求書の保存期間は、確定申告期限にあたる翌2026年3月16日の翌日から5年間です。
なお、法人の場合は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存が必要です。また、欠損金の繰越控除と呼ばれる制度を利用する場合は、原則10年間保存が必要となります。
保存対象となる請求書は、受領した分も発行した分も該当します。
適格請求書(インボイス)の場合は7年間保存する
個人事業主が消費税の納税義務者(課税事業者)の場合、適格請求書(インボイス)の保存期間は7年間です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)下では、請求書等の適格請求書(インボイス)を受け取った課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、個人や法人にかかわらず、該当の適格請求書(インボイス)を7年間保存しなければなりません。
なお、保存期間の起点は、「受領日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日」になります。例えば、個人事業主の場合、2025年1月1日から12月31日の課税期間に受け取った適格請求書(インボイス)は、2026年1月1日から2か月後の2026年3月1日を起算日として、2033年2月28日まで保管が必要です。
また、適格請求書発行事業者は、発行した請求書等の適格請求書(インボイス)の控えについても上記同様7年間の保存が必要になります。
ただし、適格請求書発行事業者が簡易課税制度を選択している場合は、受領する請求書などが適格請求書であるかどうかを問いません。そのため、保存期間は前項までの個人事業主や法人などそれぞれの保存期間に準じます。
なお、電子取引で適格請求書(インボイス)を受領した場合は、インボイス制度に従った方法での保存と法定期限までの電子保存が必要となります。
適格請求書(インボイス)や電子帳簿保存に関わる書類保存については、以下の記事で詳しく紹介しているので参照ください。
【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト
個人事業主の領収書の保存期間
領収書もまた、保存すべき書類の1つです。領収書の保存期間は、青色申告と白色申告で違いがあります。また、領収書で適格請求書(インボイス)にあたる書類の場合、請求書と同様に7年間保存が必要です。
なお、法人の場合の保存期間は、「その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日」を起点として、原則7年間、欠損金の繰越控除を利用する場合は10年間です。ケースに応じて保存期間が異なるので間違えないように注意しましょう。
青色申告の場合、領収書は原則として7年間保存する
青色申告の場合、領収書の保存期間は、「その年の確定申告書の提出期限の翌日」を起点として、原則として7年間です。ただし、前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合の保存期間は、5年間となります。
白色申告の場合、領収書は5年間保存する
白色申告の場合、領収書の保存期間は、「その年の確定申告書の提出期限の翌日」を起点として5年間です。白色申告では、請求書や納品書、送り状なども同様に5年間となります。
【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト
個人事業主の帳簿の保存期間
帳簿とは、仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの書類を指します。個人事業主の帳簿の保存期間は、青色申告か白色申告かで以下のような違いがあります。
青色申告の場合、帳簿は7年間保存する
青色申告の場合、帳簿の保存期間は、「その年の確定申告書の提出期限の翌日」を起点として、7年間です。なお、損益計算書や貸借対照表、棚卸表などの決算関係書類も、同じく7年間保存しなければなりません。
白色申告の場合、帳簿の種類によって5~7年間保存する
白色申告の場合は、帳簿の種類によって保存すべき期間が異なります。「法定帳簿」と呼ばれる、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存期間は7年間です。一方、「任意帳簿」と呼ばれる、法定帳簿以外の帳簿の保存期間は5年間です。
なお、決算に関して作成した棚卸表などの書類についても、5年間の保存が必要となります。起点はいずれも、「その年の確定申告書の提出期限の翌日」です。
帳簿ごとに保存期間を管理するのは大変なので、すべての帳簿に関して最長の期間に合わせて7年間保存するルールにしておくと良いでしょう。
【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト
確定申告書類の保存方法
請求書や領収書、帳簿類、決算書類等の保存は、紙と電子データの2つの方法があります。受領した書類が紙の場合は保存方法を選べますが、書類が電子データの場合は電子データで保存しなくてはなりません。ここでは、紙と電子データの一般的な保存方法を見ていきましょう。
なお、紙でも電子データでも保存期間は変わりません。
紙で保存する
帳簿や決算書類など、紙で保存するとかさばる書類は、ファイルやバインダーにとじておくのが一般的です。また、領収書など細かな書類は、別紙に貼り付けてからバインダーにとじておくと、紛失防止に役立ちます。
書類は、日付が早い順に並べ、確定申告した年度別に整理しておけば、保存期間の経過がわかりやすくなります。保存する書類が多い場合は、年度別に加えて費目別のファイルやバインダーを用意すると便利です。継続的な取引先への請求書等に関しては、取引先別に管理すると見やすくなるでしょう。取引先ごとに請求書を分けて管理すると、売掛金や買掛金の回収漏れや支払漏れのチェックも楽になります。
電子データで保存する
電子データで受け取った請求書や領収書などは、原則として電子データのまま保存しなければなりません。紙に印刷して保存することは認められません。
なお、紙で受け取った請求書・領収書をスキャンして電子データで保存することは可能です。ただし、その場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法は、国税関係書類などの保存に関する要件を定めた法律で、個人事業主や法人などが対象です。電子帳簿保存法には、「電子取引のデータ保存」「スキャナ保存」「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)」の3つの区分があり、以下表のように分けられます。
電子帳簿保存法の3つの保存方法
| 保存方法 | |
|---|---|
| 電子取引のデータ保存 ※義務 | メールやクラウド上などで電子的にやりとりした国税関係書類を電子データのまま保存する |
| スキャナ保存 ※任意 | 紙で受け取ったレシート・請求書・領収書などの取引関係書類や自身で作成した書類の写しをスキャン、またはスマートフォンのカメラで撮影し、電子データとして保存する方法 |
| 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存) ※任意 | パソコンなどで作成した国税関係帳簿や書類を電子データのまま保存する方法 |
電子取引のデータ保存は、「真実性の確保」と「可視性の確保」が要件です。
また、スキャナ保存で、紙の証憑を電子データ化する際の要件として、解像度(200dpi 以上)や階調(原則としてカラー画像)の他、タイムスタンプの付与などが設けられています。要件は改定されることもありますので、国税庁の「電子帳簿等保存制度 特設サイト」も併せてご確認ください。
電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存、スキャナ保存については、以下の記事で詳しく解説していますので参照ください。
【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト
保存が必要な書類を毀損や紛失した場合
保存が必要な書類を毀損や紛失した場合、税務署から申告内容について確認があった際に問題になります。その場合は、正直に原因を説明しましょう。
また、保存義務違反として、消費税の仕入税額控除が認められないなどのペナルティを受ける可能性があります。青色申告の取り消しを危惧する方もいるでしょう。もちろん、災害や火事で破損・紛失が起きた場合は、罹災証明書などを提出することで不問にされることはあります。
なお、災害などのやむを得ない事情がなく、保存が必要な書類に不備があったとしても、直ちに青色申告が取り消しとなるわけではありません。青色申告の承認の取り消しについては、国税庁の事務運営指針である「個人の青色申告の承認の取消しについて」にもとづき、検討したうえで判断されます。
ただし、税務調査の際に帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、その提示を拒否した場合などでは、所得税法・法人税法に則り、青色申告の承認の取消事由に該当することになります。
【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト
確定申告後は書類の種類ごとに適切に保存しよう
確定申告に必要な帳簿や領収書、請求書などは、書類の種類や申告方法によって、保存期間が定められています。青色申告の場合、帳簿や決算関係書類、現金預金取引等関係書類は原則7年間保存が必要ですが、請求書などその他の書類の保存期間は原則5年間となります。必要な書類を毀損や紛失するとペナルティを受ける可能性もあるため、年分ごとに管理して保存しておきましょう。
photo:Getty Images
【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト
よくあるご質問
個人事業主が5年間保存する書類は?
個人事業主が5年間保存しなければならない書類は、青色申告と白色申告で種類が異なります。 また、青色申告の場合の帳簿や決算関係書類などは原則7年間保存が必要です。申告方法以外に書類の種類によっても以下のように保存期間が異なるので注意しましょう。
青色申告で5年間保存が必要な主な書類
- 決算関係や現金預金取引等関係書類以外の請求書、契約書、納品書など
- 前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合は、現金預金取引等関係書類を含む
白色申告で5年間保存が必要な主な書類
- 業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿
- 決済に関して作成した棚卸表など
- 業務に関して作成または受領した請求書、領収書など
確定申告書類の保存期間についてはこちら
白色申告者の書類の保存期間は?
白色申告者の書類の保存期間は、以下の表のとおりです。
白色申告者の書類の保存
| 帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年間 |
| 業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿 | 5年間 | |
| その他の書類 | 決済に関して作成した棚卸表など | 5年間 |
| 請求書、領収書など、業務に関して作成または受領したもの | 5年間 |
なお、個人事業主が消費税の納税義務者(課税事業者)になっており、仕入税額控除の適用を受ける場合は、適格請求書に該当する請求書、領収書などは7年間の保存が必要になります。
白色申告者の書類の保存期間についてはこちら
【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。










