個人事業主は福利厚生費を計上できる?その要件や迷いやすい例を解説
監修者: 岡本匡史(税理士)
更新
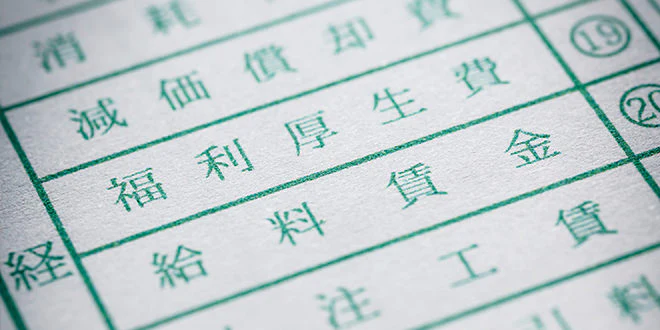
事業者が従業員向けに、給与以外の報酬として提供するサービスのようなものを福利厚生といい、そのための費用は福利厚生費に分類されます。多くの企業で福利厚生を提供しており、その企業の魅力となっているケースもあります。それでは、個人事業主は、従業員への福利厚生に関する費用を福利厚生費として計上できるのでしょうか。
ここでは、個人事業主が福利厚生費を計上するための要件や福利厚生費の例、福利厚生を導入するメリットのほか、福利厚生費と迷いやすい支出に関しても例をあげて解説します。従業員を雇用している個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。
福利厚生費とは従業員のための給与以外の支出のこと
福利厚生とは、従業員を雇用するうえで、働きやすさや慰安のために給与とは別に従業員やその家族のために提供するサービスのようなものです。そのためにかかる費用は、福利厚生費として計上できます。ただし、福利厚生と一口にいっても、法律で定められている項目と事業主が独自に用意する項目がある点に注意が必要です。
法律で定められている福利厚生は法定福利厚生といい、雇用保険や健康保険、厚生年金保険などが該当します。その保険料は事業主と従業員がそれぞれ一定の割合で負担することになっており、このうち事業主負担の部分を法定福利厚生費として計上できます。これは個人事業主も同様です。
一方、個人事業主を含む事業主が独自に用意する福利厚生を法定外福利厚生といい、これらに関する支出は法定外福利厚生費に分類されます。法律で定められているわけではないため、どのような福利厚生を提供するかは事業者ごとに決めることが可能です。
福利厚生費として計上できる項目には、さまざまな種類があります。例えば、従業員が仕事中に飲食するために用意した飲み物やお菓子の購入費用、残業時の夜食、出張に行った際の出張日当といった日々発生する費用も福利厚生費として計上できます。また、従業員が結婚したときなどの慶弔費や社員旅行費、従業員の歓送迎会の費用、事業主が用意した保養所などの維持や管理にかかる費用なども福利厚生費として計上が可能です。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
個人事業主本人とその家族の分は福利厚生費として計上できない
福利厚生費は、給与以外で従業員の生活の支えとして事業主が負担する費用です。例えば、青色申告者である個人事業主が青色事業専従者などの家族従業員と旅行した場合、それは家族旅行となるため、福利厚生費にはできません。
そのため、一人社長やひとり親方のように、個人事業主1人だけの場合も、福利厚生が成り立ちません。ただし、旅費日当については、一人社長の会社であっても、あらかじめ出張旅費に関する規定を作成していれば、認められます。
なお、個人事業主が家族以外に、パートやアルバイトも含む従業員を雇っている場合には、家族従業員の分にも福利厚生費を計上できるケースがあります。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
個人事業主が福利厚生費を計上するための要件
個人事業主が福利厚生費を計上するには、満たしておくべき要件があります。要件の具体的な内容を見ていきましょう。
従業員の全員に平等に適用される
福利厚生費を計上するには、その福利厚生が、特定の従業員や一部の従業員だけではなく、全従業員に対して平等に提供される内容でなくてはなりません。正社員やアルバイトといった雇用形態によって、提供の有無を区別してはならない点に注意が必要です。
ただし、役員と正社員とアルバイトなど、社内での役割や働き方の違いといった合理的な理由があれば、福利厚生費の金額や内容などに差が生じても差し支えありません。例えば、慶弔費に関して、フルタイム勤務の従業員は5万円、アルバイトは1万円といった設定にすることも可能です。
社会通念上妥当と思われる金額の範囲内であること
福利厚生費として計上できる金額は、社会通念上妥当と思われる範囲内であることが要件となります。具体的な金額の上限は定められていませんが、あまりにも高額だと福利厚生費として認められない可能性が高くなります。
福利厚生は全従業員に対して平等に適用しなくてはなりません。そのため、全従業員が福利厚生制度を利用しても事業主が問題なく費用を支払える範囲内であれば、福利厚生費として妥当な金額であると考えられます。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
福利厚生費の具体例
福利厚生費には、具体的にどのような項目が考えられるのでしょうか。一般的な福利厚生費の例を紹介します。
社員旅行にかかる費用
従業員の慰安を目的とした社員旅行にかかる費用は、福利厚生費の典型的な例です。ただし、社員旅行の費用を福利厚生費として計上するには、以下の要件を満たしている必要があります。
社員旅行の費用を福利厚生費として計上する要件
- 旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合は機内を除く現地での滞在が4泊5日以内)であること
- 従業員の50%以上が参加すること
- 従業員の全員が参加できる旅行であること
健康診断の費用
従業員に年1回の健康診断を受診させることは、事業主に課せられた義務です。ただし、健康診断にかかる費用に関しては法定福利厚生費ではなく福利厚生費として計上します。なお、個人事業主本人の健康診断費用は福利厚生費にはできません。
ただし、健康診断は、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制を適用する場合に必要な「健康の保持増進および疾病の予防への取り組み」の要件の1つです。個人事業主にとって、取り組みを実施したことの証明になるため、健康診断を受けた際の記録は保管しておき、確定申告でセルフメディケーション税制の適用に活用することも検討しておくとよいでしょう。
慶弔・災害などの見舞金
結婚・出産祝い金や死亡弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金などは、いずれも福利厚生費として計上できます。社会通念上妥当と思われる範囲の金額で、かつ全従業員が対象であれば福利厚生費として計上して差し支えありません。
例えば、従業員が亡くなった場合に遺族へ渡す弔慰金に関しては、以下の範囲内であれば福利厚生費として計上します。なお、見舞金は非課税となるため、受け取る側の遺族に所得税などは課税されません。
福利厚生費として計上できる弔慰金の金額
- 業務上の死亡であるとき:死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
- 業務上の死亡でないとき:死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
- ※国税庁「弔慰金を受け取ったときの取扱い
」
スポーツクラブの利用に関する費用
スポーツクラブの利用料に関しても、個人事業主が契約主体で、かつ従業員全員が利用できる場合には福利厚生費として計上できます。
なお、従業員がそれぞれ個別に契約して精算した費用を個人事業主が負担する場合には、福利厚生費ではなく現物給与として従業員に支給することになるため、所得税が課税される可能性があります。スポーツクラブの利用を福利厚生の一環として位置づけるには、法人契約が可能かどうかをあらかじめスポーツクラブに確認を取っておくことをおすすめします。
なお、個人事業主の利用分については、従業員分と一緒に契約したとしても福利厚生費として計上できません。誤って計上することのないよう、十分に注意してください。
食費
残業中の従業員に軽食や弁当、デリバリーなどによる食事を支給した場合や、従業員にふるまった外食などの食費は、全額を福利厚生費として計上できます。また、従業員向けにオフィスに設置するコーヒーメーカーやウォーターサーバーなどにかかる費用も同様です。
飲食店などで、まかないとして食材を購入した場合は、その購入代金が福利厚生費となります。金額や人数に制限はありません。まかないが給与扱いになるケースもあります。以下の記事の関連項目を参考にしてください。
ただし、いずれの場合も個人事業主本人の分については福利厚生費として計上できない点に注意が必要です。
なお、個人事業主や家族が商品を自宅で使用したりしたときには「自家消費」の勘定科目で計上します。
例えば、飲食店で事業主本人と家族がお店の食材を使用して調理した料理を食べた場合、食事の代金を自分で支払うわけではありませんが、自家消費として食事代を計上しなければいけません。
自家消費について詳しくは、「個人事業主の自家消費(家事消費)とは?使える例と仕訳方法を解説」をご覧ください。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
福利厚生を導入するメリット
福利厚生の導入は個人事業主にとって、どのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットとして以下の2点が考えられます。
従業員の働く意欲の向上
福利厚生の導入が、従業員の働く意欲の向上につながるという点はメリットの1つです。福利厚生を制度として設けることにより、従業員は自分たちが事業主から大切にされていると実感できます。会社に貢献しようという意識が高まり、離職率が低下するといった効果も期待できるでしょう。
また、福利厚生の導入は、人材採用にも良い影響をもたらすと考えられます。福利厚生が充実していることを求人情報などでアピールすることにより、優秀な人材が集まる可能性が高くなります。
節税効果
節税効果を得られる点も福利厚生を導入するメリットです。福利厚生費を必要経費として計上できるため、課税所得を減らすことにつながります。
また、福利厚生制度を利用する従業員にもメリットがあります。例えば、慶弔見舞金として従業員がお金を受け取った場合、そのお金は給与とは扱いが異なり、所得税が課税されません。このように、福利厚生の導入は個人事業主・従業員の双方にとって節税メリットがある取り組みといえます。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
福利厚生費と迷いやすい支出の例
従業員への福利厚生に関する支出が、福利厚生費として認められるには所定の条件を満たしている必要があります。そのため、支出の種類によっては福利厚生費に該当するのか、別の勘定科目を用いるべきなのか迷うケースが出てくる可能性もあります。福利厚生費と迷いやすい支出の例を見ていきましょう。
交際費や会議費
交際費や会議費を福利厚生費として計上してよいかどうかは、相手によって異なります。福利厚生費はあくまでも従業員のための費用であることから、その支出が、従業員向けかどうかが見分けるポイントです。
例えば、飲食店を利用した場合、従業員の歓送迎会にかかった費用であれば福利厚生費として計上できます。しかし、取引先との食事であれば、会議費や交際費として処理します。同様に祝儀や香典といった慶弔費に関しても、従業員に対する費用であれば福利厚生費、取引先への結婚祝いや香典であれば交際費として処理するのが基本的な考え方です。
なお、同一の支出のうち一部を交際費や会議費に充て、従業員分については福利厚生費として計上するといったことはできません。一例として、取引先と食事をした際に、自社の従業員が2人参加したため、2人分のみ福利厚生費とし、残りは交際費とするといったことは認められない点に注意してください。このようなケースでは、全員分の支出を交際費として計上する必要があります。
通勤費
通勤費に関しては、一般的に旅費交通費として処理します。公共交通機関を利用する際には、運賃や通勤時間、距離などの事情を鑑みて、最も経済的かつ合理的な経路を利用することが前提です。
これは、通勤定期券の購入費用を一括で支給する場合も、1日ごとの往復交通費を支給する場合も同様です。通勤手当として給与の一部として支給する方法と、経費精算によって支給する方法がありますが、支給方法によらず、旅費交通費として計上します。企業によっては、通勤費や出張費を福利厚生費として処理するケースもあります。
なお、通勤手当として支給する場合に非課税となる金額の上限は月15万円です。
自家用車での通勤に関しては、片道の通勤距離が2km以内であれば、支給される通勤手当は全額が課税対象となります。片道2kmを超える通勤に関しては距離に応じて上限額が定められており、上限は55km以上で3万1,600円です。公共交通機関と自家用車の両方で通勤している場合には、公共交通機関のみ利用している場合と同様、月15万円が非課税となる上限額です。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
福利厚生制度は、個人事業主も従業員もメリットがあるため最大限に活用しよう
福利厚生制度は事業主・従業員の双方にとってメリットのある制度です。所定の要件を満たしていれば、個人事業主も福利厚生費を計上できます。ただし、福利厚生費はあくまでも従業員に対する支出についてのみ適用されます。個人事業主本人には適用できない点に注意しましょう。
なお、家族従業員の福利厚生費の扱いについては、税法で明確に定義されていないため、ほかに従業員がいるなどの状況によっても見解が異なります。悩む場合は、顧問税理士や管轄の税務署にご相談することをおすすめします。
福利厚生制度を導入する際には、福利厚生費として計上すべき支出と、その他の勘定科目を使用する支出を明確に区別しておくことが大切です。特に交際費や会議費、食費のように、相手によって福利厚生費にも、ほかの費用にもなり得る支出については注意しておく必要があります。
必要経費をシンプルかつ正確に記帳したい方には、「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」の活用をおすすめします。初心者にもわかりやすい直感的な操作で、日々の記帳や確定申告をスムーズに行える点が弥生のクラウドソフトの特徴です。初年度は無料で利用できることに加え、無料期間中もすべての機能を利用できます。弥生のクラウドソフトを活用して、福利厚生費の適切な管理を実践してみてはいかがでしょうか。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。
この記事の監修者岡本匡史(税理士)
「岡本匡史税理士事務所」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。









