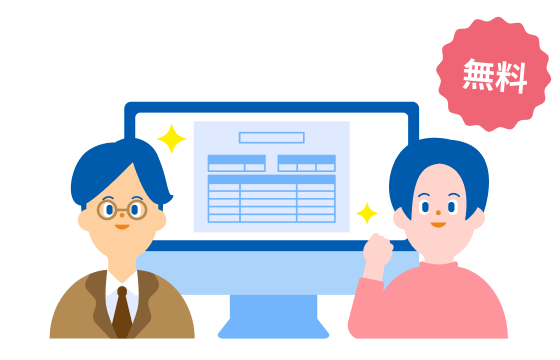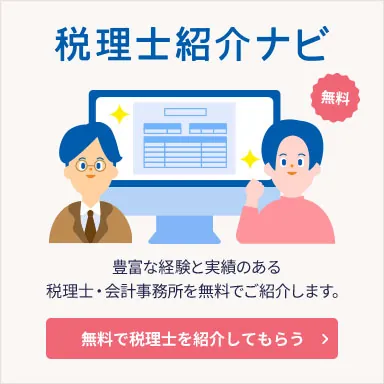会社設立で代行できる手続きは?費用や依頼先、メリット・デメリットを解説
監修者: 高崎 文秀
更新

会社を設立しようとすると、必要な手続きなど調べなければいけないことが数多く生じます。そのため、「自分1人で行うのは大変だ」「誰かに手続きを代行してもらいたい」と考える方もいるのではないでしょうか。そのような時に頼れるのが、司法書士や税理士、行政書士、社会保険労務士といった専門家です。
しかし、これらの専門家はそれぞれ専門分野が違うため、代行できる業務も同じではありません。ここでは、会社の設立代行の依頼先や、各専門家が代行できる手続きの種類、代行を依頼するメリットとデメリット、費用相場などについて解説します。本記事を読めば、会社設立代行を依頼する際に知っておきたいポイントを把握できます。
会社を設立する際に必要な手続き
会社を設立するにはいくつかの手続きが必要です。まずは、会社設立時の流れと必要な手続きを確認していきましょう。
会社設立の流れ
-
STEP1 会社の概要を決める
-
STEP2 法人用の実印を作成する
-
STEP3 定款を作成し、認証を受ける
-
STEP4 出資金(資本金)を払い込む
-
STEP5 登記申請書類を作成し、法務局で申請する
-
STEP6 設立登記後の手続きを行う
STEP1. 会社の概要を決める
まずは会社を設立するにあたっての、会社の基本事項を決めます。社名(商号)、事業目的、所在地、資本金、会計年度(事業年度)、株主(発起人)の構成などが具体例です。これらの事項は、後で作成する定款にも記載が必要なので慎重に決めましょう。
STEP2. 法人用の実印を作成する
社名が決まったら法人用の実印を作り、印鑑届書を提出します。商業登記法が改正され、設立登記をオンラインで申請する場合、法人用の実印の登録は任意となりました。しかし、金融機関への融資申請や取引先との契約など、会社設立後に法人用の実印を使う場面は多いため、法人登記の際に印鑑登録を済ませておくことをおすすめします。
法人用の実印の他、法人口座の開設に用いる銀行印と、請求書や納品書などに押印する角印(社判)も一緒に作成するのが一般的です。
STEP3. 定款を作成し、認証を受ける
定款(ていかん)とは、会社の運営に関するルールをまとめた会社の憲法のようなものです。定款にはSTEP1で決めた会社の基本事項などをまとめて記します。
設立するのが株式会社の場合は、作成した定款を公証役場に提出して認証手続きを行います。その際は公証役場に直接行くのではなく、予約が必要です。また、定款認証の嘱託をオンラインで行うことも可能です。
参照:法務省「オンラインによる定款認証および設立登記の同時申請の取り扱いを開始しました」
なお、合同会社、合資会社、合名会社の場合は、定款の認証は必要ありません。
STEP4. 出資金(資本金)を払い込む
資本金の振込先は、会社設立時に定款に署名する発起人の個人口座です。会社法では資本金の下限が定められていないため1円から申請できるものの、資本金があまりにも少ないと事務所の契約料や備品の購入費など、会社設立後すぐに代表者個人からの借り入れに頼ることになってしまいます。また、資本金が少なすぎると金融機関から融資を受けようと思っても信用を得るのが難しくなるかもしれません。
最低限の資本金として、初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は用意しておくと良いでしょう。
STEP5. 登記申請書類を作成し、法務局で申請する
出資金を払い込んだら、登記申請書などの登記に必要な種類を作成し、法務局に法人登記を申請します。書類に不備がなければ1~2週間程度で登記されるので、これで会社の設立は完了です。法人登記の申請を行った日が会社の設立日になります。
STEP6. 設立登記後の手続きを行う
設立登記が完了したら、会社の所在地を管轄する税務署や都道府県税事務所、市町村役場へ所定の届出書を提出し、税金関連の手続きを行いましょう。また、健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入するため、年金事務所に届け出ます。従業員を雇う場合は労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをすることも必要です。
法律上の許認可が必要な事業では、この他に所定の許認可手続きを行います。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
専門家が代行できる会社設立の手続き
会社設立の手続きには手間や時間がかかりますが、専門家の力を借りればそれらの負担を軽くできます。会社設立手続きのうち、専門家に代行を依頼できる手続きは下記のとおりです。
- 法人用実印の作成
- 定款の作成と認証
- 登記申請書類の作成と申請
- 税務・社会保険・労働保険関係の設立登記後の手続き
先に解説した6つのステップのうち、会社を設立する本人がやらないといけないのは会社概要の決定と資本金の振り込みの2つのみです。つまり、専門家に依頼すれば、会社設立に必要なほとんどの作業を代行してもらえます。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立手続きの代行を依頼できる専門家
会社設立の際に手続きの代行を依頼できる専門家としては「司法書士」「行政書士」「税理士」「社会保険労務士」が挙げられます。それぞれの士業には専門領域があるため、会社設立の手続きは士業どうしが提携して対応しています。
どの専門家にどのような手続きを依頼できるのか、士業ごとの役割の違いは以下のとおりです。

司法書士は設立登記の専門家
司法書士には、会社設立にかかわる書類の作成、定款認証代行、法務局への設立登記申請代行など、会社設立登記の手続きを依頼できます。特に法人の設立登記の手続きは、司法書士しか代行できません。
行政書士は行政提出書類の専門家
行政書士は会社設立にかかわる書類の作成や定款認証代行が可能です。ただし、設立登記申請の代行などはできません。許認可取得に必要な書類作成を専門領域としているため、飲食や建設、運送業といった許認可が必要な業種の場合に代行依頼するのがおすすめです。
税理士は税務の専門家
税理士は税金や決算などにかかわる業務を専門としているため、税務関係の手続き・届出の代行や融資関係書類の作成ができます。また、設立後に節税や資金面の相談に乗って欲しい時も、税務面からさまざまなアドバイスを受けられます。
また、会社概要を決める際にも、税理士に相談すると会社設立の段階から、税を含むお金についてのアドバイスを期待できます。特に株式会社の場合は、資本金や株主構成、役員報酬の他、決算月の決め方などが会社設立後の税金にも大きくかかわってきます。その他、経理のしくみづくりや売上予測、資金繰りなど設立後でも力を借りられるのはメリットです。
社会保険労務士は社会保険手続きの専門家
社会保険労務士(社労士)は、健康保険や厚生年金保険といった社会保険関係の手続きの他、労働基準監督署やハローワークでの労働保険関連の手続きを代行できます。ただし、社労士の助力が本格的に必要になってくるのは雇用する従業員が増えてきてからです。最初のうちは自力か単発依頼で済ませ、顧問契約の検討は従業員数が増えてきてからでもよいでしょう。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立代行の費用相場
会社設立代行の依頼先ごとの大まかな代行費用の相場は以下のとおりです。かっこ内は代行できる主な業務を指します。
-
- 司法書士:5~15万円(会社の実印作成・定款作成認証・登記申請書類の作成・申請)
- 行政書士:10万円前後(会社の実印作成・定款の作成・許認可の申請)
- 税理士:月3~5万円(設立後の届出・登記前後の経理・毎月の税務処理)
- 社労士:3~5万円(健康保険・厚生年金保険新規適用届の代行)
なお、上記の代行手数料の他に、会社の設立そのものにかかる費用も必要です。具体的には主に以下のような出費が想定されます。
-
- 定款認証手数料:3~5万円(合同会社の場合は不要)
- 謄本手数料:250円×枚数(およそ8枚で約2,000円)
- 定款印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
- 登録免許税:
株式会社の場合=資本金額の0.7%または15万円の高い方
合同会社の場合=資本金額の0.7%または6万円の高い方
参照:日本公証人連合会「Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」
その他、印鑑証明書代や登記事項証明書の発行費用、会社印の作成代など細々とした支払いも必要です。
登録手数料の下限額が安価であることや、定款に関係する費用が不要であることから、株式会社より合同会社の方が費用負担は小さくなります。
以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立代行を選ぶ際のポイント
自社に合った代行サービスを選ぶためには、以下の3つのポイントを意識することが大切です。
- 電子定款対応可否
- 依頼したい業務の対応可否
- 利用条件
電子定款対応可否
コスト削減を願うなら、電子定款に対応している代行業者を選ぶのがおすすめです。先述のとおり、紙の定款の場合、4万円の印紙代が必要になります。その点、電子定款ならば無料で済むので、その分だけ会社設立に必要な費用を抑えられます。自分で手続きする場合には電子申請に必要な機器やソフトウェアを用意する必要がありますが、業者に依頼するならそれらの費用や労力も不要です。
依頼したい業務の対応可否
依頼先がどこまでの業務に対応できるかという点も、確認するようにしましょう。例えば、行政書士は申請書類の作成はできても登記申請の代行はできません。登記申請の代行ができるのは司法書士のみです。後になってから他の代行サービスを探したり、自力で手続きしたりする事態にならないように、あらかじめ代行してもらいたい業務を明確化し、それに対応可能な依頼先を選びましょう。
利用条件
代行サービスを選ぶ際は、利用条件を十分に確認しましょう。サービスによっては、代行手数料を安価に抑える代わり、継続的な顧問契約の締結を利用条件にしている場合があります。この点を認識しないまま契約すると、いくら初期費用は抑えられても、継続的な出費に苦しむことになりかねません。こうしたトラブルを防ぐためにも、利用条件は確認する必要があります。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立の手続きを代行してもらうメリット
会社設立手続きは自分でも行えますが、専門家の力を借りることで以下のようなメリットを得られます。
- 時間を節約できる
- 手続きの間違いを防げる
- 不安な部分や節税対策などを相談できる
- 設立後の顧問契約を前提に無料・低価格で手続きを依頼できる場合もある
時間を節約できる
手間を要する複雑な手続きを専門家に代行してもらうことで、会社設立にかかる時間を節約できます。開業に向けて多くの重要な仕事が待ち受けている中、煩雑な手続きに貴重な労力や時間を掛けるのは避けたいという方も多いはずです。その点、信頼できる代行業者に依頼すれば、いち早く事業に集中できます。
手続きの間違いを防げる
会社を設立するにはいくつもの煩雑な手続きが必要です。特に、法務局に提出する設立登記申請書類は非常に種類が多いため、間違えることなく自分で作成するのは容易ではありません。慣れない作業に手間取った挙句、書類不備が発覚し、手続きがやり直しになってしまうこともあります。しかし、会社設立の経験が豊富な専門家に代行を依頼すれば、このような間違いを防いでストレスなく手続きを進められます。
不安な部分や節税対策などを相談できる
会社設立に関する不明点や疑問点の相談相手ができることもメリットです。初めて起業する場合、経営戦略の策定から許認可などに関する実務的な処理まで行うべきことが多々あるため、不安に感じるはずです。そのようなとき、相談できる専門家がいれば非常に心強いはずです。中でも、税理士からは会社設立後に税制面で不利にならないためのアドバイスを受けられます。
設立後の顧問契約を前提に無料・低価格で手続きを依頼できる場合もある
税理士は、設立後の顧問契約を前提に司法書士や行政書士と連携して会社設立の手続きを無料または低価格で対応していることがあります。法人の場合、設立後には顧問税理士をつけるケースがほとんどなので、顧問契約を前提に会社設立の手続きを無料・低価格で依頼できるのはメリットです。
なお、会社設立に必要な手続きを代行に依頼すべきか検討している方には、「弥生の設立お任せサービス」がおすすめです。「弥生の設立お任せサービス
」では、弥生の提携先となっている起業に強みを持つ専門家に、会社設立の手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。
確実かつスピーディーな会社設立ができるだけでなく、事業の展望などを踏まえ、融資や助成金、節税などのアドバイスも受けられます。会社設立後、専門家とご相談のうえ会計事務所との税務顧問契約を結ぶと、割引が受けられ、サービス利用料金は実質0円になります。ただし、定款の認証手数料や登録免許税など行政機関への支払いは別途必要です。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立の手続きを代行してもらうデメリット
会社設立を代行してもらうことには以下のようなデメリットもあります。代行サービスを利用するか否かは、メリットとデメリットの双方を天秤にかけて判断するのが大切です。
- 専門家を探す手間がかかる
- 費用がかかる
専門家を探す手間がかかる
第一のデメリットは、自社に合った専門家を探すのに手間がかかりやすいことです。士業や会社設立代行サービスは数多く存在するので知人の紹介などのつながりがないと、信頼できる専門家を探し当てるのは一苦労です。特に顧問契約を結ぶ場合は長期的に関係を持つことになるので、相性のいい専門家を根気強く探す必要があります。
費用がかかる
会社設立手続きを専門家に依頼すると、費用がかかってしまうのもデメリットです。自分で設立手続きを行う場合の手間や時間と手続きを代行した場合のコストを比べて、どちらが良いか検討しましょう。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立代行の種類
会社をスムーズに設立をする方法としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 専門家(士業)に依頼する
- 会社設立代行サービスに依頼する
- 会社設立サービスを利用して自分で手続きする
それぞれの概要は以下のとおりです。
専門家(士業)
第一の方法は、司法書士、行政書士、税理士、社労士などの士業に手続きする代行してもらうことです。会社の設立(登記申請)に焦点を当てるなら、登記申請まで代行できる司法書士に依頼することをおすすめします。一方会社設立後に税理士と顧問契約を検討している場合には、会社設立サービスを提供している税理士事務所に依頼するのも一案です。
会社設立代行
会社設立代行を専門としているサービスを利用するのも効果的です。税理士と司法書士など複数の士業が在籍するサービスを利用すれば、個別に士業へ依頼するよりもスムーズに包括的なサポートを受けられる可能性があります。
「弥生の設立お任せサービス」は、会社の設立に関する書類作成や登記申請を専門家がワンストップで代行するサービスです。融資や助成金、節税などに関する相談もできます。税理士と顧問契約を結ぶことで、実質0円で代行サービスを利用できるのも魅力です。詳しくはこちらをご覧ください。
会社設立サービス
代行サービスを利用せず、Web上のサポートツールを利用して自力で手続きするのも検討の価値があります。こうしたツールを使えば、完全に自力でこなすよりも遥かに効率的に手続きを進めることが可能です。
「弥生のかんたん会社設立」は、必要な情報をフォームに入力していくだけで電子定款を作成できるサービスです。登記申請・登記後申請もWebで完結できるので、法務局に出向く手間と時間を省けます。サービスは原則無料で利用できるので、手続きに必要な実費以外の費用負担を大きく減らすことが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立の代行はどの専門家にお願いすればいい?
士業にはそれぞれ専門領域があり、対応できる業務が異なります。1つの士業だけで会社設立前後の手続きをすべて完結できません。そのため、どの士業に依頼しても実際は他の士業と提携しながら手続きを進めることがほとんどです。したがって、検討すべきは「だれに最初に相談したらいいのか」になります。
登記申請を最優先に考えるなら、想定されるのは登記のプロである司法書士ですが、設立後の税務処理なども見据えるなら、税理士を最初の相談相手に選ぶこともおすすめできます。税理士は税金面で不利にならない会社概要の相談から設立後の節税対策まで、さまざまなアドバイスをしてくれます。創業融資や助成金・補助金のサポートを受けたい場合も対応可能です。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立の手続き代行先を手軽に見つける方法
会社設立手続きについて税理士など専門家に相談したいと思っても、自力で税理士を探そうとすると手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ 」がおすすめです。
「税理士紹介ナビ」は、起業全般や税、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模の全国13,000のパートナー会計事務所から、ぴったりの税理士や会計事務所を最短で翌日にご案内できます。完全無料で、会社所在地や業種に合わせた最適な税理士をご紹介します(2025年8月時点)。
「税理士紹介ナビ」には、事業者のお困りごとに沿って弥生スタッフが最適な税理士や会計事務所を紹介する「税理士紹介サービス」と、ご自身で自由に税理士を探すことのできる「税理士検索
」の2つのサービスがありますので、ご自身の状況に合ったサービスをご活用ください。
「税理士紹介ナビ」はこんな方におすすめ
「税理士紹介ナビ」は、特に次のような方におすすめです。
初めて会社を設立する方
会社を設立する際には、必要な手続きや資金調達など多くの不安や疑問が生じることがあります。「税理士紹介ナビ」なら、これから事業を始める方の悩みや困りごとに合わせて、最適な税理士探しをサポートします。個人事業主から法人成りを予定している方にもぴったりです。
起業後の会計処理や決算が不安な方
会社を運営するうえでは、法人税や地方税、消費税など、さまざまな税や固定資産の知識が必要になります。そのような場合も、会計処理や決算に関することをまとめてプロに相談できます。
できるだけ節税したい方
「節税したいが方法がわからない」という方にも「税理士紹介ナビ」はおすすめです。税理士からのアドバイスで節税方法を理解できれば、戦略的な経営にも役立つでしょう。
記帳業務を丸ごとプロに任せたい方
日々の取引を記帳するには手間や労力がかかります。売上が増えるとともに経理作業量も増え、負担が大きくなってしまうでしょう。記帳業務を税理士に丸投げできれば、その分しっかり本業に集中できるようになります。
豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介!詳細はこちら
会社設立の手続きは税理士に相談しよう
会社設立代行を依頼できる士業としては、司法書士、行政書士、税理士、社労士が挙げられます。中でも税務の専門家である税理士は、会社設立後にも節税などで力を借りる機会が多い専門家です。
特に会社設立後に税理士と顧問契約を結ぶことを検討している場合は、それと引き換えに無料・低価格で会社設立の手続きをしてくれる税理士を探すと、非常にお得になります。自分に合った税理士を探したい場合は、ぜひ弥生の「税理士紹介ナビ 」をご活用ください。
この記事の監修者高崎 文秀
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。