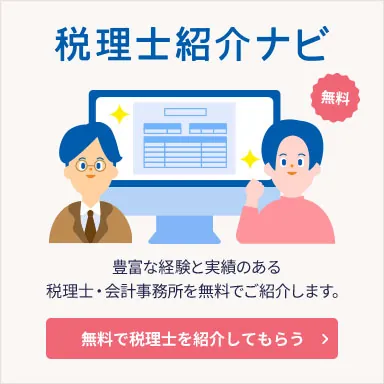相続に強い税理士の探し方と選び方!報酬相場や相談すべきケースも解説
監修者: 宮川 真一
更新

相続は人生で何回も経験するものではないため、手続きの煩雑さや難しさに圧倒されてしまうかもしれません。お金が絡むため、他の相続人とどのように分割すべきか、手続きが順調に進むか不安に感じている方もいることでしょう。
相続に詳しい税理士に頼むことで、スムーズに手続きを終えられるだけでなく、節税対策になることもあります。しかし、税理士といってもそれぞれに得意なジャンルが違うため、依頼先を適切に選ぶ必要があります。今回紹介する探し方や選び方を知り、相続に強い税理士に依頼しましょう。
相続に強い税理士の探し方
税理士を探すにはいくつかの方法がありますが、ここでは主要な探し方を3つ紹介します。
誰かに紹介してもらう
もし友人や知人などの中に、相続関連で税理士を利用したことがある人や、知り合いに税理士がいる人がいる場合は、紹介してもらうことも1つの方法です。税理士と一口に言っても専門分野や実力、性格などはさまざまです。紹介者が既に利用していれば、実際頼んでみてどうだったか、報酬の目安はどれくらいかなど、気になる点を直接聞くことも可能です。結果としてミスマッチも起こりにくくなります。
インターネットで探す
現在、税理士を探す方法の主流はインターネットを使う方法です。検索エンジンで「相続 税理士 地域名」と検索し、検索結果に出てきた会計事務所の公式サイトを開いて見ていきます。手数料がかからず直接依頼できるのがメリットですが、公式サイトの内容が事務所ごとに異なるため、複数の事務所を比較検討しにくいことがデメリットです。
税理士紹介サイトや税理士マッチングサービスを利用するのもよい方法です。条件にあった税理士を探しやすく、料金やその他の条件の比較検討も容易に行えます。弥生の「税理士紹介ナビ」なら、ご希望の条件に沿って税理士・会計事務所を無料でご紹介します。税理士探しの際は、ぜひご活用ください。
SNS、ブログ、YouTubeなど、税理士が個人で情報発信している場合もあり、こうした情報を見て依頼することも可能です。得意分野がわかりやすいのはメリットですが、人気があり過ぎて依頼できないこともあります。
無料面談で複数の税理士と会って対応を比較する
税理士は無料面談を行っている場合もあるため、実際に会ってサービス内容や相性を確認するのも1つの方法です。
無料面談の際には、相談内容だけに注意を集中するのではなく、専門分野、料金体系、契約内容、相性といったポイントをよくチェックするようにしましょう。事前に聞きたいことをまとめて、短い時間を有効活用することがおすすめです。
ミスマッチを防ぎやすいというメリットがある一方で、手間がかかるというデメリットもあります。日程調整なども必要になるため、私生活や仕事が忙しいとなかなか時間を取るのが難しい方もいるでしょう。ある程度候補を絞って、最終的に選択する際に利用するのも一案です。
相続手続きを税理士に依頼する際の報酬相場
税理士を探す際に重要なのが税理士報酬(依頼料)です。報酬には「基本報酬」「加算報酬」の2つの種別があります。
「基本報酬」は、相続税申告を税理士に依頼する際にかかる費用です。多くの会計事務所では、相続財産の総額に応じた金額を設定しています。費用相場は相続財産総額の0.5〜1.5%ほどです。たとえば、相続する額が5,000万円だった場合は、25万円〜75万円という計算となります。
「加算報酬」は、条件によって加算される費用です。事務所によっても異なりますが、以下のような条件では、費用が加算されるのが一般的です。
- ・相続人の数が複数人
人数が増えるごとに、基本報酬の10~15%程度が加算されます。たとえば、基本報酬が50万円の場合、相続人が2人なら5万~7.5万円程度、3人なら10万~15万円程度が加算されます。
- ・土地の評価
相続財産の中に自宅以外の土地があるときや、土地の形が複雑で評価が難しいときなどに加算される場合が多いです。
- ・非上場株式の評価
非上場株式の評価には当該企業についての調査が必要になるため、加算報酬を請求されるのが一般的です。
- ・申告期限が間近
相続税の申告期限が迫っている場合は急いで作業する必要があるため、加算報酬が必要です。
安価な料金を提示している事務所と契約すると、説明なしに成功報酬などを別途請求されることがあります。そのようなトラブルを避けるためにも、適正な相場を知っておくことが役立ちます。
以下の記事でも税理士報酬相場について詳しく解説しています。
関連記事
相続に強い税理士の選び方のポイント
税理士が活躍する分野は、相続税の他にも、法人税や所得税、会社の経理、経営や創業など多岐にわたります。そのため相続に関して相談したい場合は、数ある税理士の中から相続に強い税理士を探すことが必要です。相続に強い税理士を選ぶためにチェックしたい5つのポイントを解説します。
相続税に関する知識・経験がある
多くの税理士は、企業の決算や法人税の申告を主な業務としており、相続税を専門に取り扱っている会計事務所はあまり多くありません。税理士でも相続税申告の手続きには詳しくないこともあるため、相続税についてある程度知識経験のある税理士を探す必要があります。
また、相続と一口に言っても、経営者と一般的な会社員とでは相続財産の内容は大きく異なります。都市部と地方など、地域性によっても相続財産の内容や相続人の状況が異なることもあるでしょう。相続財産の中には、土地などの不動産、自社株など、さまざまなものがあります。海外の資産や賃貸アパートなど、複雑なケースの場合はさらに深い専門性が必要です。せっかく相続専門の税理士を探しても、自分の状況とは合わないこともあるため、慎重に探す必要があります。
相続税の申告数が多い
税理士のホームページに「相談件数○件」と宣伝していることもありますが、相談件数が多くても、実際に依頼にまでたどり着いたかどうかは別問題です。そのため、「申告件数」の実績に注目するようにしましょう。
税金の申告の中でも相続税は税務調査の対象になりやすい傾向にあります。少しでもリスクや不安を減らすため、相続に実績のある税理士に任せることをおすすめします。依頼する税理士によって、相続財産の評価額が変わることもあります。
報酬が明瞭かつ適正である
税理士の報酬は、法律で決められていないため、税理士・会計事務所によって費用が大きく異なります。前述したように後々に費用を請求する税理士もいるため、料金体系が明瞭かつ適正である事務所を選び、契約が確定する前に書面で確認することが大切です。通常の報酬と別に、成功報酬などの名目で請求される場合もあります。そのため、追加の費用が発生するかどうかも契約前に確認しておくとよいでしょう。
また、報酬の安さにひかれて依頼した結果、財産の申告漏れなど、事務所側が仕事にしっかりと時間をかけなかったために発生した申告ミスによって、加算税などが発生するケースもあります。事務所側のミスにより多額のペナルティが発生した場合は保証を行う事務所もあるので、気になる場合はその点を確認しておきましょう。報酬の相場を知った上で、適正な料金体系を持っている依頼先を選ぶことが大切です。
他の士業と連携している
相続の際には、相続税の申告だけでは済まないことがあります。たとえば、土地など不動産の相続登記に司法書士のサポートを要したり、遺産分割で紛争が生じて弁護士の介入が必要になったりする場合です。このようなときに税理士が他の士業と連携していると、自分で探さずに一括して任せることが可能です。税理業務だけで済まないことが予想される場合は、他の士業と連携している税理士を探しておくと、探す労力を軽減できます。
依頼人に寄り添った対応をしてくれる
税務処理は税法で決まっていることなので、どうすべきか正解は決まっているように思われがちです。しかし相続には複数の人がかかわることが多く、さまざまな事情が絡むため、状況に合わせた対応が求められます。依頼者側の希望や意図をくんで、寄り添った対応をしてくれる税理士を選びましょう。
相続の性質上、何度も依頼を経験している人は少ないのが一般的です。プロが言っていることであれば正しいのだろうと思い、疑問点があっても質問せずに、後に問題を抱えるケースもあります。このような問題を起こさないためにも、よくわからない部分はしっかりと質問して、それに対してわかりやすく適切に答えてくれるかを確かめましょう。
相続手続きを税理士に相談すべき主なケース
相続手続きは個人でも行うことは可能ですが、税理士に依頼したほうがよいケースもあります。税理士に相談してみるのがおすすめなのは、以下の2つのケースです。
相続財産が基礎控除を超えている場合
相続税の基礎控除は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。相続財産がこの金額を超えるときは相続税がかかるので、申告が必要です。相続税の計算や申告書の作成は時間や労力がかかる上、初めての申告で相続の知識がない場合は難しく感じるため、税理士に依頼したほうがよいでしょう。自分で計算した結果、相続財産がぎりぎり基礎控除内に収まっていたとしても、思わぬミスで実際は基礎控除をオーバーしている可能性があるため、念のためプロに計算してもらうほうが無難です。
また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を適用すると節税になりますが、適用する場合は、基礎控除を超えていなくても申告の義務があります。適用にはさまざまな条件を満たす必要があるため、自分の場合は適用できるのかも含めて、税理士に相談してみるとよいでしょう。
評価の難しい財産が多い場合
相続税は財産の評価額によって決まります。相続税法や相続税財産評価基本通達に従って計算する必要があり、プロでないと正確に計算するのは難しいです。以下のようなものは、専門家でない人は評価が特に難しいと言えます。
-
- 特殊な土地:広大地や不整形地など
- 非上場株式:同族経営の会社の株式など
- 賃貸物件:経営していたアパート・マンションなど
- 美術品・貴金属:市場価格が変動するもの
土地1つにしても、相続税を計算する際は、路線価方式と倍率方式の2つの評価方法があります。また、非上場株式は市場価格がないため、専門家でない人による評価は難しいです。
相続手続きで税理士に相談できること
相続の発生前と発生後、相続税申告後に、税理士が対応できるものには、以下のような項目があります。
- 1. 相続の発生前
- 相続税試算
- 相続税対策
- 遺言の作成
- 2. 相続の発生後
- 相続税申告書の作成
- 相続財産の評価
- セカンドオピニオン
- 3. 相続税の申告後
- 税務調査の立ち合い
- 相続税の還付請求
相続手続きにおける税理士の基本的な業務は、相続発生後の「相続税申告書の作成」「相続財産の評価」です。他の税理士が計算した評価額が適正であるかについて、セカンドオピニオンを依頼することも可能です。また、相続発生前(生前)から、相続がスムーズに進められるように、相続税の節税対策や遺言の作成に関してアドバイスをもらうこともできます。相続税申告後にもしも税務調査があった場合でも、当日までの資料の準備や、当日の立ち合いを税理士に依頼することができます。
相続手続きを税理士に依頼するメリット
税理士に相続を依頼することで以下のような4つのメリットがあります。
手間や時間を削減してスムーズに申告できる
税理士に相談すると、相続にかかわる手間や時間を削減して、スムーズに申告を済ませられます。もし、相続の申告を個人で行う場合、以下のような事柄をすべて行う必要があります。
-
- 財務の調査(プラスの財産に加え、債務などマイナスの財産もすべて)
- 財産の評価
- 相続人の確認
- 相続税の計算
- 遺産分割にかかわる協議
- 相続税申告書の作成
- 相続税の納税
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内と決められています。日々の生活をしながら、この期間内に上記の事柄すべてを行うのは多くの人にとって大変なことです。期限を過ぎた場合でも相続手続きは可能ですが、特例は適用できなくなるうえ、延滞税などが発生することもあるので注意が必要です。
節税対策になる
税理士を活用する大きなメリットの1つに、節税対策が挙げられます。個人で相続手続きを行うと、申告するだけで精一杯かもしれませんが、税理士であれば適切に節税しながら申告することが可能です。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を適用できる場合は、積極的な利用がおすすめです。たとえば、小規模宅地等の特例では、評価額を最大80%軽減することが可能です。宅地等の評価額を下げることで、その宅地等を相続するための相続税を少なくすることができます。また、土地の評価についても、狭い道や私道に面している、間口が狭い、区画整理の計画がある、といった条件によっては評価額を下げられる場合もあります。
税理士に依頼することで、どのような節税対策をとれるのか確認や判断をしてもらい、適用できるように申告するところまでサポートを受けることが可能です。
二次相続の対策ができる
税理士に相続手続きを依頼すると、二次相続のことも考えた相続税対策をしてもらえるのもメリットです。二次相続とは、最初に財産を相続した相続人が亡くなった際に発生する相続のことを指します。
二次相続が問題になりやすいのは、夫婦と子供がいる家庭で、夫が先に亡くなって妻が相続し、数年後に妻が亡くなって子供が相続するケースです。妻が夫から相続する際は、配偶者の税額軽減が適用できるため、相続税がかからないことが少なくありません。しかし、妻が亡くなって子供が相続する際には、軽減措置が利用できないうえ、妻がもともと持っている財産も加わるため、子供に相続税が重くのしかかることがあります。相続人が減ることで基礎控除も減り、高い相続税率が適用されて、相続税が高額になるといった問題も発生します。
二次相続を考慮に入れずに相続すると、二次相続の際に多額の相続税がかかり、トータルで見ると財産が大きく減少して、後悔することになるかもしれません。相続に詳しい税理士であれば、二次相続も見越した対策が可能です。
税務調査の相談ができる
税務調査は法人税や所得税などに対しても行われますが、相続税は特に税務調査が行われやすいと言われています。税理士に相続税申告書の作成を依頼した場合、税務調査への対応やサポートもしてもらえるのが一般的です。税務調査の際にも税理士に立ち会ってもらえて、不安や負担を和らげられるでしょう。
税務調査には、任意調査と強制調査があります。脱税など悪質なケースや任意調査を拒否した場合を除いて、通常は任意調査が行われます。任意調査は、事前に連絡が来た日時に調査が行われます。そのため、調査の前に税理士と相談して、問題点がないかチェックしたり、調査官の質問に適切に答えられるように準備したりすることも可能です。
特筆すべき点は、税理士だけが相続税申告の際に「書面添付制度」を利用できることです。書面添付制度とは、申告書を提出する際に、計算や内容の根拠を詳細に説明した書面を添付し、申告書の内容が適正であることを税理士が保証する制度です。疑問に思われやすい点をあらかじめ説明しておくことで、税務調査が入る確率を減らすことができます。書面添付をしていた場合、税務調査を実施する前に、調査官は税理士に意見を述べる機会を与えることになっています。それによって疑問点が解決し、調査の必要性がないと判断されると、税務調査は行われません。
参照:日本税理士会連合会「書面添付制度」
【Q&A】相続を税理士に依頼するか検討する際のよくある質問
相続手続きを税理士に依頼することについて、よくある質問に対する質問と回答をご紹介します。
相続手続きにそもそも税理士は必要?
相続が発生した際に税理士がいらないケースは、相続額が基礎控除を明らかに下回っているときです。基礎控除額を超えなければ税金は発生しないので、申告の必要もありません。しかし、控除額が基礎控除に近い場合や、相続財産をすべて把握できない場合、相続額が基礎控除を超えてしまうことがあります。放置していると無申告となって、後から延滞税や無申告加算税、重加算税、過少申告加算税などが課される可能性があるので注意が必要です。
相続手続きを税理士に依頼するタイミングは?
相続人が亡くなった後は、葬儀の手配などがあるため、すぐに税理士に依頼することが難しいかもしれません。四十九日を過ぎたころであれば、葬儀なども終えて相続の手続きだけに集中しやすくなるタイミングであり、おすすめです。前述したとおり相続の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内なので、早めに相談しましょう。
相続について相談できる税理士を探す方法
相続手続きについて税理士に相談したいと思っても、自力で税理士を探そうとすると手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。
「税理士紹介ナビ」は、起業全般や税、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模の全国13,000のパートナー会計事務所から、ぴったりの税理士や会計事務所を最短で翌日にご案内できます。完全無料で、会社所在地や業種に合わせた最適な税理士をご紹介します(2025年8月時点)。
「税理士紹介ナビ」には、事業者のお困りごとに沿って弥生スタッフが最適な税理士や会計事務所を紹介する「税理士紹介サービス」と、ご自身で自由に税理士を探すことのできる「税理士検索
」の2つのサービスがありますので、ご自身の状況に合ったサービスをご活用ください。
「税理士紹介ナビ」はこんな方におすすめ
「税理士紹介ナビ」は、特に次のような方におすすめです。
初めて会社を設立する方
会社を設立する際には、必要な手続きや資金調達など多くの不安や疑問が生じることがあります。「税理士紹介ナビ」なら、これから事業を始める方の悩みや困りごとに合わせて、最適な税理士探しをサポートします。個人事業主から法人成りを予定している方にもぴったりです。
起業後の会計処理や決算が不安な方
会社を運営するうえでは、法人税や地方税、消費税など、さまざまな税や固定資産の知識が必要になります。そのような場合も、会計処理や決算に関することをまとめてプロに相談できます。
できるだけ節税したい方
「節税したいが方法がわからない」という方にも「税理士紹介ナビ」はおすすめです。税理士からのアドバイスで節税方法を理解できれば、戦略的な経営にも役立つでしょう。
記帳業務を丸ごとプロに任せたい方
日々の取引を記帳するには手間や労力がかかります。売上が増えるとともに経理作業量も増え、負担が大きくなってしまうでしょう。記帳業務を税理士に丸投げできれば、その分しっかり本業に集中できるようになります。
相続税手続きは税理士への相談がおすすめ
相続税に強い税理士を探す場合は、相談件数ではなく申告実績を参考にして探すことが大切です。報酬が適正であるかも選択基準になりますが、基本報酬の相場は、相続財産の総額の0.5〜1.5%ほどであることを覚えておくと役立つでしょう。相続財産が基礎控除を超える可能性があるときや、評価が難しい財産があるときは、税理士に依頼することをおすすめします。
インターネットや紹介などで探すことができますが、多くの税理士は法人税の申告を主な業務としており、相続に特化した税理士は少ないのが現状です。そこで弥生では、税理士を探すサポートをするための税理士紹介ナビを運営しています。無料で実績のある税理士が探せるので、ぜひ一度ご利用ください。
この記事の監修者宮川 真一
税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表
税理士/CFP®
1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応をはじめ、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っている。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事する。