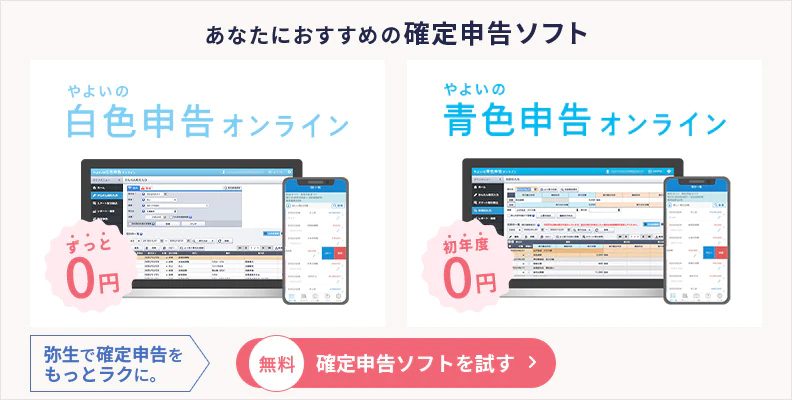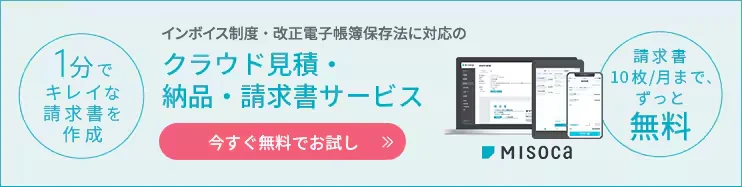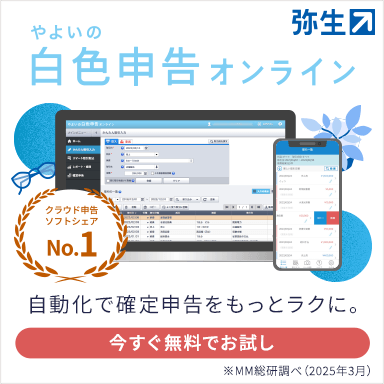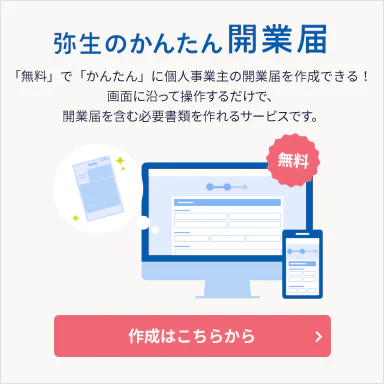副業でできるネット物販とは?始め方や注意点を詳しく解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

副業として取り組める仕事で、「物販」を考えたことがある人もいるでしょう。副業の物販とはどのようなものがあるのか?リスクは?
本記事では、ネット物販をはじめとする副業物販の特徴やメリット・デメリット、必要な事前準備についてわかりやすく解説します。副業で物販に取り組む際の注意点もまとめていますので、参考にしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
ネット物販などの物販ビジネスとは?
物販とは、「商品を仕入れて販売する」ことなどを指します。仕入れ方や売り方にはさまざまな方法がありますが、基本的な流れは次のとおりです。
〈物販の流れ〉
-
1.商品を仕入れる(または製作する)
-
2.商品を売り出す(販売する)
-
3.商品が売れる
-
4.代金を回収する
物販は長年にわたって存在するビジネスですが、近年ではフリマアプリやECサイト、ネットオークションなどが広く活用されるようになったため、個人でも始められるビジネスとして認知されてきています。物販の中でもインターネット上で取引されるビジネスが「ネット物販」です。
物販と転売の違い
物販と転売の主な違いは、仕入先と販売価格にあります。
物販の場合、メーカーや卸業者から仕入れたり、自分で作ったりした商品を扱うのが一般的です。転売の場合は、一般的な小売店や個人から買った商品を販売します。物販が「小売店向けの商品」を仕入れるのに対して、転売は「一般消費者向けの商品」を仕入れているケースが少なくない点が大きな違いです。
販売価格を決める際には、物販の場合、仕入原価や送料を差し引いても利益を確保できるよう、適正な売値を検討したうえで価格を決定するのが一般的です。転売の場合も同様に、仕入値に利益を上乗せして販売します。
しかしし、転売の場合は物販と異なり、需要が供給を上回る場合には非常に大きな利益を乗せて売ろうとするケースも見られます。とはいえ、取引される商品が法律や条例に抵触していないものであれば、転売行為自体は問題ありません。
物販・転売ともに「その価格で買いたい人がいるかどうか」という需要と供給のバランスで成り立っている点では共通しています。
副業で物販を行うメリット
フリマアプリやECサイトが広く浸透している昨今では、副業で物販ビジネスに取り組むことも可能です。副業で物販を行うことによって得られる主なメリットを見ていきましょう。
スキルがなくても始められる
物販ビジネスを始めるにあたって特別なスキルは必要ありません。前述のとおり、「商品を仕入れて販売する」というシンプルなしくみだからです。
とはいえ、商品を販売しても購入する人がいなければビジネスとして成立しません。販売する場所や販売方法について勉強していく必要があります。きちんと利益が出るように仕入先を選定したり、需要のある商品を見分けたりするには相応の慣れも必要です。
すきま時間で行える
物販ビジネスは勤務時間が決められている仕事ではないため、すきま時間を活用して取り組めるというメリットもあります。例えば、商品のリサーチや商品説明文の作成といった一つひとつの作業は、慣れれば短時間で終えることも可能です。
ただし、完全に時間が自由になるというわけではありません。ネット販売している商品が売れた場合、できるだけ早く商品の梱包・発送作業をする必要があるからです。
比較的時間の融通が利く仕事ではあるものの、時間の制約を一切受けないビジネスではない点を認識しておきましょう。
副業で物販を行うデメリット
副業で物販ビジネスに取り組む場合、デメリットとなり得る面もあります。メリット面だけでなく、次にあげるデメリットについても理解しておくことが大切です。
元手がかかる
物販ではまず商品を仕入れる必要があることから、始めるにあたって仕入原価が発生します。商品を自分で製作する場合には材料費がかかります。こうした元手がかかる点は、物販のデメリットの1つです。
特に高額商品を扱う場合には、仕入原価も相当な金額に達することが想定されます。物販に挑戦するにあたって、持ち出しなしでは始められない点に注意してください。
在庫を抱えるリスクがある
取り扱っている商品が売れなかった場合、在庫を抱えるリスクがあることも物販のデメリットです。在庫を抱えるということは、元手がかかっているにもかかわらず、売上につながっていないことを意味します。商品の需要を見誤ると、多く仕入れすぎたり製作しすぎたりする原因にもなりかねません。
さらに、在庫が増えるにつれて在庫管理も煩雑になります。商品が破損したり劣化したりすれば販売できなくなってしまうため、保管場所の確保も必要です。商品の大きさや壊れやすさなども考慮したうえで、取り扱う商品を慎重に決定することが求められます。
配送がある場合、梱包などの手間がかかる
購入された商品を配送する必要がある場合には、梱包や発送作業が発生します。売れる商品点数が少ないうちは問題なく対応できたとしても、販売点数が増えるにつれて配送作業の負担が大きくなりかねません。売れれば売れるほど多くの労力を費やすことになりがちです。
前述したとおり、物販は比較的時間の融通が利く副業ですが、配送が必要な場合には相応の作業時間を確保する必要があります。こうした時間を捻出するのが難しい場合、物販に取り組むのが困難な可能性があることを押さえておいてください。
副業物販の事前準備
副業で物販を始めるにあたって、必要な準備について解説します。取り扱う商品によらず、物販に必要な事前準備の基本はほとんど同じです。具体的には、次にあげる4つの準備を進めておきましょう。
販売するジャンル・商品のリサーチ
初めに、販売する商品のジャンルや取り扱う商品の候補をリサーチします。自分が売りたい商品であることはもちろん重要ですが、実際に需要があるかどうかを確認しておくことも大切なポイントです。売れているジャンルや商品は何かのリサーチを入念に行ってください。
また、物販を成功させるには、できるだけ利益率の高い商品を取り扱うのが得策です。一般的な販売価格と仕入価格の差が大きい商品を探すといいでしょう。購入者への配送が必要なネット物販の場合には、今後かかってくるコストを想定するために商品サイズや重量、壊れやすさなども考慮しておく必要があります。
販売する商品の仕入先の調査
次に、販売する商品の仕入先を調査します。仕入先は大きく分けて「ネットの卸先」と「リアルの卸先」の2種類です。さらに、ネットの卸先であれば国内だけでなく、海外の卸先を利用して仕入れる方法もあります。リアルの卸先から仕入れる際には、商社や卸業者が仕入先の候補となります。
商品を販売するプラットフォームの精査
仕入先が決まったら、仕入れた商品を販売するプラットフォームを選定します。ネット販売の場合は、次のプラットフォームが販売場所の例としてあげられます。
〈副業物販を行うプラットフォームの例〉
- メルカリ:CtoC(個人間取引)に特化したフリマアプリ
- Creema:ファッション・アクセサリー・インテリアのハンドメイドマーケット
- minne:家具や食品、アクセサリーなどのハンドメイド作品が取引されているマーケット
- BASE:初心者でも手軽に自分のネットショップを作成できるサービス
- Amazon:大手企業から個人まで出品できるECモール
また、実店舗にて商品を販売する場合には、物件や販売手段についても確保しておく必要があります。初めから独立店舗を開業するのはリスクが高いため、既存店舗の一角を間借りできないか交渉したり、委託販売を行ったり、物販のための貸しスペース・イベントスペースを利用したりするのも1つの方法です。
商品の保管場所の検討
仕入れた商品が売れるまでの保管場所についても、事前によく検討しておくことが大切です。取り扱う商品の大きさや形状にもよりますが、品切れを起こさないようにするには相応のスペースを確保しておく必要があります。保管状況によっては商品の破損や劣化の原因にもなりかねないので注意が必要です。
自宅では保管場所を確保できないようなら、レンタル倉庫などの契約も検討する必要があります。仕入れた商品は売上を作るための重要な資産と捉え、保管場所を慎重に検討することをおすすめします。
副業物販を始める手順
副業物販を成功させるには、商品が着実に売れるしくみを確立することが重要です。副業物販の始め方から、商品の宣伝までの流れについて、詳しく見ていきましょう。
1. 販売計画を立てる
副業物販を始めるにあたって、第一に策定しておきたいのが販売計画です。副業とはいえ、個人商社として物販ビジネスに参入する以上は、不可欠なプロセスと捉えてください。
具体的には、どのくらいの売上を想定しているのか、目標とする売上を達成するにはいくらの商品をどれだけの数量売ればよいのかを検討します。先に目標を立て、目標から逆算して取り扱う商品や数を絞り込んでいくのがポイントです。
2. 売る商品を仕入れる
取り扱う商品が決まったら、実際に商品を仕入れます。初めから多すぎる数量を仕入れてしまうと、在庫を抱え過ぎるおそれがあるため注意してください。まずは少量を仕入れ、売れ行きを確認しながら仕入れの数量や頻度を調整していくことが大切です。
また、同じ商品であっても、仕入先によって仕入値が異なるケースがあります。1つの仕入先にこだわらず、さまざまな仕入先をリサーチしてできるだけ安く仕入れることも重要です。
3. 販売するプラットフォームを選ぶ
ネット販売の場合は、事前準備の段階で選定した販売プラットフォームのうち、取り扱う商品に最も適したプラットフォームを選びます。同じジャンルの商品が数多く販売されているプラットフォームであれば、顧客ニーズとの親和性が高い可能性があります。
また、競合がすでに多数参入していないか、想定していた販売価格よりも安い価格で販売している事業者が複数見られないかといった点も確認しておくことが大切です。
実店舗での販売の場合は、すでにある店舗での委託販売や間借りしての販売など、一角を借りるくらいの小規模で始められるように交渉しておきます。最初はリスクを下げて開業し、業績が伸びてから拡大した方が無難です。
ネット販売と同様に、同じジャンルの商品が置いてある店舗や販売したい商品と世界観が似ている店舗を選ぶのがおすすめです。
4. 商品を出品して販売する
販売する商品を仕入れ、販売方法が決まったらいよいよ商品の販売を開始します。ネット販売であれば、商品を出品する必要があります。
ネット販売はその特性上、顧客は商品の実物を見たり手に取ったりすることなく購入を決めなくてはなりません。商品の写真や説明が購入意思の決定打となるケースも少なくないため、掲載する画像や文面には十分こだわってください。
例えば、商品紹介文では具体的な機能や使い方のほか、商品サイズ・重量・素材などの情報を詳細に記載しておく必要があります。顧客の疑問点や不明点が解消されないと、購入を見合わせる要因にもなりかねません。商品写真をできるだけ多く掲載するとともに、詳細な説明文を添えるなど、安心して購入してもらえるように工夫することが大切です。
実店舗での販売でも、自身が売場に立たない委託販売などの場合には、事前に店舗の従業員に十分な商品の説明を行い、理解を深めてもらえるよう伝えることが重要になります。
5. 出品した商品の宣伝を行う
特に物販を始めたばかりの頃は、ショップの存在や取り扱っている商品がほとんど知られていません。できるだけ多くの人に商品を見てもらい、購入を検討してもらうためにも、宣伝を行う必要があります。
例えば、SNSでショップの専用アカウントを作成し、出品している商品を紹介していくのは有効な方法です。SNSであれば広告費をかけずに情報を発信することもできます。
投稿に「いいね」やコメントが付いた場合にはリアクションや返信をするなど、地道な積み重ねを通じてファンを醸成していくことが重要です。
副業物販の注意点
副業で物販に取り組むにあたって、いくつか注意しておきたい点があります。トラブルに発展するのを避けるためにも、次の4点を押さえておくことが大切です。
違法となる商品の販売に気を付ける
物販ビジネスに取り組む際には、取り扱えない商品があることを押さえておく必要があります。例えば、商標や著作権を侵害する模造品、薬品類、イベントチケットなどは、いずれも販売が禁止されている物品です。たとえ偽物と気付かずに仕入れた場合でも違法行為となりますので、十分に注意してください。
その他、アルコールや食品を販売する場合には酒販売免許や食品衛生法の営業許可といった各種届出が必須です。必要な届出をすることなく販売すれば処罰の対象となります。取り扱う商品について、必要な届出や許可がないか事前に確認してください。
判断に迷う場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。
商品の破損や保証・保険の対応を行う
取り扱う商品によっては、配送中の破損に備えて保険に加入しておくのが望ましいでしょう。どれほど注意して扱っていても、荷崩れや輸送中の事故などが原因で破損する可能性があるからです。配送保険に加入しておくことにより、こうした損害を補償してもらえます。
また、商品を購入した顧客が利用可能な保証についても検討しておきます。商品到着後、顧客の過失によらず短期間で商品が使えなくなってしまった場合などには、交換や修理に応じる条件を設けておくことが大切です。
こうした保証が用意されていることは、顧客に安心して購入してもらうためにも重要なポイントといえます。
在庫がある場合は棚卸しが必須
期末に在庫を抱えている場合には、棚卸しを実施する必要があります。棚卸しとは、純利益を確定させるために、実際の在庫数を確認するプロセスのことです。その在庫数と帳簿上の在庫数との照合も行いましょう。商品点数が少ないうちは棚卸しの手間もかからないものの、取り扱う商品の種類が増えていくと棚卸しの負担が大きくなりがちです。
在庫管理は適切な仕入れを行うためにも重要なポイントといえます。帳簿上の在庫数と大きなずれが生じている事実が期末になって発覚することのないよう、定期的に棚卸しを実施することが大切です。
収益を得たら確定申告をする
物販による副業の所得が年間20万円を超えた場合、所得税の確定申告を行う必要があります。所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額のことです。
例えば、年間の売上が100万円であっても仕入れやその他の経費に85万円かかったのであれば、所得は15万円です。本業以外でこの副業の所得しかないのであれば、確定申告は必要ありません。ただし、確定申告が不要である場合でも利益が出ているので、住民税の申告は別途必要です。居住地の役所へ住民税を申告するのを忘れないようにしてください。
また、適格請求書(インボイス)発行事業者として登録する場合、消費税の申告および納付が必須となります。販売先が適格請求書発行事業者の場合、適格請求書(インボイス)の発行を求められることがあります。一方で販売先が一般消費者の場合は、適格請求書(インボイス)は不要です。副業で物販を始める際には、販売する先を考えて、適格請求書発行事業者の登録と、消費税の申告・納付について判断するようにしましょう。
副業でも物販は可能!物販ビジネスに挑戦しよう
物販ビジネスは、副業として取り組むことも十分に可能です。特別なスキルがなくても始められるうえ、すきま時間を活用しやすい物販ビジネスは、副業に適したビジネスといえます。
物販は仕入れや販売によって常にお金が動き続けるビジネスのため、副業であっても日頃から帳簿付けを行う習慣を身に付け、お金の動きを把握しておくことが大切です。
とくに事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
物販ビジネスを始める人はぜひご活用ください。
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。また会計ソフトとの連携も可能なため、請求業務から会計業務を円滑に行うことができます。