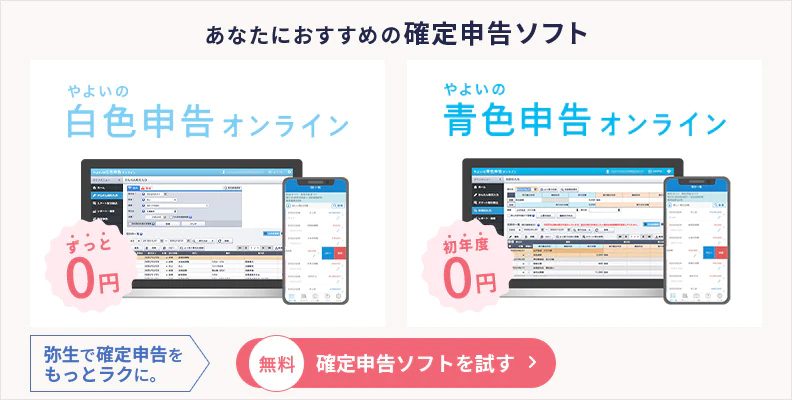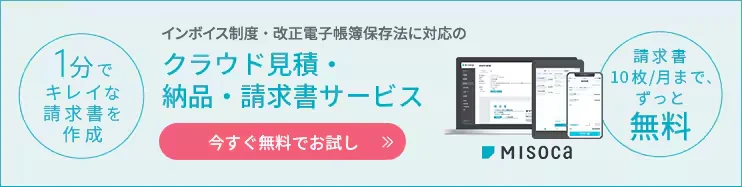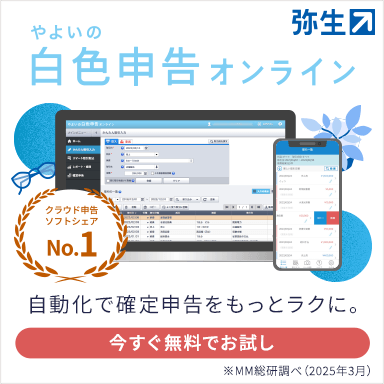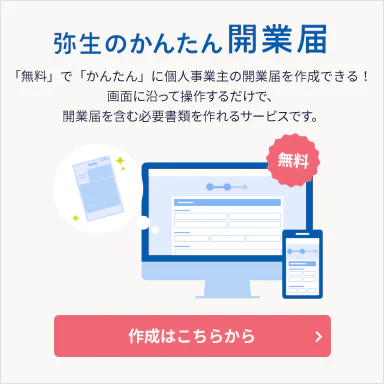副業でふるさと納税の上限額は変わる?計算方法や注意点を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

ふるさと納税を活用して節税したり、返礼品を受け取ったりしたいと考えている人はいることでしょう。一方で、副業で収入が増えることによってふるさと納税の上限額が変わるのか、疑問に感じている人もいるはずです。
今回は、ふるさと納税の基本的なしくみや利用するメリット、納税額の年間上限額についてわかりやすく解説します。副業収入がふるさと納税にもたらすメリットのほか、会社に副業がばれる可能性を含めたデメリットにも触れていますので、参考にしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
ふるさと納税のしくみ
ふるさと納税とは、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。任意の自治体に自分の意思で寄附をすることで節税につながったり、返礼品を受け取れたりする制度です。
ふるさと納税で寄附した金額を確定申告時に申告することにより、所得税や住民税が還付・控除が適用されるしくみです。また、自治体ごとに返礼品を用意しているケースも多く見られ、寄附者が希望すれば返礼品を受け取ることもできます。
ふるさと納税は、お得になるからといって、上限なく寄付ができるわけではなく、収入や家族構成で控除限度額が決められています。
1月1日~12月31日の1年間にふるさと納税で納めた寄附金額から、自己負担分の2,000円を除いた金額のうち、年間の上限額内に収まっている分が当年分の所得税の還付・控除や、翌年度の住民税控除の対象となります。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
ふるさと納税の特徴
続いて、ふるさと納税の主な特徴を見ていきましょう。ふるさと納税特有のポイントは次のとおりです。
好きな自治体に納税できる
ふるさと納税の寄附先は、寄附者が自由に決められます。故郷かどうか、住んだことがあるかどうかを問わず、どの自治体にも納税(寄附)が可能です。
また、寄附税金の使い道を寄附者が指定できる自治体があることも大きな特徴の1つといえます。
税金の還付や控除がある
ふるさと納税のしくみを利用して自治体に寄附すると、自己負担分の2,000円を超える寄附金額に関しては、当年度の所得税の還付・控除や翌年度の住民税控除の対象となります。つまり、ふるさと納税の制度を活用することで、節税効果が得られるのです。
ただし、収入や家族構成、各種保険料、控除額に応じて年間の上限額が決められているため、無制限に控除が適用されるわけではない点に注意してください。
返礼品がもらえる
ふるさと納税では、寄附金額の3割以内であれば「返礼品」を各自治体が用意することが認められています。返礼品とは「お礼の品」という意味で、自治体ごとに多種多様な返礼品を用意していることもあります。
ふるさと納税の限度額は副業所得も加味される
ふるさと納税で自己負担分の2,000円を除いた寄附金額が税金から控除される年間上限額は、収入や家族構成などに基づいて計算される所得控除の状況によって変わるしくみです。基本的には、収入が多い人や扶養家族の人数が多い人ほど納税額の年間上限額が上がり、より多くの控除を受けられる傾向にあります。そのため、本業の給与所得のほかに副業所得があると収入を合算することになり、納税額の年間上限額はその分上がると考えられます。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
ふるさと納税の年間上限額の目安
ふるさと納税で自己負担分の2,000円を除いた寄附金額が税金から控除される年間上限額は、納税を行う人の所得と家族構成で異なります。具体的な年間上限額の例を見てみましょう。
給与所得と副業所得がある場合の年間上限額例1
- 本業の年収(給与所得)500万円
- 副業の年間所得20万円
- 配偶者の給与収入:0円
- 扶養家族(配偶者以外):なし
- 控除限度額:約53,000円(※)
給与所得と副業所得がある場合の年間上限額例2
- 本業の年収(給与所得)800万円
- 副業の年間所得50万円
- 配偶者の給与収入:90万円
- 扶養家族(配偶者以外):15歳以下2人
- 控除限度額:約128,000円(※)
- ※生命保険・地震保険料、医療費控除、住宅ローン減税を加味しない場合の年間上限額
上記のように、副業を含めた収入、配偶者の所得、家族構成によって控除額は変化します。総務省が公開している「ふるさと納税ポータルサイト」で、納税を行う人の所得と家族構成別にふるさと納税の年間上限額の目安が掲載されていますので、一部抜粋して紹介しましょう。
| ふるさと納税を行う本人の給与収入(所得) | ふるさと納税を行う人の家族構成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身または共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | ― |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
- ※「共働き」は、ふるさと納税を行う本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指す(配偶者の給与収入が201万円超の場合)。
- ※「夫婦」は、ふるさと納税を行う人の配偶者に収入がないケースを指す。
- ※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す。
- ※中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
- ※総務省「「ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ」
」
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
ふるさと納税の年間上限額の計算方法
ふるさと納税によって還付や控除される税金額は、どのように計算されるのでしょうか。前述の総務省が公開している「ふるさと納税ポータルサイト」では、税金の控除額のシミュレーションが可能なExcelファイルが提供されているため、試算したい場合には活用することをおすすめします。
ここでは、税金がいくら控除されるかを自分で計算する方法について見ていきましょう。
1. 所得の総額を出す
初めに、年間所得の総額を計算します。所得の総額とは、本業と副業の所得金額の合計額のことです。副業所得(雑所得または事業所得)は収入から必要経費を差し引いて算出してください。また、利子所得や不動産所得など、その他の所得がある場合はすべて合算します。
本業や副業が給与所得であれば、勤務先で発行される源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」で所得金額を確認できます。漏れのないよう、すべての所得を合算することが大切です。
2. 課税所得金額を把握する
次に、課税所得金額を把握します。課税所得金額とは、所得の総額から控除額を差し引いた金額のことです。具体的には、所得から基礎控除や社会保険料控除、配偶者控除などを差し引くことで課税所得金額が算出できます。
課税所得金額を知るには、毎年5~6月ごろに勤務先または自治体から受け取る「住民税決定通知書」を参照してください。ここに記載されているのはあくまでも前年分の住民税計算上の課税所得金額ですが、前年と比べて所得に大きな変動がないようなら、全額控除されるふるさと納税の上限額を算出する際の参考になります。
3. 所得税と住民税の控除額を計算する
ふるさと納税による所得税や住民税の還付額・控除額を具体的に計算するには、前述の総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」からダウンロードできるExcelファイルを活用するのがおすすめです。収入や家族構成、ふるさと納税金額を入力することで、還付額や控除額を簡単に算出できます。
なお、ふるさと納税の寄附額が還付額および控除額を超えてしまった分は、控除の対象とはならないので注意してください。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
ふるさと納税の控除を受ける方法
ふるさと納税で控除を受けるためには、納税した翌年の3月15日までに、納税した自治体から送付される「寄附金受領証明書」を使用して所得税の確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うと、寄附金控除として所得税控除が適用され、還付金を受け取ることが可能となり、さらに住民税も減額されます。
なお、年末調整のみで確定申告の必要がない会社員の場合、「ワンストップ特例制度」を使うことができます。ワンストップ特例制度とは、1年間でふるさと納税した自治体数が5つ以下であれば、各自治体から取り寄せる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入して送付するだけで、確定申告が不要で住民税の控除が受けられるしくみです。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業収入がある人がふるさと納税を行うメリット
副業収入がある人の場合、本業の給与所得と合算することで所得の総額が増えます。その増えた分だけふるさと納税ができる金額も増える点があります。
また、より多くの寄附が可能になれば、当年分の所得税の還付・控除や翌年度の住民税の控除が受けられ、節税効果が高まります。
なお、年間上限額を超えた金額を寄附することもできますが、超過分には所得税の還付・控除や住民税の控除が適用されません。したがって、収入や家族構成などに応じて算出される年間上限額の範囲内で寄附するのが一般的です。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業収入がある人がふるさと納税を行うデメリット
副業収入を得ていることで、ふるさと納税の制度を利用する際にデメリットとなり得る面もあります。副業収入がある人は、次の2点についてあらかじめ理解しておきましょう。
ワンストップ特例制度が使えない
ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行なくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられるしくみです。ふるさと納税による所得税の還付・控除や住民税の控除を受けるためだけに、確定申告をしなければならない手間を省くための制度といえます。
ただし、ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税の申告をしていない人が対象のため、副業している会社員はこの制度を利用できません。そのため、ふるさと納税の控除を受けるには、年間の副業所得が20万円以内であっても、確定申告を行う必要があります。
特に2024年(令和6年)分は、注意が必要です。副業をしている会社員は、ふるさと納税分だけでなく、定額減税分を確定申告書に記入する必要があります。
定額減税の対象者は、確定申告書に定額減税の記載漏れがあると定額減税が無効になります。扶養親族が定額減税の対象に含まれていた場合、あわせて無効になりますので、漏れなく確定申告書に記載をしましょう。
定額減税に関して確定申告をする場合は、以下の記事も参考にしてください。
副業禁止の会社の場合、ふるさと納税でばれる可能性がある
副業を認める企業が増えているものの、情報漏えいなどのリスクから、就業規則で副業を禁止しているケースもあります。
また、副業が禁止されていなかったとしても、事前に届け出ることが必要な企業もあります。そのため、就業規則や秘密保持誓約書、副業に関する規程などをあらかじめよく確認したうえで、リスクを想定して実際に副業に取り組むかどうかを検討する必要があるでしょう。
もし、副業禁止にもかかわらず、副業を行った所得を含めてふるさと納税を行うと、住民税が発端となり、副業をしている事実が勤務先に知られてしまう可能性があります。住民税には普通徴収(自分で納付する方法)と特別徴収(給与から天引きする方法)があり、特段の事情がない限り特別徴収による納付が一般的です。
副業を会社に知られたくない場合、普通徴収を選んでいる場合が多いはずですが、ふるさと納税の控除額が副業の住民税額を超えてしまう場合、自治体によっては特別徴収に切り替えられてしまうケースがあります。
また、副業分の所得を申告すると、本業と副業を合算した所得に基づいて住民税が計算されるため、翌年度の住民税が上がってしまいます。本業の勤務先で給与額を基に計算した住民税額よりも実際の住民税額が高ければ、本業以外に収入があることが勤務先に知られることになります。
このように、副業をしていることが住民税によって勤務先に知られるリスクを完全に排除するのは困難です。とはいえ、ふるさと納税による節税のメリットが大きく、副業の所得を知られたくないという理由でふるさと納税分を申告しないのはあまり得策とはいえません。あえてふるさと納税を行い、減税をしたほうがよい場合もあります。
本業の会社が副業を容認している場合は、ふるさと納税のメリットを考慮したうえで、ふるさと納税を行うかどうかを判断するとよいでしょう。
なお、住民税の特別徴収税額決定通知書という、会社経由で従業員に渡させる書面が圧着式などになっていて、会社の人が見えないようになっている場合には、ふるさと納税が原因で会社に副業が知られる可能性は非常に低いでしょう。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業を行った際の確定申告の方法
副業の所得が年間20万円を超えた場合のほか、医療費控除や住宅ローン控除など、年末調整で申告できない控除を適用する場合は、確定申告を行う必要があります。この場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度が適用されなくなるため、確定申告を行うとよいでしょう。ただし、副業の年間所得が20万円以下でも、ふるさと納税を利用する場合には確定申告が必要になる点に注意してください。
副業による所得は、収入から必要経費を差し引いて算出します。副業のために支払った費用の中には、経費として申告できるものが少なくありません。例えば、副業を始めるにあたって購入したソフトウェアや、業務に利用しているインターネット回線使用料、スマートフォンなどの通信費などは、いずれも経費として計上できます。
また、販売相手が法人・個人事業主にかかわらず、消費税の課税事業者の場合、適格請求書(インボイス)の発行を要求される場合があります。適格請求書(インボイス)発行事業者として登録すると、副業でも消費税の確定申告も必要になります。販売相手が最終消費者の場合には、適格請求書(インボイス)の発行は必要がありません。つまり、副業を始める際には、販売相手先によっては適格請求書発行事業者の申請や消費税の申告も視野に入れて検討しておくことが大切です。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業の所得を本業分と合算したふるさと納税の年間上限額を把握して、効果的に活用しよう
ふるさと納税は、うまく活用することで多くのメリットを得られる制度です。ただし、ふるさと納税の年間上限額は副業分を含む所得金額や家族構成によって異なるため、自分の上限額を把握したうえで納税額を見極める必要があります。今回紹介した副業を行っている人がふるさと納税を行う際のポイントや注意点を参考に、ふるさと納税を効果的に活用してください。
なお、ふるさと納税にかかわらず、副業が事業所得に該当して確定申告が必要になる場合は、初めての人でも無料で利用できる「やよいの白色申告 オンライン」がおすすめです。帳簿や所得税の確定申告書、収支内訳書、消費税の確定申告書なども簡単に作成できて、e-Tax(電子申告)も直接できます。
副業が雑所得に該当する場合でも、帳簿付けをすれば、売上と経費から所得の算出が容易になります。帳簿があれば事業所得で申告ができる可能性が出てきます。雑所得の場合は「やよいの白色申告 オンライン」では申告ができませんので、集計資料をもとに国税庁の確定申告等作成コーナーで申告を行ってください。無料で使えるので「やよいの白色申告 オンライン」での帳簿付けを気軽にお試しください。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。また会計ソフトとの連携も可能なため、請求業務から会計業務を円滑に行うことができます。