売上原価とは?製造原価との違いや計算方法、仕訳方法を解説
更新
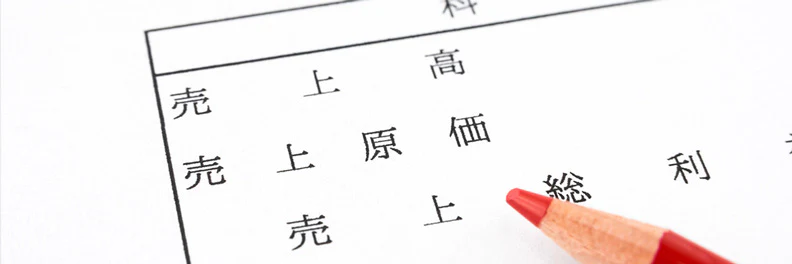
売上原価とは、期中に販売した商品の仕入や製造にかかった費用のことです。売上原価は、商品を販売した際の利益を決定する重要な指標となります。なお、売上総利益(粗利)は、売上高から売上原価を差し引いて求められます。企業の経営状態や収益性を分析し、有効な施策を打ち出すためには、売上原価の正確な把握が不可欠です。売上原価を正しく把握するためには、計算方法や含まれる費用を正確に理解しなければなりません。
本記事では、売上原価と製造原価の違いや売上原価の計算方法、仕訳方法などを解説します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
売上原価とは期中に販売した商品の仕入・製造にかかった費用のこと
売上原価とは、期中に販売した商品を仕入れたり製造したりする際にかかった費用のことです。売上原価に含まれる費用の範囲は業種によって異なりますが、主に仕入代金や材料費などが該当します。なお、売上原価は、あくまでも当期の売上に対しての経費なので注意しましょう。例えば、1個100円の商品を500個仕入れて5万円を支払い、そのうち期中に300個を販売した場合、売上原価に該当するのは販売した300個分の仕入代金「100円×300個=3万円」です。
売上原価は、損益計算書に記載される項目の1つ
売上原価は、一会計期間における企業の収益と費用の損益計算をまとめた損益計算書の記載項目の1つで、多くの場合、売上高のすぐ下に記載されています。売上に対して売上原価が低ければ利益が高く、反対に、売上に対して売上原価が高ければ、利益が低いことを意味します。売上原価を正確かつタイムリーに把握することは、企業の経営状態や収益性を分析するうえで重要です。
損益計算書についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
売上原価に含まれる費用の範囲は業種によって異なる
売上原価に含まれる費用の範囲は、業種によって異なります。ここでは、小売業、飲食業、サービス業、製造業それぞれの業種における、売上原価の範囲を見ていきましょう。
小売業:仕入代金のうち実際に販売された商品分
小売業では、仕入代金のうち、実際に販売された商品分が売上原価に該当します。
ただし、棚卸時に不足が発生したロス分や、経年劣化などによる評価損は一般的には棚卸減耗費として販売管理費に含めます。例えば、帳簿上は50個あるはずの商品在庫が、倉庫や店舗にある商品の在庫を実際に数えて確認する実地棚卸で49個しかなかった場合、不足していた1個分の仕入代金については仕入高から棚卸減耗費に振り替えるのが一般的です。
販売員の人件費や店舗運営に必要な事務消耗品費、チラシ・Web広告といった広告宣伝費などは、売上原価には含みません。これらの費用は、売上原価ではなく、販管費(販売費及び一般管理費)として計上します。
飲食業:食材の仕入代金
飲食店では、主に食材の仕入代金が売上原価となります。
例えば、レストランやカフェであれば、料理の材料費、ジュース・アルコール類の仕入代金が主な売上原価です。店舗の光熱費や人件費、割りばしなどの消耗品費といった経費は、売上原価には該当しません。ただし、焼き鳥店で串打ち専門の職人を雇っている場合など、飲食物の調理に特化した従業員の人件費は、売上原価に含める場合もあります。
サービス業:外注費以外はほぼ発生しない
サービスを提供するサービス業では、商品の仕入や製造を行うことがないため、売上原価はほとんど発生しません。
客先にサービスを提供するために必要な外注費は売上原価に該当しますが、それ以外の費用はほぼないといえるでしょう。このように、サービス業では売上高から差し引く売上原価が低くなることから、売上総利益の割合(粗利率)が高くなる傾向があります。その一方で、従業員の人件費や広告宣伝費など、販管費が大きくなりやすいのが特徴です。
製造業:売上原価ではなく製造原価として計上される
製造業における材料費や製品の製造コストは、販売する製品を製造するためにかかった製造原価として計上されます。その製造原価のうち、販売されたものに係る分が売上原価として計上されています。
製造業では、他の業種とは違い、単純に「原価=材料の購入費用」とはなりません。製造業が製品を販売するまでには、材料や原料、部品などを購入し、工場で機械を使って加工する、といったさまざまな製造プロセスがあるためです。そこで、製造業においては「原価=製造にかかったすべてのコスト」と捉え、材料・原料・部品代をはじめ、製造に携わる労働者の給与、工場の賃料や水道光熱費、機械・設備の費用なども製造原価として計上します。
なお、製造業でも製造だけでなく自社で小売も行っている場合は、製造原価の他に小売分の 売上原価も併せて損益計算書に記載することがあります。
売上原価と製造原価の違い
上述したように、売上原価と製造原価は対象となる費用の範囲が異なるため、両者の違いを正しく理解することが大切です。
売上原価は、期中に販売した商品を仕入れたり、作ったりする際にかかった経費を指します。売上原価はあくまでも売上に対しての経費であり、当期に販売されていない商品のコストは含まれません。それに対して、製造原価は製品を製造するためにかかったすべての費用のことです。
製造原価は「材料費」「労務費」「経費」の大きく3つに分類され、製品の製造に必要な材料費や部品代の他、製造に関わった従業員の人件費、工場の水道光熱費、設備・機器の減価償却費なども含まれます。また、売上原価とは異なり、当期に販売されていない在庫や、製造途中で完成していない状態の製品(仕掛品)の費用も製造原価に計上されます。
製造原価は、自社で製品の製造・加工をしている製造業において発生する費用で、小売業や卸売業、サービス業などには発生しません。
売上原価の計算方法
売上原価は、一般的に仕入れた商品の費用から期末の棚卸資産を差し引いた金額です。計算式にすると、以下のようになります。
売上原価の計算式
売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高
売上原価はあくまでも売上が発生した商品に対する仕入のみで判断するため、算出には棚卸高の把握が必要です。
上の計算式にある期首商品棚卸高とは、期首(会計期間の開始日)に保有している在庫の金額を指します。企業は商品を販売するために仕入を行いますが、期中に仕入をした商品がその期のうちにすべて売り切れるとは限りません。そのため、前期に売れ残った在庫は翌期に繰り越され、当期の期首商品棚卸高となります。
その一方で、期末商品棚卸高とは、期末時点で保有している在庫の金額のことです。期末時点で売れ残っている在庫の数量に仕入単価(評価額)を掛けた金額が期末商品棚卸高となります。期末の在庫である期末商品棚卸高は、そのまま翌期首の在庫、つまり翌期の期首商品棚卸高になります。
売上原価は売上総利益(粗利)の計算に用いられる
企業の売上総利益(粗利)は、1年間の売上高から売上原価を引くことで求められます。計算式にすると、以下のとおりです。
売上総利益の計算式
売上総利益=売上高-売上原価
売上総利益は、企業の競争力を把握するうえで重要な指標となります。売上総利益がプラスになっていなければ、自社で取り扱っている商品やサービスには、原価以上の価値がないと判断できるでしょう。売上総利益を正確に算出するためにも、自社の事業内容に合わせて売上原価を適切に定義することが大切です。
なお、売上高における粗利の割合を「粗利率」と呼びます。
計算式は、「粗利率=(売上高-売上原価)÷売上高」で求められ、粗利率が大きいほど、売上に対して原価が少なく、利益が高いことを意味します。ただし、業種や経営方針などによって適切な粗利率は変わるため、自社の状況に応じて確認が必要です。
売上総利益(粗利)についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
売上原価の計算例
では、実際に売上原価を計算してみましょう。
売上原価と売上総利益の計算例
- 売上高:1,000万円
- 期首商品棚卸高:100万円
- 当期商品仕入高:500万円
- 期末商品棚卸高70万円
売上原価=100万円+500万円-70万円=530万円
売上総利益(粗利)=1,000万円-530万円=470万円
売上原価の仕訳方法
売上原価を計上するには、商品の取引に関する仕訳が必要です。主な仕訳方法には、「三分法」「売上原価対立法」「分記法」「総記法」の4つがあり、どの仕訳方法を採用するかは、企業の任意となります。それぞれの仕訳方法について、詳しく見ていきましょう。
三分法:「仕入」「売上」「繰越商品」の勘定科目を使って仕訳をする
三分法は、商品を売買する際に「仕入」「売上」「繰越商品」という勘定科目を使って仕訳をする方法です。
期中に仕入れた商品を仕入、販売した商品を売上で仕訳し、決算整理で在庫を繰越商品として処理します。決算整理後の仕入勘定が、そのまま売上原価の金額となるのが特徴です。三分法は、決算整理が終わるまで正確な売上原価を把握できませんが、仕訳がシンプルでわかりやすい方法といえるでしょう。
仕入額500円の商品を100個仕入れ、1,000円で80個販売した場合の三分法を用いた仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:商品を仕入れたとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
仕訳例:商品を販売したとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 80,000円 | 売上 | 80,000円 |
決算整理仕訳についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
売上原価対立法:「商品」「売上」「売上原価」の勘定科目を使って仕訳をする
売上原価対立法は、「商品」「売上」「売上原価」という勘定科目を使って仕訳をする方法です。
商品を販売する際には、その都度、売上原価を計算して計上します。売上原価対立法は、他の仕訳方法に比べて手間がかかりますが、決算時の仕訳は不要です。また、売上原価勘定を確認すれば、期中でも容易に売上原価を把握できます。
仕入額500円の商品を100個仕入れ、1,000円で80個販売した場合の売上原価対立法を用いた仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:商品を仕入れたとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 商品 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
仕訳例:商品を販売したとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 80,000円 | 売上 | 80,000円 |
| 売上原価 | 40,000円 | 商品 | 40,000円 |
この場合の売上原価は、「仕入額500円×販売数80個=4万円」です。
分記法:「商品」「商品売買益」の勘定科目を使って仕訳をする
分記法は、「商品」「商品売買益」という勘定科目を用いて仕訳をする方法です。
商品を販売したときには、その都度、商品売買益を計算して計上します。なお、売上原価を直接示す勘定科目はありません。分記法は、取引ごとに仕入額と売買益を確認できる点が特徴です。また、期中に原価管理を行いたい場合には適していますが、管理が煩雑になりやすいため注意しましょう。
仕入額500円の商品を100個仕入れ、1,000円で80個販売した場合の分記法を用いた仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:商品を仕入れたとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 商品 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
仕訳例:商品を販売したとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 80,000円 | 商品 | 40,000円 |
| 商品販売益 | 40,000円 | ||
商品を販売したときには、「仕入額500円×販売数80個=4万円」を、商品勘定で貸方に計上します。商品販売益は「8万円-4万円=4万円」となります。
総記法:「商品」の勘定科目のみを使って仕訳をする
総記法は、「商品」という1つの勘定科目のみを用いて仕訳をする方法です。
他の仕訳方法とは異なり、商品の仕入と販売をしたときのいずれも、勘定科目は商品を用います。総記法は、勘定科目が1つだけなので仕訳の手間がかからない一方で、商品勘定に仕入額と売上額が混在するため、期中に原価管理はできません。なお、決算整理をしないと売上原価を把握できないため、実務で使用されるケースは少ないでしょう。
仕入額500円の商品を100個仕入れ、1,000円で80個販売した場合の総記法を用いた仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:商品を仕入れたとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 商品 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
仕訳例:商品を販売したとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 80,000円 | 商品 | 80,000円 |
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
売上原価を正しく把握して、収益力分析に役立てよう
売上原価は、売上総利益(粗利)の金額を決めるものであり、企業の経営状態や収益性を測る重要な指標です。自社の売上原価と売上総利益を確認することで、商品にどれだけの付加価値をつけられているのかを把握できるでしょう。まずは、損益計算書を確認して、売上と売上原価の比率や売上総利益の推移を確認することをおすすめします。
損益計算書を作成するには簿記の知識が必要ですが、会計ソフトを利用すれば、初心者でもスムーズに作成が可能です。「弥生会計 Next」なら、カード明細や銀行明細の自動取込・自動仕訳など、便利な機能が充実していて、入力と仕訳の効率化ができます。売上原価を正しく把握し、収益力の向上につなげるためにも、ぜひ「弥生会計 Next」をご活用ください。
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。










