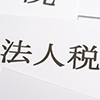益金とは?収益との違いや益金不算入、注意点などを解説
更新

法人税の計算の基になる課税所得は、事業の収益である益金から損金を差し引いて求められます。この益金は税法上の概念で、会計上の収益と似ていますが、同じではありません。
法人税の計算をするときには、益金と収益の違いや益金に算入されるものとされないものなどを正しく把握する必要があります。税務申告の際に益金について理解していないと、法人税の計算にも誤りが生じてしまうため注意しましょう。
本記事では、税法上の益金と会計上の収益との違いや益金不算入、益金算入と益金不算入における注意点などについて詳しく解説していきます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
益金とは法人税を計算したときの収益のこと
益金は、商品や製品などの販売による売上高、土地・建物の売却収入など、法人の資産を増加させる収益のうち、法人税法における「別段の定めがあるもの」を除いた収益です。なお、「別段の定め」とは、後述する益金算入・損益不算入などの税務調整が該当します。
法人税の計算の基になる課税所得は、益金から損金を差し引いて求められますが、その一方で、会計上の利益は、収益から費用を差し引いて算出します。収益と益金、費用と損金は似ていますが同一ではありません。例えば、会計上は収益とされても、税法上は益金に含まれない受取配当金や税金の還付金などがあり、これを「益金不算入」と呼びます。
益金に該当するもの
益金は、法人税法上で定められている概念です。法人税法第22条の2では、「別段の定めがあるもの」を除いた以下の5つが益金に該当するとされています。それぞれ具体的に見ていきましょう。
資産の販売による収益
資産の販売による収益とは、自社の商品や製品などを販売した際に得られる収益のことを指します。損益計算書では「売上高」に該当します。
有償または無償による資産の譲渡による収益
有償または無償による資産の譲渡による収益とは、土地や建物をはじめとした固定資産、債権・投資信託などの有価証券の譲渡によって得られる収益のことです。損益計算書では「営業外収益」や「特別利益」に該当します。
有償または無償による役務の提供による収益
有償または無償による役務の提供による収益とは、サービスの提供によって得られる収益のことです。具体的には、建設工事やシステム開発などの請負仕事の報酬、金銭・不動産の貸付による利子、その他のサービス提供にかかわる収益などが含まれます。損益計算書では業種に応じて「売上高」や「営業外収益」に該当します。
無償による資産の譲受による収益
無償による資産の譲渡による収益とは、資産を無償で取得した場合に得た収益のことを指します。例えば、メーカー側の負担で店舗に販売コーナーを設置してもらった、製品を購入した際に先方がサービスとして多めに納品してくれた、などのケースです。また、債権者による債務免除についても、経済的価値があることから、この収益に含まれます。損益計算書では「営業外収益」や「特別利益」に該当します。
その他の取引で資本等取引以外のものによる収益
その他の取引で資本等取引以外のものによる収益とは、上の4つに該当しない収益、および資本等取引以外の収益のことです。資本等取引とは、株主からの出資額増減や自己株式の取得、余剰金の配当などが該当します。このような資本等取引は、税法上、益金には含まれません。
益金と収益の違い
益金も収益も、「企業の資産を増加させる収入」という意味では同じです。しかし、益金が税法上の概念であるのに対して、収益は会計上の考え方という違いがあります。
前述したように、法人税の計算の基になる税法上の所得は、益金から損金を差し引いて求めますが、会計上の利益は、収益から費用を差し引いて算出します。益金と収益、損金と費用は一見似ていますが、内容は異なるため、税法上の所得と会計上の利益は、必ずしも一致しません。所得と利益を求める計算式はそれぞれ以下のとおりです。
税法上の所得の計算式
所得(税法上の儲け)=益金-損金
会計上の利益の計算式
利益(会計上の儲け)=収益-費用
税法上の所得は、税法の規定に従い、担税力(税を負担できる力)に応じた課税の公平性を実現するために用いられます。それに対して、利益を算出する目的は、企業の業績や財政状態を正確に把握し、株主・債権者といったステークホルダーに報告することです。なお、所得と利益を算出する際、会計上は収益や費用として計上できても、税法上は益金や損金と認められないものがあるため注意しましょう。
決算の際には、当期の利益を算出して貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成し、その後、税務申告のために所得を計算します。基本的には、会計上の利益を先に算出してから税法の規定に合わせて調整し、税法上の所得を計算する流れです。会計上の収益・費用に計上されていても税法上は認められないものや、反対に会計上は収益・費用にならなくても税法上は益金・損金に計上するものは、「別段の定め」として法人税法に規定されています。別段の定めにより、会計上の利益と税法上の所得には、ずれが生じることが一般的です。
費用と損金の違い
費用も損金も、「事業を営むうえで発生するお金」という意味では同じですが、費用は会計上の考え方であるのに対し、損金は税法上の考え方という点が違います。
そのため、会計上は費用にできても、税法上は損金と認められないものがあります。例えば、取引先を接待するためにお金を使った場合、会計上は、実際に支払った交際費が全額費用になります。しかし、税法上は、法人の交際費は原則として損金に算入できません。
また、ある設備の耐用年数について、A社は頻繁に使うため3年、B社はそれほど使わないため6年と考えたとします。これは各企業の実態のため、会計上は問題ありません。しかし、税金の計算をするときに各企業が異なる耐用年数を設定すると、課税の公平性が崩れてしまいます。そのため、税法上は、資産ごとに定められた耐用年数に応じて減価償却費を計上することになっています。
益金算入のタイミング
益金算入とは、課税所得の計算をする際に、会計上の収益には計上しないものを税法上の益金として計上することです。法人税法第22条の2では、益金算入のタイミングは、資産の販売または譲渡・譲受の場合は「目的物(資産や商品など)の引き渡しが行われた日」、役務の提供の場合は「役務を提供した日」と定められています。ただし、支払が続く取引や建設業における大規模工事などの長期にわたるケースでは、特例が適用されることがあるため注意しましょう。
また、会計上は収益として扱わないものを益金として計上することも、益金算入といいます。この場合、益金算入のタイミングは主に法人税の計算をするとき、つまり決算時です。益金算入の例としては、法人税額から控除する外国子会社の外国税額や、国庫補助金等にかかる特別勘定の取崩額などがあげられます。
益金不算入とは会計上は収益に計上するが税務では益金として計上しないもの
益金算入とは反対に、会計上は収益として計上し、税法上は益金とされないものを、益金不算入といいます。益金不算入の対象になるのは、「益金とする条件を満たさないもの」または「益金の条件には当てはまるが、益金とすると不合理になるもの」です。具体的には、益金とする条件を満たさないものとして、資産の評価益、益金とすると不合理になるものとして、受取配当金や税金の還付金が、益金不算入に該当します。
資産の評価益
資産の評価益とは、企業が保有する資産の時価が、帳簿価額(簿価)を上回ったときの差額のことです。保有資産の時価が帳簿価額を上回った場合、評価替えをして帳簿価額を増額すると、評価益が発生します。法人税法第25条では、この資産の評価益について、益金の額に算入しないものとしています。また、原則として、資産の評価益は会計上の収益にも計上しません。
受取配当金
株式の配当金をはじめとする受取配当金は、会計上は収益として計上しますが、税法上は益金不算入が認められています。これは、二重課税を防ぐためです。
例えば、A社がB社に配当金を支払ったと考えてみましょう。A社が支払う配当金の原資は、A社が法人税を納めた後に残った当期純利益(税引き後利益)ですが、B社が受け取る配当金にも法人税が課税される場合、法人税が二重に課されることになります。このような二重課税を回避するため、法人税の計算にあたり、受け取った配当金については、一部または全部を益金に算入しなくてもよいことになっています。
なお、2015年度の税制改正により、受取配当等の益金不算入制度の見直しが行われ、受取配当金を益金不算入にできる上限額が以下のようになりました。
受取配当金の益金不算入額
| 株式等保有割合(株式等の区分) | 受取配当金の益金不算入額 |
|---|---|
| 100%(完全子法人株式等) | 受取配当金の全額 |
| 3分の1超100%未満(関連法人株式等) | 受取配当金全額-負債利子 |
| 5%超3分の1以下(その他の株式等) | 受取配当金の50% |
| 5%以下(非支配目的株式等) | 受取配当金の20% |
| 証券投資信託 | なし(全額益金算入) |
税金の還付金
法人税や法人住民税といった税金の還付金は、会計上は仕訳の方法によっては収益として処理する場合もありますが、税法上は益金不算入です。還付金が発生する例としては、中間申告によって納税した額が確定申告の税額を超えていた場合や、欠損金の繰戻しを行った場合、誤って本来の納税額よりも多く申告したために更正の請求を行った場合などがあげられます。法人税や法人住民税は、税金を納めたときにも損金には算入できません。そのため、還付金についても益金不算入となります。
益金算入と益金不算入における注意点
益金に算入するもの、不算入とするものについて扱いを間違えると、法人税が正しく算出できなくなります。益金算入と益金不算入における注意点について見ていきましょう。
受取配当金の処理
受取配当金とは、企業が所有する株式などを通じて、他の法人から受け取る配当金のことで、信用金庫や信用組合などからの余剰金の分配も受取配当金に該当します。受取配当金は、会計上は収益と見なされ、損益計算書では「営業外収益」として計上されます。しかし、法人税を計算するうえでは、受取配当金は益金不算入が認められているため、益金に算入すると課税所得が増え、税負担が大きくなるので注意しましょう。
ただし、前述したように、受取配当金はすべての場合において全額を益金不算入にできるわけではありません。配当をした企業の株式をどれだけ持っているかによって、益金不算入となる金額は異なります。区分や計算方法を誤ると、納税額が大きく変わってしまう可能性があります。
税金の還付金の処理
税金の還付金は、会計上は仕訳の方法によっては収益として処理する場合もありますが、税法上は原則として益金不算入です。法人税や法人住民税の還付を受けた場合は、益金として計上する必要はありません。なお、法人税などが還付されるとき、還付金の利息にあたる金額が戻ってくることがあり、これを還付加算金といいます。還付金と還付加算金は、益金算入・不算入の扱いが異なるため注意しましょう。還付金は過去に納めた税金の払い戻しのため、益金不算入です。それに対して、還付加算金は受取利息の性質を持つため、益金として扱われます。一般的に、還付金と還付加算金は同時に振り込まれるため、それぞれの金額を分けて処理することが必要です。他に、法人事業税や自動車税など、納めたときに損金算入できる税金が還付された場合は、益金算入となります。
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
益金算入と益金不算入を正しく把握しておこう
法人税の計算をするときには、益金から損金を差し引いて課税所得を求めます。益金とは税法上の考え方であり、会計上の収益とは似ていますが同じではありません。会計上は収益にならなくても税法上は益金とするものを益金算入、会計上は収益であっても税法上は益金に算入されないものを益金不算入として、正しく処理することが大切です。益金算入と益金不算入を把握していないと、法人税の計算にもずれが生じます。適切な税務処理のためにも、税法上の益金について理解しておく必要があります。
また、税務処理を正しく行うためには、日々の帳簿付けが欠かせません。効率的かつ正確な帳簿付けを行うには、「弥生会計 Next」などの会計ソフトの利用がおすすめです。自社に合った会計ソフトを活用して、業務の効率化とミスの軽減を目指しましょう。
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。