経理で起こりやすいミスを防ぐ方法は?適切な対処方法などを解説
更新
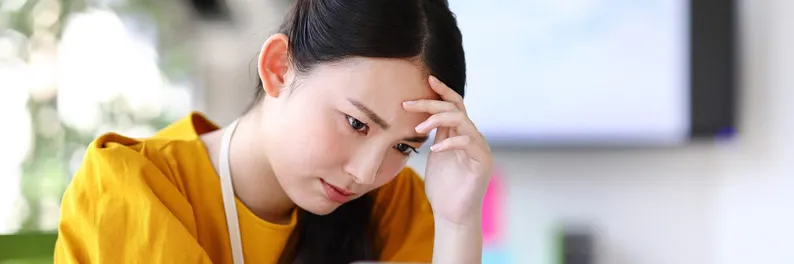
日々の売上管理や経費精算、帳簿の作成など経理担当者が行う業務は多岐にわたります。経理業務でミスが発生した場合、企業の売上や税金などにも影響を及ぼすことがあるため、十分注意しなければなりません。経理業務のミスを防ぐためには、ミスが起こりやすいポイントをあらかじめ把握しておくことが大切です。併せて、万が一ミスが起こってしまった場合に備え、適切な対処方法についても知っておく必要があります。
本記事では、経理業務で起こりやすいミスと適切な対処方法、ミスを防ぐ方法などについて解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経理のミスは重大なトラブルに発展することもある
企業の数字を管理する役割を担う経理は、正確性が求められる業務です。その一方で、経理は細かい計算や複雑な作業が多く、ミスが起こりやすいという実情があります。
経理の仕事は企業のお金に直結するため、ミスの種類によっては、少しの不注意が重大なトラブルにつながることもあるため気を付けなければなりません。例えば、売上や経費の金額が誤っていた場合、申告・納付する税金が多すぎたり、少なすぎたりするといった問題が起こることも考えられます。また、請求に漏れやミスがあった場合、資金繰りの悪化や取引先からの信頼が低下することもあるため、経理業務にあたっては、ミスのないように十分に注意を払う必要があります。
そこで大切なのが、起こりやすいミスを把握して事前に予防策を立てておくことやミスの対処方法を知っておくことです。経理業務でミスが発生しても、適切に対処すれば、影響を最小限に抑えることができるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経理で起こりやすいミス
経理とは、企業の経済活動にかかわるお金と取引の流れを記録し、管理する業務のことです。具体的な例をあげると、伝票や請求書の作成から、入出金の管理、各種帳簿への記帳、固定資産台帳の管理、経営にかかわる資料の作成まで、会社のお金に関すること全般を担当します。
では、経理で起こりやすいミスには、どのようなものがあるのでしょうか。業務内容別に見ていきましょう。
経費精算業務
経費精算は多くの企業で日常的に発生する業務であり、それだけにミスも起こりやすい業務です。事業に必要な経費を従業員が立て替えた際には、後日、領収書を受け取って内容を確認し、給与支給のタイミングなどに銀行振込や小口現金で経費精算を行います。経費精算をするときには仕訳を行う必要があるほか、経費精算に用いる領収書やレシートは、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(繰越欠損金の控除を受ける場合は10年間)の保存が義務付けられています。
-
国税庁:「No.5930 帳簿書類等の保存期間
」
このとき起こりやすいのが、精算する経費を帳簿に記録する際の金額の入力ミスや勘定科目の間違いです。また、領収書やレシートを紙で管理している場合、誤って紛失してしまうこともあります。領収書を紛失すると、仕訳の確認の際に支障をきたすなどの恐れがあります。また、帳簿に記載されている内容の領収書がなかった場合、架空の経費ではないかと指摘されてしまう場合もあるでしょう。
会計業務
会計の基本は日々の取引の記録です。毎日行う業務としては、経費などの領収書の整理と仕訳、売上(売掛金)や仕入(買掛金)の記録、現金出納帳の記入とチェック、未払金・立替金の処理などがあげられます。さらに、事業年度ごとに会社の収支をまとめて決算書を作成し、税務申告を行うことが必要です。
こうした会計業務の中で起こりやすいミスとしては、仕訳の際の金額の入力ミスや勘定科目の間違い、帳簿の借方・貸方の取り違え、売上・費用の計上漏れまたは二重計上などがあります。また、決算で棚卸しを行ったときに在庫を正しく計上できていなかったり、経過勘定を適切に反映できていなかったりすることもあります。
その他、会計業務の中でよく見られるミスが、消費税区分の誤りです。日々の取引を帳簿に記録する際、課税取引と非課税取引を間違えると、消費税の申告にも誤りが生じるため注意しましょう。
請求業務
請求書の作成や送付、入金の確認といった請求業務も、経理の仕事の1つです。請求業務を正確に行わないと、企業に入金されるはずのお金が、正しく入ってこなくなります。
請求業務では、請求書作成時の金額の記載・入力ミス、二重請求、請求書の送付先間違い、請求書の送付漏れなどのミスが起こりやすく、企業の信用を大きく低下させる要因になりかねません。特に、金額のミスによる過剰請求や請求書の管理が不十分なために起こる二重請求などは、取引先とのトラブルを招くこともあります。
支払業務
経理で欠かせない業務として、支払業務もあげられます。具体的には、仕入先や外注先への支払い、従業員に対する給与支払いなどの業務です。お金を直接扱う支払業務は、ミスのないように特に注意を払う必要があります。しかし、振込金額や振込先の誤り、二重振込、振込漏れ、振込期日の間違いなど、支払業務におけるミスは少なくありません。中には、仕入先や外注先から受け取った請求書を紛失したために、代金の支払いが漏れてしまうケースも考えられます。
なお、支払いに漏れや遅れがあると、仕入先などの資金繰りの悪化にもつながり、企業としての信頼を失うだけでなく、その後の取引に悪影響を及ぼす可能性もあります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経理のミスが起こった場合の対処方法
経理のミスに気付いたときには、できるだけ早く適切に対処する必要があります。経理の仕事は、1つの作業で完結するものではなく、前後の処理が密接に関連し合っているものです。例えば、日々の取引を帳簿に記録する際、金額や勘定科目に誤りがあったとします。帳簿の内容は決算書作成の基礎になるため、帳簿が正しく記載できていなければ、貸借対照表や損益計算書といった決算書の内容にも不備が生じます。さらに、税務申告は決算書の内容を基に行うため、納税額の計算にも影響を及ぼすことがあり、税務申告に誤りがあると、税務調査で指摘を受け追徴課税が発生したり、企業の信用を低下させたりすることになるかもしれません。このように、ミスそのものは些細な不注意によるものであっても、対処が遅れることで企業に大きな損害を与える場合があります。
経理のミスが起こってしまった場合には、ミスの内容と他の業務に与える影響を把握し、上司や部署の責任者に迅速に伝えることが大切です。上述の例でいえば、帳簿のミスにすぐに気付けば、担当者が記載内容を修正するだけで済むでしょう。しかし、ミスに気付かないまま次の処理に進んでしまった場合は、担当者だけでリカバリーしようとすると、かえって状況が悪化することがあります。特に、人員が少ない中小企業では、ミスを起こしてしまったときに相談できる相手がおらず、対応が遅れてしまうことも考えられます。ミスを隠したり放置したりせず、発見しだいすぐに報告し、上司の指示を仰ぐことが大切です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経理で起こりやすいミスを防ぐ方法
経理の業務内容は幅広く、さまざまなミスが起こるリスクがあります。経理のミスを防ぐためには、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。ここからは、経理で起こりやすいミスを防ぐために、普段から意識しておきたいポイントを紹介していきます。
ミスが起こりやすい業務を把握しておく
経理のミスを防ぐために大切なのは、起こりやすいミスのパターンを把握しておくことです。ミスが起こりやすいポイントをあらかじめ認識しているのと、何も意識せずに作業にあたるのとでは、正確性やミスの発生率に大きな差が生じます。どのような業務で、どういったミスが起こりやすいかを把握していれば、より注意して作業を進められるようになるでしょう。
特に、帳簿をはじめとする各種書類の入力ミスや漏れ、紛失、二重計上、二重発行などは、どの企業でも起こりやすいミスです。数字を入力するときや書類を作成するときには、「内容に誤りがないか」「重複はないか」を意識することで、ケアレスミスを事前に防ぐことができます。
整理整頓を行う
経理で起こりやすいミスの1つに、領収書や請求書といった重要書類の紛失があります。このようなミスを防ぐには、日ごろからの整理整頓が欠かせません。デスク周りはもちろん、書類を保管するファイルやロッカーなども、どこに何があるかがすぐわかるように整理整頓を心掛けましょう。
領収書などを紙で管理している場合は、ペーパーレス化を検討するのもおすすめです。例えば、紙の領収書を電子帳簿保存法の要件を満たした形でスキャンしてデータで管理するようにすれば、紛失や破損のリスクを軽減できるうえ、保管のためのスペースも不要になります。
集中力を維持できる環境を整える
経理業務には細かい計算や複雑な作業も多く、集中力が求められます。経理のミスを起こさないようにするには、集中力を保った状態で業務に取り組める環境づくりも大切です。特に、月末や月初、決算期などの繁忙期には業務が集中しやすくなります。忙しいからといって業務を詰め込みすぎると、集中力が低下し、結果としてミスが発生しやすくなってしまいます。一人ひとりに適切な仕事量を割り振ったり、一定の休憩を取ったりするなど、従業員が集中力を維持できるようなサポートを行いましょう。
ダブルチェックを行う
どれほど気を付けていても、人の手で作業する以上、ミスの可能性をゼロにすることはできません。しかし、ミスが起こってもすぐに発見して修正すれば、大事に至らずに済むでしょう。ミスの早期発見に効果的なのが、ダブルチェックの実施です。1人だけでは見過ごしてしまうようなケアレスミスも、複数人でチェックすれば、次の処理に進む前に発見できる場合があります。
ダブルチェックをする際には、実施タイミングとチェック項目を決め、業務フローに組み込んでおくことをおすすめします。すべての項目をダブルチェックするのが難しい場合は、「請求や支払いなど重要度の高い業務はダブルチェックを行う」「取引金額が大きい場合はダブルチェックを行う」など、優先順位を付けるのも1つの方法です。
マニュアルやルールを作成する
経理業務には、日次、月次、年次、という3つのサイクルがあり、日次業務の積み重ねが月次業務へ、月次業務の積み重ねが年次業務へとつながっていきます。それぞれの業務をミスなくスムーズに進めるために、「いつ、何を、どのように行うか」というマニュアルを作成しておきましょう。細かい部分までマニュアルを作り込んでおくことで、業務の質が一定になり、ミスを防げるだけでなく業務の属人化防止にも役立ちます。
さらに、マニュアルを作成する際には業務の見直しを行うため、無駄な作業を省いて効率化を目指せるメリットもあります。なお、作成したマニュアルやルールは経理部門の全員で共有し、いつでも確認できるようにしておくことが大切です。
会計ソフトを導入する
経理のミスを防止するには、会計ソフトの導入もおすすめです。会計ソフトを利用すると、経理業務の基本となる帳簿付けを自動化できます。正確性が向上することに加え、データの入力がスムーズになり、業務効率化にも大いに役立つでしょう。
手書きで帳簿を作成する場合、どうしても書き間違いや抜け漏れ、計算ミスなどが起こりがちです。さらに、手書きで帳簿を付けるには専門知識が不可欠なので、業務の属人化を招く一因にもなりますが、会計ソフトを使えば、手作業での計算や転記が不要になるため、ミスの防止と同時に業務負担の軽減にもつながります。さらに、会計ソフトの中には、銀行明細やクレジットカードなどの取引明細、レシート・領収書のスキャンデータなどを自動で取り込み、仕訳できるものもあります。こうした会計ソフトを活用すれば、通帳や領収書を見ながら数字を手入力する必要がなくなり、ミスのリスクを低減させることが可能です。
無料お役立ち資料【一人でも乗り越えられる 会計業務のはじめかた】をダウンロードする
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトを活用して経理のミスを未然に防ごう
経理は、企業のお金を扱い経営を支える重要な仕事です。それだけに、少しのミスが重大なトラブルに発展してしまうことがあります。経理のミスを防ぐには、起こりやすいミスのパターンを事前に把握したうえで、ダブルチェックやマニュアル作成などの環境を整えておくことが大切です。同時に、会計ソフトを活用して、ミスが起こりにくいしくみづくりを行うこともおすすめします。会計ソフトを利用すれば、入力ミスや計算間違い、計上漏れ、二重計上、仕訳の誤りといった人的ミスを大幅に軽減することができます。さらに、会計ソフトに入力したデータを基に、決算書もスムーズに作成可能です。会計ソフトを上手に使って、経理業務のミス軽減と効率化を目指しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。










