未払消費税とは?経理方式の違いや消費税の仕訳方法などを解説
更新
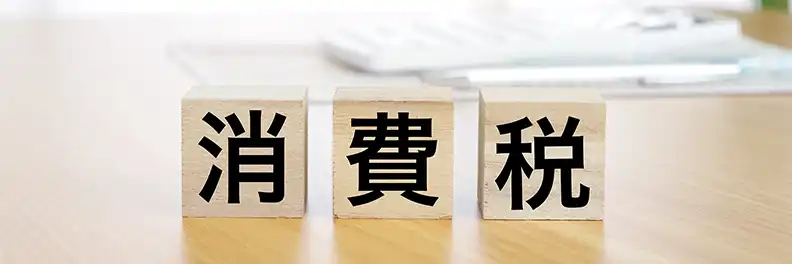
未払消費税とは、消費税の仕訳の際に使用する勘定科目の1つです。課税事業者は、商品・製品などを販売したときに消費者や取引先から預かった消費税のうち、仕入の際に支払った消費税を差し引いて、消費税の納付額を計算します。決算の時点で、支払うべき消費税額がある場合には、未払消費税の勘定科目での処理が必要です。消費税の仕訳に用いられる勘定科目には、未払消費税の他にもいくつかの種類があります。また、消費税の会計処理を行う方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があり、消費税の仕訳をするうえでは、経理方式の違いについても理解しておかなければなりません。
本記事では、未払消費税をはじめとする、消費税の仕訳に用いる勘定科目について解説します。併せて、消費税の税込経理方式と税抜経理方式の違いや消費税の具体的な仕訳方法なども紹介します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
未払消費税は決算のタイミングで未納付の消費税について計上する勘定科目
未払消費税とは、消費税および地方消費税(以下、消費税)の未納税額を処理する勘定科目です。消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される間接税です。商品などの価格に上乗せされた消費税は、消費者に代わって事業者が納めるしくみになっています。消費税の申告・納付義務のある事業者を課税事業者と呼び、事業年度が終了した時点で、1年分の消費税の合計を取りまとめて申告・納税します。ただし、消費者から預かった消費税を全額納付するわけではありません。事業者自身も、仕入や経費の支払にあたっては消費税を負担しています。そのため、売上にかかる消費税額から、仕入や経費にかかる消費税額を差し引いて、消費税の納付税額を計算します。
消費税の申告・納付期限は、法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人事業主の場合は翌年の3月31日までです。決算時に計算した消費税額は、「将来支払う義務のある未納付の消費税」として、未払消費税の勘定科目で計上した後、消費税を納付したときに、未払消費税の消込処理を行います。なお、未払消費税は、貸借対照表の「流動負債」に分類され、短期間で支払うべき負債を示します。
未払消費税を計上する理由
消費税の課税期間は当期ですが、納付が実行されるのは翌期です。期末(決算)の時点で未払消費税を計上しておかないと、当期に対応する消費税がいくらなのか決算書からはわからなくなります。将来必ず支払わなければならない消費税額を未払消費税として計上し、貸借対照表に記載することで、より正確な財務状況を把握できます。
消費税の仕訳に用いる経理方式
未払消費税について正しく理解するためには、消費税の経理処理の方法を知っておく必要があります。消費税の経理処理には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があります。税込経理方式でも税抜経理方式でも最終的な納付額は変わらず、課税事業者はどちらの方式を選んでもかまいません。なお、未払消費税の仕訳は、経理方式によって取り扱いが異なります。税込経理方式と税抜経理方式が、それぞれどのような経理処理なのかを確認しておきましょう。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
税込経理方式
税込経理方式は、仕入や売上などの取引を記録する際に、商品やサービスの価格と消費税を合わせた金額(税込価格)で記帳する経理方式です。日々の記帳では、仕入にかかる消費税は仕入金額に、売上にかかる消費税は売上金額に含めて計上し、消費税の納付時に「租税公課」としてまとめて計上します。租税公課とは、国税や地方税などの「租税」と、国や地方公共団体、その他公共団体に納める罰金や会費に当たる「公課」を示す費用を計上する勘定科目です。
税込経理方式では、原則として、申告書が提出された日の属する事業年度に消費税(租税公課)を経費計上するため、基本的には決算時の未払計上は行いません。ただし、例外として、決算で未払処理をした場合は、その経理をした事業年度における経費計上が可能です。
税込経理方式のメリットとして、帳簿付けに手間がかからないことがあげられます。また、帳簿に記録するのは税込価格なので、仕訳もシンプルです。その一方で、簡易課税制度を選択しているような場合を除いて実際に納税する消費税がいくらになるかが貸借対照表上から一目でわからないため、期中の損益を把握しにくいというデメリットがあります。特に、取引に標準税率10%と軽減税率8%が混在している場合は、帳簿上で正確な金額を把握するのが難しくなります。
税抜経理方式
税抜経理方式は、仕入や売上などの取引を、本体価格と消費税に分けて記帳する経理方式です。仕入にかかる消費税は「仮払消費税」、売上にかかる消費税は「仮受消費税」として、本体価格と分けて計上します。決算時には、仮受消費税から仮払消費税を引いて納付する消費税額を求めて計上します。
税抜経理方式は、本体価格と消費税を別に仕訳するため、経理処理が煩雑になりますが、消費税の額が損益計算書から常に除かれた状態になるため、期中の損益状況を正確に把握することが可能です。また、消費税を分けて計算するため、取引に標準税率10%と軽減税率8%が混在している場合でも経理処理の方法を変更する必要がなく、異なる税率を区別して仕訳ができるメリットがあります。決算を待たず、月次で仮受消費税と仮払消費税を集計し、リアルタイムの納税額を確認することもできます。
消費税の仕訳に用いる勘定科目
消費税の仕訳にあたっては、未払消費税の他にもさまざまな勘定科目を使用します。ここからは、消費税の仕訳に用いる勘定科目について見ていきましょう。
租税公課
租税公課は、国税や地方税などの「租税」と、国や地方公共団体、その他公共団体に納める罰金や会費に当たる「公課」を示す費用の勘定科目です。
租税公課を用いるのは、消費税の経理処理に税込経理方式を選択した場合で、日々の仕訳では税込価格で記帳し、申告納税した消費税額をまとめて租税公課として費用計上します。なお、税抜経理方式では、消費税の仕訳に租税公課を用いることはありません。租税公課は、損益計算書の「販売費及び一般管理費」に記載されます。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
仮払消費税
仮払消費税は、課税仕入にかかる消費税額を処理する勘定科目で、税抜経理方式を選択した場合に使用します。商品などの仕入を行ったり経費を支払ったりしたとき、税抜経理方式では本体価格と消費税額を分けて処理し、支払った消費税額を仮払消費税として計上します。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
仮受消費税
仮受消費税は、課税売上にかかる消費税額を処理する勘定科目です。仮払消費税と同様に、税抜経理方式を選択した場合に使用します。税抜経理方式では、商品やサービスを販売したとき、売上代金と消費税額を分け、受け取った消費税額を仮受消費税として記帳します。
決算の際には、仮受消費税から、前述した仮払消費税を差し引いて、消費税の納付額を求めることが必要です。差し引いた額がプラスなら、仕入などで支払った消費税より消費者から預かった消費税の方が多いことを表すため、その金額を納付します。反対にマイナスなら、支払った消費税の方が多いため、還付を受けられます。なお、仮受消費税と仮払消費税は決算で消去されるため、決算書には記載されません。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
未払消費税
未払消費税は、決算にあたり確定した消費税の未払額を計上する勘定科目です。税抜経理方式では、決算時に仮受消費税から仮払消費税から差し引き、その残額を未払消費税として計上します。未払消費税は、貸借対照表の「流動負債」に記載されます。
未収消費税
未収消費税は、還付予定の消費税額を計上する勘定科目です。決算時に仮受消費税から仮払消費税を差し引いたとき、その残額がマイナスだった場合、要件を満たせば消費税の還付を受けられます。この場合は、決算時に、還付予定の金額を未払消費税で仕訳することが必要です。未収消費税は、貸借対照表の「流動資産」に記載されます。
未払消費税の仕訳方法
ここからは、未払消費税の仕訳方法について、具体的に紹介します。未払消費税の仕訳方法は、税込経理方式と税抜経理方式で異なります。それぞれのケースごとに仕訳例を見ていきましょう。
税込経理方式のケース
税込経理方式では、期末に未払消費税を計上しない場合(原則)と、計上する場合(例外)があります。それぞれの仕訳例を紹介します。
未払消費税を計上しない場合
税込経理方式では、原則として決算時の仕訳は不要です。申告書が提出された日の属する事業年度(翌期)に租税公課を経費計上するため、決算時に未払消費税の計上は行いません。そのため、仕訳をするのは、実際に消費税を納付したときになります。
例えば、決算時に消費税額を算定し、納付すべき消費税額が5,000円と確定した場合は、仕訳は行いません。決算時に確定した消費税額5,000円を、現金で納めた場合の仕訳例は以下のとおりです。
納付時の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
翌期に確定納付額を支払った際は、租税公課で処理します。口座から支払った場合は、貸方科目に「普通預金」を用いましょう。
未払消費税を計上する場合
税込経理方式の例外として、決算時に確定納付額を未払計上する場合は、未払消費税の勘定科目を用います。決算で未払処理をしたときはその経理をした事業年度(当期)で経費計上が可能です。決算時に消費税額を算定し、納付すべき消費税額が5,000円と確定した場合の決算時の仕訳例と、決算時に確定した消費税額5,000円を、現金で納めた場合の納付時の仕訳例は以下のとおりです。
決算時の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 5,000円 | 未払消費税 | 5,000円 |
納付時の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払消費税 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
税抜経理方式のケース
税抜経理方式で仕訳する場合は、課税売上にかかる消費税額(仮受消費税)と課税仕入にかかる消費税(仮払消費税)の差額を未払消費税で処理します。当期の仮受消費税は1万5,000円、仮払消費税は1万円だった場合を例にして見ていきましょう。決算時に仮受消費税と仮払消費税の精算を行い、納付額5,000円が確定した場合と、決算時に確定した消費税額5,000円を、現金で納めた場合の納付時の仕訳例は、以下のとおりです。
決算時の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮受消費税 | 15,000円 | 仮払消費税 | 10,000円 |
| 未払消費税 | 5,000円 | ||
納付時の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払消費税 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
消費税の中間申告における仕訳
消費税の申告・納付には、確定申告と中間申告があります。確定申告とは、事業年度ごとに納めるべき税金の額を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。中間申告は、事業年度の途中で、その期の税金の一部を納めることを指します。
消費税は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税を除いた確定消費税額が48万円を超えた事業者に中間申告が必要になります。消費税の中間申告の回数は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、年間に1回、3回、11回のいずれかです。また、中間申告の義務がなくても「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄の税務署に提出することで、中間申告が可能になります。
なお、消費税の中間申告を行ったときにも仕訳は必要です。中間申告における仕訳方法も、税込経理方式と税抜経理方式で異なります。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
税込経理方式のケース
税込経理方式の場合は、中間申告で納めた額を租税公課で処理します。期中の納付なので、未払消費税は使用しません。中間消費税12万円を現金で納めた場合の仕訳例は以下のとおりです。
中間申告の納付時の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 120,000円 | 現金 | 120,000円 |
税抜経理方式のケース
税抜経理方式で中間申告を行った場合は、決算時の仕訳も変わってきます。税抜経理方式の場合、中間消費税を支払ったときは、仮払金または仮払消費税で仕訳します。中間消費税12万円を現金で納めた場合の仕訳例は以下のとおりです。
中間申告の納付時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮払金 | 120,000円 | 現金 | 120,000円 |
既に支払った中間消費税は決算時に精算し、確定納付税を未払消費税として計上します。
なお、仮受消費税と仮払消費税の差額が、常に未払消費税の金額と一致するとは限りません。消費税の計算では端数を切り捨てることから、少額の差額が生じることがあります。端数の処理によって差額が出た場合は、「雑収入」もしくは「雑損失」として処理します。
決算時における仮払消費税の残高は20万円、仮受消費税の残高は40万円、中間納付額は12万円、確定した消費税の納付額は7万9,800円だった場合の仕訳例は以下のとおりです。
決算時の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮受消費税 | 400,000円 | 仮払消費税 | 200,000円 |
| 仮払金 | 120,000円 | ||
| 未払消費税 | 79,800円 | ||
| 雑収入 | 200円 | ||
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
消費税の仕訳には会計ソフトの利用がおすすめ
未払消費税は、将来納付する予定の消費税額を処理する際に用いる勘定科目です。決算時に確定した消費税額は翌期に納付しますが、未払消費税を計上すれば当期の費用計上ができます。ただし、消費税の仕訳は、税込経理方式か税抜経理方式かによって処理方法が変わってくるほか、税込経理方式と税抜経理方式のどちらが適しているかは、事業者によって異なります。税抜経理方式は、税込経理方式に比べて記帳が複雑になりますが、会計ソフトを利用して効率化すると手間の軽減が可能です。会計ソフトなら納税額も自動で計算できるので、ミスや漏れの心配もありません。「弥生会計 Next」などの会計ソフトを上手に活用して、消費税の仕訳を効率良く行いましょう。
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。










