社会保険料の勘定科目は?仕訳例や仕訳時の注意点と共に解説
監修者: NA税理士法人
更新
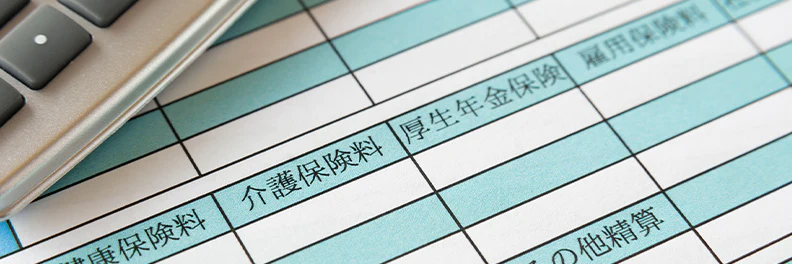
従業員が負担する社会保険料は、企業が毎月の給与から徴収(天引き)し、本人に代わって納めます。また企業側は、事業主負担分の社会保険料を納める義務もあります。
このように、社会保険料を徴収したり、納めたりしたときには、適切な勘定科目で仕訳をしなければなりません。給与から天引きした社会保険料と、企業が負担する社会保険料では、勘定科目が異なるため注意が必要です。
本記事では、社会保険料の仕訳に用いる勘定科目や社会保険料の仕訳方法、仕訳時の注意点などを解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
社会保険料とは社会保険の加入者が納める保険料のこと
社会保険料とは、社会保険の加入者が納める保険料のことです。社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの保険を指します。このうち、従業員と企業がそれぞれの負担割合に応じて保険料を支払う保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険の4つです。労災保険のみ、保険料の全額を企業が負担します。
株式会社や合同会社などの法人は、従業員の人数を問わず、社会保険の加入義務のある「強制適用事業所」となります。同時に、社会保険の加入条件を満たす従業員は、社会保険に加入して保険料を納めなければなりません。従業員負担分の社会保険料は、企業が月々の給与から徴収(天引き)したうえで、事業主負担分と合わせて納めます。そのため、従業員が自分で納付手続きをすることはありません。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
社会保険料の勘定科目は?
社会保険料の勘定科目は、従業員負担分と事業主負担分で異なります。前述したように、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険は、従業員と企業の双方が保険料を負担します。健康保険、厚生年金保険、介護保険は労使折半です。雇用保険料の負担割合は事業内容によって異なりますが、従業員よりも事業主の負担の方が多く設定されています。
事業主負担分の社会保険料を処理する勘定科目は、「法定福利費」です。それに対し、従業員の給与から徴収した社会保険料(従業員負担分)は、「預り金」または「法定福利費」で計上します。預り金とは、他者から預かったお金のことで、所得税の源泉徴収の際にも用いられる勘定科目です。また、法定福利費は、企業に負担が義務付けられている保険料などを指します。
社会保険料のうち、事業主負担分については費用計上が可能ですが、従業員負担分は本人の代わりに企業が納めているだけなので、費用にはなりません。社会保険料を仕訳するときは、事業主負担分と従業員負担分をきちんと区別し、適切な勘定科目で処理することが大切です。
社会保険料の勘定科目は、事業主負担分と従業員負担分で、それぞれ以下のとおりです。
| 区分 | 勘定科目 |
|---|---|
| 事業主負担分 | 法定福利費 |
| 従業員負担分 | 法定福利費または預り金 |
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
社会保険料の仕訳例
社会保険料の仕訳は、どのように行えばよいのでしょうか。ここからは、社会保険料の仕訳方法について、具体的な例をあげながら解説していきます。
企業負担分を未払費用に計上する場合の仕訳例
厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料の納付期限は、対象月の翌月末となります。例えば、4月分の保険料であれば、5月末日が納付期限です。
日本の会計ルールでは、費用については発生主義、売上・収益については実現主義で計上するのが原則です。発生主義は、実際にお金が動いたときではなく、取引が発生したタイミングで帳簿に記録する方法で、実現主義は、実際に代金などによって収益を得る権利が確定した時点で、収益を確定する方法を指します。
事業主負担分の社会保険料は費用なので、納付時ではなく対象月に、「未払費用」として計上します。例えば、社会保険料の事業主負担分30万円を未払計上した場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 300,000 | 未払費用 | 300,000 |
なお、雇用保険料と労災保険料については、原則として毎年1度、概算の申告と納付を行い、その後、金額が確定してから差額を調整します。これを「年度更新」といいます。年度更新の時期は、毎年6月1日から7月10日の間です。
そのため、雇用保険料と労災保険料を、他の社会保険料と分けて仕訳することもあります。なお、雇用保険と労災保険の2つをまとめて、労働保険と呼びます。
例えば、社会保険料の事業主負担分30万円のうち、労働保険料4万5,000円とその他の社会保険料を分けて仕訳した場合の仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 255,000 | 未払費用 | 255,000 |
| 法定福利費 (労働保険料) |
45,000 | 未払費用 (労働保険料) |
45,000 |
従業員負担分を預り金に計上する場合の仕訳例
従業員負担分の社会保険料は、月々の給与から徴収します。その後、事業者負担分と従業員負担分を合わせて、社会保険料を納付します。
従業員負担分に「預り金」の勘定科目を使用することで、企業と従業員がそれぞれ負担する社会保険料を明確に区別することができます。
例えば、給与25万円の従業員から4万円の社会保険料を徴収した場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与 | 250,000 | 普通預金 | 210,000 |
| 預り金 | 40,000 | ||
また、事業主負担分と従業員負担分の社会保険料を納付した場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 40,000 | 普通預金 | 80,000 |
| 預り金 | 40,000 | ||
事業主負担分の法定福利費と、従業員から預かった社会保険料は、まとめて普通預金から支出します。社会保険料を現金で納めた場合は、貸方の勘定科目は「現金」になります。
従業員負担分を法定福利費に計上する場合の仕訳例
従業員負担分の社会保険料を「法定福利費」の勘定科目で計上する場合も、基本的な流れは同じです。まず、従業員の給与から社会保険料を徴収し、その後、事業主負担分と合わせて納付します。
例えば、給与25万円の従業員から4万円の社会保険料を徴収した場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与 | 250,000 | 普通預金 | 210,000 |
| 法定福利費 | 40,000 | ||
社会保険料を納付するときには、事業主負担分と従業員負担分を合算し、法定福利費として借方計上します。この処理によって、事業主負担分の社会保険料だけが、法定福利費として費用計上されることになります。
例えば、事業主負担分の社会保険料4万円と従業員負担分の社会保険料4万円を納付した場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 80,000 | 普通預金 | 80,000 |
なお、現金で納付した場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。
従業員負担分の社会保険料を計上するタイミングは?
給与から徴収する従業員負担分の社会保険料を、どのタイミングで計上するかは、会計処理を「発生主義」と「現金主義」のどちらで行っているかで変わります。発生主義とは、前述したように、費用や収益が発生したタイミングで会計帳簿に記録する方法です。それに対して、現金主義とは、実際に金銭のやりとりが起こったときに費用や収益を計上する方法です。
法人も個人事業主も、原則的には、発生主義で会計処理を行います。ただし、発生主義だけでは収益を正しく認識できない場合があるため、売上・収益の記帳に関しては、発生主義をさらに制限した「実現主義」が採用されています。実現主義とは、実際に商品の引き渡しやサービスの提供が行われ、代金を受け取る権利が確定した時点で帳簿付けをする方法のことをいいます。
税務上、現金主義での記帳が認められるのは、一定条件を満たした個人事業主のみです。ただし、自社の経営状況を把握するために企業が独自で行う管理会計であれば、現金主義を採用しても問題はありません。
ここからは、給与の支払いを「月末締め、翌月25日払い」としている企業の1月給与を例に、発生主義と現実主義のケースごとに、社会保険料の仕訳の流れを解説します。なお、社会保険料は、労使のどちらの負担分も4万円とします。
関連記事
発生主義に則って計上した場合の仕訳例
発生主義の場合、1月末の締め日時点で社会保険料を計上します。そして、納付期限の2月末に、事業者負担分と従業員負担分の社会保険を納付する仕訳を行います。
例えば、従業員負担分の社会保険料を「預り金」で計上した場合と、「法定福利費」で計上した場合に分けたときの仕訳例は、以下のとおりです。
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与の計上 | 給与 | 250,000 | 未払費用 | 210,000 |
| 預り金 | 40,000 | |||
| 社会保険料の計上 | 法定福利費 | 40,000 | 未払費用 | 40,000 |
| 給与の支給 | 未払費用 | 210,000 | 普通預金 | 210,000 |
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料の納付 | 未払費用 | 40,000 | 普通預金 | 80,000 |
| 預り金 | 40,000 | |||
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与の計上 | 給与 | 250,000 | 未払費用 | 210,000 |
| 法定福利費 | 40,000 | |||
| 社会保険料の計上 | 法定福利費 | 80,000 | 未払費用 | 80,000 |
| 給与の支給 | 未払費用 | 210,000 | 普通預金 | 210,000 |
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料の納付 | 未払費用 | 80,000 | 普通預金 | 80,000 |
現金主義に則って計上した場合の仕訳例
現金主義の場合は、実際のお金の動きに従って仕訳を行います。従業員負担分の社会保険料を「預り金」で計上した場合と、「法定福利費」で計上した場合に分けたときの仕訳例は、以下のとおりです。
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与の計上 | 給与 | 250,000 | 未払費用 | 210,000 |
| 預り金 | 40,000 | |||
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与の支給 | 未払費用 | 210,000 | 普通預金 | 210,000 |
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料の納付 | 法定福利費 | 40,000 | 普通預金 | 80,000 |
| 預り金 | 40,000 | |||
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与の計上 | 給与 | 250,000 | 未払費用 | 210,000 |
| 法定福利費 | 40,000 | |||
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与の支給 | 未払費用 | 210,000 | 普通預金 | 210,000 |
| 内容 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料の納付 | 法定福利費 | 80,000 | 普通預金 | 80,000 |
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
社会保険料の仕訳を行う際の注意点
同じ社会保険料でも、厚生年金保険、健康保険、介護保険は月1回、雇用保険と労災保険は年1回と、納付タイミングが異なるため注意しましょう。
社会保険料のうち、厚生年金保険、健康保険、介護保険の3つの保険料は、対象月の翌月末までに日本年金機構に納付することになっています。それに対して、労働保険と呼ばれる雇用保険料と労災保険料の納付時期は、原則として年1回です。労働保険の保険料の納付は、事前に見込み額を納めておいて、差額を精算する「年度更新」によって行われます。
さらに、労働保険の中でも、労災保険料は全額事業主負担ですが、雇用保険料は従業員も一定割合を負担します。つまり、雇用保険料に関しては「徴収は月1回、納付は年1回」というイレギュラーな形になるということです。計上タイミングを間違えないように、労働保険料は他の社会保険料と分けて仕訳するのがおすすめです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
社会保険料の勘定科目を理解して正しく仕訳をしよう
社会保険料とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の保険料のことです。労災保険を除く社会保険料は、従業員負担分を給与から徴収し、事業主負担分と合わせて企業が納付します。社会保険料の事業主負担分を計上するときや、従業員負担分を徴収するとき、労使双方の負担分を合わせて納めるときは、それぞれ適切な勘定科目で仕訳を行う必要があります。
事業主負担分の社会保険料は、「法定福利費」の勘定科目を使います。その一方で、従業員負担分は、「法定福利費」または「預り金」で計上します。どちらを用いても問題ありませんが、より明確に管理するのであれば、「預り金」を使用する方がいいでしょう。
煩雑になりがちな社会保険料の仕訳も、会計ソフトを活用すればスムーズに進めることができます。社会保険料の仕訳の効率化のために、弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ











