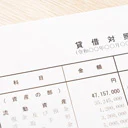資本準備金とは?資本金との違いやメリット、注意点などを解説
更新

株式会社の設立や株式の発行に際して資金が払い込まれたときには、資本金とは別に「資本準備金」を積み立てることが認められています。資本金は事業の元手になる資金で、企業を設立する際には必ず用意しなければならないものです。企業の設立や運営にあたり、資本金のことは知っていても、資本準備金についてはよくわからないという方も多いのではないでしょうか。資本準備金は、上手に活用すると税制面や増資手続きなどにおいてメリットがあります。
本記事では、資本準備金と資本金や資本剰余金との違いの他、資本準備金を計上するメリットと注意点についても解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資本準備金とは資本金として組み入れられなかった部分のこと
資本準備金とは、株主から払い込まれた資金のうち、資本金に組み入れられなかった部分のことです。企業設立や株式発行の際に株主から払い込まれた金額は、全額を資本金としたり、資本金と分けて一部を資本準備金としたりすることも可能です。
ただし、資本準備金とすることができる金額には条件があります。会社法では、資本準備金の額について、「資本金の2分の1を超えない金額」と定められています。例えば、企業設立時の資金が1,500万円あった場合、最大750万円まで資本準備金として計上できるということです。
また、企業設立や株式の発行に際して払い込まれた金額のうち、資本金に計上しなかった部分の金額を、資本準備金以外に計上することはできません。資本金に計上されなかった額は、必ず資本準備金に計上する必要があります。
資本準備金の大きな目的は、万が一のときの準備金とすることです。事業を続けていく中で、多額の支出や赤字が発生することがあるかもしれません。そのようなとき、資本金を取り崩すと、株主総会の特別決議や変更登記の手続きが必要になり、手間とコストがかかります。資本準備金を計上していれば、手続きも比較的スムーズです。資本準備金には他にもさまざまなメリットがありますが、詳しくは後述します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資本金との違い
資本金と資本準備金は、どちらも株主から払い込みを受けた資金であり、貸借対照表上の「純資産の部」に記載されます。そのため、資本金と資本準備金は同じようなものと考える方もいるかもしれません。確かに、資本金も資本準備金も、返済の必要がない自己資本という点では同じです。しかし、資本金と資本準備金には、役割や金額、登記に違いがあります。資本金と資本準備金との違いについて詳しく見ていきましょう。
役割の違い
資本準備金が多額の赤字など万が一のときの準備金なのに対して、資本金は事業を運営していくための元手となる資金というのが、資本準備金と資本金の主な役割の違いです。なお、資本金は企業体力や信用度を表す指標にもなります。初めて取引をする企業の与信を確認する際や、金融機関から融資を受ける際には、資本金が判断材料の1つになるケースが多々あります。実際の資本金の役割はさておき、一般的なイメージとして資本金が大きければ安定した経営を行っていると判断され、小さければ事業を運営する資金がない、返済能力が低いなどと見なされる可能性があるでしょう。
また、資本金は、株式会社設立時に必ず用意しなければならないもので、株式会社設立登記の申請にあたっては、資本金の払い込みを証明する書類を提出する必要があります。その一方で、資本準備金は企業が任意で計上できるものです。そのため、企業設立時に用意した資金をすべて資本金とし、資本準備金を計上しなくても問題はありません。
金額の違い
資本金と資本準備金は、金額の定めにも違いがあります。資本金には下限の規定がなく、法律上は1円から株式会社設立が可能です。また、資本金には上限の定めもありません。ただし、詳しくは後述しますが、資本金の額が一定額以上になると税制面でさまざまな影響を受けます。
それに対して、資本準備金には「資本金の2分の1を超えない金額まで」という上限の定めがあります。下限の規定はなく、そもそも資本準備金は必須ではないため、0円でもかまいません。
登記の違い
資本金と資本準備金は、登記事項も違いの1つです。資本金の額は、登記事項に含まれており、登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されます。そのため、資本金の額を変更する場合は、変更登記の手続きと、所定の登録免許税が必要になります。また、資本金の額を減少させる(減資)には、原則として株主総会の特別決議が必要です。
その一方で、資本準備金の額は登記事項には該当しません。資本準備金に増減があっても、変更登記の手続きや登録免許税は不要な他、資本準備金を取り崩す場合も、株主総会の普通決議のみで済みます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資本剰余金との違い
資本金や資本準備金と似たものに「資本剰余金」があります。資本剰余金も、資本金や資本準備金と同様に、貸借対照表上の純資産の部に記載されます。
資本剰余金は、株主から払い込まれた資金のうち、資本金に組み入れられなかった資本準備金と、増資や減資、自社株式の取得や処分などの資本取引によって発生した剰余金を中心とする「その他資本剰余金」からなります。つまり、資本準備金は、資本剰余金に含まれるということです。
なお、資本金と資本準備金は株主への配当の原資にはできませんが、その他資本剰余金は配当の原資として認められています。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資本準備金を計上するメリット
資本準備金の計上は義務ではありませんが、資本準備金を計上しておくと、さまざまなメリットがあります。税制における優遇措置や赤字の補填、資本金の増資などに関するメリットについて見ていきましょう。
税制における優遇措置を受けられる
資本金の額は、消費税や法人住民税、法人税といった税金に影響します。資本準備金を計上して資本金の額を一定以下に抑えることで、これらの税金に対する優遇措置が受けられます。
消費税
資本金が1,000万円未満で設立された企業は、原則として、設立1期目と2期目の消費税の申告・納付の義務が免除されるメリットがあります。その一方で、企業設立時の資本金が1,000万円以上の場合は、設立1期目から消費税の納税義務が生じます。
なお、資本金が1,000万円未満で消費税の納税義務が免除されても、1期目の前半6か月の売上または人件費(役員報酬含む)支払額が1,000万円を超えた場合は、2期目から消費税の納税義務は免除されません。また、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するために適格請求書発行事業者の登録を行った場合は、登録日以後については資本金や売上などの額にかかわらず1期目から消費税の申告・納付が必要になります。
法人住民税
法人住民税には、赤字でも必ず納めなければならない「均等割」という税金があり、資本金の額と資本準備金額の額の合計額が1,000万円を超えると課税額が大きくなります。例えば、東京都23区で従業員数が50人以下の法人の場合、資本金と資本準備金額の額の合計額が1,000万円以下なら均等割の年額は7万円ですが、資本金と資本準備金額の額の合計額が1,000万円を超えると均等割の年額は18万円になります。
法人税
法人税の税率は、資本金が1億円を超えるかどうかで大きく変わります。資本金1億円以下の法人は、年間所得が800万円以下なら所得税率は15%、800万円を超える部分については23.2%です。その一方で、資本金が1億円を超える法人は、年間所得額にかかわらず所得税率が一律23.2%となります。
資本準備金を計上することで資本金額を低くすれば、これらの優遇措置を受けやすくなります。例えば、企業設立時の資金が1,500万円ある場合、750万円を資本金、750万円を資本準備金とすれば、資本金が1,000万円未満になり、消費税の納税義務の免除を受けることが可能です。
ただし、資本金の額が極端に少なくなると、対外的な信用力が低下するおそれがあるため注意しましょう。
スムーズに赤字の補填が可能
資本準備金を計上していると、スムーズに赤字の補填ができるというメリットもあります。事業を運営していると、多額の赤字が発生したり、累積赤字が大きくなってしまったりすることがあるかもしれません。資本金を取り崩して赤字を補填すると、減資という扱いになり、株主総会での特別決議や定時株主総会での普通決議、変更登記の手続きが必要になります。そのような場合に、資本準備金が計上されていれば、資本金を取り崩すことなくスムーズに赤字を補填できます。
資本金の増資ができる
企業の成長や事業の拡大に伴い、資本金を増額したいと考えることもあるでしょう。資本準備金を計上しておくと、そのような増資にあたって役立つこともメリットの1つです。
増資をするには、株主から資本の払い込みを受けるか、資本準備金を資本金に振り替えるという2つの方法があります。ただし、資本の払い込みを受けるには新たな出資者や出資金を募る必要があり、思うような結果が得られない可能性があります。それに対して、資本準備金を資本金に組み入れる方法であれば、株主総会の普通決議で対応できるため、確実かつスムーズな増資が可能です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資本準備金を計上する際の注意点
資本準備金にはメリットがある一方で、注意点もあります。企業の状況や業種などによっては、資本準備金の計上額が事業に影響を及ぼすことも考えられます。資本準備金を計上する場合には、以下の注意点を確認しておきましょう。
事業によっては資本金の最低金額が決まっている
事業によっては、営業にあたって所定の行政機関による許認可が必要で、許認可の要件の中には、資本金の額に縛りがあることがあります。許認可の要件に最低資本金額の定めがある場合は、資本準備金の計上にも注意しましょう。
資本金が許認可の要件に含まれる例としては、貨物利用運送業が300万円以上、一般建設業が500万円以上、有料職業紹介業が事業所につき500万円以上、などがあげられます。このような業種の場合、資本金の金額が要件を満たさないと許認可がおりず、事業を行えなくなります。ただし、許認可によっては資本金と資本準備金を合算した自己資本で判断するケースもあります。例えば上記の貨物利用運送業や有料職業紹介事業、一般建設業は、厳密には資本金ではなく資本準備金も合算した自己資本の額で判断します。
資本金を減らしすぎると事業規模が小さいと判断されることもある
資本金の額は、企業の社会的な信用度にかかわります。一般的に、資本金が大きければ企業の体力に余裕があると見なされ、取引先や金融機関からも信用を得やすくなりますが、資本金が少ないと、財務の安定性が疑問視されてしまうことがあります。実際に払い込まれた金額は「資本金+資本準備金」であっても、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されるのは資本金だけです。そのため、資本準備金を多く計上して資本金が少なくなった場合、事業規模が小さいと判断される可能性があります。
特に大企業などでは、初めて取引をする企業の与信を確認する際に、資本金の額を見て信頼性を判断するケースも少なくありません。資本準備金の計上により資本金額を減らしすぎると、新規の相手と取引ができなくなる可能性があるため注意しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資本準備金の特徴を理解して上手に活用しよう
資本準備金とは、株主から払い込まれた資金のうち、資本金として組み入れられなかった部分のことです。企業設立や株式発行の際に株主から払い込まれた資金は、資本金の2分の1を超えない範囲であれば、資本準備金として計上することが認められています。
資本準備金は、資本金と同様に返済の必要がない自己資金であり、万が一のときの準備金の役割を持つ資金です。赤字を補填したり、資本金を増額したりする際も、資本準備金を計上していればスムーズに対応できます。また、払い込まれた金額のうちの一部を資本準備金とし、資本金を一定額以下に抑えることで、税制面での優遇が受けられることもメリットです。その一方で、資本準備金を計上したことによって、資本金額が少なくなりすぎると、必要な許認可が受けられなかったり、企業の信用力が低下してしまったりする可能性があります。資本準備金の特徴を正しく理解したうえで、資本金額とのバランスを考え、上手に活用するようにしましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。