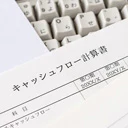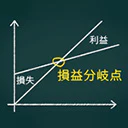資金繰り表とは?作り方や作成するメリットなどを解説
更新

事業を継続的に安定運営するには、資金繰りが重要な課題となります。資金繰りの管理に役立つ資料としては、過去から将来に向けて現金の流れを把握できる資金繰り表があげられます。資金繰り表は、過去の実績データをまとめるだけでなく、将来の資金計画を可視化する点が特徴です。
本記事では、資金繰り表を作成するメリットや作り方の他、キャッシュ・フロー計算書との違いについて解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資金繰り表とは、事業者の一定期間における現金の収入や支出を管理する集計表
資金繰り表とは、事業者の一定期間における現金・預金の収入や支出をまとめ、現金の流れを可視化するために作成される集計表のことです。一定期間内に発生したすべての現金の収入や支出をそれぞれ分けて集計することにより、収支状況や現金の過不足といった実態の把握に役立ちます。
資金繰り表は毎月作成するのが基本です。資金の増減を随時記録することで、計画的な経営が可能になります。企業間取引では、売上・仕入のタイミングと実際の入金・出金のタイミングがずれるため、現金が現状どのくらいあるのかを把握することが大切です。また、近い将来どういった現金の動きが生じるのかを予測できるようにしておきましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資金繰り表とキャッシュ・フロー計算書の違い
資金繰り表とキャッシュ・フロー計算書は、構成が似ている部分があるため混同されがちですが、書類を作成する目的が異なります。キャッシュ・フロー計算書を作成する目的は、現在までの現金の流れを把握することです。これに対して、資金繰り表は将来の予測を含む現金の流れを見るために作成されます。
キャッシュ・フロー計算書は、貸借対照表や損益計算書と共に財務三表の1つです。営業活動、投資活動、財務活動の3つについて、それぞれの現金の流れがまとめられています。上場企業においては、キャッシュ・フロー計算書の作成が義務付けられています。中小企業に関しては作成が義務付けられていないため作成しているケースは数少ないです。
資金繰り表は、現在までの現金・預金の流れと今後の予測をまとめた資料です。現状だけでなく、将来の予測まで含めて現金の流れを可視化する点がキャッシュ・フロー計算書と大きく異なります。なお、資金繰り表は、上場企業や中小企業といった企業規模を問わず法的な作成義務はありません。その一方で、資金の現状をリアルタイムに把握しつつ将来の資金の状態を予測できる資金繰り表は、資金繰りに悩むことが多い中小企業に適した資料といえるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資金繰り表を作成するメリット
お金の流れが可視化される資金繰り表を作成する主なメリットとしては、以下の3つがあげられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
収支予定を把握できる
資金繰り表を作成するメリットは、収支予定を把握できることです。
今後の収支金額を予測・記載することにより、将来的な資金ショートの防止や適切な資金調達につながります。現金の流れを可視化することで、問題の早期発見や手持ち現金の管理がしやすくなり、黒字倒産の予防にも役立ちます。黒字倒産とは、会計上は黒字にもかかわらず、現金がないために期日までに支払を行えず倒産してしまうことです。
例えば、売上が500万円(現金100万円、売掛金400万円)、仕入が300万円(買掛金300万円)、その他の経費が50万円(現金払い)の企業を例として、黒字倒産のしくみについて紹介します。この企業の場合、帳簿上は「500万円-300万円-50万円=150万円」の利益が出ていますが、実際に手元にある現金は「100万円-50万円=50万円」だけです。この状態で、売掛金が入金される日より先に買掛金の支払日を迎えてしまうと、支払ができなくなってしまうおそれがあり、黒字倒産に至る典型例といえるでしょう。
その点、資金繰り表に一連の現金の流れが記録されていれば、資金不足に陥るリスクの有無を早期に察知できます。結果として、融資の申込みなど資金ショートを防ぐための対策を早期に講じることが可能です。このように、資金繰り表を作成して収支予定を正確に把握することは、黒字倒産を防ぐためにも重要なポイントといえます。
資金繰りにおける改善点が見つかる
資金繰りにおける改善点が見つかることも、資金繰り表を作成するメリットのひとつです。
例えば、売掛金の回収期間が長かったり、買掛金の支払期日が短かったりするなど、資金繰りに関する問題点はできるだけ早期に洗い出しておく必要があります。そのうえで、収支と支出の改善点について対策を講じておかなくてはなりません。
こうした問題点を資金繰り表から察知できれば、支払期日や入金期日を取引先と交渉したり、金融機関からの資金調達を行ったりするなど、資金不足を防ぐための適切な対策を講じられます。資金ショートのリスクに見舞われることのないよう先手を打って改善策を講じられることは、資金繰り表を作成するメリットといえるでしょう。
金融機関からの融資がスムーズになりやすい
金融機関から融資を受ける際に、説得力のある説明をするのに役立ち、融資がスムーズになりやすいことも、資金繰り表を作成するメリットとしてあげられます。
金融機関に融資を申し込む際には、融資を受ける理由を論理的に説明できる状態にしておかなければなりません。資金繰り表を作成することで、将来的な資金計画や売掛金の回収見込みを明確に伝えやすくなります。将来の資金計画を立てることは、客観的で説得力のある説明をするうえで重要なポイントです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資金繰り表を作成する際に用意するもの
資金繰り表を作成するにあたっては、月次試算表、現金出納帳、預金出納帳の3つの書類を用意する必要があります。それぞれの書類の主な役割と資金繰り表の作成に役立つ理由を見ていきましょう。
月次試算表:月別の経営活動を管理する
月次試算表とは、月別の経営活動を管理するための試算表のことです。貸借対照表と損益計算書の2つから構成されたものを、1か月単位で作成します。月ごとの収支がまとめられているため、経営上の課題を定量的に把握するうえで役立つ書類です。
月次試算表を確認することで未回収の売掛金や不良在庫などの状況がわかるため、自社の経営状態を把握するのはもちろんのこと、納税額の予測などにも活用されます。また、金融機関が融資の審査を行う際にも参考資料として提出を求める場合があります。このように月単位で経営状態を把握するうえで役立つことから、月次試算表は資金繰り表を作成する際にも有効な資料の1つといえるでしょう。
試算表についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
現金出納帳:現金による入出金を記録する
現金出納帳とは、現金による入出金を記録するための帳簿です。帳簿の残高と現金残高が一致しているかを常に確認することで、小口現金などの適切な管理に役立ちます。入出金があった取引の内容や時期、取引先、用途などを可視化し、不正を抑止することも現金出納帳を作成・管理する目的の1つです。
現金出納帳で管理するのは主に少額の現金によるやりとりですが、1円単位で正確に経理業務を遂行するには欠かせない帳簿といえます。特に、正確性が求められる資金繰り表は、現金出納帳も必ず参照しつつ作成しなければなりません。
なお、現金出納帳に記載されている残高と実際の現金残高は、常に一致しているのが基本です。双方の金額が合わず、その原因が判明しない場合には「現金過不足」という勘定科目で一時的に処理することになります。その場合、残高が一致しない原因が判明しだい、しかるべき勘定科目へと振り替えて現金過不足を取り消す処理を行わなくてはなりません。金額の不一致の原因が期末までに判明しないようなら、「雑損失」もしくは「雑収入」として処理します。こうした不明の損失や収入が生じることのないよう、現金出納帳を適切に管理することが正確な資金繰り表を作成するうえで重要なポイントです。
現金出納帳についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
預金出納帳:預金口座における入出金を記録し残高を管理する
預金出納帳とは、預金口座における入出金を記録し、残高を管理するために作成される帳簿のことです。複数の法人口座がある場合には、すべての口座について預金出納帳を作成します。その際、複数の口座を1つの帳簿でまとめて管理するのではなく、口座ごとに管理するのが正確な残高管理のポイントです。
現金出納帳と同様に、預金出納帳に記録されている残高とその時点での口座残高は常に一致している必要があります。預金口座を介した取引の内容や時期、取引先、用途などを正確に記録し、可視化することが預金出納帳を作成する主な目的です。資金繰り表を正確に作成するには、預金出納帳に関しても適切に管理する必要があります。
預金出納帳についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資金繰り表の作り方
資金繰り表には標準的なフォーマットは存在しません。したがって、自社の状況に合わせて入出金の額や時期がひと目でわかるように作成する必要があります。資金繰り表の主な作成方法は以下のとおりです。
1. 雛形などを利用してフォーマットを作成する
はじめに、自社の状況に合った資金繰り表のフォーマットを作成します。Excelなどの表計算ソフトで作成することもできますが、インターネット上に数多く公開されている雛形を活用すると効率良く作成できるでしょう。
なお、資金繰り表のフォーマットは、経常収支・非経常収支・財務収支などの必要な項目が区分された、シンプルな作りにするのがポイントです。各項目は以下のように区分されます。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 経常収支 | 毎月経常的に発生する収入・支出 例)売上による収入、人件費、家賃、原材料費などの支出 |
| 非経常収支 | 毎月経常的に発生しない収入・支出 例)固定資産の売却益や購入に伴う支出、法人税などの支払による支出 |
| 財務収支 | 金融機関からの借入や返済の状況 |
さらに、各項目を以下のように分割して小項目を作成していきます。
経常収支の小項目例
- 前月繰越:前月末に確定した翌月繰越金額を反映したもの
- 現金売上:毎月の売上
- 売掛金回収:実際に入金された分の売上
- 買掛金支払:仕入のために支払った金額
- 人件費:経費のうち、人員に関するもの
- 諸経費:人件費以外の経費
- 支払利息等:支払に伴って発生した利息など
非経常収支の小項目例
- 設備投資:設備関連の収支
財務収支の小項目例
フォーマットを一度作成すれば、以後は数値を入力するだけで資金繰り表が作成できます。ただし、計算式の誤りや入力ミスが発生した場合、資金繰り表そのものが不正確なものになりかねません。そのため、正確かつ過不足のないフォーマットを作成する他、レイアウトは見やすく整える必要があります。こうした懸念を解消するには、資金繰り表の作成に対応した会計ソフトを活用するのがおすすめです。会計ソフトであれば、自社で計算式を設定したり、レイアウトを整えたりする工程を省略でき効率良く資金繰り表を作成できます。
2. 月次試算表や現金出納帳、預金出納帳を参考に数値を入力する
資金繰り表のフォーマットに沿って、月次試算表や現金出納帳、預金出納帳の各項目から、現金預金の入金・支出を転記していきます。転記の際には漏れや重複のないよう慎重に行うと共に、複数名によるチェックを実施しましょう。
なお、会計ソフトによっては、日々入力した入出金データが自動で反映される場合もあります。会計ソフトのこうした機能を活用することで転記漏れや重複を防ぐと共に、資金繰り表を効率良く正確に作成することが可能です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
資金繰り表を作成して、お金の流れを正確に把握しよう
資金繰り表は、過去から将来にわたる現金の流れを把握するために重要な資料となります。一定期間における現金・預金の収入・支出が集約されるため、収支状況や過不足の実態を可視化するうえで有効です。資金繰り表の作成・管理を通じて現金の流れをより正確に把握し、経営改善や資金繰りに役立ててみてはいかがでしょうか。正確な資金繰り表を効率良く作成するためには、会計ソフトの利用がおすすめです。「弥生会計 Next」の「資金予測機能」なら、AIによる資金予測により、事業の安定化をサポートします。ぜひ弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」をご活用ください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
よくあるご質問
資金繰り表とは何ですか?
資金繰り表とは、事業者の一定期間における現金・預金の収入や支出をまとめ、現金の流れを可視化するために作成される集計表です。一定期間内に発生したすべての現金の収入や支出をそれぞれ分けて集計することにより、収支状況や現金の過不足といった実態の把握に役立ちます。 詳しくはこちらをご確認ください。
資金繰り表とキャッシュフロー計算書との違いは?
資金繰り表は将来の予測を含む現金の流れを見るために作成されるのに対し、キャッシュ・フロー計算書は現在までの現金の流れを把握することを目的に作成されます。資金繰り表は、法的な作成義務はありませんが、キャッシュ・フロー計算書の作成は上場企業に対し義務付けられています。 詳しくはこちらをご確認ください。
資金繰り表を作成する目的は?
資金繰り表は、将来の予測を含む現金の流れを見るために作成されます。過去の実績データをまとめるだけでなく、将来の資金計画を可視化する点が特徴で、資金繰り表の作成・管理を通じて現金の流れをより正確に把握し、経営改善や資金繰りに役立てることができます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。