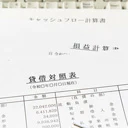税効果会計とは?メリットや手順、仕訳方法などを解説
更新

税効果会計とは、企業会計と税務会計のずれを調整する手続きのことです。企業の中には、決算時に税効果会計が適用される必要がある場合もあります。ただし、税効果会計はすべての企業に適用義務があるわけではありません。適用が義務付けられている企業の要件が定められているため、自社が該当するかを把握することが大切です。税効果会計を導入することで、企業はさまざまなメリットを得られます。適用義務のない企業であっても任意で導入できるので、税効果会計がどのようなものか正確に理解しておいたほうがいいでしょう。
本記事では、税効果会計を導入するメリットや種類、税効果会計を行う手順、仕訳方法などを解説します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
税効果会計とは会計のずれを調整して適切に損益を算定する手続きのこと
税効果会計とは、財務会計と税務会計のずれを調整し、適切に期間損益を算定する手続きのことです。
財務会計は、企業の業績を把握することを目的とした会計のことを指します。その一方で、税務会計は公平な課税を実現することが目的の会計です。両者間にはさまざまなずれが生じるケースがあるため、一般的に会計上の利益と税法上の課税所得は一致しません。
例えば、ある設備の耐用年数について、頻繁に使うA社が3年、B社はそれほど使わないため6年と設定した場合、これは各企業の実態に即して判断した結果であるため、企業会計上は問題ありません。しかし、税金の計算をするときに各企業がそれぞれ異なる耐用年数を設定していては、課税の公平性が崩れてしまいます。そのため、税務会計では減価償却資産の耐用年数が定められています。このような、会計上・税務上のずれを解消するための手続きが税効果会計です。
財務会計と税務会計のずれが大きくなると、利害関係者が企業の経営実態を正確に把握できない問題が生じます。こうした問題を解消するために導入されたのが税効果会計と捉えましょう。現在では、主に会社法上の大企業を中心に税効果会計の適用が義務化されています。適用義務がある企業の要件は以下のとおりです。
税効果会計の適用義務がある企業
- 上場企業
- 金融商品取引法の適用を受けている非上場企業
- 会計監査人を設置している企業(非上場企業を含む)
税効果会計のメリット
税効果会計を導入することで得られるメリットとして、「正確に当期純利益を把握できる」「経営指標の健全化が期待できる」「利害関係者に正確な情報開示ができる」の3つがあげられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
正確に当期純利益を把握できる
税効果会計のメリットは、当期純利益を正確に把握できることです。
税効果会計を適用することで財務会計と税務会計のずれが調整されるため、実際の業績が反映された会計上の当期純利益が把握できます。当期純利益とは、損益計算書で示されるその期の最終的な利益のことで、税引前当期純利益から法人税等の税金を差し引いて求めます。税効果会計を適用しない場合、ここで算出された法人税等の額は税務上のルールに基づいて計算されたもので、会計上必ずしも正しいとはいえません。
しかし、税効果会計で会計上と税務上のずれを調整することで、実際の業績が反映され、会計上より正確な当期純利益が把握できるようになります。当期純利益を正確に把握することは、自社の経営状態を正しく知るうえで重要なポイントです。
経営指標の健全化が期待できる
経営指標の健全化が期待できる点も税効果会計のメリットとしてあげられます。
税効果会計によって、前払した税金を「繰延税金資産」として貸借対照表上の資産に計上することで、資産が増えれば、帳簿上の自己資本比率の改善につながります。繰延税金資産は、会計と税務の認識の違いによって発生する、一時的な差異を調整するために使われる勘定科目です。
会計上は費用として支出している金額でも、税務上は損金として見なされず、その分税金を多く支払うことは決して珍しくありません。このような場合に、払いすぎた税金相当額を繰延税金資産として貸借対照表の資産の部に計上します。財産の総額に対する自己資本の割合を示す自己資本比率が高いほど、企業の経営は安定していると見なされるため、経営指標の健全化にも役立ちます。
ただし、繰延税金資産は将来の課税所得が黒字になり、税金を払える状況になることを前提としているため、赤字が続いている場合は健全化の効果は期待できず、資産計上できない場合もある点に注意しましょう。
利害関係者に正確な情報開示ができる
利害関係者に正確な情報を開示できる点も、税効果会計のメリットの1つです。
会計の本来の目的は、企業が事業収支などのお金の流れを記録し、その結果明らかになった財務状況や経営状態を利害関係者に報告することにあります。金融機関や投資家といった利害関係者の多くは、企業の財務状況や経営状態を決算書で確認します。しかし、決算書だけでは、会計上と税務上のずれが発生していても、実態が把握できません。そのため、税効果会計により正確な税引後の損益を決算書に示すことで、利害関係者に適切な情報を開示できるようになります。
税効果会計の種類
税効果会計の種類には「資産負債法」と「繰延法」という2つの方法があります。このうち、日本を含めた世界的な会計基準として採用されているのは資産負債法です。それぞれどのような方法なのかを見てみましょう。
資産負債法:会計上と税務上の資産金額の違いに着目する方法
資産負債法とは、会計上の資産金額と税務上の資産金額の違いに着目する方法のことです。
資産負債法は、税効果会計の処理方法として広く採用されています。具体的には、会計上と税務上の資産金額の違いによって生じる税額のずれを埋めるために、差異が発生した年度に「繰延税金資産」または「繰延税金負債」を計上し、その差異が解消されるまで毎期再計算を行います。このとき適用される税率は、ずれが解消されると想定される会計期間、つまり将来の税率です。
繰延法:企業会計と税務会計の期間の違いに着目する方法
繰延法とは、企業会計と税務会計の期間の違いに着目する方法のことです。
期間差異に対する税額を「繰延税金資産」または「繰延税金負債」として計上し、再計算します。会計上の収益・費用と税務上の益金・損金は、同じタイミングで計上されるとは限りません。繰延法は、会計上と税務上の期間の違いによって起こるずれについて、そのずれが解消するまでの措置といえます。このとき適用される税率は、差異が生じた年度のものです。
税効果会計で生じる差異
税効果会計において調整される差異には、「一時差異」と「永久差異」の2種類があります。それぞれの違いをしっかりと理解しておきましょう。
一時差異:会計の認識や計上されるタイミングで発生するずれ
一時差異とは、会計の認識や計上されるタイミングによって発生する差異のことで、将来的に解消される差異が該当します。
例えば、会計上減価償却費を法定耐用年数より少ない年数で計上した場合でも、法定耐用年数が経過すれば税務上のずれは解消されます。そのため、最終的に計上された金額は法定耐用年数で計上した場合と変わりません。あくまでも一時的な差異であることから、一時差異として処理されるという考え方です。税効果会計の対象となるのは一時差異のみで、後述する永久差異は対象になりません。
なお、一時差異はさらに「将来減算一時差異」と「将来加算一時差異」に分けられます。将来減算一時差異とは、将来的に税金が減る結果をもたらす差異、将来加算一時差異とは、将来的に税金が増える結果をもたらす差異のことです。両者は別々に計算して管理する必要があります。
永久差異:企業会計と税務会計の計上基準の違いで生じるずれ
永久差異とは、財務会計と税務会計の計上基準の違いによって生じる差異のことです。
財務会計と税務会計ではそもそも会計処理の考え方が異なることから生じた差異は、時間の経過に伴って解消されるものではありません。例えば、損金算入限度額を超える交際費や寄附金の損金不算入部分などが該当します。なお、永久差異に関しては一過性のものではないことから、税効果会計の対象外です。
税効果会計を適用する手順
税効果会計を適用するためには手順があります。ここからは、税効果会計の基本的な手順について詳しく見ていきましょう。
1. 一時差異を集計する
はじめに、会計上の収益・費用と、税法上の益金・損金を確認して一時差異を集計します。
前述のとおり、会計上・税法上の計上するタイミングによる差異には一時差異と永久差異があるため、両者を見分けることが大切です。翌期以降に解消される一時差異の例として、貸倒引当金などの引当金の損金不算入額、減価償却費の損金不算入額、資産または負債の評価替えにより生じた評価差損などがあげられます。これに対して、寄附金の損金不算入額、交際費の損金不算入額など、実際に収入や支出のあったものは将来においても解消されない永久差異に該当します。
2. 繰延税金資産や繰延税金負債を算出する
集計した一時差異に法定実効税率を掛けて、繰延税金資産や繰延税金負債を算出します。
法定実効税率とは、税務会計上の法人税、住民税、事業税の表面税率を基に算出される税率のことです。使用される法定実行税率は、差異が解消されると見込まれる期の税率となります。なお、繰延税金資産は将来的に会計と税務のずれが解消されることが計上の要件になります。繰延税金資産を計上する際には、その回収可能性について十分検討しておきましょう。
3. 税効果会計の仕訳計上を行う
最後に、税効果会計の仕訳計上を行います。
仕訳計上を行う際には、繰延税金資産・繰延税金負債のどちらも相手勘定を法人税等調整額とし、損益計算書に調整科目として記載します。
以上が税効果会計の基本的な手順です。なお、税効果会計の導入については、顧問税理士・会計事務所など専門家への相談が欠かせません。導入する際には、手順についても顧問税理士などの指示に従うようにしてください。
税効果会計の仕訳方法
税効果会計では、差異の発生時と解消時にそれぞれ仕訳を行います。繰延税金資産と繰延税金負債の仕訳例をそれぞれ確認しておきましょう。
繰延税金資産の仕訳例
繰延税金資産とは、将来の税金の減額が見込まれる分を指す勘定科目です。そのため、企業会計と税務会計のずれの発生時には借方に「繰延税金資産」、貸方に「法人税等調整額」を計上します。また、ずれの解消時には借方に法人税等調整額、貸方に繰延税金資産を計上し解消します。
例えば、20万円の繰延税金資産が発生した場合と、その20万円が税務上の損金として認識され、繰延税金資産が解消した場合の仕訳例は以下のとおりです。
繰延税金資産が発生した場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 200,000円 | 法人税等調整額 | 200,000円 |
繰延税金資産が解消した場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法人税等調整額 | 200,000円 | 繰延税金資産 | 200,000円 |
繰延税金負債の仕訳例
会計上の利益が税務上の課税所得を上回った場合、その差額には翌期以降の会計期間で課税されることになります。このような、実質的な税金の後払(税金の未払)に該当する金額は、「繰延税金負債」として計上します。繰延税金負債を計上するのは、会計上の利益を税金計算上の益金に合わせる場合で、利益を益金に調整することはそれほど多くありません。そのため、繰延税金資産に比べて、繰延税金負債を計上するケースは限定的です。繰延税金負債も、発生時と解消時にそれぞれ仕訳を行います。
例えば、20万円の繰延税金負債が発生した場合と、解消した場合の仕訳例は以下のとおりです。
繰延税金負債が発生した場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 法人税等調整額 | 200,000円 | 繰延税金負債 | 200,000円 |
繰延税金負債が解消した場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金負債 | 200,000円 | 法人税等調整額 | 200,000円 |
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
税効果会計の目的とルールを理解して正しい会計処理を行おう
税効果会計とは、財務会計と税務会計の差異を調整し、企業の正確な利益を把握するために行う手続きのことです。会計上の収益・費用と税法上の益金・損金はそれぞれ計上できる範囲やタイミングが異なるため、差異が生じるのは避けられません。税効果会計によって差異を調整することで、当期純利益を正確に把握できるほか、金融機関や投資家といった利害関係者にも適切な情報を開示できます。会計上と税務上の差異には、一時差異と永久差異があり、税効果会計の対象となるのは将来的に解消される一時差異のみになります。
税効果会計の導入に関しては、顧問税理士・会計事務所など専門家への相談が不可欠です。また、税効果会計の手順についても顧問税理士などの指示に従う必要があります。顧問税理士や会計事務所とのやりとりやデータの受け渡しをスムーズに行い、ルールに則った正しい会計処理を行うためにも、会計ソフトの活用がおすすめです。会計ソフトの導入をお考えの場合は「弥生会計 Next」の活用をご検討ください。
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。