キャッシュ・フロー計算書とは?目的や作り方の手順などを解説
更新
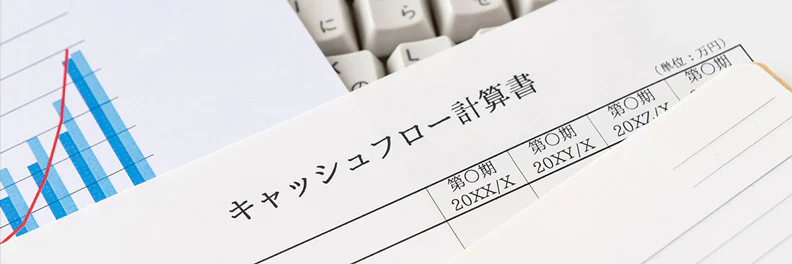
キャッシュ・フロー計算書は、決算書(財務諸表)の1つで、事業の資金の流れを把握するために用いる書類を指します。事業や企業を運営するうえで、資金の流れを把握することは非常に重要です。損益計算書や帳簿上では利益が出ていても、資金がうまく流れていないと、運転資金や手元の現金が足りずに事業が存続できなくなることもあります。経営状況を客観的に判断するのに役立つのが、キャッシュ・フロー計算書です。
本記事では、キャッシュ・フロー計算書を作成する目的や作り方の手順などを解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
キャッシュ・フロー計算書は、一定の会計期間における企業の資金の流れを示す書類
キャッシュ・フロー計算書とは、その名前のとおりキャッシュ(資金)のフロー(流れ)を表した会計書類のことです。会計期間中に、どのような理由でいくらのお金の出入りがあったのかを表します。
その期に企業がどれほど儲けたかは、損益計算書からも読み取れます。しかし、損益計算書で利益が出ていたとしても、実際にキャッシュが増加しているとは限りません。売掛金や買掛金といった掛取引を行っている場合、損益計算書上では売上となっていても手元に現金がない、仕入があっても現金が出ていかない、といったことが起こりえます。また、貸借対照表でも前期と比べて具体的なキャッシュの増減までは把握できません。そこで、キャッシュ・フロー計算書を読み解くことで、損益計算書や貸借対照表だけを見るよりも、具体的かつ詳細に経営実績や財政状態を確認できるようになります。
決算書(財務諸表)の中でも、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書は、「財務三表」と呼ばれる重要な書類です。財務三表のうち、貸借対照表と損益計算書はすべての企業に作成義務がありますが、キャッシュ・フロー計算書は金融商品取引法により上場企業にのみ作成が義務付けられています。非上場企業には、キャッシュ・フロー計算書の作成・提出義務はありませんが、キャッシュ・フロー計算書は、自社や他社の経営状況を客観的に判断するうえで非常に有効なツールです。また、金融機関に融資を申し込む際にも役立つため、中小企業の経営者や個人事業主もキャッシュ・フロー計算書の読み方と作り方を知っておくことをおすすめします。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
キャッシュ・フロー計算書の区分
キャッシュ・フロー計算書では、「営業活動によるキャッシュ・フロー」「投資活動によるキャッシュ・フロー」「財務活動によるキャッシュ・フロー」という大きく3つの区分ごとに、資金の増減を把握できます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、本業である事業でどれだけのキャッシュが生み出されているかを表します。
具体的には、現金取引で生じた収支や売上債権の回収または仕入債務の支払、従業員への給与の支払、現金で支払った経費などの現金収支です。なお、営業活動によるキャッシュ・フローのプラスが大きいほど、本業で十分に稼げていることを示します。逆に、マイナスの場合は、本業が好調でない、または売掛金の回収が滞っているなどの原因が考えられます。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、企業の投資活動におけるキャッシュの動きを表すものです。
例えば、固定資産の購入・売却、有価証券や投資有価証券の取得・売却など、将来に向けた投資のためにキャッシュがどれくらい増減したかを示します。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資を行うとマイナスに、所有する資産を売却するとプラスになります。企業が成長するには設備投資が必要なので、マイナスが悪いわけではありません。むしろ、積極的に投資を行っているともいえます。そのため、投資活動によるキャッシュ・フローは、プラスとマイナスのどちらが良いということではなく、その内容を見て判断することが大切です。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、資金調達や返済などの財務活動によるキャッシュの動きを表すものです。
具体的には、金融機関などからの融資の借入れや返済、株式・社債の発行、配当金の支払などによる現金の増減を表します。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金を返済するとマイナスに、資金調達をするとプラスになりますが、増減は企業の経営方針や経営者の意思決定によって変わります。例えば、さらなる事業拡大を目指して資金調達をした場合などは、財務活動によるキャッシュ・フローはプラスになりますが、逆にマイナスなら、金融機関への返済が進んでいることが読み取れるでしょう。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
フリーキャッシュ・フロー
上にあげた3つの区分の他に、企業が自由に使える現金を示す「フリーキャッシュ・フロー」があります。フリーキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フロー(具体的には、設備投資などに関する支出)を差し引くことで求めることが可能です。
フリーキャッシュ・フローがプラスであれば、投資した資金が本業によって回収できていることになり、企業の財務状況は健全と判断されます。その一方で、マイナスの場合は、本業で十分収益を上げられているか、投資活動が適切かなどについて検討する必要があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
キャッシュ・フロー計算書を作成する目的
前述したように、非上場の中小企業にはキャッシュ・フロー計算書の作成義務はありません。しかし、キャッシュ・フロー計算書を作成すると、さまざまなメリットがあります。キャッシュ・フロー計算書を作成する目的は、主に以下の3つです。
経営の健全性と安全性を高める
キャッシュ・フロー計算書を作成する目的の1つは、自社の経営の健全性・安定性を高めることです。
キャッシュ・フロー計算書を作成することで、売上債権の回収状況や貸倒れのリスク、損益計算書だけではわからない現金の流れなどを、早い段階で把握できるようになります。あらかじめキャッシュが必要になることがわかっていれば、早めに現金を確保するなどの対策もとりやすくなるでしょう。また、キャッシュ・フロー計算書によってキャッシュの増減要因を詳細につかめるため、経営判断を適切に行うための判断材料としても役立ちます。
資金繰りの悪化を防ぐ
資金繰りの悪化を防ぐのも、キャッシュ・フロー計算書を作成する目的です。
企業の売上の多くは掛取引であり、商品やサービスの提供後、すぐに現金が入ってくるわけではありません。現金の流れをきちんと把握していないと、入金より先に仕入などの支払期限が来てしまい、手元の資金が不足する可能性があります。帳簿上は売上があっても、実際に現金がなければ、運転資金が不足して事業の継続が難しくなってしまうかもしれません。キャッシュ・フロー計算書でキャッシュの流れを把握することで、このような資金繰りの悪化を防ぐことができます。
金融機関などからの信用を得る
キャッシュ・フロー計算書を作成する目的として、金融機関などから信用を得やすくなることもあげられます。
特に、金融機関などに融資を申し込む場合、キャッシュ・フローが良好であれば、返済が滞るリスクは少ないと判断されるでしょう。キャッシュ・フロー計算書を作成し、資金の増減状況を明らかにすることは、スムーズな資金調達を行ううえでも重要です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
他の財務三表との違い
決算書(財務諸表)の中で「財務三表」と呼ばれる重要な書類が、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書です。キャッシュ・フロー計算書と他の財務三表には、どのような違いがあるのか見ていきましょう。
キャッシュ・フロー計算書と貸借対照表との違い
キャッシュ・フロー計算書は現金の流れを表すのに対して、貸借対照表は企業の資産や負債の状況を表す点が異なります。
貸借対照表は、会計期間の終了日(決算日)時点で企業が保有する資産、負債、純資産の状況を表す決算書です。バランスシート(Balance Sheet)と呼ばれ、頭文字を取って「BS(ビー・エス)」と表記されることもあります。貸借対照表を読み解くことで、企業の資金調達方法や資金の使い道について把握できます。
キャッシュ・フロー計算書は、会計期間中に、どのような理由でどれだけの現金が入ってきたのか、または出ていったのかを表すものです。貸借対照表だけでは把握できない項目ごとの現金の出入りが可視化され、現金がどのような原因で増減したのかがわかるようになります。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
キャッシュ・フロー計算書と損益計算書との違い
キャッシュ・フロー計算書は現金の流れを表し、損益計算書は一定期間の企業の経営状況を表す点が異なります。
損益計算書は、企業が会計期間内に上げた収益、使った費用、得た利益を示す決算書です。英語のProfit and Loss Statementを略して、「PL(ピー・エル)」とも表記されます。損益計算書には収益、費用、利益の3つの要素が記載され、売掛金や買掛金のように、実際に入出金が発生していないものでも収益・費用として認識されます。
キャッシュ・フロー計算書は、このような売掛金や買掛金を反映せず、実際の現金の流れのみを表すため、入出金が発生していないものは計上されません。キャッシュ・フロー計算書と損益計算書を併せて見ることで、計上された利益と実際の現金の動きのずれを確認することができます。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
キャッシュ・フロー計算書の作成方法
キャッシュ・フロー計算書の作成方法には、「間接法」と「直接法」の2つの形式があります。直接法は、投資活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローに適用されます。営業活動によるキャッシュ・フローについては、間接法と直接法のどちらかを各社で選ぶことが可能です。間接法と直接法の内容について詳しく見ていきましょう。
間接法:項目ごとに現金の増減を表していく方法
間接法は、税引前当期純利益をスタートラインとして、項目ごとに現金の増減を表していく方法です。損益計算書の税引前当期純利益から、現金の増減と関係のない「非資金損益」を足し引きして営業活動によるキャッシュ・フローを求めます。直接法に比べて作成の手間が少ないため、キャッシュ・フロー計算書の作成義務がない非上場企業にも多く選ばれています。
直接法:現金の流れを主要な項目ごとに集計する方法
直接法は、実際の現金の流れを主要な項目ごとに集計して表す方法です。営業収入や仕入、人件費といった営業活動の項目別に、収支をそれぞれ集計していきます。キャッシュの増減を項目ごとに把握でき、詳細がわかりやすいというメリットがありますが、貸借対照表と損益計算書以外に取引ごとのキャッシュ・フローに関するデータが必要なため、間接法に比べて作成に手間がかかることがデメリットです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
間接法を用いたキャッシュ・フロー計算書の作成手順
キャッシュ・フロー計算書の2つの作成方法のうち、間接法は作成の手間が少ないため多くの企業で採用されています。ここからは、間接法によるキャッシュ・フロー計算書の作成手順を紹介していきます。
1. 損益計算書より税引前当期純利益を参照する
間接法でキャッシュ・フロー計算書を作成する際には、当期の損益計算書と前期および当期の貸借対照表を用意します。
まず、損益計算書に記載された税引前当期純利益の額を、キャッシュ・フロー計算書の「税金等調整前当期純利益」の項目に転記します。
2. 非資金損益項目を調整する
次に、非資金損益項目の調整を行います。
非資金損益項目とは、現金の増加や減少を伴わない項目のことで、減価償却費、のれん償却額、減損損失、貸倒引当金の当期繰入額などです。これらの項目は、損益計算書上では費用として計上されていますが、実際に現金の支出があったわけではありません。そのため、キャッシュ・フロー計算書においては加算します。なお、貸倒引当金については、前期分と当期分の貸借対照表を用意し、前期から増加していれば加算、減少していれば減算します。
3. 営業外損益・特別損益を調整する
非資金損益項目以外に営業外損益や特別損益がある場合は、その調整も行います。
営業外損益とは、本業以外の活動によって経常的に生じる収益(営業外収益)や費用(営業外費用)のことです。また、特別損益は例外的な出来事によって一時的に発生した利益や損失を指します。本業以外によって生じた損益を除外し、本業の損益を把握するために、損益計算書に営業外損益や特別損益が計上されている場合は加減調整を行いましょう。
4. 営業活動によるキャッシュの増減を計算する
最後に、営業活動によるキャッシュの増減を計算します。
具体的に該当するのは、売掛金や買掛金、未収入金、未払金などです。例えば、売掛金は実際には入金がないため「売上債権の増減額」の項目で減算、買掛金は実際には支出がないため「仕入債務の増減額」の項目で加算となります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
健全な企業経営のためにキャッシュ・フロー計算書を活用しよう
企業を経営するうえで、キャッシュ・フローを把握することは非常に大切です。中小企業にはキャッシュ・フロー計算書の作成義務はありませんが、資金繰りの悪化を防ぎ、健全な企業経営を目指すにはメリットが大きいため、作成をおすすめします。
なお、キャッシュ・フロー計算書を作成するには、損益計算書と貸借対照表から関連項目をピックアップし、金額を当てはめていく作業が必要になります。また、損益計算書と貸借対照表の作成には、日々の正確な記帳が不可欠です。記帳の手間やミスを軽減し、効率良く業務を進めたい場合は、「弥生会計 Next」などの会計ソフトの利用をおすすめします。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。











