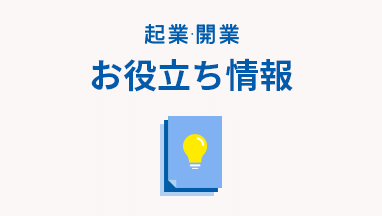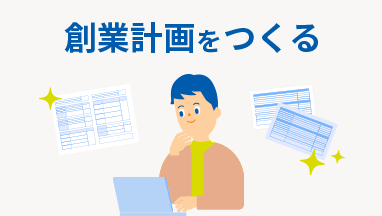「すべての信号が青になるまで待っていたら、一生踏み出せない」。中古の軽トラ1台で始めた私の起業。
- 起業時の課題
- 集客、顧客獲得, 仕入先確保

静岡県磐田市でエクステリアデザインの設計・施工・管理を行う「株式会社soto.Craft」。代表の木村文哉さんは、地元で庭師として技術を磨いたのち、20代半ばで1から空間デザインの勉強をするために上京、その後Uターンして独立されたという行動力の持ち主です。現在では、紹介制のみの案件受注という経営スタイルで、それでも受注が相次ぎ新規の問い合わせを断らざるを得ない状況が続いていることからも、事業の好調さが窺えます。
起業は目的ではなく手段だと語る木村さんが、経営において大切にしている考え方とは。専門職の独立開業や1人起業を成功させたい人必見のインタビューです。
会社プロフィール
| 業種 | 建設・工事業(外装工事)、設計事務所 |
|---|---|
| 事業継続年数(取材時) | 6年 |
| 起業時の年齢 | 30代 |
| 起業地域 | 静岡県 |
| 起業時の従業員数 | 0人 |
| 起業時の資本金 | 300万円 |
話し手のプロフィール

- 木村文哉
株式会社soto.Craft 代表取締役
静岡県磐田市生まれ。磐田農業高校の環境科学科を卒業後、地元の造園会社にて7年間職人として修行し、25歳の時に建築設計の学校へ通う為上京。卒業後、セキスイエクステリア株式会社(現、セキスイデザインワークス株式会社)に勤務し、デザインショップ The Season のデザイナーとして個人住宅やマンション等の外空間の設計・営業・施工管理に従事。新人賞・優秀賞・施工コンテスト等、数々の賞を受賞。その後帰郷し、地元である静岡県磐田市にてsoto.Craftを起業。デザイン〜施工までエクステリアのすべてを行う。
目次
庭師として修行した末に下した意外な決断。

起業に至るまでの経緯についてお聞かせください。
農業高校の造園科を卒業後、7年間ほど庭師として修行しました。その後、東京で建築設計を学び、エクステリア設計の仕事を経験しました。そして地元の静岡県にUターンして起業したという流れです。
庭師から建築設計へ転身されたのは、どのようなきっかけがあったのでしょうか?
庭師として働いていたころ、施工はしても設計をしていなかったがゆえに、「自分で庭を作った」と言い切れないもどかしさがあったんです。また、時代の変化も感じていました。分譲地の区画が小さくなり、庭師だけでは需要が減っていくんじゃないかと
それで思い切って庭師の仕事を辞め、上京したんです。東京で建築設計の学校に1年間通い、さらにエクステリア設計の会社に就職しデザイナーとして経験を積みました。
その後、静岡へのUターン起業を決意されたのはなぜですか?
もともと、地元に帰る前提で東京に出ていたので、帰るイメージは持っていましたが、タイミングとしては、東日本大震災と結婚がきっかけになりましたね。
なるほど。奥さまは静岡への移住についてどのような反応だったのでしょうか?
妻は宮崎の出身なので、静岡とは縁もゆかりもありませんでしたが、「やりたいんでしょ」と言って背中を押してくれました。ある意味男らしいといいますか、不安はなかったようですね。どうなっても大丈夫だって。私のことを信用してくれていたのもあると思います。…いや、興味がないだけなのかな(笑)。
現場仕事中心の創業初期。そこから設計業務を受注できた理由。

起業当初はどのような状況からスタートされたのでしょうか?
最初は個人事業主として開業しました。本当に小さな規模からのスタートでしたよ。事業の立ち上げに必要だったのは、30万円ほどの中古の軽トラックと脚立、剪定ばさみくらい。あとはパソコンも用意しましたが、全部合わせても50万円ぐらいの初期投資でした。
もともと私にとって、起業のハードルはそれほど高くなかったんです。庭師として修行を積み、身に付けた技術を活かして独立するのは自然な流れで、職人の世界では、こういった形で起業するのは珍しくない、という感覚でした。
では、どのように仕事を獲得されていったのでしょうか?
最初のころは、以前働いていた会社へ手伝いに行っていました。1日いくら、という日雇いのような形で現場で働いて生計を立てていたんです。それと並行して、友人や知人から設計の仕事を依頼してもらうようになりました。
設計業務の受注に関してはFacebookの存在が大きかったですね。地元を離れていた期間があったので、Facebookで久しぶりに旧友とつながることもできて。当時私の年齢は31歳。家を建てる友人が増え始めたタイミングでもありました。私が「地元に戻って庭師として起業します」と投稿をしたら、「それならうちもやってよ」と相談してもらえるようになったんです。
SNSが大きな役割を果たしたんですね。最初のころの仕事の進め方はどのようなものでしたか?
本当にアナログでしたよ。設計図は手で描いて、それをお客さまに提案して…、その繰り返しでした。ただ、設計の依頼はコンスタントにあるわけではなく、1件終われば次の依頼まで2、3か月空くこともありました。それでも、1つずつ実績を積み重ねていったんです。
資材の調達や仕入れ先などはどのように見つけていかれましたか。
開業にあたっては、前職のつてなどはほぼゼロの状態だったので、新規開拓する必要がありました。自分で調べたり足を使いながら調達先を少しずつ見つけて行きました。
他にも、印象に残っている起業初期のエピソードがあれば教えてください。
実は、起業して2年目に心臓病が発覚し、手術を経験したのですが、これも大きなターニングポイントになりました。手術の成功率は90%と言われてしまいましたが、逆に言えば1割の確率で失敗するということですよね。やっぱりすごく怖さはありました。手術前は仕事をセーブしないといけないし、手術後の復帰も不透明です。実際、命に別状はなかったものの、結局3、4か月は無収入でした。生活は、妻の給料と貯金を切り崩しながらなんとかやっていました。
ただその後、以前と同じように仕事が途切れず入ってきたんです。
この経験から学んだのは、仕事をいただくためにへりくだる必要ない、皆平等だ、ということでした。職人も取引先さまも、お客さまも建築会社も平等で、仲間です。逆に、自分の収入が減ったときに「仕事をください」とへりくだると人間関係のバランスが崩れてしまいます。
そこから、私はそれまで以上に人とのつながりやご縁を大切にするようになりました。仕事は単なる取引ではなく、人と人とのつながりです。広告プロモーションや営業は一切せず、「紹介制」という形で仕事を受注する方法を選んだんです。
いい仕事が新しい仕事を呼ぶ。「紹介制」という意外な顧客獲得方法。

「紹介制」というのは珍しいようにも感じます。なぜそのようにされたのでしょうか?
もともと知人からの紹介で仕事をいただく機会も多かったんですが、コロナ禍を機に少し状況が変わりました。たくさんの方が庭づくりに興味を持って問い合わせが増えた反面、正直冷やかし程度に話を聞きに来る方もいましたし、限られた時間の中ですべての方にじっくり向き合う時間が取りづらくなったんです。そこで、お客さまとより深く、誠実なコミュニケーションを取るために「紹介制」という形を取ることにしました。
ただ、「紹介制」という言葉で表現していますが、実際はそれほど厳密なものではありません。例えば、問い合わせフォームから連絡をいただいた方に対しても、「今は込み合っている状況なので、共通の知り合いがいる方のみで対応させていただいています。その方のお名前を伺ってもよろしいでしょうか」とお聞きしています。
面白いのは、最初は共通の知り合いがいないと思われた方でも、話を進めていくうちに意外なつながりが見つかることがあるんです。例えば、「木村さんが庭を作った家に住む人を知っている」とか、「甥っ子が通っている剣道教室の先生と木村さんがつながっている」といったケースもありました。
つまり、私の「紹介制」は、厳密な紹介システムというよりは、人とのつながりを大切にし、お互いに誠意ある対応を約束したい気持ちから生まれた仕組みなんです。この方法によって、本当に私に仕事を依頼したいと思ってくださるお客さまとじっくりと向き合うことができ、結果的に仕事は増えていきました。
例えば、ハウスメーカーや建築会社からの紹介でお仕事につながることもあるのでしょうか?
当社の場合、そもそも個人のお客さまの割合がかなり多いのですが、ただ、私の事務所を建ててもらった建築会社からお仕事を紹介してもらうこともあります。その会社は、私の高校の同級生が経営しているのですが、元請け・下請けの関係ではなく、あくまでも“個人的な紹介”なんですよ。紹介料のやりとりも一切ありません。
これは当初から建築会社の経営者の方々と話をしているんですが、結局、“いいもの”を作れば紹介につながるんです。広告や宣伝にコストをかけるくらいなら、“いいもの”を作ることに注力した方が絶対にいい。
建築会社とそういったスタンスを共有したうえで、純粋に「いいものを作る会社だから」「好きな会社だから」という理由で、お互いにお客さまを紹介し合う関係性ができました。損得勘定じゃありません。だからこそ、この関係性が続いているんだと思います。
事業者同士とても良い関係性を築いているんですね。地域とのつながりについてはいかがでしょうか?
そこも大切ですね。私は地元のために何か恩返しをしたいという想いが強いんです。例えば、創業10周年を記念して地域イベントを開催したときは、2500人もの方に来ていただきました。
すごいですね!そういった活動が、事業にも良い影響を与えているんでしょうか?
間違いなくそうですね。「知り合いが多ければ、お客さんが増える」んです。イベントを通じて知り合いが増えれば、紹介される可能性も高くなります。ただし、これも損得勘定でやっているわけではありません。純粋に地元が好きだから、地元をよくしたいと思ってやっているんです。
法人化に踏み切った理由は節税よりも◯◯。

木村さんは個人事業として開業され、のちに法人化されていますが、その背景やきっかけを教えてください。
事務所兼自宅を建てたタイミングで法人化しました。お客さまに安心感を持ってもらうために法人化した方がいいかなと思ったんです。売上がいくら以上とか、節税とかは、あまり考えなかったですね。法人化の手続きは行政書士さんにお願いしました。
バックオフィス業務はどのように対応されていますか?
会計業務については、法人化する前は自分でエクセルを使って管理していました。どの現場で何日働いて、いくら収入があって、どんな資材を購入したかを管理する程度だったので、それほど手間ではありませんでした。現在は、妻と税理士に協力してもらっていて、会計ソフトは「弥生会計 オンライン」を使用しています。
餅は餅屋といいますか、専門家にお願いすべきことはお願いするようにしています。起業したてのころは、コストを抑えるために何でも自分でやろうとする人もいるかもしれませんが、それが本当に効率的かどうかは考え物ですね。私の場合は、行政書士は高校の先輩、ホームページ制作は中学の同級生というように、信頼できる人を選んでお願いしています。
結局のところ、人にお願いすることは自分にも返ってくるんです。だから、お互いを尊重し合える関係性を築くことを重視してきました。自分の強みに集中しつつ、足りない部分は信頼できる専門家に任せる。そのバランスが大切だと思います。
事業規模を拡大するために、従業員を増やすことは考えていないのでしょうか?
今のところは考えていません。自分がやりたいからやっているんです。従業員を増やすと、個人的なつながりやご縁を重視する今のやり方が変わってしまうでしょう?それは避けたいんですよね。
ただし、すべてを一人でやっているわけではありません。例えば、駐車場のコンクリート打ちやブロック積み、カーポートやフェンスの設置など、設計図があれば対応できる部分は外注さんにお願いしています。一方で、植木を植えたり石を扱ったりする仕事、つまり寸法だけでは表現しきれない部分は自分で施工しています。
ここ5年は月4~5件、だいたい年間50~60件の施工をお受けしていて、それ以上は私の手が回らなくなるので、お断りする場合もあれば、お待ちいただいているお客さまもいます。
売上や利益を伸ばすことは、私にとって最優先事項ではないかもしれませんね。むしろ、お客さまとの関係性を重視しているんです。紹介制を導入しているのも、仕事を選別するためではなく、本当にsoto.Craftの仕事を求めてくれるお客さまと出会うため。「何のために」という目的を常に意識し、自分のやりたいことと、お客さまの求めていることのバランスを取りながら仕事をすることで、結果として事業も続いていくのだと思います。
仕事の本質を考え直すきっかけをくれた、1人のお客さまとの出会い。
エクステリアデザイナーとして起業された木村さんが大切にしている考え方はありますか?
まず私は起業後に、「デザイン」の定義を自分なりに考え直しました。「相手が潜在的に求めているものを引き出して形にする。その結果できあがったものがデザインだ」と思い至りました。
だから、華やかさやオシャレさを追求するだけでなく、例えば砂利を敷くだけでもコンクリートを打つだけでも、お客さまが満足しているならそれはデザインです。
その考え方はどこから生まれたのでしょうか?
昔、庭師として働いていたときの経験からです。あるご年配のお客さまの家で庭木の剪定をしたときに、私が仕事の手を止めて話し相手になったことがありました。その分工期が1日伸びてしまったのですが、そのお客さまは怒るどころか、喜んで工期が伸びた分の費用をお支払いしてくださったんです。
そのとき、自分のやっていることは単に木を切ることじゃなくて、お客さまを喜ばせること、気持ちよくなってもらうことなんだと気づきました。自分の事業を通じて、何を提供したいのかが明確になったんです。
なるほど。そういった経験が今の仕事観につながっているんですね。
そうです。私の職業は「造園業」ですが、実際の「仕事」は「暮らしやすくすること」だと思っています。この考えは、事業のかたわらで行っている小中学生への講演活動でも伝えているんです。将来の夢を「職業」で語るのではなく、「仕事」として何をやりたいのかを考えることが大切だと。
素晴らしい活動ですね。
「起業を迷っているならやめた方がいい」その真意とは。

最後に、起業を目指す人へのメッセージをお願いします。
率直に言うと、「迷っているならやめた方がいい」と思います。起業を考えている人には、まず「何のために起業するのか」を自分に問い直してほしいですね。
それは少し厳しい意見のようにも感じますが、どういった意図がありますか?
起業はあくまで手段であって、目的ではないんです。本当にやりたいことを叶えるための手段として起業が必要なら、するべきだと思います。でも、単に「起業したい」という漠然とした思いだけでは難しいですよ。
具体的にどのようなことを考えるべきでしょうか?
例えば、「人を助けたい」という想いがあれば、それを実現する手段はたくさんあります。消防士になるのも1つの方法ですし、看護師になるのも方法です。起業して自分のビジネスを通じて人を助けるのも方法の1つです。大切なのは、自分が何をしたいのかをしっかり見極めることです。
起業にあたって、準備はどの程度必要だと思いますか?
よく聞かれる質問ですが、私の答えは「考えすぎないこと」です。すべての信号が青になるのを待っていたら、一生踏み出せません。1つの信号が青になったら進む。次の信号が青になったらまた進む。そうやって一歩ずつ前に進んでいけばいいんです。私も、軽トラック1台と必要最小限の道具だけで事業を始めましたから。
大切なのは、自分がやりたいことを明確にすること。そして、それが決まればあとは考え過ぎず、小さな一歩を踏み出す勇気を持つことです。これから起業される方の次の一歩を応援しています。
取材協力:創業手帳
インタビュアー・ライター:間宮 まさかず
ビジネスを成功させる起業マニュアル
事業アイデアをビジネスモデルに落とし込む方法、そして、実行に向けた必要な取り組みを解説します。
こんな方におすすめ
どうすれば起業できるか知りたい
失敗しない起業のコツを知りたい
ビジネスプランの作り方を知りたい

資金調達につながる創業計画書の書き方
起業前に事業計画を作ることで必要な資金が把握できます。資金調達の種類と方法、そして必要な準備を解説します。
こんな方におすすめ
起業前後に必要な資金を調達したい
創業計画書の作成ポイントを知りたい
専門家のサポートを受けたい
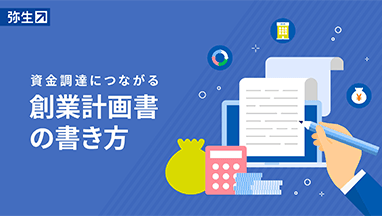
チェックガイド付き会社設立マニュアル
会社設立の手順と必要な準備、そして、会社設立後にやるべきことを解説します。チェックガイドに沿って進めてください。
こんな方におすすめ
自分に合った起業の形態を知りたい
会社設立の手続きをスマートに済ませたい
専門家に手続きを代行してほしい