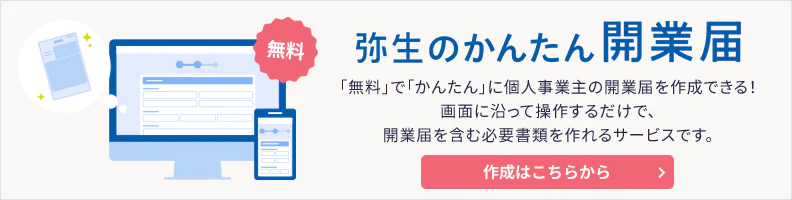個人事業主が加入できる社会保険は?条件や従業員を雇う場合も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

個人事業主は、会社員とは加入する社会保険が異なります。また、個人事業主本人が加入する公的保険制度とは別に、従業員を雇用したときには事業所として社会保険の手続きが必要です。
では、個人事業主が利用できる公的保険制度にはどのような種類があり、従業員を雇用した際には、どのような社会保険への加入が必要になるのでしょうか。
本記事では、個人事業主が加入できる公的保険制度や、従業員を雇用したときに必要になる社会保険の加入手続き、条件などについて解説します。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主と会社員で加入できる社会保険は異なる
個人事業主は、会社員とは加入できる社会保険が異なります。社会保険と言ってもさまざまな定義がありますが、ここでは、会社員や公務員などが加入する健康保険・厚生年金・介護保険に、雇用保険・労災保険を加えた5つをまとめた総称とします。
これらの社会保険のうち、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4つは会社員や公務員、会社役員といった給与所得者を対象とした制度であるため、事業所得者である個人事業主は加入できません。なお、健康保険・厚生年金・介護保険の3つのみを、狭義の社会保険と呼ぶこともあります。
個人事業主の場合は、健康保険(協会けんぽや健康保険組合)ではなく国民健康保険、厚生年金ではなく国民年金に加入することになります。介護保険には加入することになりますが、労働者を対象とした雇用保険や労災保険に、個人事業主自身が加入することは、基本的にはありません。
日本の医療制度では、日本に住む方全員に保険加入が義務付けられる国民皆保険制度が導入されているため、会社員や個人事業主、専業主婦、学生なども含めて、すべての国民が健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入する必要があります。また、20歳以上60歳未満のすべての国民は厚生年金や国民年金などの公的年金に加入する必要があり、40歳以上の場合は介護保険にも加入しなければなりません。
個人事業主の方は、会社員を対象とした社会保険ではなく、次の項目以降で解説する、自身が加入できる公的な保険制度を押さえておきましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主が加入できる公的医療保険には複数の種類がある
個人事業主が加入できる公的医療保険には、複数の種類があります。個人事業主は、条件を満たした場合は国民健康保険以外の公的医療保険に加入できるため、場合によっては複数の選択肢から加入する保険を選ぶことも可能です。個人事業主は、主に以下のような公的医療保険に加入できます。自身が入れる公的医療保険があるか確認しましょう。
個人事業主が加入できる公的医療保険
| 加入対象者 | 保険者(運営団体) | 保険料負担 | |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険組合(国保組合) | 所定の事業・業種に従事する方※ | 各業種の国民健康保険組合 | 全額自己負担 所得にかかわらず保険料は一定 |
| 健康保険の任意継続 | 前の勤務先で継続して2か月以上健康保険に加入していた方 | 前の勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) | 全額自己負担 保険料は退職時の標準報酬月額に応じて決まる |
| 健康保険の被扶養者になる | 配偶者、親など、家族が健康保険に加入していて、健康保険の被扶養者の条件に該当する方 | 家族(扶養者)の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) | 保険料負担なし(扶養者の保険料も上がらない) |
| 国民健康保険 | 他の公的医療保険(健康保険や後期高齢者医療制度など)に加入していないすべての方 | 都道府県および市区町村 | 原則として全額世帯主が負担 保険料は前年の世帯所得などに応じて決まる |
- ※建設業・飲食業・理容業など、同種の事業または業務に従事する方で組織される国民健康保険組合の加入要件を満たす方
国民健康保険組合に加入する
個人事業主は、場合によっては、国民健康保険組合に加入できます。国民健康保険組合は、同種の事業または業務に従事する方で組織される公的医療保険であるため、国民健康保険組合が組織されている業種に携わる個人事業主は、国民健康保険組合に加入することが可能です。例えば、建設業・飲食業・理容業など、さまざまな業種の国民健康保険組合が運営されています。
国民健康保険組合に加入するには、各団体が設ける要件を満たさなければなりません。フリーランスのデザイナーやライター、イラストレーターなどが加入できる可能性がある「文芸美術国民健康保険組合」の場合、組合の加盟団体に加入したうえで、審査に通過する必要があります。
国民健康保険組合の保険料は、多くの場合は収入や所得にかかわらず一定ですが、団体ごとに異なるため、確認してから加入を決めましょう。加入手続きは、各国民健康保険組合で行いましょう。
勤務先の健康保険を任意継続する
会社を辞めて個人事業主になった場合は、退職前の勤務先の健康保険に最大2年間引き続き加入する任意継続を利用することができます。任意継続ができるのは、前の勤務先で健康保険に加入していた期間が継続して2か月以上ある方です。被扶養者がいた場合は、任意継続の健康保険に被扶養者として加入させることも可能です。
任意継続を利用したい場合は、退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しなければなりません。健康保険を任意継続した場合の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて計算されます。
なお、会社員の場合は健康保険料の半額を勤務先が負担しますが、任意継続になると全額自己負担となるため、任意継続する場合は保険料が増加することも念頭に置いて検討しましょう。
扶養家族として家族の健康保険に加入する
個人事業主は、配偶者や親などの家族が健康保険に加入していて自分の収入が一定額以下である場合、家族の健康保険の被扶養者として公的医療保険に加入できます。被扶養者になった場合、自身の保険料の負担はなく、扶養者の保険料も増加しません。健康保険の被扶養者になるには、家族の勤務先を通じて手続きを行います。
家族の健康保険の扶養に入るには、向こう1年間の見込み年収が130万円未満で、その家族の年収の2分の1未満でなければなりません。この130万円の基準は、従業員101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業などに週20時間以上勤務している場合、106万円となります。
個人事業主の場合、年収の金額は事業所得(売上から経費を差し引いた金額)が基準とされるのが一般的です。また、健康保険組合の中には、例えば個人事業主が従業員を雇用して給与を支払っている場合に、給与の支払い額が一定額以上のケースについて、被扶養者になることを認めない健康保険もあります。被扶養者の条件や個人事業主が扶養に入れるかどうかなどは、家族が加入する健康保険に確認しましょう。
国民健康保険に加入する
個人事業主が「国民健康保険組合」「退職前の勤務先の健康保険」「家族の健康保険」のいずれにも加入できない場合、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は、都道府県および市区町村が運営する公的医療保険です。国民健康保険料の計算方法は自治体によって異なりますが、前年の所得などに応じて決まるため、所得が多いほど納付する保険料も高くなります。また、勤務先と被雇用者で保険料の負担を折半する健康保険とは異なり、保険料は全額世帯主負担です。
例えば、会社を退職して個人事業主になった方は、任意継続する場合を除き、原則として退職日から14日以内に健康保険から国民健康保険に切り替える手続きを行わなければなりません。住んでいる市区町村の役場で、手続きを行いましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
40歳以上の個人事業主は介護保険に加入しなければならない
個人事業主も含め、40歳以上の方は介護保険に加入し、介護保険料を納付しなければなりません。介護保険は、高齢などによって介護が必要になった方を社会全体で支えることを目的とした社会保険であるため、40歳になると自動的に介護保険に加入します。
健康保険料に介護保険料が上乗せされるため、手続きは必要ありません。介護保険料は、加入している健康保険の保険料と一緒に納めることになっています。例えば、国民健康保険に加入している場合は、前年の所得などに応じて介護保険料が決まり、国民健康保険料と合わせて市区町村に納付します。また、国民健康保険組合の場合は、介護保険料の計算方法や納付方法は組合によって異なるため、気になる場合は国民健康保険組合のWebページで確認しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
20歳以上60歳未満の個人事業主は国民年金に加入しなければならない
20歳以上60歳未満の個人事業主は、国民年金に加入しなければなりません。公的年金制度として、20歳以上60歳未満のすべての国民は国民年金に加入することとされているため、個人事業主も国民年金に加入する必要があります。会社員や公務員などは、国民年金に加えて厚生年金にも加入しますが、個人事業主は厚生年金には加入できません。
会社を退職して個人事業主になった場合は、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。健康保険のような任意継続制度はありません。国民年金保険料は、収入や所得にかかわらず全加入者で一律です。国民年金の保険料は、日本年金機構のWebページ「国民年金保険料」で調べられます。
また、配偶者が厚生年金に加入していて、基本的に年収(または所得)が130万円以下かつ配偶者の年収の2分の1未満の方は、厚生年金制度上の扶養に入れます。この場合、第3号被保険者となり、年金保険料の負担なしに国民年金に加入することが可能です。なお、健康保険とは異なり、配偶者以外の家族の扶養に入ることはできないため、その場合は個人事業主や学生などが加入する第1号被保険者として国民年金に加入しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主は雇用保険・労災保険には加入できない
個人事業主は、会社員のように雇用保険や労災保険に加入することはできません。雇用保険と労災保険はまとめて労働保険と呼ばれ、労働者の保護と雇用の安定を図ることを目的としているため、労働基準法上の労働者ではない個人事業主は雇用保険や労災保険の対象外となります。ただし、個人事業主でも、一人親方など特定の条件を満たす場合は、労災保険の特別加入が認められます。
基本的に個人事業主は、例えば廃業して無職になったり、業務上のケガや病気で仕事を休んだりしても、失業給付や休業補償給付を受けることはできません。会社員に比べて保障が手薄になってしまうため、必要に応じて自身でリスクに備える必要があります。廃業したときに金銭を受け取れる小規模企業共済や、民間の医療保険、就業不能保険への加入も検討してみましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主が従業員を雇った場合は、事業所としての社会保険の加入手続きが必要
個人事業主が従業員を雇った場合は、状況によっては狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)について、事業所として加入手続きを行う必要があり、また、従業員のために事業所として、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きも行わなければなりません。健康保険法や厚生年金保険法など、それぞれの制度のルールを定める法律で事業所の加入義務が定められているため、個人事業主であっても、従業員を雇用すると事業所としての加入が必要になる場合があります。
加入条件や手続きは、社会保険と労働保険で異なります。また、事業所としての加入手続きと、条件を満たした従業員を加入させる手続きがそれぞれ必要になるため、以下のように対応しましょう。
常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、狭義の社会保険への加入手続きが必要
常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、一部の業種を除き、狭義の社会保険への加入手続きが必要です。この条件を満たすと、狭義の社会保険の適用事業所となるため、事業所として健康保険、厚生年金保険、介護保険に加入手続きを行わなければなりません。
狭義の社会保険の加入条件は共通しているため、加入手続きも共通の書式を使います。条件を満たした日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を年金事務所へ提出します。
また、適用事業所で社会保険の加入要件を満たす従業員を雇用した際には、従業員の社会保険加入手続きが必要です。従業員が以下の条件のいずれかに該当する場合は、該当する従業員の入社(または条件を満たしたとき)から5日以内に、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
狭義の社会保険に加入する従業員の条件
- 適用事業所に常時雇用されている70歳未満(厚生年金保険)・75歳未満(健康保険)の従業員
- パート・アルバイトで、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の従業員
40歳以上の従業員は、健康保険と併せて介護保険にも加入します。健康保険の加入手続きをすると、年齢に基づき介護保険にも自動加入となります。
なお、1年のうち6か月間以上、狭義の社会保険の被保険者である従業員が51人以上いる「特定適用事業所」に該当する場合は、以下の条件をすべて満たすパート・アルバイトについても、狭義の社会保険に加入させる必要があります。
特定適用事業所で狭義の社会保険に加入するパート・アルバイトの条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 月の賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
例えば、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上のパート・アルバイトも、この条件を満たせば狭義の社会保険に加入しなければなりません。
特定適用事業所の条件は、2024年10月以前は従業員数101人以上でしたが、51人以上に変更されています。適用範囲の拡大によって新たに特定適用事業所になった場合は、忘れずに対応しましょう。
※社会保険の加入方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください
従業員を1人でも雇用した個人事業主は、労働保険への加入手続きが必要
従業員を1人でも雇用した個人事業主は、労働保険への加入手続きが必要です。フルタイム、パート、アルバイトなど雇用形態や勤務時間を問わず、従業員を雇用した時点で労働保険の適用事業となるため、労働保険の加入手続きを行わなければなりません。
初めて従業員を雇用した日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」を、50日以内に「概算保険料申告書」を、所轄の労働基準監督署に提出するなどの加入手続きを行います。また、労災保険と雇用保険に関する保険料の申告・納付をまとめて行う必要がある農林漁業や建設業以外の事業所では、事業所の設置日の翌日から10日以内に、「雇用保険適用事務所設置届」も所轄のハローワークに提出しなければなりません。
従業員の加入条件については、労災保険と雇用保険で条件が異なります。労災保険の加入対象になるのは、パートやアルバイトを含むすべての従業員です。初めて従業員を雇用したときに労働保険の加入手続きを行えば、2人目以降は個別の従業員についての手続きは不要です。それに対して、雇用保険に加入するのは、以下の条件にすべて当てはまる従業員です。
雇用保険に加入する従業員の条件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して雇用される見込みがある
- 昼間部の学生ではない(休学中、事業主の命で大学院に在学中など、一部例外あり)
例えば、1週間の所定労働時間が20時間以上でも、契約期間が1か月に満たない場合は、雇用保険に加入する必要はありません。
雇用保険の加入条件に該当する従業員を初めて雇用したときは、翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を、所轄のハローワークへ提出します。労災保険の加入手続きは行っても、雇用保険の手続きは行わなくていいケースもあるため、加入条件について迷う場合は電話などでハローワークの窓口に確認しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業手続きを手軽に行う方法
ここまで見てきたように、保険手続きひとつとっても自分でゼロから調べて必要書類を揃えようとすると労力と時間がかかります。そこで、個人事業主の開業手続きを手軽に行いたい場合は「弥生のかんたん開業届」がおすすめです。
「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。パソコンでもスマホでも利用でき、開業届をはじめ、青色申告承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書などもスムーズに作成することができます。
また、開業後は、日々の帳簿付けや毎年の確定申告が必要になります。事業が本格的に動き出してから慌てることのないように、開業のタイミングで会計ソフトや確定申告ソフトを導入しておくといいでしょう。クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件を満たした青色申告の必要書類が簡単に作成できます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業する際には社会保険の手続きも忘れずに行おう
個人事業主は、加入できる社会保険が会社員とは異なります。特に、会社を退職して個人事業主になるような場合は、それまで加入していた社会保険からの切り替え手続きを忘れないようにしましょう。また、個人事業主でも従業員を雇用する場合は、事業所として社会保険に加入しなければなりません。開業する際には、事業の準備だけではなく、社会保険関係の手続きにも適切に対応してください。
また、個人事業主として開業する際には、煩雑な各種手続きや確定申告を「弥生のかんたん開業届」や「やよいの青色申告 オンライン」といったクラウドサービスで効率化するのもおすすめです。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。