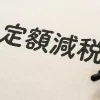復興特別所得税の計算方法は?概要や税率、納付方法を解説
更新

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興の財源を確保するために創設された税金です。2013年1月1日~2037年12月31日の25年間に得た所得に対しては、所得税に復興特別所得税が上乗せされます。復興特別所得税は所得税と一緒に納めるため、給与計算をするときには、所得税と併せて復興特別所得税も源泉徴収が必要です。
なお、所得税と復興特別所得税は税率が異なるため、それぞれの違いをしっかり理解しておく必要があります。本記事では、復興特別所得税の概要や税率、計算方法の他、復興特別所得税の納付方法についても解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
復興特別所得税は東日本大震災からの復興の財源
復興特別所得税は、(2011年3月11日に発生した)東日本大震災からの復興財源の確保を目的とした税金です。2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づいて創設され、2013年から課税されています。
復興特別所得税はすべての所得税の納税者が対象
復興特別所得税の課税対象者になるのは、すべての所得税の納税者です。所得税を納める人は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
復興特別所得税は、課税期間が2013年1月1日~2037年12月31日の25年間に限定されています。この期間に生じた所得に対しては、所得税に加えて復興特別所得税が課税されます。企業は、従業員の給与から所得税を源泉徴収するとき、併せて復興特別所得税を徴収して、その合計額を国に納付しなければなりません。また、個人事業主などは、確定申告を行い所得税と復興特別所得税を一緒に申告・納付します。
復興特別所得税の使い道
前述したとおり、復興特別所得税の使い道は、東日本大震災からの復興です。主に、「被災者支援」「住まいとまちの復興」「産業・生業(なりわい)の再生」「原子力災害からの復興・再生」「創造的復興」に関するさまざまな施策に用いられています。
「復興庁」のWebサイトでは、復興に向けた具体的な取組の他、復興の現状と課題などを確認できます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
復興特別所得税の税率と計算方法
給与や賞与から源泉徴収する復興特別所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」や「賞与に対する源泉徴収税額の算定率の表」に含まれています。
2013年分以降の給与や賞与は、源泉徴収税額表に基づいて計算すれば、所得税と復興特別所得税を合わせた源泉徴収額が算出できるので、給与計算のときに復興特別所得税だけを個別で計算する機会は少ないかもしれません。
しかし、個人事業主などの確定申告では、所得税と復興特別所得税をそれぞれ計算して、合計額を申告・納付することになっています。また、そもそも復興特別所得税は所得税とは違う税金ですから、給与から源泉徴収する際にも、復興特別所得税のしくみや税率などを正しく知っておくことが大切です。
ここからは、復興特別所得税の税率や計算方法について、詳しく解説していきます。
復興特別所得税の税率
復興特別所得税額は、その年分の基準所得税額(所得税額から税額控除額などを差し引いた後の金額)を基に、以下の計算式で算出されます。
復興特別所得税額の計算式
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
つまり、復興特別所得税額を算出するには、まず所得税額を計算し、その金額に2.1%を掛けるということです。1円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。
なお、外国税額控除の適用がある場合は、外国税額控除額を控除する前の所得税額が基準所得税額となります。また、控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合は、超える金額をその年分の復興特別所得税額から控除できます(ただし、国外所得に対応する部分の金額を限度とします)。
復興特別所得税の計算の流れ
個人事業主などの場合、所得税と復興特別所得税をそれぞれ計算して、合計額を申告・納付します。復興特別所得税額を計算する手順は、以下のとおりです。
復興特別所得税の計算の流れ
-
1 収入から経費や所得控除を差し引き、「課税所得」を求める。
-
2 課税所得に所定の所得税率を掛け、所得税額を求める。
-
3 算出した所得税額から税額控除などを差し引き、「基準所得税額」を求める。
-
4 基準所得税額に2.1%を掛け、復興特別所得税額を算出する。
所得税は、所得が多いほど税率が高くなる累進課税制度が採用されています。課税所得に応じた所得税率は、以下のとおりです。なお、課税所得とは、収入から経費や所得控除を差し引いた金額のことであり、収入額そのものではありません。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
」
給与所得者の場合は経費の代わりに、年収に応じた給与所得控除を収入から差し引くことができます。また所得控除には、合計所得金額が2,500万円未満のすべての人に適用される基礎控除の他、該当する場合に利用できる配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などがあります。
復興特別所得税の計算例
課税所得300万円の場合を例にあげて、所得税額と復興特別所得税額を計算してみましょう。なお、ここでは税額控除はないものとして考えます。
課税所得300万円の場合の復興特別所得税額の計算
基準所得税額=300万円×10%−9万7,500円=20万2,500円
復興特別所得税額=20万2,500円×2.1%=4,252円(1円未満切り捨て)
給与・賞与に対する源泉徴収税額の計算
給与や賞与から源泉徴収する場合は、国税庁が定める源泉徴収税額表に基づいて計算すれば、所得税と復興特別所得税を合計した源泉徴収税額がわかるしくみになっています。
給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」または「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
」を用いて計算します。また、賞与の場合は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
」を利用します。いずれも、課税対象額や扶養親族等の数などによって源泉徴収額が決まります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
復興特別所得税の期限
復興特別所得税は、所得税と一緒に納付することになっているため、納付期限も所得税と同じです。従業員から源泉徴収した復興特別所得税は、本人に代わって事業主が納めなければなりませんし、個人事業主は確定申告を行い、所得税と併せて納付することが必要です。
ここでは、給与所得者の場合と、個人事業主の場合の納付期限について解説します。
給与所得者の場合
従業員の給与や賞与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、従業員本人ではなく、事業者(源泉徴収義務者)が税務署に納付します。納付時には、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」が必要です。
納付期限は、給与などを支払った月の翌月10日までです。ただし、給与を支払う従業員の数が常時10人未満であれば、特例により、半年分をまとめて納付することが可能となっています。
この特例を適用するには、あらかじめ税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
個人事業主の場合
個人事業主の所得税および復興特別所得税は、確定申告の期限内に申告・納付を行う必要があります。確定申告の期間は、原則として毎年2月16日~3月15日(期限日が土・日・祝日の場合は翌平日)です。申告期限と納付期限は同じ日なので注意しましょう。提出先は、納税地を所轄する税務署です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
源泉所得税の納付方法
源泉所得税は、従業員に代わって事業者(源泉徴収義務者)が納付する場合も、個人事業主が確定申告を終えた後に納付する場合も、納付方法は同じです。
源泉所得税の納付方法としては、以下のような方法があります。
所得税および復興特別所得税の納付方法
- 指定された金融機関の預貯金口座からの振替納税
- e-Taxまたはインターネットバンキングを利用した電子納税
- コンビニエンスストアで納付
- クレジットカードによる納付
- 金融機関または税務署の窓口での現金納付
- スマホアプリ納付
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
復興特別所得税の予定納税に注意
個人事業主は場合によって、所得税および復興特別所得税の予定納税を行わなければならないケースがあります。予定納税とは、所得税および復興特別所得税の金額が一定額以上となる見込みの人が、税金の一部を前払いすることです。
その年の5月15日現在において、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合は、予定納税を行わなければなりません。
予定納税では、予定納税基準額の3分の1にあたる金額を、第1期分として7月1日~7月31日に、第2期分として11月1日~11月30日に納めることになっています(特別農業所得者を除く)。その後、確定申告の際に、納めるべき税額から予定納税で納付した税額が差し引かれ、過不足が精算されます。予定納税が必要な人には、税務署から通知が来るので、忘れずに納付するようにしましょう。
なお、会社員などの給与所得者の場合は、年末調整によって税額の精算が行われるため、基本的には予定納税の対象になりません。ただし、会社員でも一定額以上の副業収入(または所得)があるなど、確定申告義務がある人は、予定納税の対象になる可能性があるため注意してください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
復興特別所得税を含む税額計算には給与計算ソフトを
2037年12月31日までに支払う給与や賞与からは、所得税と併せて復興特別所得税の源泉徴収が必要です。源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、所定の期限までに、従業員本人に代わって税務署に納付しなければなりません。さらに、給与や賞与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税に関しては、1年間の給与支払額が確定した年末に、年末調整を行う必要があります。税額の計算は煩雑なうえ、間違えると従業員の手取りや納税額にも影響してしまいます。
復興特別所得税を含む税額計算を正確かつスムーズに行うには、弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」が役立ちます。給与支給額を自動で計算することができ、給与明細や源泉徴収票のWeb配信もできるため、給与計算業務の手間や人的ミスが軽減されます。また、税金や保険料率の変更にも自動で対応するため、給与計算のたびに最新の料率や法令をチェックする必要がありません。給与計算業務の効率化を目指し、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。