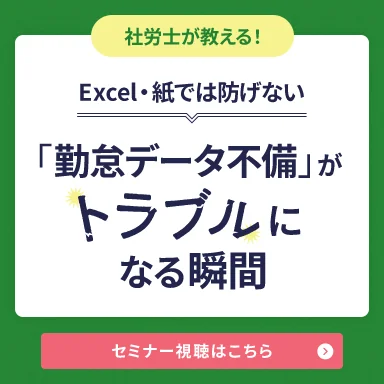変形労働時間制とは?残業の扱い方やメリット・デメリットをわかりやすく解説
監修者: 下川めぐみ(社会保険労務士)
公開

通常、正社員の雇用契約における労働時間は1日8時間、週5日勤務といった内容で締結され、特別な契約がない限り雇用形態が変わることはありません。しかし、時期によって繁忙期と閑散期がはっきり分かれる職種もあります。そのような場合に適している働き方が、変形労働時間制です。
制度としては複雑な部分もあるため、残業の扱いなどに関して正しく理解したうえで導入する必要があります。本記事では、変形労働時間制の種類やメリット、導入方法や注意点についてわかりやすく解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
変形労働時間制とは
変形労働時間制は、一定の期間において、労働時間の柔軟な配分を可能にする働き方です。この制度では、1年、1か月、または1週間単位で労働時間を調整できます。通常、労働基準法では1日8時間以内、1週間40時間以内といった法定労働時間が決められていますが、変形労働時間制の場合はこれにこだわらず、業務の状況やニーズにあわせて労働時間を調整できるのが特徴です。
例えば、業務が忙しい時期は労働時間を増やし、逆に閑散期は労働時間を減らせます。この制度は労働者の働き方に柔軟性をもたらし、労働環境の改善やワークライフバランスの向上に効果的です。
変形労働時間制について詳しくは以下の記事をご覧ください。
裁量労働制との違い
裁量労働制と変形労働時間制には、労働時間の考え方に違いがあります。裁量労働制はあらかじめ定めた時間分を働いたとみなす制度であり、時間外労働の概念がないため、基本的には残業が発生しません。ただし、所定のみなし労働時間が法定労働時間を超える場合や休日出勤などの特殊なケースでは、残業代の支払いが発生することもあります。
変形労働時間制では、通常の所定労働時間を超えて働く場合には、36協定の範囲内での労働とすることや、割増賃金の支払いなどの対応が必要となります。裁量労働制があらかじめ時間を定めるのに対し、変形労働時間制は期間内での柔軟な調整が可能となる点が異なります。
交代勤務制(シフト制)との違い
変形労働時間制は、繁忙期や閑散期などのタイミングにあわせて従業員の所定労働時間を増減させる制度です。交代勤務制は従業員どうしが曜日や時間帯ごとに交代で勤務する制度であり、管理者が従業員の希望や業務のニーズを考慮してシフト表を作成し、労働時間を管理します。
変形労働時間制では業務の繁閑にあわせて労働時間を定めることによって効率化を図ることができ、交代勤務制は業務の特性や従業員の希望を考慮しながら労働時間を適切に配分でき、それぞれのメリットがあります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
変形労働時間制の種類
変形労働時間制は、一定の期間で労働時間の配分を調整するもので、具体的には1年単位、1か月単位、1週間単位で設定するものの3種類があります。また、一定期間内の総労働時間の管理を自ら行うフレックス制も変形労働時間制の1つです。ここからは、期間ごととフレックスタイム制の詳細について解説します。
1年単位で設定
1年単位で設定される変形労働時間制は、1か月以上1年間以内の労働時間の配分を調整する制度です。この制度では、平均して1週間の労働時間が法定労働時間内に収まれば、特定の日に8時間、または特定の週に40時間を超えた所定労働時間を設定できます。ただし、1年間の労働日数は280日、1日の所定労働時間は10時間、1週間の所定労働時間は52時間が上限となります。
この期間設定は、特定の季節や月などに繁忙期がある場合に適しています。閑散期に休暇(労働時間0時間)を設け、その分を繁忙期の労働時間に振り分けることも可能です。例えば、閑散期に10日間の長期休暇をとり、繁忙期の2か月間は規定の上限を超えないように80時間(10日×8時間)の労働時間を振り分けられます。
1か月単位で設定
1か月単位で設定される変形労働時間制は、1か月の平均で週40時間(特例事業は44時間)以内であれば、日・週の法定労働時間を超えた労働日数や労働時間を設定できる制度です。これにより、月初が閑散期で月末が忙しいといったように、月ごとの業務の状況にあわせて労働時間を柔軟に調整できます。特定の週に繁忙期がある企業や、月初や月末に業務の集中がある場合に適しています。
例えば、1日8時間の勤務時間で週5日(40時間)勤務の職場で、1か月のうち1週目が比較的落ち着いており、4週目に業務が集中する場合、1週目の水曜日を休暇とし、4週目の月・火・木・金曜の所定労働時間を10時間とすることが可能です。月末の労働時間を増やしながらも週当たりの労働時間平均は40時間に収まります。このように、月単位で業務の状況を考慮して労働時間を調整できるのが1か月単位での変形労働時間制の特徴です。
1週間単位で設定
1週間単位で設定される変形労働時間制は、従業員が30人に満たない小売業や旅館、料理・飲食店の事業において適用されます。この制度では、毎日の労働時間を1週間単位で決められます。所定労働時間は1週間当たり40時間以内、1日当たり10時間以内と定められており(特例事業も含む)、それを超過する分については割増賃金を支払う必要があります。
この期間設定は、業務の繁閑が予測しにくい場合や、業務の状況が週単位で大きく変動する業種に適しています。例えば、週末や祝日に忙しくなるレストランでは、以下の例のように週ごとに柔軟に労働時間を調整できます。
- (適用例)
- 1週目:土曜日曜に10時間勤務、月曜火曜は休み、水曜木曜は6時間、金曜は8時間勤務
- 2週目:土曜日曜と祝日になった月曜に9時間勤務、火曜水曜休み、木~金曜は6.5時間勤務
このように、週40時間の労働時間上限を超えない範囲で、労働時間を配分することが可能です。また、各日の就業時間を就業規則に定める必要はありませんが、前の週末までに決定して従業員に書面で通知しなければいけません。たとえ就業規則への記載がなくても、労働時間の透明性や公平性の確保が必要です。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、あらかじめ特定の期間で定められた労働時間の枠内で従業員が自ら始業・終業時間を決める制度です。この制度では、必ず働く時間帯(コアタイム)と、従業員が自分の裁量で働ける時間帯(フレキシブルタイム)に分けて実施されることが一般的です。具体的には、10時~15時をコアタイムとして定めた場合(ただし12時~13時は休憩時間)、その時間帯は全員が出勤することが求められますが、それ以外は自分の都合にあわせて勤務できます。
フレックスタイム制は、始業・終業時刻を従業員に自由に決めても、業務上大きな問題が生じない場合に適しています。通勤ラッシュの多い大都市や、子育て世代で実施すると特に効果的です。従業員のワークライフバランスを考慮しつつ、効率的な業務遂行が可能となります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
変形労働時間でも残業代は発生する
変形労働時間制を採用していても、残業が発生した場合には残業代の支払いが必要です。この場合の残業代は、所定労働時間と法定労働時間のうち長い方を超えた時間について計算されます。残業代の計算式は「残業時間×1時間当たりの賃金×割増率」です。なお、賃金の割増率は、時間外労働が1.25倍、休日労働が1.35倍、深夜労働が1.50倍と、一般的な場合と変わりません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
変形労働時間制における残業の扱い方
変形労働時間制を適用している場合も、決定された所定労働時間を超えた分については残業代が支払われますが、その残業時間の考え方は設定している期間の長さごとに変わります。また、フレックスタイム制の場合は清算期間ごとに考えることにも注意が必要です。
ここからは、変形労働時間制が1年単位、1か月単位、1週間単位のそれぞれで設定されている場合や、フレックスタイム制の場合の考え方についても詳しく解説します。
1年・1か月・1週間単位の場合
変形労働時間制の残業に関する考え方は、1年・1か月・1週間単位の中からどの期間が設定されているかによって異なります。1週間単位であれば、日ごとの所定労働時間と週40時間の労働時間を超えている分が残業の扱いです。1か月単位の場合は、1週間単位の考え方に月の単位も追加して考える必要があります。さらに、1年単位の変形労働時間制ではそれに加えて年単位の労働時間についてのカウントも必要です。
以下、1年単位の変形労働時間制の場合、日、週、対象期間で残業時間をどのようにカウントするのか、例を記載します。
- ※1日の所定労働時間は8時間とします。
| 単位 | 設定 | 残業としてカウントする部分 |
|---|---|---|
| 日 | 1日8時間勤務と設定した場合 | 8時間を超えた部分 |
| 週 | 週50時間と設定した場合 | 50時間を超えた部分 |
| 月 | 28日の場合 | 160時間を超えた部分 |
| 月 | 29日の場合 | 165.7時間を超えた部分 |
| 月 | 30日の場合 | 171.4時間を超えた部分 |
| 月 | 31日の場合 | 177.1時間を超えた部分 |
| 年 | 365日の場合 | 2085.7時間を超えた部分 |
| 年 | 366日(うるう年)の場合 | 2091.4時間を超えた部分 |
フレックスタイム制の場合
フレックスタイム制の残業は、日ごとの単位ではなく1か月から3か月の間で設けられる清算期間の単位で考えます。2019年の労働基準法改正により、清算期間は最大3か月まで延長され、より柔軟な働き方ができるようになりました。この期間内での実労働時間が所定労働時間を超えた時点から残業代が発生します。残業代の計算が適切に行われるためには、労働時間の把握と管理が重要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
変形労働時間制のメリット
変形労働時間制のメリットとして以下の3点が挙げられます。
- 残業代を抑えられる
- メリハリのある働き方ができる
- 人員の過不足を管理しやすくなる
繁忙期や閑散期がはっきり分かれている事業の場合は、これらのメリットが得られるため変形労働時間制の導入に適しています。
残業代を抑えられる
繁忙期がある事業では、1日8時間以上働く日も多く、残業代がかさむ傾向があります。しかし、変形労働時間制を導入すると残業代を抑えることが可能です。例えば、通常の所定労働時間が8時間のところを、繁忙期の所定労働時間のみ9時間に設定している場合、繁忙期では1日の労働時間が9時間を超えたところから残業代が発生するため、企業側は経済的なメリットを得られます。
メリハリのある働き方ができる
変形労働時間制を採用すると、メリハリのある働き方を実現できることもメリットです。繁忙期はしっかり働き、閑散期は労働時間を減らすようにすれば、従業員の負担を軽減し、モチベーションの維持や向上にもつながります。また、閑散期には短時間労働や休暇の取得を推進することで、従業員のリフレッシュを促し、効率的な業務運営が可能となります。
人員を管理しやすくなる
変形労働時間制は人員管理をしやすくする利点もあります。労働時間の調整によって人員の過不足を管理することで、労働力の最適化や生産性の向上が期待できます。適切なスケジュール管理をすることは、従業員の体調不良や過労の防止にも効果的です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
変形労働時間制のデメリット
変形労働時間制のデメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。
- 勤怠管理が複雑になる
- 他部署との就業時間が合わなくなる
変形労働時間制を導入すると、繁忙期や閑散期で所定労働時間が変わるなど、常に一定の勤務時間で働くわけではないゆえのデメリットもあります。
勤怠管理が複雑になる
一定期間ごとに所定労働時間を設定する変形労働時間制は、勤怠管理が複雑になりやすく、残業時間が発生した場合は通常とは異なる算出方法での計算が求められます。そのため、労務担当者を増やしたり、あらかじめ勤怠管理システムを導入し、データベースを作成したりするなどの対策も必要です。
他部署との就業時間が合わなくなる
また、他部署との就業時間が合わなくなることもデメリットのひとつです。変形労働時間制を一部の部署で採用した場合、他部署とは就業時間が異なる可能性があります。例えば、閑散期に所定労働時間を短く設定していても、他部署とのかかわりで結局長く働いてしまうことがあります。所定労働時間よりも多く働きすぎると法律違反になる恐れもあるため、組織全体での協力や理解が不可欠です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
変形労働時間制の導入方法
変形労働時間制を導入するために求められる手順は以下のとおりです。
-
1.勤務実態の調査
-
2.労働時間や対象者の決定
-
3.就業規則の変更と労使協定の締結
-
4.労働基準監督署への届出
-
5.従業員に周知して運用を開始
1. 勤務実態の調査
変形労働時間制は、勤務実態の調査なくしていきなり導入することはできません。そもそも変形労働時間制は、繁忙期や閑散期が分かれている場合に効率よく業務を遂行することに適した制度です。そのため、まずは実際の勤務実態を調査することから始めます。
具体的には、繁忙期と閑散期にあたる期間の調査や、繁忙期にどのくらいの勤務時間を確保することが望ましいかなどを、調査であらかじめ把握します。
2. 労働時間や対象者の決定
調査結果が出た後は、実際に導入する際の所定労働時間や、対象となる部署、対象者を決定します。対象者については調査結果を参照し、どの時期にどのくらいの残業が発生しているかを確認しながら、繁閑の差が出るスパンなども含めて総合的に判断することが重要です。
3. 就業規則の変更と労使協定の締結
変形労働時間制の導入によって労働条件が変更になるため、就業規則の見直しが必要です。具体的な内容として、以下のような項目が挙げられます。
- 対象労働者の範囲
- 対象期間と起算日
- 労働日と労働時間
- 有効期限
変形労働時間制の導入にともない、企業は就業規則の変更および対象者との間で労使協定を締結する必要もあります。ただし、週単位や年単位の変形労働時間制を導入する場合には労使協定を締結する必要がある一方で、月単位の変形労働時間制については、就業規則に一定の内容を定めるだけでよく、労使協定は不要です。
就業規則の変更や労使協定の締結が完了したら、対象者に対して交付します。これは、対象者が自身の労働条件を把握するための重要な措置です。
4. 労働基準監督署への届出
さらに、厚生労働省が指定した届出書を作成し、労働基準監督署へ提出することも必要です。この届出書には、変形労働時間制の導入に関する詳細な情報や就業規則の変更内容が記載されます。また、残業や休日出勤の可能性がある場合には、36協定も提出する必要があります。
5. 従業員に周知して運用を開始
労働基準監督署への届出が完了したら、変形労働時間制の運用を開始できます。ただし、従業員の混乱を避けるために、導入の1か月前までには全従業員に対して制度の概要や導入背景について説明しておくことが必要です。事前の準備期間を設けることにより、従業員が制度について理解を深め、円滑な運用が可能になります。
また。運用開始後は、設定した就業規則や所定労働時間を厳守して運用することが重要です。運用中に問題や疑問が生じた場合には、誠実に対応して労使間の信頼関係を構築することで、効果的な変形労働時間制の運用が可能になります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
変形労働時間制の注意点
変形労働時間制の導入を検討する際は、以下の注意点について理解しておきましょう。
- 労働時間の繰り越しはできない
- 所定労働時間は後から変更できない
- 満18歳未満の従業員には変形労働時間制を適用できない
ここからは、それぞれの注意点について詳細を解説します。
労働時間の繰り越しはできない
変形労働時間制では、日ごとの所定労働時間を厳守する必要があります。つまり、労働時間を繰り越して所定労働時間と相殺することはできません。例えば、1日の所定労働時間が8時間と定められている期間で、1日に9時間働いた場合は、別の日に1時間早く退勤したとしても相殺されず1時間分の残業代が発生し、1時間分の早退扱いになります。
所定労働時間は変更できない
所定労働時間は一度決定したら基本的に変更できません。労働者の権利を保護し、労働時間の安定性を確保するために労使協定や就業規則で定められているため、決定後はその範囲内での労働が原則となります。
たとえ1週間の労働時間が40時間以内に収まっている場合でも、所定労働時間を変更するだけで変形労働時間制の要件を満たせなくなります。そのため、導入開始前には十分なデータ分析を行い、適切な所定労働時間を設定することが必要です。労働時間の適正な管理と労使の合意内容を遵守し、変形労働時間制を円滑に運用しましょう。
満18歳未満には変形労働時間制を適用できない
満18歳未満の年少者には、原則としてフレックスタイム制を含めた変形労働時間制を適用できません。ただし、労働基準法第60条3項により、以下の2つの例外が認められています。
- 1週間の労働時間が40時間以内かつ、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内にした場合、他の日の労働時間を10時間まで延長可能
- 1週間の労働時間が48時間以内かつ1日8時間以内の範囲内で、1か月や1年単位の変形労働時間制を実施
年少者を雇用する場合は、正しい知識で法令違反にならないような対応が必要です。
参考:労働基準法 60条3項
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
変形労働時間制の適切な管理には給与ソフトの導入を検討しよう
変形労働時間制は、時期によって繫閑の差が顕著な場合に多くのメリットが得られる働き方です。ただし導入する際は、就業規則の変更や労働基準監督署への届出など適切な手続きをする必要があるほか、労働時間の繰り越しや決定した所定労働時間の変更ができない点には注意してください。
変形時間労働時間制のような特殊な雇用形態でも、正確な給与計算を行うためには「弥生給与 Next」などのクラウドサービスの導入がおすすめです。給与計算や年末調整をスムーズに行えるうえ、他社の勤怠管理サービスと連携可能です。業務効率化にぜひお役立てください。
- ※本記事は2024年5月時点の情報をもとに執筆しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者下川めぐみ(社会保険労務士)
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ所属社労士。
医療機関、年金事務所等での勤務の後、現職にて、社会保険労務士業務に従事。