住民税の基本的な計算方法は?計算期間・納付方法などを解説
更新
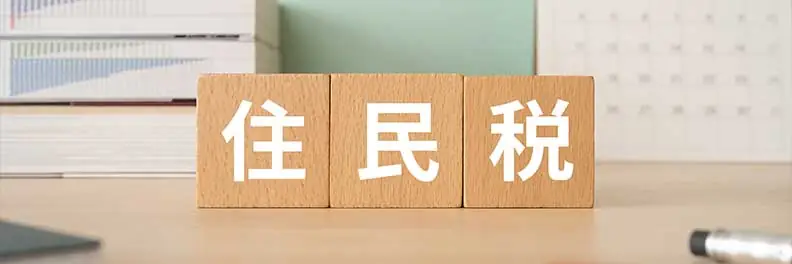
給与明細を見ると控除の欄に必ず「住民税」がありますが、住民税の計算方法はあまり知られていません。また、そもそも住民税についてよく知らないという方も多いでしょう。
本記事では、住民税の求め方を大まかに知りたい人や、住民税の計算方法に興味がある給与担当者に向けて、住民税の計算方法や計算期間、納付方法などをまとめました。また、住民税とは何かを解説したうえで、住民税に関するよくある質問とその回答も紹介します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
住民税の基本的な計算方法
そもそも住民税は、住民票のある地方自治体(市区町村)が金額を計算して徴収するため、企業や個人が計算しなければならないケースはほとんどありません。地方自治体によっては、納税額を知りたい人に向け、住民税額を大まかに計算できるシミュレーションツールや計算ツールをWebサイトで公開している場合もあります。
まずは、住民税額や税額を決める要素を知りたい人向けに、住民税の計算方法を解説します。
1. 総所得額を求める
住民税額は所得金額によって変わるため、まずは納税者の総所得額を求めます。会社などに雇用されている人は「自分には給与所得しかない」と思いがちですが、ケースによってはそれ以外の所得があることも考えられます。以下に所得の種類とその内容を簡単に紹介しますので、該当するものがないかご確認ください。
- 給与所得…雇用されている人がもらう給料や賞与の総額
- 事業所得…事業による所得。会社組織でなくても、農業や漁業、フリーランスなどの自営業も含む
- 利子所得…国内外すべての預貯金の利子、国債や地方債などの特定公社債の利子
- 配当所得…保有する株式の配当金、出資余剰金や証券投資信託などの分配
- 不動産所得…土地や賃貸住宅、航空機、船舶などの貸付による所得
- 一時所得…満期保険金や懸賞などの賞金(ただし宝くじの当選金は課税対象ではない)
- 譲渡所得…土地や住宅、株式やゴルフ会員権、機械設備などを譲渡したとき得た収入
- 雑所得…年金や恩給、原稿料や講演料、暗号資産で得たお金などの主な生業以外の副収入
- 山林所得…5年を超えて所有する山林を伐採、または立木のまま売って得た収入
- 退職所得…いわゆる退職金
2. 課税所得額を求める
次に、課税対象となる課税所得額を求めましょう。課税所得額は、総所得額から所得控除額を引くとわかります。住民税の所得控除は、「基礎控除」や「扶養控除」など、以下のとおりです。
- 基礎控除
- 扶養控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
自分が受けられる控除の内容と、控除額を確認しておきましょう。
なお、住民税を算出する際は所得控除によって課税額が減額されますが、「ふるさと納税」は、税額控除の一種として扱われます。
3. 税率をかけて税額控除額を引き所得割額を算出する
「所得割額」とは、住民税のうち、個人の所得額によって変わる税額のことです。課税所得額に税率をかけ、調整控除を適用したうえで税額控除を差し引いて計算します。
住民税の税率 は一般的に10%で、内訳は6%が市区町村民税、4%が都道府県民税(政令指定都市の場合は8%が市民税、2%が道府県民税)です。ただし、財政上の理由から税率が異なる市区町村もあります。例えば神奈川県 では、2026年度まで県民税に「水源環境保全税」の0.025%が加算されるため、税率は10.025%です。また、兵庫県豊岡市は超過課税を適用しているため、10.1%となっています。
課税所得額に税率をかけた後、調整控除を適用し、さらに税額控除を差し引いて計算します。調整控除とは、所得税と住民税で人的控除の額が違うことから発生する税負担を調整するためのものです。税額控除には、ふるさと納税の他、所得税から控除しきれなかった分の住宅ローン控除や外国税額控除などがあります。
4. 所得割額と均等割額をたす
最終的に納付する住民税額は、「所得割額」と「均等割額」を合算します。均等割額とは、住民税が課税されるすべての人に一律に課せられる金額です。均等割額は一般的に、都道府県民税1,000円、市区町村税3,000円、2024年度から課せられるようになった森林環境税1,000円の計5,000円ですが、異なる均等税額を採用している市区町村もあります。
例えば、兵庫県神戸市と宮城県仙台市の均等割額は6,200円です。地域だけでなく年度によっても変わることがあるため、確認しておきましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
そもそも住民税とは?
住民税とは、住んでいる地方自治体に納める地方税で、「市区町村民税」と「都道府県民税」を合わせたものです。納税者は両方をまとめて市区町村に納め、その後市区町村が都道府県民税分を都道府県に払い込むしくみになっています。納めた住民税は、地域の教育や福祉、上下水道の整備、ごみ処理、消防や救急の活動など、生活を支える行政サービスの財源として活用されています。
住民税の金額は、一律の「均等割」と、所得額に応じて変わる「所得割」の合計です。ただし、所得が基準に満たない場合や生活保護法による生活扶助を受けている場合は、均等割と所得割の両方が非課税 となります。
住民税の納付先は、「1月1日時点で住民票がある地方自治体」です。例えば2月に異なる市区町村に引っ越した場合でも、その年は1月1日に住民票があった市区町村に住民税を払うことになります。
住民税の計算期間は1月1日~12月31日
住民税は、1月1日から12月31日までの所得を基に計算された税額を次の年度に納税します。
例えば学生時代に所得がない新社会人の場合、入社した年は住民税が課税されず、2年目の6月から給与からの天引きが始まります。その一方で、自営業の場合は、確定申告をした年の6月ごろに、前年の所得に基づく納税額が記載された「住民税決定通知書」が郵送されてきます。納税は一括の他、4回に分けて払うことも可能です。住民税決定通知書に添付されている納付書を確認し、指定された期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどで支払いましょう。
なお、個人事業主やフリーランスの住民税の計算期間は、1月から12月までの売上から経費や控除額を引いた所得を基本として計算されます。入金が翌月や翌々月になるケースであっても、基本は売上発生時に計上される点に注意してください。
また、現在働いていない人でも、前の年に一定額を超える所得があれば納税の義務が発生するため、この点にも注意が必要です。
住民税の納付方法は普通徴収と特別徴収の2つ
住民税には、2種類の納付方法(徴収方法)があります。どちらの納付方法になるかは、基本的に働き方によって決まるため、自分の意思で好きな方法を選べるわけではありません。それぞれの納付方法の違いを確認しておきましょう。
普通徴収
普通徴収とは、納税者が市区町村に直接住民税を納める方法のことです。対象者は主に、個人事業主やフリーランスといった給与所得者以外の人です。
普通徴収では、住民票がある市区町村から届いた納税通知書に添付されている納付書を使用して住民税を納めます。銀行やコンビニエンスストアで納付できる他、クレジットカードやインターネットバンキング、二次元バーコード決済などでの納付も可能です。利用する決済サービスによってはポイントを獲得できることもあるため、確認しておくとよいでしょう。ただし、決済時に別途手数料やシステム利用料などがかかる場合があります。
普通徴収の場合、一括納付もしくは4回の分割納付が選択できます。いずれの場合も期限内に納付を済ませましょう。期限を過ぎてしまうと延滞金が発生するため、注意が必要です。
特別徴収
特別徴収とは、企業や公共団体が給与から天引きし、従業員の代わりに納税する方法のことです。企業に勤めている人や、国や地方自治体に勤務する公務員などの給与所得者は、原則として、特別徴収による納付が義務付けられています。
特別徴収では、毎月支払われる給与から住民税が天引きされるため、個人で納税する手間がかからず、納税をうっかり忘れることがありません。加えて、1年分の住民税を12か月かけて分割で納付できるため、1回当たりの納税額を抑えられる点も従業員側のメリットが大きいでしょう。とはいうものの、事業者側としては従業員全員の住民税をミスなく管理する必要があり、なおかつ従業員の居住地ごとに異なる市区町村へ納めなければならないため、手間がかかります。
特別徴収について、こちらの記事で解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税の計算でよくある質問
住民税についてわかりにくいことや、よくある疑問を質問と回答の形でまとめました。ぜひ参考にしてください。
住民税が非課税になる条件は?
住民税が非課税になるケースでは、所得割と均等割の両方(住民税そのもの)が非課税になる場合と、所得割のみ非課税になる場合があります。それぞれのケースについて解説します。
〈所得割と均等割の両方が非課税になる条件〉
所得割と均等割のどちらも非課税になる条件は、自治体によって定められています。詳細な条件は各自治体によって異なるため、確認しておきましょう。
一例として、東京23区の場合、住民税が非課税になるのは以下の条件に該当するときです。
-
- 1月1日の時点で生活保護法に基づく生活扶助を受けている
- ひとり親または寡婦(夫と離別や死別した女性)、未成年者、障害者の場合:前年所得が135万円以下(給与所得者の場合は年収204万4,000円未満)
- 扶養する親族や生計を同じくする配偶者がいない場合:前年所得が45万円以下
- 扶養する親族や生計を同じくする配偶者がいる場合:前年所得が「(本人・扶養親族・同一生計配偶者の合計人数)×35万円+31万円」以下
〈所得割のみが非課税になる条件〉
住民税のうち、所得割のみが非課税になる条件も、自治体によって異なります。東京23区の場合は以下の条件に当てはまるときです。
-
- 扶養する親族や生計を同じくする配偶者がいない場合:前年所得が45万円以下
- 扶養する親族や生計を同じくする配偶者がいる場合:前年所得が「(本人・扶養親族・同一生計配偶者の合計人数)×35万円+42万円」以下
住民税はだれが計算する?
住民税を計算するのは、市区町村です。これは給与から天引きする特別徴収であっても同様で、雇用する側(事業主)の経理担当者や給与担当者が計算する必要はありません。ただし、雇用側は特別徴収の手続きを行う必要があります。
雇用する側は、従業員の住民票がある各市区町村から「特別徴収税額の決定通知書」を受け取り、前年の所得に対する住民税を6月から翌年5月にかけて控除する必要があります。このとき、雇用する側を「特別徴収義務者」、雇用されている従業員を「納税義務者」と呼びます。従業員から控除した税額は、翌月10日に各市区町村に納付しなければなりません。
従業員が入社したときに必要な住民税の手続きは?
入社の前年に所得がなかった入社1年目の従業員の場合、住民税に関して事業所がする手続きなどはありません。入社2年目以降は、その従業員の住民票がある市区町村からの特別徴収税額通知に沿って雇用側が給与から控除し、該当する市区町村に納税する義務を負います。
入社した従業員が普通徴収で住民税を納めていた場合は、事業所が従業員の住民票がある市区町村に「特別徴収切替依頼書」を提出します。その後、市区町村から「特別徴収額の決定・変更通知書」が届いたら、給与からの天引きを開始しましょう。
さらに、入社した従業員が前職でも特別徴収で納税していた場合は、前職の事業所から送付される「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、退職日の翌月10日までに市区町村に提出することになっています。これにより、前職の特別徴収を引き継げます。
従業員が退職した場合の住民税はどうなる?
従業員が退職した場合は、事業所が退職日の翌月10日までに、従業員の住民票がある市区町村に「給与所得者異動届出書」を出してください。
退職者の住民税の取り扱いは、退職する月によって異なります。退職日が1月1日から5月31日の場合、原則として、5月分までを最後の給与または退職手当から一括徴収しなければなりません。また、退職日が6月1日から12月31日の場合は、普通徴収に切り替えるか、最後の給与または退職手当から一括徴収することになります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税は企業での計算は不要だが特別徴収の手続きが必要
住民税は、市区町村がインフラや福祉、消防や救急体制などを維持するために徴収される税金です。
住民税の計算は、納税者が住民登録している市区町村が行うため、個人や事業所が計算する必要はありません。ただし従業員を雇用する場合は、前年に所得があったかどうか、前職では普通徴収だったのか、それとも特別徴収だったかを踏まえて、特別徴収を行うための手続きを進めます。また、従業員が退職する場合は、退職月によって徴収の仕方が異なるため、注意しておきましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。







