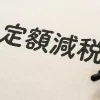2025年(令和7年)分の年末調整の変更点は?留意事項も解説
更新
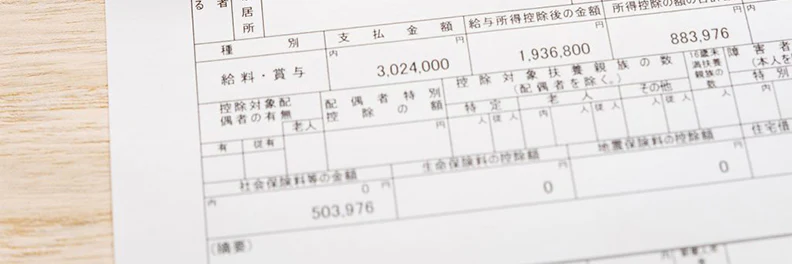
2025年分の年末調整の変更点について、注意すべきポイントを解説します。2025年は基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正、特定親族特別控除の創設など、大きな制度改正が実施されました。これにより、年末調整時の業務内容はこれまでと異なる点が多くなります。
そこで本記事では、2025年分の年末調整における主な変更点をまとめました。改正後の控除額や必要書類など、重要なポイントを押さえ、年末調整業務をスムーズに進めましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
2025年(令和7年)分の年末調整における変更点は4つ
2025年分の年末調整では、主に4つの重要な変更が予定されています。これらの変更は、国税庁が公表する「令和7年4月源泉所得税の改正のあらまし」や、財務省「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」などの内容に基づいています。
-
- 基礎控除の見直し
- 給与所得控除の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族等の所得要件の改正
上記の変更点は、従業員の扶養状況や所得水準によって影響が異なるため、年末調整を行う事業者や担当者は早めに内容を確認し、対応することが求められます。ここから、それぞれの変更点について詳しく解説していきます。
-
参照:国税庁「令和7年4月源泉所得税の改正のあらまし
」P1-2,4
-
参照:財務省「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
」
変更点1. 基礎控除の見直し
2025年分の年末調整では、「基礎控除」の適用要件と控除額が見直されました。所得水準に応じて控除額が変動するしくみは従来と同様ですが、判定に用いる所得金額の区分方法などに一部変更があります。
具体的な変更点
従来は、合計所得金額が2,400万円以下の納税者に対しては、一律48万円の基礎控除が適用されていました。しかし改正後は、合計所得金額が2,350万円以下である場合に、所得に応じて段階的に58万円から95万円の基礎控除額が適用されるしくみに変更されました。最大となる95万円の控除が認められるのは、合計所得金額が132 万円以下の場合です。改正により、所得の少ない納税者ほど控除額が増えるため、低所得者層および中所得者層の税負担軽減が期待されます。
年末調整においては従業員の合計所得金額を正しく把握したうえで、適切な控除額を適用することが求められます。控除額の詳細な区分は次項の表で確認してください。
基礎控除額の表
以下の表は、改正後の基礎控除額を合計所得金額ごとにまとめたものです。なお、「特定支出控除」や「所得金額調整控除」の適用がある場合は、以下の金額と異なる場合がありますので、注意してください。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和7・8年分) | 基礎控除額(令和9年分以降) |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
変更点2. 給与所得控除の見直し
「給与所得控除」にも一部見直しが加えられました。年収が比較的低い層に対して控除額が引き上げられるよう調整されています。
具体的な変更点
給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円に引き上げられました。これにより、給与収入が190万円以下の場合は、控除額が一律65万円となり、所得税の負担が軽減されます。また、給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例も、必要経費算入金額が65万円に引き上げられています。
給与所得控除の表
改正された給与所得控除額について、給与等の収入金額の区分別にまとめたものが以下の表です。給与所得控除の最低保障額が引き上げられたため、年収が190万円以下の方は一律で65万円の控除が適用されます。給与の収入金額が190万円を超える場合の控除額については、変更はありません。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
変更点3. 特定親族特別控除の創設
新たな控除として特定親族特別控除が創設されます。これは、特定の親族を扶養している納税者に対して、税負担の軽減を図ることを目的としたものです。
具体的な内容
特定親族特別控除の対象となる「特定親族」とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色・白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。なお、親族には児童福祉法に基づき養育を委託された里子も含まれます。
従来、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、合計所得金額が48万円を超えると扶養控除の対象外とされていました。しかし今回の改正により、合計所得金額が58万円以下であれば特定扶養控除の対象となり、さらに58万円を超えても123万円以下であれば、所得に応じて段階的に特定親族特別控除を受けられるようになりました。
特定親族特別控除の適用を受けるためには、年末調整時に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。申告書の提出がない場合は控除が適用されません。
-
参照:国税庁「No.1180 扶養控除
」
特定親族特別控除額の表
以下の表は、特定親族の合計所得金額ごとに適用される特定親族特別控除額をまとめたものです。ただし、特定支出控除の適用がある場合は、表の控除額と異なる場合がありますので、注意してください。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
変更点4. 扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除などの適用対象となる扶養親族等の所得要件も見直されました。控除の可否が従来と異なるケースが出てくる可能性があるため、年末調整時には対象者の所得状況を改めて確認しましょう。
具体的な変更点
基礎控除の見直しに伴い、扶養控除や配偶者控除、ひとり親控除、勤労学生控除などに関する所得要件が改正されます。
-
- 扶養控除および配偶者控除の対象となる扶養親族や生計を一にする配偶者の合計所得金額要件が、従来の48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
- ひとり親控除の適用を受けるための要件である、生計を一にする子の総所得金額等も、同様に48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
- 勤労学生控除の適用を受ける場合の合計所得金額要件は、75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
また、給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等(家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人など)に適用される事業所得等の所得計算の特例において、必要経費として認められる金額が、従来の55万円から65万円に引き上げられます。
所得要件の表
以下の表は、主な扶養親族等の所得要件をまとめたものです。なお、特定支出控除の適用がある場合は、実際の金額が異なる場合がありますので、注意しましょう。
| 区分 | 所得要件 |
|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 58万円以下(合計所得金額) |
| ひとり親の生計を一にする子 | 58万円以下(総所得金額等) |
| 勤労学生 | 85万円以下(合計所得金額) |
-
参照:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
」
-
参照:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A
」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
2026年(令和8年)以降の年末調整に反映予定の変更点
2026年(令和8年)以降に適用が見込まれる税制改正では、生命保険料控除の制度見直しや、特定親族特別控除の適用拡大などが予定されています。これらの改正により、従業員ごとに影響の有無が分かれる可能性があるため、変更内容を正確に把握しておきましょう。
生命保険料控除の拡充
一般生命保険料控除について子育て世帯向けの拡充措置が導入されます。具体的には、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、所得税の一般生命保険料控除の上限額が現行の4万円から6万円へと引き上げられます。
この一般生命保険料控除の拡充は2026年分のみの時限的措置であり、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除の上限額、また3つの控除の合計適用限度額(12万円)には変更がありません。なお、対象となるのは23歳未満の扶養親族がいる場合のみであり、該当しない世帯は従来どおりの控除額が適用されます。
-
参照:厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)
」P.23
特定親族特別控除の適用
2026年(令和8年)1月以降に支払われる給与や公的年金等からは、特定親族特別控除が源泉徴収の際にも適用されます。給与の場合、19歳以上23歳未満の生計を一にする親族の合計所得金額が58万円超100万円以下であれば、扶養控除等(異動)申告書に「源泉控除対象親族」として記載することで、毎月の源泉徴収税額の計算時に控除が適用されます。
それに対して、公的年金等については、19歳以上23歳未満の生計を一にする親族の合計所得金額が58万円超85万円以下の場合「源泉控除対象親族」として認められ、同様に源泉徴収の際に特定親族特別控除が適用されます。合計所得金額が100万円超123万円以下の特定親族については、給与所得の源泉徴収税額の計算には反映されませんが、年末調整時に「特定親族特別控除申告書」を提出することで、最終的に控除が適用されます。
また、公的年金等の源泉徴収税額の計算においては、合計所得金額が85万円超123万円以下の特定親族は控除が適用されませんが、確定申告を行うことで、特定親族特別控除の適用を受けることが可能です。
-
参照:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
」P.7-9
-
参照:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A
」P.8-10
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
2025年(令和7年)分の年末調整における留意事項
2025年の年末調整では、上述のとおり複数の重要な改正が適用されます。ここでは、年末調整を円滑に進めるうえで特に留意すべきポイントを解説します。
従業員に改正で新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認する
2025年の税制改正により、扶養親族等に関する所得要件の引き上げや、特定親族特別控除の創設が行われたことで、これまで控除対象外だった親族が新たに対象となるケースが増加しています。そのため、年末調整の手続きでは従業員に対して、新たに扶養控除等の対象となる親族がいないか確認が求められます。該当する親族がいる場合は、「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらわなければなりません。また、特定親族特別控除の適用を希望する従業員がいる場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出してもらいましょう。これらの申告書が提出されていない場合、控除が適用されず、従業員の税負担が増えることとなります。
改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて年末調整の計算をする
2025年分の年末調整からは、改正後の基礎控除額や給与所得控除額、特定親族特別控除額、そして扶養親族等の所得要件に基づいて計算を行うことになります。これらの控除額や所得要件の変更は、各従業員の所得税額に直接影響するため、正確な計算が求められます。計算方法の詳細は、国税庁のホームページで公開されています。年末調整事務を適切に進めるためにも、国税庁の最新情報を定期的に確認し、正確な知識をもって対応することが大切です。
-
参照:国税庁「令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
年末調整は早めの準備が大切
2025年分の年末調整は、4つの変更点があります。
-
- 基礎控除額の見直し
- 給与所得控除額の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族等の所得要件の改正
特に新しい控除の創設や所得要件の変更は、従業員の税額計算に大きな影響を与えるため、経理担当者はこれらの変更点を正確に理解し、準備を進めましょう。スムーズな年末調整事務を行うためにも、国税庁からの最新情報の確認、従業員への周知、そして必要な申告書の準備など、早めの対応が非常に大切です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
年末調整をスムーズに進めるなら「弥生給与 Next」
2025年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件改正、さらには特定親族特別控除の創設など、対応すべき改正点が多岐にわたります。これらの変更に正確かつ効率的に対応するためには、業務フローの見直しや従業員への案内、書類の管理が不可欠です。
「弥生給与 Next」は、円滑な年末調整業務を実現するクラウド給与計算ソフトです。従業員からの申告情報のオンライン収集や、年税額の自動計算、源泉徴収票のWeb配信などにも対応しており、煩雑になりがちな年末調整業務を大幅に効率化します。また、紙による申告情報の提出にも対応しているため、全従業員に対して柔軟なワークフローを提供できます。法改正への確実な対応と業務負担の軽減を両立したい方は「弥生給与 Next」の活用をご検討ください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。