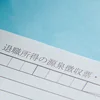年末調整は退職者も対象?例外となるパターンもわかりやすく紹介
更新

年末調整は、従業員の年間所得に基づいて所得税の過不足を精算する手続きです。対象となるのは12月31日時点で会社に在籍している従業員ですが、それ以前の年内に退職した人についても、状況によっては年末調整の対象となるケースがあります。対象とならない場合でも、退職者本人が確定申告を行い、所得税の過不足を精算することが必要です。
本記事では、退職者に対して会社が行う年末調整の基本的なルールや、病気などによる特例的な取り扱い、さらに確定申告との違いや関係性について詳しく解説します。源泉徴収票の取り扱いや紛失時の対応など、よくある質問もまとめているのでぜひ参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
年末調整は退職者も対象?

年末調整の対象となるのは、原則として12月31日時点で会社に在籍している従業員です。基本的に年の途中で退職した人は対象外ですが、一定の条件を満たす場合には例外的に対象となるケースがあります。これらの例外については、次の項目で詳しく解説します。
なお、年末調整の対象かどうかに関わらず、源泉徴収票は退職者が確定申告を行う際に必要です。そのため、会社は退職者に対して源泉徴収票を交付する義務があります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
例外として退職者の年末調整を行うパターン
通常、年末調整は12月まで勤務する従業員が対象ですが、退職者でも例外的に行われる場合があります。具体的にどのような条件で退職者が年末調整の対象となるのか、5つのパターンを解説します。
海外支店等への転勤などで非居住者となった人
対象となるのは「給与の支給額が2,000万円以下」で、かつ「1年以上の海外転勤が見込まれるケース」です。この場合、出国日までに支払われる給与について年末調整を行います。
これは、海外勤務が1年未満の場合は日本の居住者とみなされ、引き続き年末調整の対象となるのに対し、1年以上になると非居住者扱いとなり、それ以降の給与は国内の年末調整で処理されなくなるためです。また、出国後に支給される給与についても、年末調整の対象外となります。
死亡によって退職した人
従業員が死亡した場合でも、その年に支払われた給与は年末調整で所得税を精算することが求められます。遺族が準確定申告を行うこともありますが、会社には死亡退職者に対して年末調整を行い、「給与所得の源泉徴収票」を作成・交付する義務があります。ただし、死亡日以降に支払期日が到来する給与は「相続財産」として扱われるため、年末調整の対象には含めず、源泉徴収票にも記載しません。
死亡退職者に関する年末調整は、通常のケースとは異なる扱いとなるため、事前の確認が望まれます。
著しい心身の障害のために退職し、年内の再就職が見込めない人
病気やけが、または精神疾患などにより退職した場合で、年内の再就職が困難と見込まれるケースでは、その退職者は例外的に年末調整の対象となります。ただし、年内に再就職して給与を受け取る可能性がある場合は、年末調整の対象外となり、確定申告で精算する必要があります。
対応にあたっては、本人の申告や会社側が独断で判断するのでなく、医師の診断書や就労困難を示す客観的な資料を基に、慎重に判断することが求められます。
12月に支給される給与等の支払いを受けた後に退職した人
年末調整の対象かどうかは、退職日が12月末かどうかではなく、12月中に実際に給与の支払いを受けているかで判断されます。そのため12月中の給与支給後に退職する従業員は、基本的に年末調整の対象となります。例えば、12月10日に最終給与を受け取り、その後12月31日付で退職したケースなどが該当します。このように、その年の給与所得が確定しており、年内に追加の支払いがないと判断されるため、会社は年末調整の実施が求められます。ただし、退職日が12月末であっても、12月分の給与が翌年1月に支払われる場合は、12月支給分(11月度)までで年末調整が実施され、翌年1月に支払われる12月分は年末調整の対象外となります。
給与の総額が123万円以下で年内に再就職で給与を受け取る見込みのない人
パートタイマーやアルバイトの退職者で、年内に再就職の予定がなく、その年の給与総額が123万円以下(※2025年(令和7年)度基準)の場合は、年末調整の対象に含まれます。ただし、この条件は年内に他の収入がないことが前提であり、再就職して給与を受け取る可能性がある場合は対象外となります。
なお、この123万円の基準は、給与所得控除と基礎控除を考慮した所得税が課税されない水準として設定されています。給与総額がこの金額以下であれば、所得税の過不足を年末調整で適切に処理することが可能です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
年末調整をしない退職者は確定申告の対象?
年の途中で退職し年末調整が行われなかった場合でも、所得税の過不足の精算は必要なため、多くは退職者が自分で確定申告をします。確定申告は会社が行う年末調整と異なり、個人が税務署に所得と税金を申告する手続きです。ここでは、退職後の再就職の有無に分けて、確定申告の必要性を解説します。
年内に再就職する退職者の場合
年末調整の前に退職した従業員が年内に再就職し給与所得を得た場合、年末調整を行うのは再就職先の会社です。そのため、退職時には速やかに源泉徴収票を交付し、再就職先の年末調整に支障が出ないよう対応することが求められます。
ただし、年末間際に入社した場合などで、扶養控除等申告書や保険料控除証明書といった必要書類がそろわないと、年末調整は行われず、退職者自身で確定申告を行う必要が生じることがあります。
中途入社従業員の年末調整について詳しくは、以下の関連記事で解説しています。
年内に再就職しない退職者の場合
年の途中で退職し、年内に再就職せず「年末調整の未済」である場合は、退職者自ら確定申告の手続きを行います。会社で年末調整が行われていないため、その年の所得税の過不足が正確に精算されていない可能性があるからです。
また、確定申告は退職者本人が行うため、会社側からはその旨を説明します。確定申告に源泉徴収票が求められるため、会社は従業員が退職する際源泉徴収票を交付しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
退職者の年末調整に関するよくある質問
退職者の年末調整では、会社側が源泉徴収票の取り扱いで戸惑うことも少なくありません。特に再発行の依頼や交付期限については、適切な対応が求められます。ここでは、会社や担当者が押さえておくべきポイントを解説します。
退職者から源泉徴収票の再発行を求められたら?
紛失などで退職者から源泉徴収票の再発行を求められる場合があります。会社側には再発行の法的義務はありませんが、可能な限り再発行に応じることが望ましいでしょう。再発行を拒否した場合、退職者が「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出することがあり、税務署から会社へ問い合わせや税務調査が入る可能性があります。
退職者の源泉徴収票はいつまでに発行する?
退職者に交付する源泉徴収票には法律で定められた交付期限があります。原則として途中退職者の場合は退職後1か月以内に発行し、郵送または手渡しでの交付が求められます。速やかに発行できるようにしておきましょう。また、給与所得以外に退職所得がある場合は、別途退職所得の源泉徴収票も発行します。
退職所得の源泉徴収票について詳しくは、以下の記事で解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
退職者の年末調整はパターンに合わせて適切に対応しよう
退職者の年末調整は、在籍期間や再就職の有無などによって対応が異なり、正確な判断と事務処理が求められます。実務に即した適切な対応をとることで、税務署からの問い合わせや従業員とのトラブルを避けられます。
「弥生給与 Next」は、最新の法令に即した自動計算をはじめ、源泉徴収票の発行や年末調整対象者の判定、マイナンバー管理、Web給与明細配信など多彩な機能を備えており、退職者を含む幅広い従業員の給与・年末調整業務を効率的にサポートします。正確でスムーズな退職者対応を実現するために、「弥生給与 Next」の導入をご検討ください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。