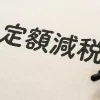定額減税を考慮した給与計算方法は?やり方や大変なポイントを解説
監修者: 中川 美佐子(税理士)
更新
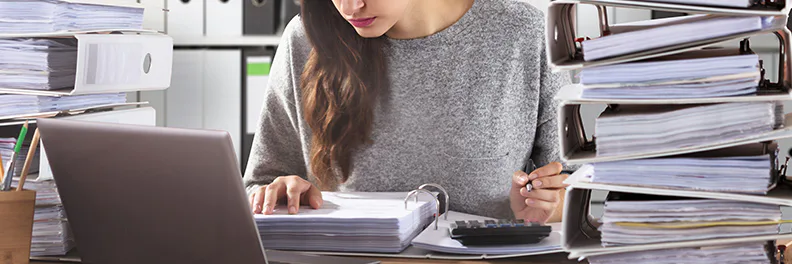
2024年(令和6年)6月から始まる定額減税は、給与計算時に通常とは異なる業務が発生します。毎月の給与計算だけでなく年末調整時にも対応する必要があるため、給与計算業務の担当者にとって大きな負担となる可能性が高く、早めの対策が大切です。
本記事では、定額減税のあらましや計算方法、事前に押さえておきたいポイントについて解説します。給与計算業務担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
定額減税とは
定額減税は、2024年(令和6年)6月から実施されている制度です。「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、2024年(令和6年)4月1日に施行されました。定額減税は「令和6年度税制改正法の大綱」に盛り込まれた項目のひとつです。
定額減税は、2024年(令和6年)6月から納税者本人と扶養家族を対象に実施されます。また、所得金額の合計が1,805万円以下(給与収入だけの場合は2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を利用する場合は2,015万円以下)であることが条件です。所得税(国税)と住民税(地方税)に対して減税が実施され、給与の支払者は月次減税事務と年調減税事務を行う必要があるため、給与計算担当者には大きな負担が予想されます。
定額減税の詳細は以下の記事を参照ください。
所得税:3万円
所得税における定額減税は1人につき3万円で、2024年(令和6年)6月給与で源泉徴収をする所得税額から減税分を控除します。控除しきれない場合は、翌月以降の所得税から減税分を控除します。
例えば、対象者が本人と扶養家族(配偶者・子どもなど)の合計が4名であれば、減税額は「3万円×4名=12万円」です。所得税額が6月・7月で各7万円だった場合、6月の源泉徴収額は「7万円-12万円=-5万円」なので徴収額は0円となり控除の余剰分の5万円が残ります。それは次月の源泉徴収額に引き継がれ、7月は「7万円-5万円=2万円」となります。
また、年末調整までに減税額を控除しきれていない場合、翌年に繰り越さないためそのときに清算しなければなりません。
住民税:1万円
住民税における定額減税は1人につき1万円で、控除後の住民税を7月から翌年5月にわたって11か月で特別徴収します。通常の徴収方法と違い、6月分の給与からは控除しない点に注意が必要です。
例えば、対象者が本人と扶養家族の計2名で、住民税が24万円だったとします。控除後の住民税は「24万円-(1万円×2名)=22万円」となるため、これを11か月で割った2万円が各月(7月から翌年5月まで)の徴収額となります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
定額減税が給与計算の負担になる理由
従業員ごとに課税額や家族構成などが異なるため、企業(給与計算業務担当者)は従業員ごとに減税額を算出し、源泉徴収する税額を個々に計算しなければなりません。2024年(令和6年)6月2日以降に中途入社した従業員は年末調整で清算、それ以前の入社だと月次対応なので控除済みの減税額を確認する必要があるなど、対応が複雑になります。また、年末調整や法定調書提出の負担が増えることが予想されます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
定額減税の実施前に押さえておきたいポイント
企業は定額減税の実施にあたって、給与計算業務で混乱が起きないよう以下のポイントを押さえておきましょう。
-
1 定額減税について従業員への説明を実施する
-
2 従業員が扶養家族などの情報を正確に申請しているか確認する
-
3 所得制限に該当する従業員の確認を行う
-
4 定額減税の事務処理を適切に行えるか、給与計算ソフトやシステムの対応状況を確認する
-
5 定額減税を反映した源泉徴収額の管理方法を検討する
-
6 定額減税開始後の業務効率化について検討する
まずは、減税対象者である従業員への周知徹底をしましょう。併せて、扶養控除等申告書を提出しているか、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者に係る申告(源泉徴収に係る定額減税のための申告書)を提出しているか、内容に間違いがないかなど、申告状況の確認も大切です。
また、実務での不備を防ぐためにも、現状の業務体制が制度に対応できるか確認しましょう。具体的には、定額減税に対応した給与計算ソフトの導入やその登録内容の確認、人員配置や業務配分などの検討が効果的です。
現場の負担やミスをなくすためにも、早めの準備・対策をおすすめします。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
【一覧】定額減税に関する国税庁のサイト
国税庁は定額減税に関する情報を提供するために、以下のサイトを公開しています。制度の把握や事前準備の参考にしましょう。
定額減税 特設サイト
国税庁の特設サイトでは、定額減税についての各種最新情報を掲載しています。相談窓口や解説動画も掲載されているため、最新情報や変更点を知りたい場合はこちらを参照しましょう。
国税庁「定額減税 特設サイト」
定額減税のしかたパンフレット
国税庁が特設サイトで配布しているパンフレットでは、給与等の源泉徴収事務に係る定額減税のしかたについて解説されています。定額減税のやり方について詳細な手順が解説されているため、実際に作業を行う経理担当者は特に目を通すことで定額減税事務の理解が深まります。
国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF)」
定額減税のQ&A
こちらは、前段のパンフレットでは記載しきれない細かな点まで言及しているQ&Aです。具体的な疑問と回答形式になっているので、給与計算業務で悩んだときは役立ちます。
定額減税に関する様式・記載例
こちらは、各人別控除事績簿や源泉徴収に係る定額減税のための申告書など、実際に給与計算業務を行うときの書類様式をダウンロードできます。年末調整の効率的な計算ができるシートもあるため、業務に活用しましょう。なお、2024年4月1日時点で様式は確定しておらず、今後変わる可能性があります。
国税庁「様式・記載例」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
定額減税のよくある質問
定額減税とは何ですか?
定額減税とは、2024年(令和6年)4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度で、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年(令和6年)の税金から控除される施策です。
定額減税について、こちらの記事で詳しく解説しています。
定額減税は住宅ローン控除にどう影響しますか?
住宅ローンを組んでいる方やこれから組む方にとって、定額減税が住宅ローンに控除にどう影響するかは気になるところです。こちらの記事で詳しく解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算ソフトを活用して給与計算業務の負担を軽減しよう
2024年(令和6年)6月から実施される定額減税により、給与計算業務の負担が増えることでしょう。定額減税対象者の判定や、家族情報の登録内容を基にした定額減税額の算出・管理など、煩雑な業務が想定されます。
定額減税にかかわる業務の効率化には、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は定額減税への対応はもちろんのこと、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しています。自社に合ったサービスを活用して、業務の効率化を目指しましょう。
- ※本記事は2024年4月1日時点の情報を基に執筆しています
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者中川 美佐子(税理士)
税務署の法人税の税務調査・申告内容の監査に29年勤務後、令和3年「たまらん坂税理士法人」の社員税理士(役員)に就任。法人の暗号資産取引を含め、法人業務を総括している。