在職証明書とは?発行が必要なケースや記載する項目を解説
監修者: 勝山 未夢(社会保険労務士)
更新
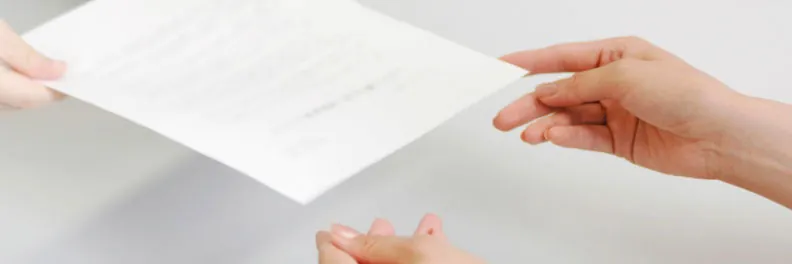
企業の人事・総務担当者は、業務の一環として「在職証明書」の発行を従業員から求められることが少なくありません。そもそも、在職証明書とはどのような書類で、何のために必要となるものなのでしょうか。
本記事では、在職証明書の基本的な知識に加え、必要な理由や用途について解説します。フォーマットや主に記載する項目、発行時の注意点など、実務に役立つ知識をわかりやすく解説しますので、在職証明書の発行業務に携わる方はぜひご参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
在職証明書とは
在職証明書とは、従業員が企業に在籍中であることを証明するための書類です。「在籍証明書」「勤労証明書」「就業証明書」など、他の名称で呼ばれることもあります。退職証明書とは異なり、在職証明書は、発行が企業へ法的に義務付けられた書類ではありません。しかし一般的には、従業員から要請があれば発行するのが通例です。
発行業務は通常、人事部や総務部が担当し、正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトとして雇用している従業員にも発行します。ただし、派遣社員の場合、発行するのは派遣元の企業が負うべき役割です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
在職証明書の発行が必要なケース
従業員が会社に在職証明書の発行を依頼するのは、主に以下のようなケースが考えられます。これ以外にも、働いていることを確認したい場面において提出が求められることがあります。
住宅ローンや賃貸の審査
従業員が住宅ローンや賃貸契約の審査を受けるときです。これらの審査に際して、従業員は申込先の機関から安定した収入や就労状況であることが求められます。そのため、ローンの返済や家賃の支払い能力を見極めるための確認書類として、金融機関や大家から在職証明書を請求されます。
子供の入園・入学
保育園や幼稚園、または学校や学童などへの入園・入学手続きです。特に保育園などの入園に際しては、家庭で子育てするのが難しい状況なのかを見極めるために、在職証明書の情報が重要な判断材料として活用されます。保育園などでは、就労状況を確認するために、通園後も在職証明書を毎年提出するのが一般的です。在職証明書のフォーマットを、保育園を管轄する自治体が用意していることもあります。
転職や副業、資格取得
従業員が転職活動や副業を行う際にも求められることがあります。これは、転職の候補企業や内定先が、応募者の提出した履歴書や職務経歴書の内容が真正であることの確認に、在職証明書の提出を要求することが多いためです。
また、公務員の社会人採用枠や資格取得の受験要件などでは、「職務経験5年以上」などの条件があるので、その証明のために必要となることもあります。また、従業員が副業や兼業を希望する場合、本業の労働時間や業務内容を把握するために、副業先が提出を求めることがあります。
外国人の滞在関連手続き
外国人が日本で就労する際にも、ビザや在留資格の申請・更新手続きのために在職証明書が必要です。特に就労ビザを取得する際には、申請者が安定した職に就いていることを示すために、この書類の提出が求められます。
ビザの更新手続きにおいても、現在の雇用状況や就労資格を確認するために、必要になるのが一般的です。さらに、外国人従業員が転職する場合にも、新たな雇用主が就労資格証明書を取得するために現職の在職証明書が必要になります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
在職証明書のフォーマット
在職証明書には、法的に定められているフォーマットはありません。ただし、公的な証明資料として機能することが求められるので、一般的な書き方や記載事項は把握しておくことが大切です。また、提出先によっては、記載すべき項目や書式が指定されていることもあるので、それにしっかりと対応することも求められます。
たとえば、住宅ローンや賃貸契約の審査に際して、金融機関や大家は申請者の経済能力を確認したいので、在職証明書にも給与に関する情報を記載するように求めることがあります。その一方で、保育園への入園手続きで重視されるのは、勤務日数や労働時間といった項目です。このように、在職証明書を作成する際は、依頼された目的や提出先の要件を把握し、必要な情報を正確に記載することが大切です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
在職証明書に含める項目例
一般的に在職証明書に記載することが多い情報は以下のとおりです。
- 【従業員の基本情報】
- 氏名、住所、生年月日など、誰の証明書なのかを示すための情報を記載します。
- 【雇用・勤務状況に関する情報】
- 正社員・パートタイムなどの雇用形態や役職、入社年月日、雇用期間、勤務時間、勤務日数など、従業員の雇用・勤務状況を示すための情報を記載します。場合によっては、給与情報や、固定時間制/変形労働時間制などの就労形態に関する情報も記載が必要です。
- 【会社の情報】
- 会社名、所在地、連絡先、代表者や担当者の氏名など、基本的な企業情報を記載します。また、会社が公式に発行した書類であることを証明するために、会社印の押印も必要です。
これらの項目は、従業員が依頼した目的や提出先の指定に基づき、適切に記載される必要があります。提出先が求める条件次第で、記載内容を調整するようにしましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
在職証明書の発行における注意点
在職証明書が適切に発行できなければ、発行を依頼した従業員だけでなく、企業側にも弊害が生じる可能性があります。たとえば、書類不備があって保育園の入園審査に落ち、その従業員が勤務に復帰・継続するのが難しくなるといったケースです。このような事態を避けるために、発行業務に携わる担当者は以下の点に注意しましょう。
記載すべき情報を確認する
在職証明書に記載すべき情報は、提出先や発行目的によって異なります。そのため、従業員から発行依頼を受けた際には、提出先や使用目的を忘れずに確認しましょう。同時に、提出先が特定の記載項目や書式を指定していないか把握することも大切です。
情報は不備なく記載する
在職証明書に記載する内容は、すべて正確でなければなりません。記載事項に誤りや抜けがあると、手戻りが発生するだけでなく、請求先の定める提出期限に間に合わなくなり、従業員に重大な不利益が生じる可能性があります。また、こうした証明書類に不備があれば、会社の信用にも悪影響が出ます。そのため、発行に際しては依頼主である従業員にも適宜確認を取り、記載事項に不備がないか念入りに確認しましょう。
時間がかかることも想定する
在職証明書の発行には、従業員の人事情報など数多くの確認を要するため、一定の時間がかかります。そのため、発行を求める従業員には、事前に発行できる時期の目安について余裕をもって伝えておきましょう。
加えて、迅速に作成できるようにするためには、人事情報の管理体制などを日頃から整備しておくことも大切です。たとえば、人事システムを活用して人事情報の管理業務を効率化したり、自社でも在職証明書のフォーマットを用意したりすることをおすすめします。ただし、自社独自のフォーマットを整備したとしても、請求先が指定する記載項目や書式がある場合はそちらに従いましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
在職証明書を適切に作成しよう
在職証明書は、従業員が自社に実際に在籍していることを証明するための資料です。在職証明書は住宅ローンの審査や子どもの入園・入学手続きなど多種多様な場面で必要とされ、記載すべき事項も用途ごとに異なります。そのため、発行に際しては、事前に記載事項を確認し、正確に作成することが大切です。
在職証明書には給与情報の記載が求められることもあります。従業員の給与管理には弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」を活用するのがおすすめです。給与計算ソフトを利用することで、給与計算・明細書発行や年末調整といった煩雑な事務作業も効率化できます。ぜひ導入をご検討ください。
- ※2024年9月時点の情報を基に執筆しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者勝山 未夢(社会保険労務士)
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ所属社労士。 立命館大学法学部国際法務特修卒業後、新卒より社会保険労務士法人にて勤務。









