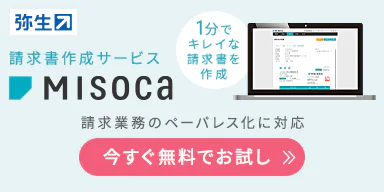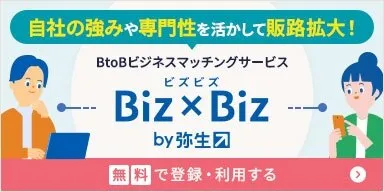海外取引には消費税が発生しない?課税対象となる取引のしくみを解説
監修者: 中川 美佐子(税理士)
更新
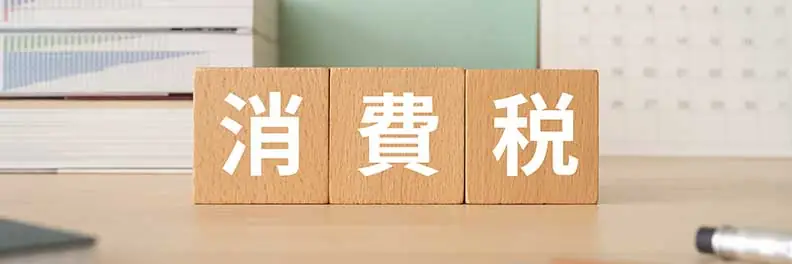
消費税は、事業者が日本国内で商品の販売や役務の提供を行い、その対価として代金を受け取った際に、確定申告で税額を計算して納付する必要がある税金です。また、事業者が商品の購入や役務の提供を受けて代金を支払った場合には、支払った消費税額を記録し、仕入税額控除の計算を行うことが求められます。そのため、国外(海外)で行われた取引についても、その取引が消費税の対象かどうかを正確に判断することが重要です。本記事では、取引が国外取引(海外取引)に該当するかどうかの判断方法や、消費税が課される場合の具体的な取引、さらにインボイス制度の影響について解説します。
原則、国外取引(海外取引)には消費税が発生しない
国外取引(海外取引)や寄付、贈与、出資に対する配当などの対価を伴わない取引は「不課税取引」とされ、消費税はかかりません。取引が国外取引(海外取引)に該当するかは、取引時点における商品の所在や役務の提供場所が国外であるかどうかで判断されます。
消費税が発生するのは「国内取引」と「輸入取引」
消費税の課税対象は国内取引と輸入取引に限られます。
国内取引とは、日本国内で商品や役務が提供・取り引きされるものを指します。国内取引に該当するかどうかは、取引時点における商品の所在や役務の提供場所が国内であるかによって判定されます。例えば、海外の事業者との契約であっても、役務の提供場所が日本国内であれば、国内取引とみなされ消費税の課税対象です。ただし、国内取引であっても以下のような取引については「非課税取引」とされ、消費税は課税しない取引となります。
- 土地の譲渡
- 有価証券や商品券の譲渡
- 医療や助産など、社会的配慮が必要な役務の提供
輸入取引とは、国外から日本国内に商品や役務を輸入する場合を指し、輸入した商品や役務の提供に対して消費税が課されます。また、国外への商品の輸出や役務提供は、「免税取引」とされ、消費税は課されません。これは「消費地課税主義」という考え方に基づいています。消費地課税主義とは、消費税は国内で消費される商品や役務に対して課税されるものであり、国外で消費されるものには課税されないという考え方です。
課税対象となる取引のしくみ
国内取引や輸入取引が課税対象となるしくみを理解することで、国外取引(海外取引)がどのように課税対象から外れるのかを理解できます。以下では、消費税の課税要件について、国内取引と輸入取引それぞれ解説します。
国内取引で課税対象となる要件
国内取引が消費税の課税対象になるかは、次の要件をすべて満たすかどうかで判断されます。
- 事業者が事業として行う取引であること
- 対価を得て行う取引であること
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
では、それぞれの要件について詳しく解説します。
事業者が事業として行う取引である
事業者とは、個人事業主と法人を指します。事業とは、「対価を得て行われる資産の譲渡などを反復、継続かつ独立して遂行すること」です。また、事業用の資産を譲渡するなどの行為も、事業に含まれます。
法人が行う取引については、すべて事業として行う取引に該当します。その一方で、個人事業主の場合、取引が事業活動に該当するか否かは、その取引が事業者として行われるか消費者として行われるかによって異なります。例えば、家庭用の家具や電化製品を売却した場合、消費者の立場による取引に分類されるため、消費税の課税対象とはなりません。
対価を得て行う取引である
消費税が課税されるかどうかは、その物品の譲渡や役務の提供に対して対価を得ているかで判断されます。無償で物品を譲渡したり役務を提供したりしている場合(みなし譲渡に該当する場合を除く)や、寄付金や補助金を払った場合は、対価を得ていないため、消費税の課税対象にはなりません。
資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供である
資産の譲渡とは、売買契約などに基づき、資産の同一性を保持しつつ、所有権を他者に移転させることです。商品の販売や事業用資産の販売も該当します。また、有形資産以外に、特許権や商標権などの無形資産の譲渡も含まれます。
資産の貸付けとは、資産を他者に貸付け使用させることです。資産の譲渡と同様、有形資産に加え、特許権や商標権などの無形資産の貸付けも含まれます。
役務の提供とは、請負契約・運送契約・委任契約・寄託信託などに基づき、労務や便益を提供することを指します。弁護士や会計士などの専門的知識を必要とする業務や、スポーツ選手や俳優などの特殊な技能を伴う業務も含まれます。
輸入取引の課税のしくみ
外国貨物を輸入する場合は、保税地域から引き取る際に消費税が課され、その引取を行う者が消費税を納める必要があります。 保税地域とは、外国貨物を一時的に国内に持ち込める地域であり、税関長が定めた場所です。 なお、保税地域内で外国貨物を消費または使用した場合、その時点で保税地域から引き取られたものとみなされ、消費税が課されます。
ただし、特定の物品を除き、輸入貨物の課税価格(商品の運賃や保険料を含む価格)が1万円以下の場合は、消費税が免除されます。
消費税の課税対象となる取引の判断方法
課税対象となる取引について解説しましたが、実際の取引はさまざまな条件で行われるため、その取引が課税対象かどうか、すぐに判断しにくい場合もあります。 以下では、国内取引と国外取引(海外取引)の判断方法について、具体例をあげて解説します。
資産の譲渡・貸付けの場合
資産の譲渡や貸付けが国内で行われても、実際にその資産が国外にある場合や、その逆の場合もあります。資産の譲渡・貸付けについては、取引時点における資産の存在場所に基づいて、国内取引か国外取引(海外取引)かを判断します。
例えば、海外の法人が日本国内の建物などの不動産を購入した場合は、国内取引に該当し、消費税の課税対象となります。ただし、同じ不動産でも、日本国内の土地の譲渡の場合は非課税取引に該当するため、消費税の課税対象にはなりません。
その一方で、日本国内の個人や法人が海外の不動産を購入した場合、国外取引(海外取引)に該当するため、消費税は課せられません。ただし、購入先の国によっては、消費税の支払いが必要になるケースも考えられます。
役務の場合
役務の提供についても、役務の契約を結んだ場所と実際に役務の提供を受ける場所が異なることがあります。 役務の提供については、その役務を提供された場所で判断し、国内であれば課税対象です。
例えば、海外在住のウェブデザイナーに依頼して、海外支店のホームページを作成してもらい、報酬を支払ったとします。この場合、役務の提供を受けた場所は国外であるため、国外取引(海外取引)に該当し、消費税は課されません。
その一方で、日本で行われた講演会において、外国人通訳に報酬を支払ったとします。この場合、役務の提供を受けた場所は国内であるため、国内取引に該当し、消費税の課税対象です。
海外の事業者との取引でインボイス制度の影響はある?
インボイス制度が導入され、海外の事業者との取引においても対応が必要か気になると思います。以下では、インボイス制度が適用される事例や影響のない事例について、紹介します。
海外の事業者との取引でインボイス制度の影響がある事例
インボイス制度とは、売り手が一定の要件を満たした「適格請求書」を発行し、買い手がその適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除を受けられる制度です。適格請求書を発行するには、売り手が適格請求書発行事業者として登録されている必要があります。
通常、海外の事業者は日本国内にPE(恒久的施設)を有していない限り、日本の法人税の課税対象にはなりません。しかし、消費税については、PE(恒久的施設)の有無にかかわらず、国内取引に該当する場合は課税対象となります。また、海外の事業者も、税務署に申請することで、適格請求書発行事業者として登録が可能です。
そのため、海外の事業者と取引する際は、相手が適格請求書発行事業者として登録されているかを確認することが重要です。そして、適格請求書を受け取り、保存しておくことで、仕入税額控除を適用できるようにしましょう。
海外の事業者との取引でインボイス制度の影響がない事例
海外の事業者との取引が国外取引(海外取引)に該当する場合、消費税は課税されないため、インボイス制度を考慮する必要はありません。また、海外の事業者へ製品やサービスを輸出する場合も、免税取引となるため適格請求書の発行は不要です。
さらに、輸入取引についてもインボイス制度の影響はありません。保税地域から外国貨物を引き取る際に交付される輸入許可通知書が、適格請求書と同等の効力を持つ証憑となるため、仕入税額控除の対象に含めることが可能です。このため、海外の事業者に適格請求書の発行を求める必要はありません。
海外送金における注意点
海外への送金には通常消費税は課されません。送金は資金を移動させるための手段であり、商品や役務の提供に対する対価ではないため、課税の対象外です。また、送金時の手数料も「外国為替業務にかかる役務の提供」として非課税取引に該当し、消費税が課されません。
ただし、送金に関連して商品や役務の提供を受けた場合には、消費税が発生する場合があります。例えば、コンサルティングサービスを受けた場合や、送金関連のオンラインサービスを利用した場合です。これらのサービスが国内取引に該当する場合、消費税が課されるため、取引内容に応じて確認が必要です。
国外取引(海外取引)には原則として消費税が発生しない
国外取引(海外取引)は原則として消費税の課税対象にはなりません。国外取引(海外取引)に該当するかどうかは、取引時点で資産や役務の提供場所が国内か国外かによって判断されます。また、インボイス制度も国外取引(海外取引)においては影響を受けません。
弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」を導入すれば、消費税を考慮しない国外取引(海外取引)の請求書と、課税対象となる国内取引の請求書の作成を簡単に行えます。さらに、会計ソフトと連携することで、仕訳処理もスムーズになり、経理業務の効率化を支援します。ぜひ、活用してください。
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
この記事の監修者中川 美佐子(税理士)
税務署の法人税の税務調査・申告内容の監査に29年勤務後、令和3年「
たまらん坂税理士法人」の社員税理士(役員)に就任。法人の暗号資産取引を含め、法人業務を総括している。