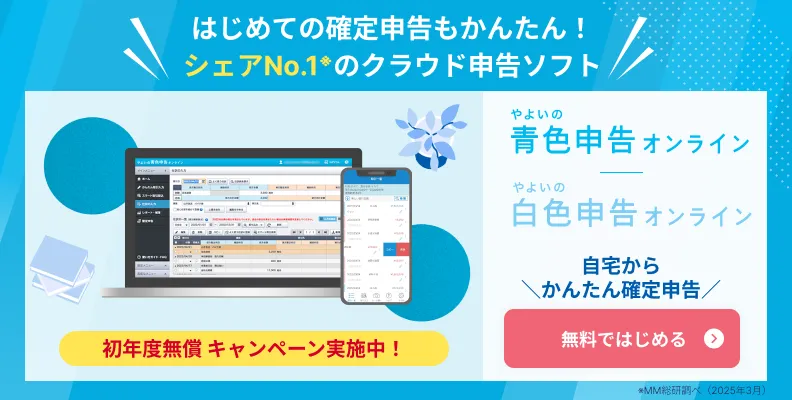脱サラした人のための確定申告ガイド
執筆者: 安田博勇
更新

筆者が勤めていた会社を退職し、ライター業を営むようになったのは数年前のこと。当時は会計ソフトを導入していなかったので、その年分の確定申告書はすべて手書きで作成しました。わからないことばかりでとても苦労したことをよく覚えています。
今回は、これから脱サラして開業することを考えている人、もしくは、脱サラしたはいいけど今年の確定申告のやり方がわからず不安になっている人に向け、会社を退職した年の確定申告の注意点を解説します。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

POINT
- 退職金も申告しなければいけないか要check!
- 開業前にかかった費用は「開業費」として任意償却
- 確定申告書の提出は郵送も可。2部提出すれば控えをもらえる
退職金も確定申告する必要がある?
まずは、確定申告時の基本的事項からです。
そもそも確定申告では「確定申告書」を使用します。なお、2022年分の申告より「確定申告書A」は廃止となり、「確定申告書B」と統合されて「確定申告書」になりました。
2021年分までは、会社から受け取る給与所得のみを申告するときは「確定申告書A」を、退職したその年に事業所得(個人で行っている仕事による所得)を得たのなら「確定申告書B」を使用していました。
なお、個人事業主は税務署に開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出しなければいけません。青色申告者になる場合はこれに加え、青色申告者になることも「所得税の青色申告承認申請書」を提出して申請しなければいけません。
ところで確定申告の前に留意しておきたいのが「退職金」です。原則、前の会社を退職した際に退職金を受け取っていれば、退職者(事業者)は退職所得を申告しなければいけません。申告の際には、事業・給与の所得とは分離し、退職所得だけで税額を算出します。
ただし、退職する際に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を会社に提出していれば、原則として確定申告は不要です。この書類を提出していない場合は、確定申告により所得税が還付されます。
以下の記事もあわせてご覧ください。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
事業所得&給与所得の確定申告は?
さて、確定申告で事業所得と給与所得を申告する際に必要となる書類には、次のようなものがあります。
- 確定申告書
- 収支内訳書 ※白色申告の場合
- 青色申告決算書 ※青色申告の場合
- 給与、年金の源泉徴収票 ※参考書類、添付不要
- 国民年金、生命保険料などの控除証明 ※添付書類
また添付の必要はありませんが、事業収入のわかる「請求書の控え」「取引先からの支払調書」もあると便利です。国民健康保険は控除証明書が発行されませんので、支払金額のわかる納付書の控えもあるとよいでしょう。
確定申告書の書き方について、詳しくは以下の記事を参照ください。
開業をした年の確定申告となれば、開業に際してさまざまな費用が発生していると思います。これらの費用は、収支内訳書・青色申告決算書(損益計算書)に記入しなければいけません。このとき、開業届に記入した”開業日”以降に発生した費用は、勘定科目ごとに経費計上すればOKですが、開業日の前に発生した費用は、どのように計上すればよいのでしょうか。
そんなときに使うのが「開業費」という科目です。名刺・印鑑の作成、関係者との飲食費、書籍などの資料代、さらには開業準備中の事務所家賃など、開業の準備に必要だった費用を「開業費」としてまとめることができます(帳簿上では摘要の欄に使途を記入しておくとよいです)。
また開業費では、事業に余裕の出てくる2年目、3年目など、事業者の好きなタイミングで費用計上ができる「任意償却」が認められています。ただしパソコンの購入など10万円以上するものは開業費に含むことができません。減価償却資産となりますので、記入の際には注意しましょう。
収支内訳書、青色申告決算書の書き方は、下記サイトを参考にしてください。
確定申告書は税務署へ郵送で提出しても問題なし!
最後に提出方法です。
毎年確定申告シーズンになると税務署に長蛇の列ができるということを耳にしたことがあるかもしれません。しかし、ここ数年、申告書作成会場の混雑回避のため、LINEアプリで入場整理券の配布を行っています。それでも提出の際には「直接持っていかなければいけないのではないか……」と気になるものですが、きちんと記載されていれば、郵送で提出してまったく問題ありません。
必要書類を封筒に入れ、管轄の税務署の業務センターに送付しましょう。このとき、封筒に「確定申告書在中」と朱書きしておけば安心です。
なお、2025年1月からは、申告書等の控えなどへの収受日付印の押なつが廃止されています。そのため、直接でも郵送でも提出をする際は、確定申告書等の正本のみを提出します。
しかし、確定申告書の控えは、融資やローンを受ける場合や賃貸契約をする場合など、収入や所得を証明するために使用することがあります。ぜひ、ご自身で控えの作成と保有、管理をしましょう。
還付がある場合、例年4月頃、税務署から「国税還付金振込通知書」が届き、確定申告書に記載した「還付される税金の受取場所」(銀行口座)に振り込まれます。
頭のなかでやり方さえ整理しておけば、実のところ確定申告はそれほど大変ではありません。ただし事業が拡大し、日々のお金で出入りが多くなればなるほど、取引を記録する帳簿付けに時間がとられていきます。事業が本格稼働する前に、帳簿付けを簡単に行えて、収支内訳書や青色申告決算書、確定申告書を作成できる”会計ソフト”の導入も検討してみるのがおすすめです。
photo:Thinkstock / Getty Images
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の執筆者安田博勇
1977年生まれ。大学卒業後に就職した建設系企業で施工管理&建物管理に従事するも5年間勤めてから退職。出版・編集系の専門学校に通った後、2006年に都内の編集プロダクションに転職。以降いくつかのプロダクションに在籍しながら、企業系広報誌、雑誌、書籍等で、編集や執筆を担当する。現在、フリーランスとして活動中。