個人事業主の生計を一にしない家族への給与は必要経費?節税策を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新
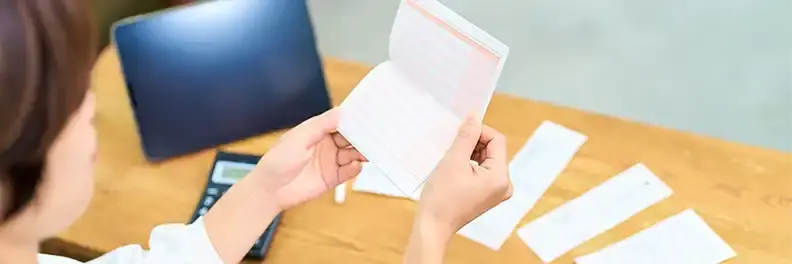
個人事業主の節税策として、家族に支払う給与を必要経費として計上する方法があります。ただし、家族に支払う給与はどのような場合でも必要経費にできるわけではありません。では、必要経費にするためにはどのような条件があるのでしょうか。
ここでは、生計を一にしない家族への給与、生計を一にする家族への給与のそれぞれのケースにおいて、家族への給与を必要経費にできる条件のほか、生計を一にする家族に支払う給与に関する節税策をわかりやすく解説します。
なお、所得税法には家族ではなく、親族と書かれています。親族とは、6親等以内の血族と、配偶者の父母・兄弟姉妹など3親等以内の姻族のことです。生計を一にするとは、共通の資金で生活を営んでいることを指しますが、例えばルームシェアをしている友人同士などは、たとえ生活費を出し合って暮らしていたとしても、親族ではないため該当しません。本記事では以降、生計を一としない親族などと表記します。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

生計を一にしない親族への給与は必要経費にできる
個人事業主が、生計を一にしない親族に支払った給与は、他人である従業員への給与と同様、必要経費として計上できます。
一方で、生計を一にする親族に支払った給与については、必要経費として認められないのが原則です。ただし、青色申告者であれば一定の手続きや条件の下で必要経費にできる場合があります。白色申告者の場合は必要経費にはできませんが、控除の適用を受けることは可能です。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
生計を一にしない親族の定義
生計を一にしない親族とは、それぞれ独立した生活費で暮らしている親族のことです。同居している親族であっても経済的に独立して生活している場合は、生計を一にしない親族といえます。
例えば、納税者である父親が個人事業主、母親は会社勤め、同居の息子夫婦も会社員で独立した収入があり、別の家計で生活をしているようなケースです。このような状況であれば、父親と母親、息子夫婦は、お互いに生計を一にしない親族といえます。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
生計を一にする親族の定義
生計を一にする親族とは、共通の資金で生活を営んでいる親族のことを指します。必ずしも同居している必要はなく、別々に暮らしていたとしても生活費を共有しているのであれば生計を一にする親族と見なして差し支えありません。
例えば、納税者が個人事業主で配偶者は専業主婦・主夫の家庭において、大学生の息子が親元を離れて、親の仕送りで生活を送っているなら、大学生の息子は同居をしていなくても生計を一にする親族といえます。
生計を一にする親族については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
個人事業主が生計を一にしない親族への給与を必要経費にする方法
個人事業主が生計を一にしない親族への給与を必要経費として計上するにあたって、特別な手続きは不要です。通常の従業員への給与と同様に、必要経費として計上することができます。
なお、生計を一にしない親族への給与を必要経費にする場合、その親族が事業に専従しているかどうかは問われません。専従とは、その言葉のとおり専属で仕事に従事することです。
例えば、普段は会社員として働いていて家の中では完全に別世帯として生活している息子が、個人事業主である父の業務を土日のみ手伝っているような場合も、生計を一にしない親族への給与として必要経費に計上できます。ただし、従業員を雇う際に必要な届出や申請をしなければならない点に注意しましょう。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
個人事業主が生計を一にする親族に給与を支払った場合の節税策
個人事業主が生計を一にする親族に支払った給与を必要経費にすると節税策になりますが、必要経費にできるのは青色申告者のみです。
白色申告者は、生計を一にする親族への給与を必要経費として計上できませんが、控除として事業所得から差し引くことができます。ただし、控除の対象となる限度額が決められている点に注意が必要です。
それぞれの場合について、以下で詳しく解説します。
青色事業専従者給与として必要経費に算入
青色申告者が生計を一にする配偶者やその他の親族に給与を支払い、かつ該当する親族が専らその事業に従事している場合、給与を必要経費にできます。必要経費にできる給与の金額に制限はありませんが、「労働の対価として相当である」と認められる金額でなければなりません。
なお、青色事業専従者給与として必要経費に算入するには、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておく必要があります。
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以降に開業したり、新たに事業専従者に給与を支払うこととなったりした場合には、その開業の日や事業専従者がいることとなった日から2か月以内です。
この届出をしていない状態で、青色事業専従者給与として必要経費に算入することは認められていない点に注意してください。
青色事業専従者給与として認められる要件としては、以下の4点があげられます。
青色事業専従者給与として認められる要件
- 青色事業専従者に支払われた給与であること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
- 届出書に記載した支払方法で、かつ支払金額の範囲内で支払われていること
- 労務の対価として相当であると認められる金額であること
事業専従者控除として事業所得から差し引く
白色申告者が生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与は、一定の要件を満たせば、事業専従者控除として事業所得から差し引くことができます。控除額は、配偶者の場合は最高86万円、15歳以上のその他の親族の場合は最高50万円です。事業専従者控除を受けるための要件は以下の2点です。
事業専従者控除を受けるための要件
- 白色申告者の営む事業の事業専従者であること
- 確定申告書に白色事業者専従者控除を受ける旨や、その金額など必要な事項を記載すること
事業専従者控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
事業専従者となる条件は「生計を一にする親族」「15歳以上」「6か月以上従事」
通常、従業員に支払う給与は必要経費として扱えますが、親族に支払う給与は原則、必要経費として認められていません。しかし、商店などでは親族が仕事を手伝うことも多いため、親族が事業専従者であれば特別の取り扱いを認められるようにしたのが青色事業専従者給与と事業専従者控除制度です。
事業専従者として認められるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
事業専従者となる条件
- 個人事業主と生計を一にして暮らしている配偶者や親族
- その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上
- 年間のうち6か月以上はその事業に従事すること
事業専従者は原則として、他のアルバイトやパートをすることは認められませんが、本業に支障のない範囲ならば許容されています。ただし、事業専従者としての給与とパート収入を合わせて103万円を超えると確定申告が必要となり、所得税が課税されるため注意してください。また、100万円を超えると住民税の課税対象となります。
なお、専業主婦・主夫として家事や子育てをしている配偶者、両親に事業専従者になってもらう場合でも、支払う給与に見合う仕事をしてもらわなければなりません。一般的には、以下のような仕事を行っていれば、事業専従者として認められます。
事業専従者として認められる主な業務内容
- 経理業務(帳簿記帳、領収書の整理、請求書発行、支払い・集金など)
- 総務業務(メール管理、在庫管理、備品管理、書類整理、片付けなど)
- アシスタント業務(個人事業主のスケジュール管理、調査、配達など)
併せて、出勤簿、日報、週報といった勤務実態の記録をつけておくと、労務管理の意味でも、税務調査に備える意味でも安心です。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
生計を一にしない親族と生計を一にする親族への給与支払額に関する注意点
生計を一にしない親族への給与と生計を一にする親族への給与支払額には、原則として上限はありませんが、注意すべき点があります。それぞれの注意点は下記のとおりです。
生計を一にしない親族の給与支払額
生計を一にしない親族への給与支払額には特に上限は設けられていませんが、労働に見合った対価として適切な金額でなければならない点に注意が必要です。明らかに過大な金額の給与を支払うのは避けましょう。労働に見合っていない金額の場合、税務署から指摘される可能性があります。
青色申告者の生計を一にする親族の給与支払額
青色申告者の生計を一にする親族への給与は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に給与額を記載して届け出た金額が上限となることに注意が必要です。
一方で、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額まではいくらでも支払うことができ、記載金額より少なくても問題ありません。給与支払日を変更する場合や、届け出た記載額より多い給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を税務署に提出する必要があります。
配偶者に青色事業専従者給与を払う場合のデメリットとして、配偶者控除を受けられないことが指摘されています。しかし、事業所得が少ない事業者は、事業専従者の給与額を所得税・住民税(所得割)が非課税となる年間100万円以内にしたり、事業所得が多い事業者は給与額を多めにしたりすれば、トータルで節税が可能です。配偶者や両親と生計を一にしている青色申告者の方は、親族と一度相談してみてはいかがでしょうか。
青色事業専従者給与については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
白色申告者の生計を一にする親族の給与支払額
白色申告者が生計を一にする親族に支払う給与には、特に上限額はありませんが、事業専従者控除として所得金額から差し引く金額は給与金額に関係なく決まっている点に注意しましょう。事業専従者控除の控除額は、以下のA・Bのうち少ない方の金額です。
事業専従者控除の控除額
-
A.配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円
-
B.事業所得を事業専従者の数に1を加えた数で割った額
例えば、白色申告者の所得金額が150万円で、事業専従者が妻1人の場合は「150万円÷(1+1)=75万円」となり、Bの金額の方が少ないため、控除額は年間75万円となります。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
個人事業主の節税に、生計を一にしない親族への給与を活用しよう
個人事業主が生計を一にしない親族へ支払う給与は、必要経費にできます。生計を一にする親族への給与は、青色申告者であれば青色事業専従者給与として必要経費にすることができ、節税が可能です。
白色申告者の場合は、生計を一にする親族に給与を支払うことで、事業専従者控除を受けられる場合があります。親族に支払う給与をはじめとする必要経費を適切に管理するには、確定申告ソフトの活用がおすすめです。
「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」は、個人事業主向けクラウドソフトです。初めて確定申告をする方にも使いやすい機能とデザインで、簿記の知識が十分にない場合も確定申告ができます。e-Taxによる製品から直接の電子申告にも対応しているため、税務署へ出向くことなく自宅から確定申告書の提出が可能です。1年間無料ですべての機能を利用できる「やよいの青色申告 オンライン」と、期間制限なく無料で利用できる「やよいの白色申告 オンライン」をぜひご活用ください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。










