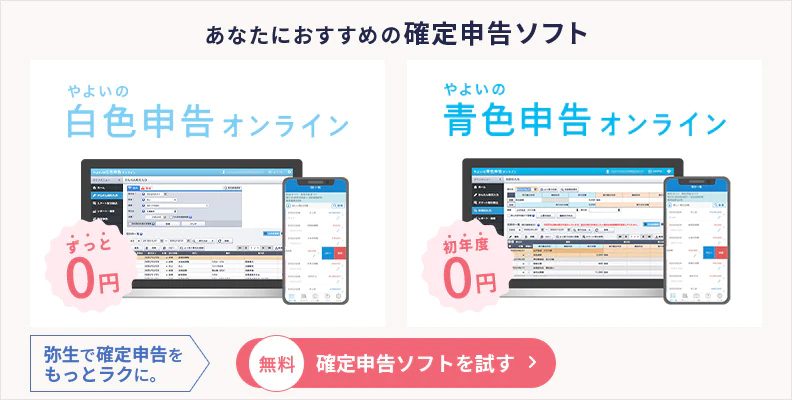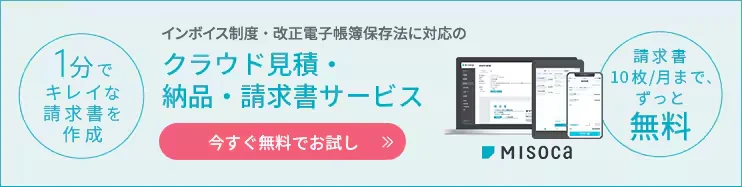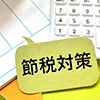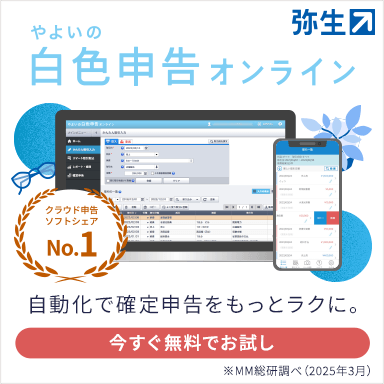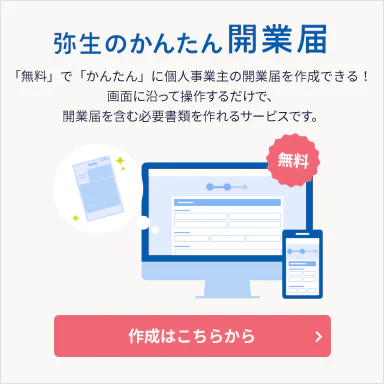副業でイラストレーターをするには?案件の種類や始め方を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

イラストを描くのが得意な人の中には、イラストレーターの副業に挑戦してみたいと考えていた人もいるでしょう。あるいは、企業にイラストレーターやデザイナーとして勤めながら、技能を活かして、副業で収入を増やしたいと考えている人もいるかもしれません。
今回は、副業でイラストレーターをするときの案件の種類や探し方について解説します。また、副業の所得を含めて本業以外の所得の総合計が20万円を超えると確定申告が必要となります。ほかにもイラストレーターで副業を始めるにあたって知っておきたいインボイス制度や住民税などの税金の知識についても触れていますので、参考にしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
副業イラストレーターの仕事内容とは?
副業でイラストレーターが行う仕事内容は、企業や個人からイラスト制作の依頼を受け、要望に沿ったイラストを制作することです。芸術性の高いイラストの制作を追求するというよりは、クライアントが求めているイラストを理解し、要望をくみ取って成果物を納品する能力が求められます。
近年はイラストを紙にペンで描くのではなく、デザインソフトとペンタブレットを使ってデジタルで制作するケースがほとんどです。
Webページなどデジタル媒体に掲載するイラストと、印刷物など紙媒体に掲載するイラストでは、色の設定や解像度など、求められる要件が異なります。どのような目的で使用されるイラストなのかを正確に理解し、相手の要望に合った成果物を納品することが重要です。
イラストを描く仕事は、自宅でできるうえ、本業の就業後や休日などのすきま時間を活用できます。納期を守れれば、自分でスケジュール管理を行うことが可能なため、副業に向いているでしょう。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業イラストレーターの案件の種類
一口にイラスト制作といっても、副業でできる案件は多岐にわたります。イラスト制作を通して副業収入を得る代表的な種類は次のとおりです。
LINEスタンプの販売
自作のLINEスタンプを制作してスタンプショップに登録し、スタンプがダウンロードされるごとに報酬を得ることができます。ただし、スタンプを申請してから販売可能な状態になるまで時間がかかることに加え、1件当たりの収益が少額になりやすいといったデメリットがあります。
その一方で、自分にとって都合のよいタイミングで制作を進められるため、すきま時間を有効活用できる点が大きなメリットです。人気スタンプになればまとまった収入を得られる可能性もあります。制作物としてのクオリティの高さに加え、実用性を備えたスタンプを考案することが大切です。
ストックイラストサイトへの登録
ストックイラストサイトとは、イラストを登録しておくとダウンロードされるごとに報酬が支払われるしくみのサービスを指します。Webページなどに掲載する目的でダウンロードされるケースが多いため、実際の利用シーンを想定したイラストを制作することが大切です。
ストックイラストは、イラストを一度登録すれば継続収入につながる可能性があるため、副業の場合、すきま時間に描いては登録することを地道に続けていくのも1つの方法といえます。
イラストバナーの制作
Webページや動画に表示されるバナー広告の素材となるイラストを作成するのが、イラストバナー制作です。あくまでも広告素材であることから、見た目のインパクトや訴求力の強さが重視されます。クライアントが扱っている商材についてリサーチし、相手の要望に合わせて制作する技量が求められます。
バナー広告の多くはコンパクトなサイズであり、必要な制作時間に対して報酬額は高めに設定される傾向があります。クライアントの要望に沿った成果物を安定的に納品できれば、継続案件を獲得することも可能です。
パンフレットなどの挿絵制作
商品やサービスのパンフレットに掲載する挿絵には、Webページ用と紙媒体用があります。紙媒体に使用する挿絵を依頼されるケースの場合は、紙の種類によって印刷の発色が変わることなど、印刷特性に関する知識も欠かせません。
また、誌面スペースを埋めるためのイメージイラストもあれば、パンフレットの説明内容を補完するための挿絵が求められる場合もあります。挿絵単体で捉えるのではなく、パンフレット全体の構成やコンセプトを踏まえて制作することが重要です。
アイコン・似顔絵の販売
SNSやブログなどのプロフィールに掲載するアイコンや似顔絵の制作依頼を受けて作成します。依頼者が求めているニュアンスやテイストを表現する必要があるため、イラスト制作のスキルだけでなく相手の意図をくみ取るコミュニケーション力も必要です。
スキル販売サイトなどで受注するケースが多いため、依頼者からの高評価が蓄積されるにつれて安定的に受注できるようになっていくはずです。
YouTubeのサムネイル制作
YouTubeなどの動画のサムネイルに表示されるイラストやデザインを制作します。サムネイルの訴求力に応じて動画の再生数が大きく左右されるケースも多いことから、結果がシビアに問われる傾向があります。
その一方で、多くのクリックを誘発するサムネイルを制作できるスキルが身に付けば、複数のクライアントから継続案件を獲得できる可能性も十分にあるでしょう。クライアントは企業から個人まで幅広いため、案件が豊富にある点も大きなメリットです。
広告用の漫画制作
WebページやSNS、パンフレットなどの広告内で使用する漫画は、クライアントからストーリーを指定されて制作するケースが大半です。ストーリーを具現化するために必要な設定を深く理解し、人物や背景を描く能力が求められます。
広告であることを踏まえて、読者が興味を持ち、続きを読みたくなるストーリーにすることが重要です。漫画を描く画力だけでなく、マーケティングの知識も求められるでしょう。
LPのイラスト制作
商品やサービスを紹介することに特化した、1ページ完結型のWebページをLP(ランディングページ)といいます。見た目のインパクトや華やかなページデザインが求められるケースが多く、ページ内に掲載するイラスト素材をイラストレーターに発注するケースがあります。
イラスト単体で捉えるのではなく、LP全体の構成や発信するメッセージの内容、紹介される商材の特徴などを踏まえてイラストを制作する技量が求められます。
同人誌の販売
同人誌とは、同じ趣味を持つ人同士の集まりにおいて取引される、自費制作冊子のことをいいます。イラストレーターとして培った画力を活かして同人誌を制作し、販売することで収入につなげることも可能です。
ただし、あくまでも自費制作であることから、売れなければ赤字になるのは避けられません。自身の作品を多くの人に知ってもらうための宣伝活動や、収支の管理なども基本的にすべて自分で行う必要があります。
イラストの講師
今まで培ってきたイラスト制作に関する知識やスキルを基に授業を行います。個人で開業することもできますが、一般的には専門学校やカルチャースクールなどから依頼を受け、講師として指導にあたるケースが多く見られます。
講師として指名されるには、相応の実績を築かなくてはなりません。また、自身がイラストを描けるだけでなく、必要な知識やスキルを初心者にわかりやすく教える能力も必要です。
漫画動画の制作
漫画動画とは、ナレーション付きの動きのある漫画のことを指します。決まっている台本からコマ割りをして仕上げていくまでを担うのが一般的です。
緻密に上手な絵が描けないと成立しないということはなく、画力というよりも、漫画の構成力が重要視されます。親しみやすい絵柄が重宝されることが多いのが特徴です。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
イラストレーターの副業案件の探し方
イラストレーターの副業を始めるにあたって、多くの人が悩むのが「どこで案件を見つければいいのか」という点です。ここでは、副業案件を探す方法を紹介しますので、案件獲得のヒントにしてください。
ポートフォリオを作成する
ポートフォリオとは、過去に制作したイラスト作品集のことです。クラウドソーシングやエージェント経由で案件に応募する際、ポートフォリオの提出を求められるケースがあります。
イラスト制作の案件を獲得するには成果物のクオリティが重要なポイントとなることから、ポートフォリオの作成は必須といえます。
ポートフォリオや自身の経歴・実績などを紹介するWebページを開設しておくと、案件を獲得する際にスキルや実績をアピールしやすくなります。ポートフォリオ掲載に特化したWebサービスもあるので、こうしたサービスを活用してポートフォリオサイトを用意するのがおすすめです。
友人・知人に案件を紹介してもらう
友人や知人に「イラストレーターの仕事をしている」と事あるごとに伝えることで、案件の紹介につながるケースもあります。近年では企業に限らず、個人がブログやWebページ、SNSを活用する事例も増えているため、人とのつながりが案件獲得に寄与することも十分に考えられるでしょう。
イラストレーターとして名刺を作成し、常に持ち歩くこともおすすめです。名刺に2次元コードを掲載し、ポートフォリオサイトをできるだけ多くの人に見てもらうことによって、案件獲得のチャンスが広がります。
SNS経由で受注する
SNS上にはイラストレーターを探しているユーザーや、イラスト案件を中心に求人している事業者が数多く存在します。イラストレーターとして専用アカウントを開設し、自身の作品を紹介したり、活動の様子を投稿したりすることで、興味を持ったユーザーからDMで依頼や相談が届く場合もあります。
SNSにはシェア機能があるため、拡散力が優れている点が大きな特徴です。ユーザーから他のユーザーへと情報が拡散されていく中で、案件獲得に結び付くユーザーとのつながりを得られる可能性があります。
クリエイター系展示会で商談する
展示会の中には、クリエイターとの商談を目的としたものも数多くあります。こうした展示会に出展することで、興味を持った企業担当者との商談を通じて案件を獲得するのも1つの方法です。
ただし、展示会によっては出展料が高額な場合もあります。展示会をきっかけに案件を獲得できれば出展料を相殺できる可能性もあるものの、案件獲得につながらない場合は赤字になりかねません。費用対効果を考慮して出展先を検討することが大切です。
出版社などマスコミへ売り込む
出版社をはじめとするマスコミに自身を売り込むことで、案件獲得につながる場合もあります。出版物にはイラストが付き物のため、編集者の目に留まれば問い合わせや案件の相談につながることもあるでしょう。
ただし、大半の出版社は、既に発注先のイラストレーターを多数確保しています。ポートフォリオなどを出版社宛てに送付しても、すぐに反応が得られないのは当然のことと捉えてください。多数のマスコミ各社に根気良く売り込みを続ける必要があります。
エージェントサイトを活用する
イラストレーターの案件を紹介・仲介しているエージェントに登録し、案件獲得につなげる方法もあります。自分で営業活動を進めなくても案件を紹介してもらえることに加え、公開されていない案件も含めて紹介してもらうことが可能です。1週間のうち稼働できる日数や、目指したい月収などを伝えておくことにより、条件に合う案件を紹介してもらえるでしょう。
ここでは、本業の勤め先でイラストレーターの仕事をしており、スキルを活かして副業に取り組みたいケースと、初めてイラストレーターとして案件を受注するケースにおいて、おすすめのエージェントサイトをそれぞれ紹介します。
実績のある人向けのサービス
本業の勤め先でイラストレーターの仕事をしている、イラストレーターとして活動していたことがあるといった人にはスキルマーケット「ココナラ」を活用してはいかがでしょう。
アイコン作成やキャラクター作成、LINEスタンプ作成などカテゴリが細かく分かれているため、自分が得意なジャンルでイラスト制作案件を募集できます。料金設定については自分で決められますが、同カテゴリのイラストレーターの単価設定を参考に料金を検討しましょう。
初めてイラストレーターとして活動する人向けのサービス
初めてイラストレーターとして活動する人には、「クラウドワークス」や「ランサーズ」といったクラウドソーシングへ登録してはいかがでしょう。案件によって求められるスキルレベル・報酬額に幅があるため、初めは難度があまり高くない案件を探して応募し、着実に成果物を納めていくことでクライアントの信頼を獲得することが大切です。クラウドソーシング経由で応募した案件が、継続受注につながるケースも少なくありません。
また、クラウドソーシングではコンペ形式での募集も行われています。応募した作品が採用されなければ収入にはつながらないものの、初心者が副業に挑戦するには良い機会となるでしょう。クラウドソーシングに登録して、自分に合った案件を探してみてはいかがでしょうか。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
イラストレーターの副業をするときの注意点
個人として副業でイラストレーターとして仕事を行う場合、注意しておきたい点が3つあります。どれも必ず確認しておきたい重要なポイントです。
著作権や模倣に気を付ける
イラストを制作する際は、既存の作品を模倣したり、著作権を侵害したりすることのないよう、細心の注意を払う必要があります。意図的に模倣したつもりがなくても、特定のブランドや作家が提供しているイラストと似たものになってしまう可能性もゼロではありません。
他人の作品をそのまま、まねしないのはもちろんのこと、既存のイラストなどは参考程度にとどめることを徹底してください。
勤め先が副業OKかの確認を行う
副業を始める前に、必ず勤め先が副業OKかどうかを確認しておきます。昨今、副業解禁の方向にはなっていますが、企業ごとに就業規則があり、副業NGにもかかわらず行った場合は罰則が設けられていることがあるので気をつけてください。まだまだ副業規制をしている会社が多いのが現状でもあります。
また、副業OKの場合でも、企業にイラストレーターとして勤めながら、副業でもイラストレーターとして活動したい場合、企業によっては同じイラストレーター業での副業はNGという規則もあるため、事前の確認が必要です。本業でイラストレーターではない場合は、副業OKならば問題ありません。
後になって問題になるケースも考えられますので、きちんと把握しておきましょう。
副業の所得が一定を超えたら確定申告をする
イラストレーターの副業で一定の収入を得るようになると、税金に関する知識も求められるようになります。副業の所得を含めて本業以外の所得の合計額が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。20万円以下でも利益が出ている場合で、税務署に確定申告をしないのであれば、居住地のある自治体に住民税の申告が必要である点には注意しましょう。
所得とは、売上から経費を差し引いた金額を指します。副業の場合、雑所得として申告することが多いと想定されますが、雑所得であっても経費として計上できるものは少なくありません。
例えば、副業でイラストレーターとして活動するうえで必要なソフトウェア代や機器・端末の購入費用、自宅で作業をする場合は家賃や電気代の一部などを経費にできます。
イラストレーターが確定申告を行ったほうがよい理由として、イラストレーターの行う業務は、デザイン報酬に該当するので報酬から所得税を源泉徴収されて支払われていることがあげられます。確定申告を行うことで、納めすぎた税金が還付される可能性が高いので、このような場合には確定申告を行うことをおすすめします。
また、取引先が適格請求書(インボイス)発行事業者の場合、適格請求書(インボイス)の発行が求められます。適格請求書発行事業者になると、適格請求書の発行と保存、消費税の申告と納税が必要です。
このように、取引にあたって必要となる手続きや申告について、理解を深めておくことが大切です。
参考
国税庁:「コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬」
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
案件の種類や始め方を把握して、イラストレーターの副業に挑戦しよう
イラストレーターの副業には受注可能な案件が豊富にあり、案件を獲得する方法も多岐にわたります。まずは、さまざまな副業案件の種類があることを知り、案件を獲得する手段を押さえたうえで、イラストレーターの副業をスタートさせるのが得策です。
今回紹介したポイントや注意点を参考に、イラストレーターの副業にチャレンジしてみてください。
なお、繰り返しになりますが、副業が雑所得に該当する場合でも、適格請求書発行事業者はインボイス制度の要件に従った帳簿付けが必要です。また、20万円を超える副業の所得が出たら、確定申告が必要になります。副業の所得が事業所得に該当する場合、初めての人でも無料で手軽に帳簿付けを進められる「やよいの白色申告 オンライン」の活用がおすすめです。
無料で利用できる「やよいの白色申告 オンライン」では、雑所得の確定申告はできませんが、その情報を転記することで国税庁の確定申告サイトから確定申告をすることもできます。帳簿をつけておくことで、継続的にビジネスをしていれば事業所得としても申告できる可能性もあります。いずれにしろ確定申告をスムーズにできるよう帳簿付をおすすめします。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。また会計ソフトとの連携も可能なため、請求業務から会計業務を円滑に行うことができます。