法人が赤字の場合に納付が不要な税金は?種類や条件などを解説
更新
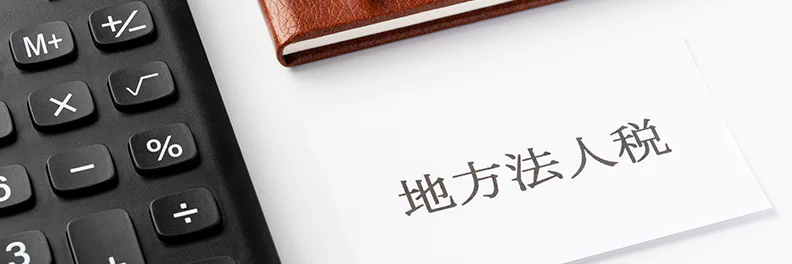
法人が納める税金にはさまざまな種類があります。そのうち、事業活動で得た所得(利益)に対してかかる税金は、赤字の場合は納税額が発生しません。その一方で、赤字であっても納めなければならない税金もあるため注意しましょう。赤字決算になったときには、納付が不要な税金と必要な税金を正しく把握することが大切です。
本記事では、法人が赤字になった場合に納税額が発生しない税金と、赤字になっても納税が必要な税金を紹介するほか、赤字決算が企業に与える影響についても解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
法人が赤字の場合の税金には納付が不要なものと、必要なものがある
法人に課せられる税金には、赤字の場合に納付額がゼロになるものと、赤字でも納税が必要なものがあります。そもそも赤字とは、支出が収入を上回り、利益がマイナスの状態を意味しています。法人は、企業の規模にかかわらず、事業年度ごとに必ず決算を行わなければなりません。決算とは、その事業年度における企業の「収益」「費用」「資産」「負債」などを計算して年間の損益をまとめ、決算書を作成する一連の手続きのことです。このとき、事業における支出が収入を上回っており、いわゆる「儲け」が出ていない状態であれば、赤字決算ということになります。
企業は、決算書を基に年に1度納めるべき税額を計算し、税務署等に申告・納付することが必要です。法人が申告する税金は、法人税や消費税、法人事業税、法人住民税などがありますが、その多くは決算で明らかになった所得金額を基にして計算されます。そのため、基となる所得がゼロ以下、つまり赤字の場合は、納税額もゼロとなるケースが少なくありません。しかし、法人に課せられる税金にはさまざまな種類があり、赤字だからといってすべての税金の納付が必要なくなるわけではないため注意しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
法人が赤字の場合に納税が必要ない税金
法人が赤字の場合に納税が必要ないのは、所得金額に基づいて納付額が計算される税金です。具体的に、赤字の場合に必要ない税金について見ていきましょう。
法人税、地方法人税
法人税は、法人の事業活動で得た所得にかかる国税です。法人税額は、益金から損金を引いた所得に、所定の税率を掛けて計算されます。益金とは、売上収入や売却収入など税法上の収益、損金とは、売上原価や販売費、損失費用など税法上の費用のことです。益金は決算書上の収益、損金は決算書上の費用とほぼ一致しますが、税法独自の規定により若干の違いが生じることがあります。損金が益金を上回って赤字になった場合は、税額計算の基準となる所得がゼロを意味するため、法人税額もゼロになります。
また、法人税と同様に企業の所得に対して課せられる税金に地方法人税があります。地方法人税は、地方という名前が付いていますが、地方税ではなく国税で、法人税と一緒に申告・納付するものです。地方法人税の税額は「法人税額×10.3%」で算出されるため、法人税額がゼロなら地方法人税の納付も不要になります。
法人事業税、特別法人事業税
法人事業税とは、法人が行う事業に対して課税される地方税です。株式会社や合同会社など、事業を行っている法人に、事務所等が所在する都道府県が課税します。資本金1億円以下の普通法人等の場合は、所得に応じて法人事業税の税額が決まるため、赤字であれば納付の必要はありません。
ただし、資本金1億円超の普通法人は、赤字であっても付加価値額や資本金等の額に応じた課税が発生します。また、電気供給業などの特定業種の法人には、収入金額に応じた収入割が課せられるため、該当する法人については、赤字でも法人事業税の納付が必要な場合があります。
その一方で、特別法人事業税とは、地方間の税収の偏りを是正するために、法人事業税の一部を分離する形で創設された税金です。特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて申告・納付します。なお、特別法人事業税額は、法人事業税額に所定の税率を掛けて求めるため、法人事業税の納付が不要な場合は法人事業税も納付が不要となります。
法人住民税の法人税割
法人住民税とは、事業所のある地方自治体に対して法人が納める地方税です。正確には道府県民税と市町村民税があり、これらを合わせて法人住民税と呼びます。
法人住民税は、法人税の税額をベースにして算出・課税される「法人税割」と、法人の資本金の金額や従業者数などに応じて算出・課税される「均等割」によって構成され、この2つの合計額によって税額が算出されます。法人住民税の法人税割は、法人税額に定められた税率を掛けて算出するため、赤字で法人税が必要ない場合は納付が不要です。ただし、均等割については、課税所得にかかわらず計算されるため、赤字でも原則として納税義務があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
法人が赤字の場合でも納税が必要な税金
法人に課せられる税金の中には、赤字であっても納税が必要なものもあります。赤字でも納税が必要なものは、法人の所得とは関係なく納税額が計算される税金や、所得の有無にかかわらず納付義務が課せられる税金です。税負担による資金不足を避けるためには、赤字でも納税が必要な税金について知っておくことが大切になります。赤字決算の場合でも納税が必要な税金は、以下のとおりです。
法人住民税の均等割
上述したように、法人住民税のうち「均等割」は、赤字でも納税が必要です。法人住民税の均等割は、法人の資本金の金額や従業者数などに応じて計算されます。道府県民税では法人の資本金等の額、市町村民税では資本金等の額と従業者数によって納める税額が区分され、課税額は資本金の金額や従業者数が多い法人ほど高くなります。
消費税
消費税は、商品やサービスなどを購入(消費)する際に発生する税金です。消費税は間接税で、税金を負担する人と納税者が異なるしくみになっています。消費税を負担するのは消費者ですが、申告・納付するのは、消費者から消費税を受け取った事業者です。2期前の課税売上が1,000万円超、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録をしているなど、所定の要件に該当する事業者は課税事業者となり、赤字であっても消費税の申告・納付義務が発生する場合があります。
ただし、消費税の申告にあたっては、売上にかかった消費税から、仕入や経費にかかった消費税を差し引いて納税額を求める「仕入税額控除」が認められます。そのため、一般課税(本則課税)を採用している事業者は、多額の設備投資などで支払った消費税が受け取った消費税を上回れば、消費税の納付は不要で、逆に還付を受けることができます。その一方で、簡易課税を選択している場合は、消費者から受け取った消費税額を基に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて納付額の計算を行うため、赤字でも課税が発生します。
源泉所得税
源泉所得税とは、給与などの支払者が支払額から徴収し、本人に代わって国に納付する所得税のことです。会社員など給与所得者の所得税は、給与や賞与などから天引きして、企業が本人に代わり納めるしくみになっています。源泉所得税は従業員個人の所得にかかる税金であり、法人の事業や所得とは無関係です。そのため、たとえ赤字決算であっても、期限までに納めなければなりません。従業員の給与などから天引きして自治体に納める個人住民税についても同様です。
印紙税
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書などに課せられる税金です。印紙税の課税対象になる文書は「課税文書」と呼ばれ、全20種類が印紙税法によって定められています。課税文書に該当する書類を作成・発行する場合は、赤字かどうかにかかわらず、必ず印紙税の納付が必要です。なお、印紙税の納付は、課税文書ごとに定められた税額の収入印紙を貼付・消印することによって行います。
登録免許税
登録免許税は、登記や登録、特許などについて課せられる国税です。法人の場合は、設立登記や変更登記の際に登録免許税を納める必要があります。また、不動産を登記する場合などにも登録免許税が課せられます。なお、登録免許税に法人の所得は関係ありません。
固定資産税
固定資産税は地方税の一種で、個人や法人が所有する固定資産に対して課せられる税金です。土地や家屋など多くの不動産が、税金を課せられる固定資産に該当します。その他、事業用として使われる機械や機器類なども、固定資産税の対象です。
固定資産税の納付額は、土地や家屋、償却資産などの固定資産の資産価値を示した評価額に応じて決まるため、赤字であっても、固定資産税の対象になる固定資産を所有していれば、納税義務が生じます。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
自動車税
自動車税(および軽自動車税)は、自動車の取得者や保有者に対して課せられる地方税です。自動車税には、自動車の取得時に課せられる「環境性能割(取得課税)」と、4月1日時点で自動車を保有している人に毎年課せられる「種別割(保有課税)」があります。それぞれ対象となる場合は、赤字でも納税義務が生じます。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計上は赤字でも税法上黒字なら税金が発生する
法人税や法人事業税などは、法人の益金から損金を差し引いた所得を基に計算されるため、赤字の場合は納税が不要となります。このとき気を付けなければならないのが、税法上の所得は、会計上の利益とは異なるということです。
税法上の所得は益金から損金を引いて求めますが、会計上の利益は収益から費用を引いて求めます。収益と益金、費用と損金はそれぞれ似ているものの、必ずしも一致するとは限りません。会計上は収益や費用として計上できても、税法上は益金や損金と認められないものもあります。例えば、法人の交際費は、会計上は費用ですが、税法上は法人規模に応じた一定額までしか損金に計上することができません。
このような所得と利益の違いを把握せずに税金の計算をすると、大きなずれが生じてしまうため注意しましょう。会計上は赤字になっていても、税務上の所得があれば、法人税などの税金が発生します。もし、会計上の利益を基に税務申告を行った場合、修正申告や追徴課税の対象になることがあります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
赤字決算のメリット
赤字決算は利益がマイナスの状態のため、基本的には避けるべきものです。しかし、赤字決算になることで、法人にとってメリットが生じる場合もあります。主な赤字決算のメリットについて見ていきましょう。
法人税を納める必要がなくなる
赤字決算で課税所得額がマイナスになった場合は、法人税を納める必要はありません。法人税額を基に計算される地方法人税や法人住民税の法人税割、課税所得がベースになる法人事業税・特別法人事業税についても、納付が不要になります。税負担を抑えられることは、赤字決算の大きなメリットといえるでしょう。
前年分の法人税の還付を受けることができる
青色申告を行っている法人が赤字になった場合、前期に黒字が出ていれば、繰戻しによる法人税の還付が受けられます。繰戻しとは、過去に申告した年度の黒字にさかのぼって、赤字を相殺できる制度です。前期の黒字と今期の赤字を通算する(前期所得から今期赤字を差し引く)ことで、前期分の法人税が軽減され、納めすぎになった分の法人税が還付されます。なお、還付されるのは前期に支払った法人税であり、前々期以前の法人税は対象になりません。
赤字を繰り越すことができる
青色申告を行っている事業者は、赤字(欠損金)を翌期以降の最大10年間繰り越せる「欠損金の繰越」を利用できます。繰り越した赤字は翌期以降の損金として計上され、その分、法人税などの負担を軽減することができます。なお、資本金が1億円を超える事業者は、繰越控除を受けて黒字と相殺できる金額に限度がありますが、資本金1億円以下の事業者であれば、黒字金額のすべてについて赤字の繰越控除により相殺することが可能です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
赤字決算のデメリット
赤字決算には税負担を抑えられるなどのメリットがありますが、デメリットやリスクもあります。赤字決算になった場合は、資金調達に影響が出たり脱税を疑われる可能性があったりすることを把握しておきましょう。
資金調達に影響が出る
赤字決算は、資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。赤字や長期的な債務超過は金融機関からの信用低下を招き、融資を受けることが難しくなる可能性があるためです。
ただし、設備投資や固定資産の売却損、天災のような特殊事情、在庫の処理といったように、一時的には赤字でも本業が順調であれば、金融機関からの借入に影響しないケースもあります。また、開業から日が浅く、数年後には黒字化が見込まれるケースも同様です。
脱税を疑われる可能性がある
赤字決算が続くと、税務調査の対象になるリスクが生じます。本来なら、赤字の状態が継続していると、経営が困難になるはずです。赤字決算が何期も続いた場合、「本当は利益が出ているのに、脱税目的で赤字に見せかけているのではないか」と税務署に疑われてしまうかもしれません。税務調査の結果、不当な会計処理があると判断されると、通常よりも重い税率で課税されることがあるので注意しましょう。
債務超過によって倒産の可能性がある
赤字決算が何期も続くと、債務超過による倒産の危険性が高まります。債務超過とは、会社が保有する資産をすべて現金化しても、借入金などの負債を払いきれない状態を指します。
一時的な赤字であれば、過去の利益(利益剰余金)でカバーしたり、資金繰りしだいで乗りきったりすることもできるでしょう。しかし、赤字が常態化すると負債が資産を上回る債務超過に陥りかねません。債務超過になると金融機関から信用されにくくなり、融資が受けにくいといったデメリットも生じます。その結果、倒産のリスクが高まる可能性があります。
無料お役立ち資料【一人でも乗り越えられる 会計業務のはじめかた】をダウンロードする
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
法人に課せられる税金の種類を正しく把握しておこう
法人には、法人税をはじめさまざまな種類の税金が課せられます。税金の中には、赤字になると納付が必要ないものと、赤字でも納付が必要なものがあるため「赤字決算だから税金を納めなくても問題ない」などと考えていると、税金負担により資金繰りが悪化することがあります。また、税金の計算や申告を行う際には、会計上の利益と税法上の所得を混同しないように注意しなければなりません。法人にかかる税金の種類やしくみを理解し、正しく納税するようにしましょう。
「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。










