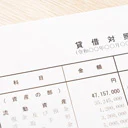自己資本比率とは?計算方法や業種別の目安、注意点などを解説
更新

自己資本比率は、企業の財務安全性を示す重要な指標の1つです。自己資本比率は貸借対照表から求められ、その数値により企業経営の安全性や健全性を判断できます。一般的に、自己資本比率が高い企業は経営の安定性が高いと評価されますが、必ずしも高ければ良いとは限りません。また、自己資本比率だけでなく、その結果を分析して経営に活かすことが大切です。
本記事では、自己資本比率の計算方法や業種別の目安、注意点などについて詳しく解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
自己資本比率とは総資本における自己資本の割合のこと
自己資本比率は、総資本(自己資本と負債を合わせた額)に占める自己資本の割合を示す指標です。自己資本は、総資本から負債(返済する必要がある資本)を差し引いて算出されます。自己資本比率が高い場合、返済不要な資産の割合が高く、企業の安定性や独立性が期待できるでしょう。そのため、中長期的な倒産リスクも低いと考えられます。なお、自己資本比率の目安は業種によって異なるため、企業ごとの状況を踏まえた分析が重要です。自己資本比率を算出するには、以下の計算式を用います。
自己資本比率の計算方法
自己資本比率(%)=自己資本÷総資本×100
なお、自己資本および総資本は貸借対照表で確認できるため、貸借対照表を参照することで自己資本比率の算出が可能です。
貸借対照表についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
自己資本とは返済の必要がない資金のこと
自己資本は、株主から調達した資金や過去の事業利益による内部留保などを原資とする、返済不要の資金です。貸借対照表では純資産の部に表示され、経営者や株主が出資した資本、事業利益を積み立てた利益剰余金、株式発行による資本剰余金などが該当します。
これに対し、資本主以外の外部(他人)から調達した資金で、返済義務のあるものを他人資本と呼びます。経営の安定性は、自己資本が多ければ高く、他人資本が多ければ低くなりがちです。よって、自己資本を増やすことが、安定した企業経営に欠かせない要素といえるでしょう。ただし、業種にもよりますが、企業が事業を営んでいくうえで借入金は不可欠です。特に、設備投資が必要な製造業や大企業などでは、あらゆる事業投資を自己資本のみでまかなうのは現実的ではないケースも多々あります。
総資本とは自己資本と他人資本の合計であり、貸借対照表の資産の部の合計額が相当します。
負債と純資産についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
自己資本比率の目安
自己資本比率の平均は業種により異なるため、一律に「何%が良い」とは判断できません。一般的には、自己資本比率が50%以上で健全とされ、30%以上を維持するのが望ましいとされています。中小企業庁「中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年度決算実績)」(2024年7月)によると、業種別の自己資本比率の平均値は以下のとおりです。
自己資本比率の平均値(産業大分類別)
| 全体平均 | 41.71% |
| 建設業 | 47.34% |
| 製造業 | 46.39% |
| 情報通信業 | 54.87% |
| 運輸業・郵便業 | 34.71% |
| 卸売業 | 42.60% |
| 小売業 | 35.06% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 36.27% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 52.29% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 16.16% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 34.79% |
| サービス業(ほかに分類されないもの) | 47.05% |
-
※中小企業庁「中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年度決算実績)
」(2024年7月)
ただし、上の平均よりも自己資本比率が高かったとしても、純資産の内訳によっては注意しましょう。例えば、利益剰余金の増加によって純資産が増え、その結果として自己資本比率が高まっているのであれば、健全な経営状態といえます。その一方で、赤字続きで利益剰余金はマイナスで株主による出資のみで自己資本比率の水準が保たれている状態だと、必要なときに借入ができずに倒産してしまう可能性も否定できません。このように、自己資本比率が一定以上に保たれていることを確認しつつ、同時に純資産の部の内容や負債と純資産とのバランスを注意深く見ていくことが大切です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
自己資本比率からみる企業の経営状況
ここでは、自己資本比率が高い場合・低い場合・マイナスの場合について、それぞれ企業の経営がどのような状況にあると考えられるのかを解説します。それぞれ詳しく見ていきましょう。
自己資本比率が高い場合
自己資本比率が高い場合、企業の内部留保が潤沢な状態にあることを示しています。資金に余裕があるため、新規事業の立ち上げなども積極的に推進していくことが可能です。また、ビジネス環境の変化にも柔軟に対応でき、設備投資や研究開発に費用を充てられるなど経営の選択肢が増えることから、将来的な事業の成長も見込めるでしょう。
自己資本比率が低い場合
自己資本比率が低い場合は、借入金依存の経営と見なされるため、取引先からの信用が低下しやすく、資金調達や新規取引に悪影響を及ぼすことも考えられます。自己資本が少なく他人資本の影響を受けやすいことから、経営が不安定で倒産リスクがある企業と見なされることもあります。特に、自己資本比率が10%以下の企業は、金融業以外では過小資本と見なされるため注意しましょう。また、返済や金利の負担がかさみ、企業経営を圧迫することにもなりかねません。
自己資本比率がマイナスの場合
自己資本比率がマイナスの場合、赤字経営の状態にあることを示しています。具体的には、他人資本が資産の部の合計を上回っており、企業が保有するすべての資産を売却しても負債を返済しきれない状態です。このような財務状況を「債務超過」と呼びます。債務超過に陥ると、銀行など金融機関から融資を受けるのも難しくなり、倒産リスクが非常に高い状態といえるでしょう。
ただし、創業したばかりの時期や大規模な設備投資を行った直後など、一時的に自己資本比率がマイナスに陥ることもあります。このような場合は徐々に自己資本比率を高め、事業の安定を図ることが大切です。また、自己資本比率がマイナスになっている主な要因が設備投資であれば、新たに導入した設備によってきちんと利益を上げられるようにしていくことが求められます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
自己資本比率を上げる方法
自己資本比率を上げるには、総資本を減少させたり、自己資本を増加させたりする方法があります。具体的な方法として考えられるのは以下の4つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
利益を出して内部留保を増やす
自己資本比率を上げる方法の1つは、利益を出して内部留保を増やすことです。
事業で出た利益から内部留保(自己資本)を増やしていくことで、自己資本比率は上昇します。内部留保は会計上、利益剰余金と呼ばれるもので、自己資本の1つです。長期にわたって継続的に利益を確保しなくてはならない難しさはあるものの、最も基本的かつ望ましい自己資本比率の上げ方といえるでしょう。
資産の合計額を減らしスリム化する
資産の合計額を減らし、経営をスリム化することで自己資本比率を上げる方法もあります。
具体的には、不良債権を貸倒損失として経費計上することで資本が減少し、不良在庫を処分すると自己資本比率が上昇します。長期間回収できていない売掛金や未収入金も資産となるため、処分してよいか見直してみるとよいでしょう。
また、企業経営に必要な運転資金を圧縮し、不良資産や事業目的の資産で稼働していない遊休資産を処分することで、総資本を縮小するのも有効な方法です。不要な資産を圧縮すると、自己資本比率の計算式の分母となる総資本が小さくなりますが、その一方で、分子となる自己資本は影響が少ないため、結果として自己資本比率が上がります。使っていない設備や事業所、土地は保有しているだけで管理費用がかかる他、固定資産税などが課される原因にもなります。そのため、不要な資産を処分して経営のスリム化を図ることは、健全な経営を実現するうえでも重要なポイントです。
負債を減らす
自己資本比率を上げる方法として、負債を減らすこともあげられます。
借入金を見直し、繰上返済が可能なものはできる限り返済することで、自己資本比率を高められます。また、買掛金の支払サイトを短縮したり、支払手形の発行を減らしたりするのも有効な方法です。ただし、繰り上げ返済や買掛取引の支払サイトを短縮することで、利益が出ていても手元資金が不足する黒字倒産の可能性があります。あくまでも自社の実態に照らし合わせて、無理のない範囲で負債の圧縮を行うことが大切です。
増資を行う
増資を行うことも、自己資本比率を上げる方法の1つです。
投資家などから出資を募る増資によって資本金が増加すれば、自己資本比率を高めることができます。また、出資された現金は借入の返済にも充てられるため、負債がある企業であれば結果的に総資本も縮小できます。増資であれば融資のように返済義務がないため、幅広く資金を活用できる点も大きなメリットです。ただし、増資は税負担が増える可能性がある他、手続きに手間がかかるデメリットもあります。また、増資によって自己資本比率を上げることは根本的な改善策にはなりません。そのため、増加した自己資本を有効に活用して、新たな利益を生み出す経営を推進していくことが重要です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
自己資本比率における注意点
自己資本比率を経営分析などに活用する際には、注意点があります。具体的な自己資本比率における注意点は以下の3つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
自己資本比率が高いと成長性は低い
自己資本比率における注意点として、ある程度成熟した企業の成長性は低いため、結果的に自己資本比率が高くなるということです。
自己資本比率が高い企業は当面の倒産リスクが低く、安全性が高いと考えられる一方で、一般的に成長性は低くなりがちです。また、自己資本比率を高めても、積極的に利益を上げて投資を行わないと、成長性が低い状態から改善できません。企業が持続的に成長するには、長期間にわたって継続的に利益を得て、投資を行う必要があります。
自己資本比率が高いと成長性が低いというよりは、成長性が低い企業は自己資本比率が高くなりがちということです。
当面の自己資本比率だけを重要視するのではなく、将来にわたって自己資本比率を安定的に維持できる収益構造となっているかを含めて分析していくことが必要です。企業の成長性を重視する場合は、状況に応じて資金調達も視野に入れて検討していく余地があるでしょう。
財務状況の変化を見極めることが大切
自己資本比率が減少している場合には、それが一時的なものか、借入金に依存した経営により資金繰りが厳しい状況に置かれているのか、財務状況の変化を見極めることが大切です。
設備投資などに伴い、固定資産にならないような支出が増えれば一時的に自己資本比率が低下することは十分にありえます。事業の成長に寄与する設備投資であれば、中長期的には財務状況を好転させる契機となる場合もあるでしょう。また、一時期の自己資本比率だけでは、その企業がどのような財務状況にあるのか正確に判断できないことが懸念されます。
自己資本比率は、あくまでも企業を分析する際の指標の1つにすぎません。企業の成長ステージや収益性などについても確認し、財務状況を総合的に判断することが求められます。自己資本比率の推移も併せて参照するなど、財務状況が常に変化していることを念頭に置いて分析を進めていくことが大切です。
ROE(自己資本利益率)が低くなる
ROE(Return On Equity:自己資本利益率)とは、自己資本を活用して企業がどれだけ利益を獲得しているのかを示す指標のことです。主に株主の視点から投資効率を確認するための指標として用いられます。ROEの計算式は以下のとおりです。
ROEの計算方法
ROE(%)=当期純利益÷自己資本(純資産)×100
自己資本比率は企業の安全性を測るための指標として用いられますが、その一方で、ROEは企業の収益性を測るために活用されています。自己資本比率が高い企業は安全性が高いと考えられるものの、利益を上げる効率を示すROEは下がります。なお、ROEが高い企業は、限られた自己資本で大きな利益を上げていることを意味するため、投資家から高評価を得られるケースが少なくありません。そのため、自己資本比率とROEのバランスを考慮していくことが重要です。
ROEについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
自己資本比率を正しく分析して企業の成長につなげよう
自己資本比率は、企業の財務安定性や健全性を評価するための重要な指標です。自己資本比率を継続的に見ていくことで、企業の財務状況をより適切に把握しやすくなります。一般的に、自己資本比率が高いほど経営が安定しており、自己資本比率が10%以下の企業は注意が必要といわれていますが、目安となる数値は業種によって異なります。
なお、自己資本比率を上げるためには、さまざまな方法が考えられますが、当面の自己資本比率だけを上げること自体を目的にすべきではありません。継続的に事業を成長させ、安定的に利益を確保することが重要なポイントです。自己資本比率を算出するのに必要な自己資本および総資本は貸借対照表で確認できます。弥生の会計ソフトを導入し、貸借対照表を効率良く適切に作成しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。