会計ソフトとは?導入するメリットや注意点、比較するポイントを解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

法人、個人事業主を問わず、決算や納税を行う事業者にとって、日々の会計業務は欠かせません。会計業務を正確に行うことで自社のお金の流れも把握しやすくなり、財務状況や事業の成績、改善すべき点なども見えてきます。
会計業務は、日々の帳簿付けや請求書や領収書などの発行・管理など多岐にわたりますが、会計ソフトを活用することで、効率化やミスを防ぐ作業につながります。
本記事では、会計ソフトを導入するメリットや注意点のほか、自社に合った会計ソフトの選び方などについて解説します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトは会計業務を効率的に行うツール
会計ソフトとは、会計業務を効率的に行うためのソフトです。事業に関する複雑な計算を自動的に行ってくれるだけでなく、帳簿や決算書などさまざまな種類の帳票を作成・出力することもできます。
お金の流れを効率的に知りたい場合も、会計ソフトを使うのがおすすめです。中小企業や個人事業主、扱う金額や取引先が少ない事業であっても、なんらかの会計ソフトを利用することで効率的な会計業務が可能になります。
【法人向け】おすすめ会計ソフト(クラウド)【弥生会計 Next】資料ダウンロード
会計ソフトを導入するメリット
会計ソフトを導入することで、具体的にどのようなメリットが期待できるのでしょうか。
ここでは、8つのポイントに分けて見ていきましょう。
業務の効率化が期待できる
会計ソフトを使うと、表計算ソフトなどを用いた手入力と比べて各段に速く会計処理を記録したり、帳簿書類を作成したりできます。入力補助機能を搭載しているため、仕訳項目もスムーズかつ正確になり、入力漏れや転記ミスも防止できるでしょう。伝票入力したデータも会計ソフト上で集計されるため、伝票の内容を仕訳帳や総勘定元帳へ転記する手間も不要です。そのため、結果として会計業務の効率化が期待できます。
また、会計ソフトのスキャン機能を使えば、スキャンで読み取ったデータが自動で入力されるため、入力の手間自体も軽減できます。さらに、スマートフォンのカメラ機能に対応している会計ソフトなら、外出先からでも経費などのデータを、かんたんに入力をすることが可能です。
ミスや不正行為の防止につながる
会計ソフトは、お金の流れを手作業で入力する必要がなくなり、入力補助機能も搭載されているため、ミスの防止にもつながります。紙の領収書や納品書、注文書をスキャンすれば自動入力できる機能もあるため、ヒューマンエラーを大幅に減らすことができるでしょう。
また、入力履歴やアクセスログを保存できる会計ソフトなら、データの書き換えや改ざんも難しくなるため、第三者による不正行為防止にもなります。
顧問税理士とのデータ共有が容易になる
会計ソフトで作成したデータは、システム上で顧問税理士と共有することもできます。決算のたびにメールや郵送でデータを送ったり、書類の確認のために来社してもらったりする必要もありません。データ上に修正箇所があった場合は、税理士側で修正してもらうことも可能です。
バックアップができる
会計ソフトを使用すれば、システム上でデータのバックアップを保存できます。帳簿を紛失したり、表計算ソフトで作成したデータを誤って消去してしまったりするリスクもなくなります。また、仕訳データの入力中も、1回入力するごとにバックアップが記録される会計ソフトもあるため、時間をかけた作業の際も安心です。
知識・経験の少ない担当者も扱いやすい
表計算ソフトや紙の帳簿では、入金、出金、振替、売掛金や買掛金といった掛け取引などのお金の動きを各伝票に記載して、それを仕訳帳や総勘定元帳へ転記しなければなりません。そのため、会計業務についてある程度の知識と経験がなければ、スムーズな処理ができないという課題がありました。
その点、会計ソフトなら自動的に仕訳され、税区分まで入力されます。会計の知識や経験に不安がある担当者でも、簡単かつ正確に入力することができるでしょう。
会計業務が属人化しづらくなる
会計業務は「業務がマニュアル化されていない」「知識と経験が豊富な担当者でなければミスが起こりやすい」「担当者が多忙なため業務改善や効率化が進まない」といった理由で、属人化しがちな側面もあります。
しかし、会計ソフトを導入すれば、仕訳や集計、帳票書類の発行、決算書の作成といった一連の業務を自動化できるようになるため、属人化の解消につながるというメリットもあります。
テレワークに対応しやすい
会計ソフトを導入すれば、紙の帳簿がなくてもシステム上で会計作業ができるようになります。紙の帳簿の場合は、経理担当者が出社しなければならずテレワークに対応できないというデメリットがありますが、会計ソフトならその問題も解決できるでしょう。
予算管理や先行投資など、意思決定が迅速に行える
会計ソフトには、入力したデータを分析し、期中の経営成績を把握するための試算表などのレポートを作成できる機能を搭載しているものもあります。会計ソフトから出力したレポートを活用して、予算管理や先行投資などの経営における意思決定を、スムーズに行えるというメリットもあります。
また、決算書や試算表などのデータを会計ソフト上で出力すれば、最新の数字を確認することも可能です。問題や課題の早期発見ができれば、経営改善につながることも期待できるでしょう。
会計ソフトを導入するうえでの注意点
会計ソフトを導入する際には、次のようなポイントに気を付けましょう。
領収書や請求書など、紙書類は整理しておく
会計ソフトが手伝ってくれるのは、あくまでも情報がデータになった瞬間からです。店舗で受け取った領収証や、取引で発生した請求書・受領書などの書類はきちんと整理し、入力しやすい環境をつくっておきましょう。
取引データの記録を確認する
クレジットカードや銀行取引などを自動で取り込み、自動仕訳をする機能がある会計ソフトもあります。そのため、事前の連携設定とインターネット環境の用意が必要です。銀行取引などは、契約銀行によっては、インターネットで取引履歴を取得できる期間が決まっていたりするため、最新の取引データしか取得できない場合もあります。
その場合、通帳や請求書や領収書を基に入力作業を行うことになります。入力する時間と作業が余計にかかることになるので、連携設定や「確実に取引データを取得し、会計ソフトに仕訳として記録できたかどうか」といった確認は怠らないようにしましょう。
ある程度の会計知識は必要
会計ソフトは初心者でも扱えるというメリットがあります。しかし、実際に会計ソフトを扱う担当者は、会計や簿記に関する知識はある程度必要ということも注意が必要です。会計関連の知識があれば、会計ソフトを使った業務もスムーズに行えるうえ、会計ソフトで作成した帳簿が合っているかどうかをチェックする際も、ミスを見落としにくくなるためです。
会計ソフトを導入するにあたり、経理部署もしくは経理担当者が既に会計業務を行っているのであれば、新たに会計や簿記関連の知識を身に付ける必要はほとんどありません。
ただし、会計や簿記の知識、経験がない従業員が新たに経理担当者となる場合は、会計や簿記の基礎知識を習得したうえで会計ソフトを使っていく必要があります。会計に関する知識を学ぶにあたり、税制度や納税ルールについても把握しておくことで、効率良く会計ソフトを活用していくことができるでしょう。
会計ソフトは無料と有料、どちらを選ぶべき?
会計ソフトには、無料で利用できる機能と有料でなければ利用できない機能は異なります。そのため、各社は「有償サービスになること・無料でできること」などを公開しており、検討する人は、自分に必要な機能やサービスが含まれているかの確認をする必要があります。
場合によっては、永年無料ですべての機能が使えるものもあれば、1か月に入力できる取引件数や出力される資料など無料でできる範囲が制限されているものもあります。最低でも次のようなことは確認しておきましょう。
無料ソフトを利用する際、確認しておきたいこと
- 機能を利用できる期間は限定されているか(いつまで無料で利用できるのか)
- 取引件数や仕訳件数は限定されているか(件数に制限があるのか)
- 仕訳などの入力や決算書作成・印刷など基本的な機能が使えるか
- 取引情報の保存機能、契約の違いなどはあるか
- 電話やチャットなどサポートはあるか
- 税制の変更などに対応しているか(改正対応をするためにどれくらいの時間がかかるか?回数や期間の制限はあるか)
特に、サポートの手厚さには大きな違いが出るため、「どこまで自分自身で管理できるか」を見極め、ソフトを選ぶ必要があります。
決めにくい場合には、期間を決めて複数の会計ソフトを利用してみる、無料トライアル期間や体験版を提供しているソフトを利用するなどして、使い勝手を確認してみてください。高価なものほどよいというわけではなく、あくまでも「自分や自分の事業に適した会計ソフトかどうか」といった視点が大切です。
クラウド型とインストール型の会計ソフトの違い
会計ソフトは、大きく分けるとクラウド型とインストール型の2つのタイプに分けられます。これらはサービスの提供形態が大きく異なるほか、それぞれメリット・デメリットも変わってくるため、自社のニーズに合ったものを選ぶことが大切です。
ここでは、各タイプの会計ソフトの特徴と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
クラウド型の会計ソフトの特徴
クラウド型の会計ソフトとは、その名のとおりデータがサーバーなどのクラウド上へ保存される会計ソフトです。利用者はインターネット経由でクラウドへアクセスして会計ソフトを使うこととなります。したがって、会計ソフトを使うためには、インターネットへ接続されているデバイスを用意する必要があります。
クラウド型のメリット
クラウド型の会計ソフトは、月額制や年額課金制のサービスに登録して利用します。そのため、会計ソフトを導入するにあたり、初期費用を抑えられるというメリットがあります。ブラウザ上で使う会計ソフトなら、OSの種類を問わず使い始めることができるでしょう。
また、クラウド型なら自動的にアップデートが行われるため、税制度の改正や会計業務に関する新制度が実施された場合でも、ソフトを自社で更新する必要がありません。最新の法律や制度に随時対応できる点も大きな強みといえます。
クラウド型のデメリット
インストール型の会計ソフトであれば、購入時以外は基本的には費用がかからないのに対して、クラウド型の会計ソフトの場合、継続的に利用料が発生するため、長期的に考えると費用の負担が大きくなってしまいます。
また、クラウド型の会計ソフトの場合、インターネットに接続できない環境では使えない点にも注意が必要です。そのため、通信障害などが発生すると、復旧するまでは会計ソフトが使えない可能性もあります。
インストール型の会計ソフトの特徴
インストール型の会計ソフトとは、会計ソフトをパソコンにインストールして使用する会計ソフトです。「パッケージ型」や「買い切り型」と呼ぶこともあり、一度購入した後は費用がかかりません。
インストール型のメリット
インストール型の会計ソフトは、インターネットに接続していないオフライン環境でも使用できます。そのため、通信障害などの影響を受けないというメリットがあります。また、導入時には購入費用がかかりますが、購入後はランニングコストがかからない点も魅力です。
インストール型のデメリット
インストール型の会計ソフトは、インストールできるデバイスの数や対応できるOSに制限のあるケースが少なくありません。また、クラウド型とは異なり自動的にアップデートされないため、法改正などが行われる場合は、自社で対応する必要があります。
会計ソフトを導入する際の流れ
実際に会計ソフトを導入する際には、どのような流れで実施すればよいのでしょうか。ここでは、会計ソフトを導入し、実際に使い始めるまでの流れを、5つのステップに分けて見ていきましょう。
1. 会計ソフトを導入する目的を決める
まずは、「経理担当者の業務負担を軽減したい」「会計処理におけるミスを防ぎたい」など、自社になぜ会計ソフトが必要なのか、目的を明確にすることが大切です。あらかじめ会計業務における課題を洗い出しておくことで、導入目的も定まりやすいでしょう。また、目的が定まれば、会計ソフトに必要な機能やサービスも選定しやすくなります。
2. 導入スケジュールを立てる
会計ソフトを導入する目的が決まったら、いつ導入して稼働させていくのか、導入スケジュールを立てます。その際には、自社の決算期や繁忙状況を考慮する必要があります。決算期については、期中に会計ソフトを導入することも可能ではありますが、期首からのデータをすべて入力しなければならない点に留意しましょう。また、業務が立て込む繁忙期に導入すると、経理担当者への負担が増してしまう点にも注意が必要です。
3. 会計ソフトの比較検討をする
導入スケジュールが決まったら、導入目的に見合う機能やサービスを搭載した会計ソフトを選びます。無料試用期間やデモ版を提供している会計ソフトがあれば、経理担当者に実際の使い心地を試してもらいましょう。
また、複数の会計ソフトを比較検討する際は、それぞれに見積もりを依頼して、初期費用とランニングコストを比較することも大切です。
4. 会計ソフトを選定し、導入する
導入する会計ソフトが決まったら、いよいよ導入に向けた準備に移ります。会計ソフトを契約または購入して、インストール作業やログイン作業を行いましょう。クラウド型の会計ソフトなら、契約した当日から利用できるためスムーズです。
5. 初期設定をして利用を始める
会計ソフトの導入準備が完了したら、まずは自社の経理処理に応じた初期設定を行います。会計年度や取引先の企業名、消費税の区分、自社の預金口座、開始残高などを設定しましょう。会計ソフト上の権限設定などのセキュリティ対策も、稼働前に済ませておくことをおすすめします。
会計ソフトを比較する際のポイント
続いては、会計ソフト選びで失敗しないためのポイントをご紹介します。自社の目的や状況に合った会計ソフトを導入するためにも、以下の6つのポイントを押さえて比較検討しましょう。
自社の事業規模に合っているか
会計ソフトは、自社の事業規模に合った機能を搭載したものを選ぶことが大切です。法人が導入する場合は、貸借対照表と損益決算書の作成機能は必須といえます。株主資本等変動計算書や個別注記表にも対応している会計ソフトを導入する必要があるでしょう。会計ソフトによっては、事業規模ごとに適したプランを用意しているところもあります。
担当者のスキルに合っているか
会計ソフトは、実際に使用する担当者のスキルに合ったものを選びましょう。会計ソフトによって、求められる会計・簿記関連の知識やスキルが異なるためです。
サポート体制は充実しているか
会計ソフトを導入する際は、サポート体制が充実しているかどうかも必ず確認しましょう。導入方法や操作方法がわからない場合やトラブル発生時に、電話やチャット、メールでスピーディに対応してもらえるかどうかが重要です。サポートデスクの時間帯と曜日も含めて確認することをおすすめします。
導入時のサポートやアフターフォローの手厚い会計ソフトなら、スムーズに導入し、運用開始後も安心して使うことができます。
直近の法改正に対応しているか
電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の開始など、近年だけでも複数の法改正が実施されました。こうした法改正に対応した会計ソフトかどうかも確認しておきましょう。会計や税金関連の法改正は今後も行われる可能性が高いため、自動でアップデートされるかどうかも併せて確認することが大切です。
顧問税理士と連携できるソフトなのか
スムーズに会計データを共有したり税務を代行してもらったりできるよう、自社の顧問税理士や会計士の利用している会計ソフトと連携可能かどうかも確認しておきましょう。クラウド型の会計ソフトなら、税理士や会計士をユーザーとして登録し、クラウド上でデータを共有しながら業務を行うことも可能です。
無料の試用期間はあるか
無料の試用期間があるかどうかも、あらかじめチェックしておきましょう。試用期間中に経理担当者に操作感を確認してもらうことで、担当者にとって使いやすく、業務効率化にもつながる会計ソフトを絞り込むことができます。
会計ソフトを使うと税理士は不要?
会計ソフトを導入すれば、税理士は不要なのか疑問に思う方もいるかもしれません。法人の場合は、会計業務そのものも増えるうえに、税務や申告に関する知識が必要な判断が増えるため、会計ソフトを使っていたとしても、税理士に相談するケースが多くなります。そのため、会計ソフトを導入しても、税理士は必要といえるでしょう。
また、次のような理由からも、法人は会計ソフトを導入しても税理士が必要となります。
法人が会計ソフトを導入しても税理士が必要な理由
- 税理士のアドバイスにより、税務調査の入る可能性が低い決算書や確定申告書を作成できる
- 節税の提案をしてもらえる
- 会計ソフトを効率良く使うためのサポートを受けられる
なお、個人事業主の場合、事業規模や会計に関する処理の多さにもよりますが、会計ソフトを導入すれば税理士は不要となるケースが多いといえます。
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
自社の業務効率化につながる会計ソフトを選ぼう
会計ソフトを使って業務を効率化させるには、自社の会計業務の状況や何を改善したいのかを踏まえて製品を選び、スケジュールも立てたうえで導入することが大切です。また、導入後も業務に支障なく使い続けられるよう、実際に会計ソフトを使う担当者にとって使いやすいものを選ぶ必要があります。
自社の業務効率化につながる会計ソフトをお探しの方は、弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
一人でも乗り越えられる会計業務のはじめかた
起業したての方におすすめ。
日々の帳簿付けから決算まで、これひとつですぐわかる!
全34ページで充実の内容です。
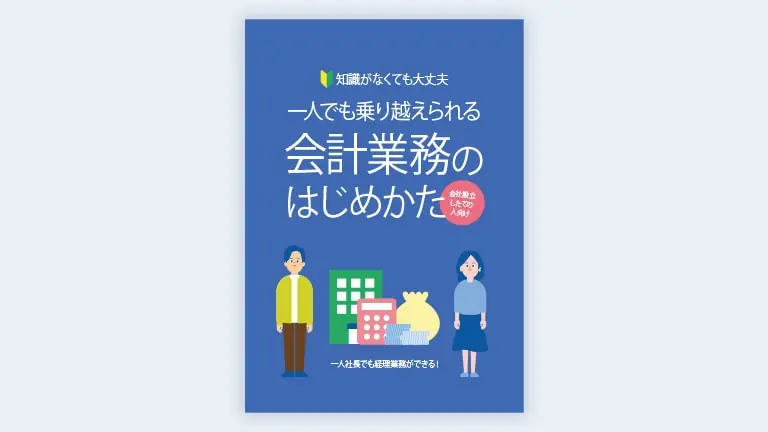
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ










