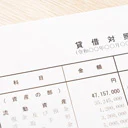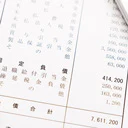流動比率とは?計算方法や業種別の目安をわかりやすく解説
更新

事業を継続するためには、常に資金繰りを意識した経営を行う必要があります。長期的に安定した経営を行うためには、中長期的な経営計画を検討することが重要です。たとえ黒字経営でも、資金がショートすれば立ち行かなくなってしまいますから、短期的な資金の状況には十分注意しましょう。
短期的な経営の安全性を測る指標のひとつに、流動比率があります。本記事では、流動比率からわかることや、流動比率の計算方法、業種別の平均値などについてまとめて解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
流動比率とは流動資産と流動負債のバランスを示す指標
流動比率は、流動資産と流動負債のバランスを示す指標です。短期的に支払いが必要な流動負債と、短期的に現金化できる流動資産のバランスを見ることで、短期的な事業の安全性がわかります。まずは、流動比率に関係する、流動資産と流動負債についてご説明します。
流動資産とは短期間で現金化できる資産
流動資産は、短期的に現金化が可能な資産を指します。流動資産には、以下のような資産が含まれます。
流動資産についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
主な流動資産
- 現金
- 普通預金
- 売掛金
- 受取手形
- 棚卸資産
以上の資産は、すべて1年以内の現金化が見込まれます。つまり、流動負債の支払いに充てることができる資産ということです。
流動負債とは短期間で返済しなければならない債務
流動負債は、短期間で返済しなければならない債務です。具体的には、以下のようなものが該当します。
主な流動負債
- 買掛金
- 未払い金
- 短期借入金(借入期間が1年以内)
これらは、1年以内に支払いが必要な債務です。支払日が到達した時点で手元に支払額を上回る現金や預金がないと、資金がショートしてしまいます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
流動比率の計算方法
流動比率は、次の計算式で求められます。
流動比率の算出方法
流動比率=流動資産÷流動負債
たとえば、流動資産900万円(現預金300万円、売掛債権500万円、棚卸在庫100万円)、流動負債700万円(買掛金400万円、未払い金300万円)の場合の流動比率は、以下のようになります。
(300万円+500万円+100万円)÷(400万円+300万円)=128.6%
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
流動比率は高い方が良い?低くても問題ない?
流動比率を見ると、今後1年以内に予定される支払いをカバーできる手元資金があるかどうかの目安がわかります。
流動比率が100%を下回っている場合、流動資産よりも流動負債のほうが大きいということになりますから、資金がショートする危険性があるといえるでしょう。また、100%を上回っていたとしても、あまりぎりぎりでは現金化のタイミングと支払いのタイミングのずれによるショートが起こりえます。そのため、流動比率は200%程度あるのが理想とされています。
ただし、理想的な比率は業種によっても異なり、120%程度で推移する業種もあれば、200%を超えるような業種もあります。例えば、毎日現金が入金される小売業と、支払いサイトが長い建設業などでは、目安となる流動比率は変わります。特に、買掛金の支払いサイトが売掛金の支払いサイトよりも短い場合、入金がある前に支払いを行わなければいけませんから、手元資金に余裕のある経営が求められるのです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
流動比率の業種別平均と目安
流動比率は、業種によってかなり違いがあります。以下は、2020年度の中小企業の流動資産と流動負債の平均から算出した、業種別の平均流動比率です。
| 業種 | 流動資産 | 流動負債 | 流動比率 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 1億4,336万6,268円 | 7,166万3,459円 | 200.1% |
| 製造業 | 3億529万7,848円 | 1億5,367万7,319円 | 198.7% |
| 情報通信業 | 1億6,283万3,500円 | 6,633万93円 | 245.5% |
| 運輸業、郵便業 | 1億8,907万166円 | 1億473万443円 | 180.5% |
| 卸売業 | 3億3,865万3,043円 | 1億9,587万228円 | 172.9% |
| 小売業 | 8,847万666円 | 5,504万3,129円 | 160.7% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 1億6,449万5,485円 | 9,297万4,541円 | 176.9% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 7,885万7,328円 | 4,168万4,587円 | 189.2% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 4,596万6,019円 | 2,967万6,291円 | 154.9% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 1億3,868万3,888円 | 8,063万6,161円 | 172.0% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1億2,229万9,663円 | 6,682万5,267円 | 183.0% |
- ※総務省統計局「令和3年中小企業実態基本調査の概要(令和2年度決算実績)
」
流動比率が高い業界としては、情報通信業や建設業、製造業などが挙げられます。これらの業界では、流動負債に対して多額の流動資産を保有しているケースが多くなっています。一方利益率が一般的に低い小売業や宿泊業、飲食サービス業では、現金の入金と費用の支払いが拮抗しがちであり、流動比率は他業種に比べて低めです。
ただし、同じ小売業でも、何を取り扱っているのかによって確保しておくべき資金の額は異なります。自社の取扱製品や支払いサイト、ビジネスモデルをもとに、適切な流動比率をキープすることが大切です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
流動比率を高くする方法
流動比率は、流動負債と流動資産の割合で算出するものです。流動比率の改善を目指すのであれば、流動負債を減らすか、流動資産を増やす必要があると考えられます。それぞれの具体的な方法について見ていきましょう。
流動負債を減らす
流動負債を減らすためには、買掛金や短期借入金などを早期に返済する、または、できるだけ利用しないようにするといった方法が考えられます。しかし、こうした対策は結局流動資産である現金や預金も同時減少するため流動比率の改善には役立ちません。
そこで、短期借入金を長期借入金にして、流動負債ではなく固定負債にするという方法があります。ただし、借り入れをしていること自体は変わりません。目先の資金繰りには余裕ができますが、その分継続して返済をしなければいけない点は意識することが重要です。また、長期借入金は短期借入金に比べて審査が厳しく、融資が受けにくい傾向があります。
流動資産を増やす
事業を軌道に乗せて利益が増えれば、流動資産の増加につながります。事業の利益率を上げたり、売上を増やしたりする工夫をしましょう。
また、在庫を早期に売却すれば、その分手元資金が増えます。在庫は、元々流動資産に含まれるため、根本的な「流動資産を増やす対策」とはいえません。しかし、在庫には、現金化にかかる時間が読めないという難点があります。つまり、流動資産の内訳を変えることで、キャッシュがショートするリスクを軽減できるのです。また、在庫を抱えると価値の減少による安値処分などのリスクで間接的に流動資産を減少させる要因にもなります。
状況によっては、固定資産の売却による現金化も効果的です。利用していない固定資産を現金化すれば、流動資産として活用できます。流動資産が増えれば、結果として流動負債の早期返済などにもつながると考えられます。
固定資産についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
流動比率を見る際の注意点
流動比率の確認を数字だけで行っていると、実態を正しく把握できない可能性があります。流動比率の数字や推移を確認する際は、内容にも注意しなければいけません。続いては、流動比率を見る際に注意すべき2つのポイントを解説します。
流動資産の内訳も重要
たとえ流動比率が高くても、内容によっては資金のショートにつながる可能性があります。例えば、以下の2つの企業はどちらも流動比率が150%です。
流動比率の比較例
企業A
- 流動資産:900万円(現預金:100万円、売掛金:300万円、棚卸在庫:500万円)
- 流動負債:600万円(買掛金:400万円、短期貸付金:200万円)
- 流動比率:900万円÷600万円=150%
企業B
- 流動資産:900万円(現預金:300万円、売掛金:400万円、棚卸在庫:200万円)
- 流動負債:600万円(買掛金:400万円、短期貸付金:200万円)
- 流動比率=900万円÷600万円=150%
企業Aは流動資産のうち棚卸在庫が占める割合が大きく、買掛金と短期貸付金を現預金と売掛金の回収額でカバーすることができません。このような状況を放置すると、支払いのタイミングでキャッシュを用意できない可能性があります。
それに対し、企業Bは流動資産のうち現預金と売掛金で流動負債をカバーできる状況にあります。売掛金の回収がスムーズにいけば今すぐに資金不足に陥るような可能性は低いでしょう。
また、売掛金の内訳にも注意が必要です。入金予定日を過ぎていて、回収の見込みが低い不良債権が混ざっていると、正確な数字が出せません。
数字が正しいかどうか精査が必要
流動比率は、流動資産と流動負債の金額が正しいという前提に立って算出するものです。買掛金の計上漏れがあったり、短期借入金と長期借入金を正しく区分していなかったりすると、正確な比率が出せません。
また、不良在庫を処分して損失計上せず資産として保有し続けているといった理由でも、比率の正確性は失われます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
間違えやすいそのほかの指標との違い
事業の安全性を測るための指標は、流動比率だけではありません。流動比率と名称が似ているそのほかの指標についてご紹介します。
当座比率
当座比率は、流動比率よりもさらに正確に短期的な資金繰りを確認するための指標です。流動比率では流動資産と流動負債の比率を見ますが、当座比率では当座資産と流動負債の比率を見ます。
当座比率の算出方法
当座比率=当座資産÷流動負債
当座資産とは、流動資産のうち、特に換金がしやすい以下のような資産のことです。
主な当座資産
- 受取手形
- 未収金
- 営業債権
- 売掛金
- 普通預金
- 現金
- 売買を目的とした有価証券
- 1年以内に回収予定の債権
なお、棚卸資産は短期的に換金できるとは限らないため、流動資産ではありますが、当座資産には含まれません。当座比率は、100%を超えていれば安全性が高いといわれています。ただし、当座資産に含まれる売掛金や受取手形は、短期的に現金化できるとはいえ、現金や普通預金などに比べると時間がかかるため、算出のタイミングには注意が必要です。これらの金額が、仕入債務を大きく上回っている場合、資金ショートのリスクがあります。
【関連記事】
固定比率
流動比率が流動資産と流動負債のバランスを見るのに対し、固定比率では固定資産と資本金のバランスを見ます。固定比率は、事業の長期的な安全性を見るときの参考になります。100%以下であれば、安全性が高いといえるでしょう。
固定比率の算出方法
固定比率=固定資産÷自己資本(純資産)
固定資産とは、土地や機械など、短期的に現金化する予定のない資産です。それに対し自己資本は、株主資本や利益剰余金などの返済する必要がないお金です。固定資産と自己資本のバランスを見ることで、固定資産への投資を過剰な借入金で行っていないかどうかがわかります。
ただし、借入金で投資を行っていたとしても、それが1年超の長期的に返済する長期借入金(固定負債)による投資であれば、投資による成果としてキャッシュを生み出すことができればそれほど大きな問題はないと考えられます。
【関連記事】
自己資本比率
自己資本比率は、自社の総資本のうち、返済する必要のない自己資本がどの程度あるのかを示す比率です。
自己資本比率の算出方法
自己資本比率=自己資本÷総資本
総資本とは、自己資本と借入金や買掛金といった他人資本を足した数字です。自己資本率が高いということは、借入金に頼らず、返済の必要のないお金で経営できているということです。反対に、自己資本比率が低い場合は、融資に頼った経営を行っている可能性があります。自己資本比率の適正割合も業種によって異なりますが、40%以上あれば問題のない水準であると考えられます。
自己資本比率についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら、日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
流動比率について正しく理解しておくことは、帳簿や決算書を作成するうえでも非常に大切です。日々の帳簿付けと法人決算をスムーズに進める大きなポイントが、使い勝手の良い会計ソフトを選ぶこと。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」です。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
流動比率を活用して企業の安全性を保とう
自社の流動負債と流動資本を確認して、流動比率を算出してみましょう。短期的な支払い能力に問題がないかどうかを定期的に確認することで、支払い不能に陥るリスクを早期にキャッチし、対策をとれるようになります。
「弥生会計 Next」では、日々の取引入力を行うだけで、簡単に流動比率の計算が可能です。その他、当座比率や固定比率などの指標も自動出力させることができますので、経営状況の把握や改善にご活用ください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。