棚卸差異による影響とは?考えられる原因と対策【仕訳例あり】
更新
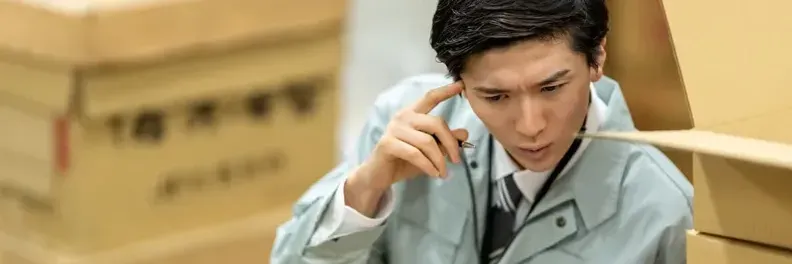
棚卸は、企業が保有するデータ上の在庫数と実在庫数が一致するかを確認する重要な作業です。決算期など各企業が定める時期に、商品の在庫がどれだけあるのかを数え、金額を計算する棚卸を行わなければなりません。ところが、どんなに気を付けていても、数に差異が生じてしまうことがあります。この差異が大きくなればなるほど経営にも影響を与える可能性が高まるため、早急に原因を究明し、対策を講じることが大切です。
本記事では、棚卸の差異がもたらす影響と考えられる原因、あらかじめ講じておきたい対策について解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
棚卸差異とは帳簿在庫と実在庫の数に誤差が生じること
棚卸とは、決算期に企業が保有する商品などの在庫数を調べ、帳簿上の数量との差異を確認する作業のことです。棚卸の実施時期や年間の実施回数は企業によって異なりますが、在庫の状態や適切な数量を把握するためにも欠かせません。
棚卸には、実際の現場で在庫数を数える「実地棚卸」と、仕入数から販売数を差し引いた帳簿上での残数を計算する「帳簿棚卸」の2つがあります。本来、実地棚卸と帳簿棚卸の数は一致していなければなりませんが、日々の在庫管理ミスなどによって数値にずれが生じます。これが棚卸差異です。
棚卸差異には、帳簿上のデータと比較して実在庫がプラスになっている「棚卸差益」と、帳簿上のデータと比較して実在庫がマイナスになっている「棚卸差損」があります。いずれのケースも企業の経営に影響を与える可能性があるため注意しましょう。
棚卸についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
棚卸差異による影響
棚卸差異が発生すると、企業にとってさまざまな問題が起こる可能性があります。ここでは、具体的にどのような影響があるのか見ていきましょう。
キャッシュ・フローが悪化する
まず考えられる影響は、キャッシュ・フローの悪化です。実在庫の数量を確認せずに帳簿上の数量だけを見て新たに商品を発注して過剰在庫となれば、コストをかけて商品を廃棄しなくてはなりません。また、帳簿上在庫があることになっていても、実際の在庫が在庫切れを起こしていることに気づけなければ、販売機会の逸失につながることも考えられます。これらの結果として企業の利益やキャッシュフローが圧迫され、資金繰りに悪影響を与えるおそれがあるのです。
作業効率が低下する
棚卸差異が出ている状態は、作業効率の低下を招く原因にもなりえます。例えば、帳簿上では在庫があるのに、実際には在庫がないといった状況が頻繁に発生すれば、商品を探すために多くの時間を費やすことになりかねません。また、棚卸差異の原因を調査するために時間を割かなければならず、本来の業務に支障をきたす可能性があります。このように、棚卸差異の発生は作業量や作業時間の増大に直結します。作業効率の低下を防ぐためにも、棚卸差異の発生を未然に防ぐことが重要です。
企業の信頼を損なう
棚卸差異は、企業としての信頼を損なうことにもつながります。在庫の実態を正確に把握できていなければ、顧客の要望に速やかに応えられない可能性があるからです。また、在庫切れの商品を誤って受注したり、在庫がある前提の納期を伝えたりすることで、顧客とのトラブルに発展するケースも考えられます。顧客からの信頼を損なわないためにも、在庫数は正確に管理すべきです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
棚卸差異が起こる原因
棚卸差異が生じる原因はさまざまですが、そのほとんどが人為的なミスによるものと言えます。主な原因として想定されるのは以下の3点です。
入力ミス・記録漏れ
棚卸差異が起こる原因として特に多いのは、システムへの入力時や伝票処理時のミス、記録漏れです。具体的には、以下のような例があります。
入力・記録ミスの例
- 仕入先が伝票の入力ミスをしてしまい、伝票と実際の納品数が異なっている
- 商品の納品から伝票到着までタイムラグがあり、伝票の処理そのものが漏れている
- 手書き伝票に記載された数字を読み間違えたまま入力している
上記のように、手作業による入力や記録はミスが起こりやすく、棚卸差異の原因になることも少なくありません。特に繁忙期など、担当者の疲労が溜まりやすい時期は集中力が低下し、ミスや漏れが増えやすいため、何らかの対策を講じる必要があります。
紛失・破損・盗難
棚卸差異が起こる原因の1つとして、商品の紛失や破損、盗難が発生していることに気づかないケースもあります。例えば、商品の保管場所が整理されていないと、どこに何があるのかが分かりにくくなり、紛失や破損のリスクが高まります。また、従業員以外が出入りできる場所や、セキュリティ対策が十分でない場所に商品を保管していると、盗難の被害が発生している可能性も否定できません。こうしたリスクを防ぐためには、商品の適切な管理方法を確立し、異常事態が発生した際に早期に察知できるよう、管理体制を整備しておく必要があります。
実地棚卸でのミス
実地棚卸の際に商品の数え漏れや二重計上が発生することもありえます。正確な実在庫数が帳簿に反映されていなければ、帳簿上の在庫数との間で整合性が失われるのは避けられません。こうした実地棚卸でのミスは、在庫の実態を正確に把握できなくなる原因になります。
また、帳簿上の在庫数が在庫管理システムなどと連動している場合、最新データが反映されるまでにタイムラグが生じているケースもあります。直近で実施した実地棚卸の結果が帳簿に反映されているかは、都度確認しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
棚卸差異が起きたときの仕訳方法
棚卸差異が生じた場合は、実在庫に合わせて帳簿を修正します。ここでは、棚卸差異が起きたときの仕訳方法について解説します。
棚卸差損の場合の仕訳例
棚卸差損が発生した場合、実在庫に合わせるために帳簿上の在庫から不足分を差し引く必要があります。このとき用いる勘定科目は「棚卸減耗損」です。例えば、帳簿上の在庫が10,000円で実在庫が5,000円だった場合、帳簿上の在庫を5,000円減らして調整するために、以下のように仕訳を行います。
仕訳例:帳簿上の在庫から5,000円を差し引く場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 棚卸減耗損 | 5,000円 | 商品 | 5,000円 |
なお、在庫の評価額は「原価×数量」で算出します。
棚卸差益の場合の仕訳例
棚卸差益が発生した場合は、帳簿上の在庫を実在庫に合わせる処理を行います。このとき用いる勘定科目は商品であれば「商品」です。例えば、帳簿上の在庫が5,000円で実在庫が10,000円の場合、帳簿上の在庫をプラス5,000円に調整するために以下のように仕訳を行います。なお、材料の場合は「商品」の代わりに「原材料」といった勘定科目を使用します。棚卸資産の種類に応じて相手となる勘定科目を決めましょう。
仕訳例:帳簿上の在庫から5,000円を加える場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 商品 | 5,000円 | 仕入 | 5,000円 |
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
棚卸誤差率(在庫差異率)の算出方法
帳簿と実在庫の差異を確認する際には、「棚卸誤差率(在庫差異率)」を算出して確認します。棚卸誤差率とは、実地棚卸の結果と帳簿上の在庫との差異を表す指標のことです。棚卸誤差率は、数量だけでなく金額やアイテム(商品の種類)数など、在庫の管理方法に応じて求め方が異なります。それぞれの計算式は以下のとおりです。
棚卸誤差率の計算方法
- 数量ベース
棚卸誤差率(%)=在庫差異があった数量(絶対値)÷棚卸後の数量×100 - 金額ベース
棚卸誤差率(%)=在庫差異があった金額(絶対値)÷棚卸後の金額×100 - アイテム数ベース
棚卸誤差率(%)=在庫差異があったアイテム数(絶対値)÷棚卸後のアイテム数×100
在庫誤差率の許容範囲は、業種や対象となる商品などによって異なりますが、10%以上に達すると企業の財務に重大な影響を及ぼす可能性があるとされています。一般的には5%以下を許容範囲とし、2~3%以下を目標としている企業が多く見られます。数量・金額・アイテム数ベースそれぞれの差異を確認したうえで、差異が大きいものについては原因を分析し、改善策を検討しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
棚卸差異を防ぐためにできる対策
棚卸差異が発生した際には帳簿を修正するだけでなく、原因を特定し、再発防止の対策を講じることが重要です。これにより棚卸精度が高まるほか、日々の商品入出庫の効率が向上する効果も期待できます。以下で、棚卸差異を防ぐためにできる対策について確認していきましょう。
業務フローの見直し、マニュアル整備
棚卸差異は、入荷・保管・出荷・棚卸・品質管理のいずれかの工程で起こります。こうしたミスを防ぐためには、まず各工程の業務フローを洗い出し、ミスが起こりやすいポイントを整理したうえで、業務の手順を見直すことが重要です。
業務フローを見直す際は、実務に携わる担当者同士で現場の実態を共有しながら改善策を検討しましょう。そのうえで、見直した手順を明文化し、マニュアルとして整備します。また、マニュアルを作成するだけでなく、内容をきちんと周知し、誰でもすぐに確認できる状態にしておくことが重要です。例えば、すぐに確認できる場所に設置するなど、現場で迷わずに作業ができる環境づくりを心掛けましょう。
在庫保管場所の整理整頓
在庫保管場所の整理整頓は、在庫を適切に管理するうえで欠かせない要素です。同一の商品を複数の場所に分けて保管していたり、保管場所が曖昧になっていたりすると、在庫の状況を把握しにくくなります。雑然とした状態で在庫が保管されていれば、商品の紛失や破損につながるほか、作業効率も低下するでしょう。また、整理整頓に改善が必要な場合は、単に「整理整頓を心がける」といった曖昧な目標を掲げるのでは対策になりません。保管棚をナンバリングして対応する商品が確実にわかる状態にしたり、商品ごとに色分けを施したりするなど、具体的なルールを定めることをおすすめします。
セキュリティ強化
棚卸差異を防ぐには、在庫保管場所のセキュリティ強化も重要なポイントです。商品の保管場所に鍵をつけるなど関係者以外が出入りできないようにしておくと、部外者による盗難などの被害を防げます。また、入退室管理や監視カメラ、ICカードキーなどのセキュリティ対策を導入することで、万が一商品の紛失や盗難が発生した際にも原因を特定しやすくなるでしょう。
定期的な棚卸の実施
棚卸差異を防ぐためには、定期的に棚卸を実施することも有効です。年に一度の棚卸では棚卸差異が大きくなりやすく、過去にさかのぼって原因を究明するのは容易ではありません。半期や四半期、月次の棚卸を行うなど、帳簿と実在庫の差異をできるだけ早く発見できるようにしておくことが大切です。
例えば、月次の棚卸を実施することで、差異が生じた場合には「どの段階まで帳簿と実在庫が合致していたのか」を特定しやすくなります。「先月末の棚卸時には棚卸差異が発生していなかった」ことが判明していれば、当月中に何らかのミスや漏れが発生したと判断できるでしょう。このように、こまめに棚卸を実施することにより、帳簿と実在庫の差異が大きくなるのを防ぐことができます。
在庫管理や棚卸の自動化
在庫管理や棚卸を自動化することも有効な対策といえます。前述のとおり、棚卸差異が発生する原因の多くは人為的なミスです。目視や手作業による工程が少なくなればなるほど、こうした人為的なミスを防ぎやすくなります。
例えば、システムを活用して伝票の作成・処理を自動化することで、入力ミスや処理漏れといったミスを防止できます。また、在庫データの管理をシステム上で一元管理するしくみを導入すれば、在庫の状況をリアルタイムで把握することができるだけでなく、棚卸差異が発生した場合もシステム上の記録を辿れるため原因を探しやすくなります。結果として在庫管理の精度が向上するほか、業務の効率化にもつながるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
棚卸差異の発生を防ぐための対策を講じよう
棚卸差異が大きくなればなるほど、経営におよぼす影響も大きくなります。そのため、早い段階で棚卸差異が発生しにくいしくみを構築しなければなりません。ここまで解説してきたとおり、棚卸差異が発生する主な原因は人為的なものです。今回紹介した棚卸差異の防止策を参考に、人為的なミスを最小限に抑えましょう。
また、在庫管理や棚卸の自動化を推進する際には、会計ソフトとの連携をおすすめします。在庫管理システムなどと会計ソフトを連携させることで、棚卸差損や棚卸差益の仕訳をよりスムーズにし、業務効率が向上する効果が期待できるからです。在庫管理方法の見直しを機に、会計ソフトの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
photo:PIXTA
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。








