源泉徴収税額表とは?見方を令和6年分で解説|甲乙の違いや賞与時の計算方法も紹介
更新
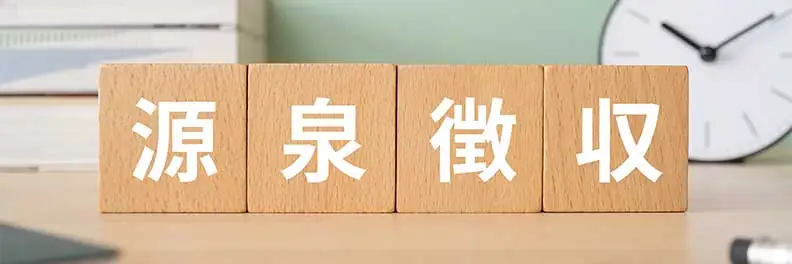
「源泉徴収税額表」とは、源泉徴収を行う際に参照する資料の1つです。本記事では、源泉徴収税額表の役割や種類、注意点、表に記載されている甲・乙・丙の違いなどを詳細に解説します。一見難しそうな源泉徴収税額表の見方や税額の計算方法が理解できるようになるため、給与計算担当の方はぜひご一読ください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
【令和6年分】源泉徴収税額表とは
「源泉徴収税額表」とは、企業が給与や賞与から差し引く従業員の所得税額を求めるために参照する資料です。給与額(その月の社会保険料等控除後の給与等の金額)や扶養親族等の数に応じた税額を網羅しているので、一目で差し引く金額がわかります。
源泉徴収税額表は毎年、国税庁が公式サイトで公表しています。令和6年分も下のURLより確認可能です。
参照:国税庁「令和6年分 源泉徴収税額表」
源泉徴収税額表の役割
企業は毎月、給与や報酬から差し引いた所得税を国に納税する源泉徴収を行います。労働者を雇用している企業には源泉徴収の義務があり、これを怠ると罰則を受ける可能性があります。
源泉徴収で差し引かれる税額は、給与額や扶養親族等の数によって異なるため、自社で行う税額の計算は煩雑で手間がかかる作業です。しかし、給与計算担当者は、源泉徴収税額表を参照することで、負担が軽減されるうえ、正確な税額を求められます。労働者の手に渡る給与は、源泉徴収による所得税や、特別徴収(給与からの天引き)による住民税などが差し引かれた金額が支給されます。
個人事業主の場合は、毎年の確定申告が必要です。企業に雇用されている労働者は、企業側が源泉徴収と年末調整を行いますが、所得が給与のみの場合は確定申告が必要ありません。企業が源泉徴収を行うことで、労働者は煩雑な作業を個人でせずに済みます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
源泉徴収税額表は3種類ある
源泉徴収税額表には3種類あり、それぞれの用途に応じて使い分けましょう。
月額表
月額表は、以下に当てはまる給与を支給する際に扱います。
-
-
1.毎月支給
-
2.毎半月、または毎旬支給
-
3.隔月・四半期・半年のいずれかに分けて支給
-
月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例
源泉徴収で差し引かれる所得税額は、原則として源泉徴収税額表を参照したうえで求めます。しかし、給与計算システムや電子計算機などを用いて処理する場合は、月額表の甲欄に当てはまるものに限り、源泉徴収税額表を参照せずに税額を求める特例が認められています。
なお、この特例は甲欄の労働者に対し支給する以下の給与が対象です。
-
-
1.支給期が毎月・毎半月・毎旬、または隔月・四半期・半年の給与
-
2.先月中に給与を受け取っていない人に支給する賞与
-
3.先月の給与額の10倍を上回る賞与
-
特例を認めてもらう場合は、給与が上の条件に当てはまるかどうか、事前に確認が必要です。
参照:国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(令和3年分以降)」
日額表
日額表は、以下に当てはまる給与を支給する際に扱います。
-
-
1.毎日支給
-
2.毎週支給
-
3.日割で支給
-
4.日雇賃金
-
- (※1~3は日雇賃金を除く)
「日雇賃金」とは、1日単位で雇用される人の勤務日数または勤務時間に基づいて計算される給与を指し、出勤するたびに支給されます。ただし、1つの勤務先から連続して、2か月を超えて給与が支給された場合、それ以降に支給される給与は含まれません。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
賞与の源泉徴収額を求める際は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照します。ただし、先月中に給与が支給されていない場合や、賞与額が先月の給与額の10倍を上回る場合は、月額表を参照しなければなりません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
源泉徴収税額表の見方【甲・乙・丙欄】
源泉徴収税額表にある税額は、雇用形態などにより、「甲」「乙」「丙」の3つに分類されています。それぞれ税額が異なるため、労働者がどの分類に属するかを把握しておくことが重要です。
| 区分 | 解説 |
|---|---|
| 甲 | 「給与所得者の扶養控除等申告書」を出している従業員に適用する区分 |
| 乙 | 「給与所得者の扶養控除等申告書」を出していない従業員に適用する区分 |
| 丙 | 日雇賃金に対して使用する区分。2カ月を超えて連続して雇用しない従業員が対象 |
企業に申告書を提出している場合も当てはまります。
注意点
甲欄の人は、乙欄の人よりも税額が低く設定されます。2か所以上から給与が支給されていても、雇用されている企業に「給与所得者の扶養控除等申告書」を差し出していなければ、乙欄に当てはまってしまうので注意が必要です。
申告書を出していないケースの中には、本来は甲欄に当てはまるにもかかわらず、申告書の出し忘れなどにより、税額が高くなっているケースもあります。労働者側が気を付けることはもちろんですが、企業側も申告書の配付漏れや回収忘れがないか必ず確認しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
【給与時】源泉徴収税額の計算方法
以下より、源泉徴収税額表のそれぞれの見方や税額の計算方法を紹介します。
月額表
まず月額表を確認する前に、交通費などの非課税支給額を除いたその月の給与総支給額から、健康保険や介護保険料などの社会保険料を控除した金額を求めておきます。
次に、月額表の左端にある「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」で、控除後の給与額に当てはまるところを探しましょう。例えば、給与額が123,800円の場合、「123,000円以上 125,000円未満」に当てはまります。
その金額の横軸と、甲または乙の縦軸が交わるところに記載されている金額が源泉徴収税額です。勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、甲欄の扶養親族等の数に応じた税額を確認します。令和6年分の源泉徴収税額表では、給与額が123,800円の場合、その数0人で源泉徴収税額が1,950円、1人で330円、それ以上になると0円です。
乙欄では給与が同額の場合、源泉徴収税額は4,800円となります。
参照:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)月額表」
日額表
まずは、非課税支給額を除いた1日の給与総支給額から、社会保険料を控除した金額を求めておきます。
そして、月額表と同様に、控除後の給与額に当てはまるところを探しましょう。例えば、1日の給与額が6,880円の場合、「6,800円以上 6,900円未満」に当てはまります。
その金額の横軸と、甲・乙・丙の縦軸が交わるところに記載されている金額が源泉徴収税額です。1日の給与額が6,880円の場合、甲欄であれば扶養親族等の数0人で源泉徴収税額は165円、1人で110円、2人で55円、3人で5円、それ以上になると0円です。
乙欄では給与が同額の場合、源泉徴収税額は750円、丙欄では0円となります。
参照:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)日額表」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
【賞与時】源泉徴収税額の計算方法
賞与時の源泉徴収税額の計算方法は、上の2つの表とは異なります。
まずは甲欄の場合、先月の給与から社会保険料等を控除した金額を求めておきます。次に扶養親族等の数の縦軸から、求めておいた金額に当てはまるところを探し、左端にある「賞与の金額に乗ずべき率」を確認します。その数字を、社会保険料等を控除した賞与額にかけた金額が源泉徴収税額です。
例えば、先月の社会保険料を控除した給与が200,000円で扶養親族等の数が2人、賞与(社会保険料を控除した後の金額)が500,000円の場合、賞与の金額に乗ずべき率は2.042%です。つまり、源泉徴収税額は500,000円に2.042%をかけた10,210円となります。
乙欄の場合、給与と賞与が同額の場合、賞与の金額に乗ずるべき率は30.630%です。つまり、源泉徴収税額は500,000円に30.630%をかけ153,150円となります。
参照:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
源泉徴収税額の計算をスムーズに行うなら給与計算ソフトがおすすめ
給与、賞与から差し引かれる所得税額は、源泉徴収税額表を参照したうえで計算が可能です。雇用形態や扶養親族等の数、給与か賞与かによって税額が変わるため、正確に求めましょう。給与計算ソフトを用いることでスムーズになるほか、記事で述べたように特例が認められる場合もあります。
弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」は、給与の自動計算や明細書のWeb配信、年末調整に向けた各種控除申告書のWeb回収、法定調書の作成など、給与に関する業務を効率化できるツールをそろえています。源泉徴収税額の計算にも活用してみてください。
- ※2024年9月時点の情報を基に執筆しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。








