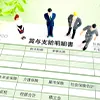賞与にかかる源泉所得税の計算方法|特殊なケースや注意点を解説
更新

従業員に賞与(ボーナス)を支給する際は、毎月の給与とは異なる税務上の取り扱いが求められます。特に源泉所得税の計算は、従業員ごとに処理が異なるため、担当者にとって悩ましい業務の1つかもしれません。
本記事では、賞与にかかる源泉所得税の計算方法を計算シミュレーション付きで解説します。「賞与が500,000円の場合、所得税と社会保険料はどうやって計算するのか」など、具体的な例や注意点を挙げながらわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
賞与(ボーナス)からは源泉所得税と社会保険料等が天引きされている
賞与(ボーナス)からは、従業員への支給時に源泉所得税と社会保険料などが天引きされます。事業主は、賞与から天引きが必要な項目や金額を理解し、正しく処理した状態で支給しなければなりません。まずは、源泉所得税や社会保険料について解説します。
源泉所得税とは?
源泉所得税とは、給与や賞与を従業員へ支給する際に、事業主が天引きして国に納付する税金のことです。このしくみを「源泉徴収」といいます。つまり、源泉所得税とは、「源泉徴収される所得税」を意味します。
なお、源泉徴収で差し引かれる税額はあくまで概算です。最終的な所得税額は、年末調整や確定申告によって確定します。最終的に確定した所得税額より源泉徴収税額が多い場合は差分が還付金として戻ってきますが、少ない場合は不足分を追加で納付します。
源泉所得税については、こちらの記事で詳しく解説しています。
社会保険料とは?
賞与や給与からは、社会保険料も天引きされています。ただし、社会保険料の天引きは「源泉徴収」ではなく「控除」といいます。控除される社会保険料の内訳は、原則として「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の4種類です。以下では、それぞれの保険料の概要を順に解説します。
健康保険料
健康保険料とは、従業員本人およびその扶養家族が病気やけがをしたときに、医療費の自己負担を軽減するために支払う保険料です。健康保険料は事業主と本人が毎月折半して負担します。健康保険には、多くの企業が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の他、企業独自や企業団体が設ける「健康保険組合」などがあり、それぞれ保険料率や給付内容が異なります。例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は都道府県によって違い、令和7年度(2025年度)納付分は、東京都が9.91%、大阪府は10.24%です。
- 参照:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
介護保険料
介護保険料とは、介護が必要になった人に介護サービスを提供するための費用として納付する保険料です。介護保険料も、従業員本人と事業主で折半します。全国健康保険協会(協会けんぽ)における令和7年度(2025年度)の保険料率は、全国一律で1.59%です。なお、対象となるのは、40歳以上65歳未満の健康保険加入者です。
- 参照:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
介護保険料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、老後の生活に備えて支払う保険料です。厚生年金保険料を支払うことで、65歳以後には国民年金(基礎年金)に上乗せする形で老齢厚生年金が支給されます。また、病気やけがなどで一定の障害を負ったときには障害年金が支給されるなど、万が一の際のセーフティーネットとしての役割もあります。対象となるのは、原則として70歳未満の会社員および公務員です。保険料率は18.3%の固定で、従業員本人と事業主で折半して負担します。
雇用保険料
雇用保険料とは、失業や育児休業の取得などで一時的に働けなくなったときの収入減に備えるほか、雇用保険被保険者へリスキングである教育訓練の機会を設ける保険料として使われます。保険料率は従業員本人と事業主で異なり、令和7年度(2025年度)は従業員負担が0.55%、事業主負担が0.9%となっています。ただし、農業や林業、建設業といった一部の業種については、一般の業種とは保険料率が異なるため、注意が必要です。
- 参照:厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
【ケース別】賞与・ボーナスから天引きされる源泉所得税の計算方法
賞与に対する源泉所得税の計算方法は、従業員が扶養している親族の人数や賞与の支給タイミングなどによって異なります。特に、前月に給与の支給がないケースや、賞与額が前月給与の10倍を超えるようなケースには、通常とは異なる取り扱いが必要です。
ここでは、基本的なケースから特殊なケースまで、賞与から天引きされる所得税の計算式とシミュレーションを詳しく解説します。
1. 基本的な計算方法
まずは、前月の給与が支給済みで、賞与額も特別高額でない基本的なケースをチェックしておきましょう。この場合、源泉所得税は以下のような計算式で賞与から天引きされます。
計算式
賞与から天引きされる源泉所得税の額は、次の計算式で算出できます。
源泉所得税=(賞与の支給額-社会保険料の額)×源泉徴収税率
計算式内の「社会保険料の額」とは、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の合計額です。源泉徴収税率は、賞与支給月の前月における社会保険料控除後の給与額と、その従業員が扶養している親族の人数によって決まります。具体的な税率については、国税庁のサイトで公開されている源泉徴収税額表の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で確認できます。
- 参照:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和7年分)」
以下では、具体的な例をご紹介します。
シミュレーション
-
- 前月の給与総支給額:300,000円
- 前月の社会保険料総額:60,000円
- 扶養人数:2名
この例の場合、計算の基準となる所得は、300,000円から社会保険料総額の60,000円を控除した240,000円です。算出された基準額と扶養人数とを、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめると、税率が2.042%であることがわかります。この例では「甲」欄を使用しましたが、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合には「乙」欄を使用してください。
下表は源泉徴収税額の算出率です(一部抜粋)。
| 所得税率 | 扶養親族等の数 | ||
|---|---|---|---|
| 0人 | 1人 | 2人 | |
| 0.000% | 68,000円未満 | 94,000円未満 | 133,000円未満 |
| 2.042% | 68,000円以上 79,000円未満 |
94,000円以上 243,000円未満 |
133,000円以上 269,000円未満 |
| 4.084% | 79,000円以上 252,000円未満 |
243,000円以上 282,000円未満 |
269,000円以上 312,000円未満 |
| 6.126% | 252,000円以上 300,000円未満 |
282,000円以上 338,000円未満 |
312,000円以上 369,000円未満 |
| 8.168% | 300,000円以上 334,000円未満 |
338,000円以上 365,000円未満 |
369,000円以上 393,000円未満 |
| 10.210% | 334,000円以上 363,000円未満 |
365,000円以上 394,000円未満 |
393,000円以上 420,000円未満 |
表の詳細については、以下の国税庁のサイトで確認できます。
参照:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和7年分)」
2. 前月の給与がない場合の計算方法
賞与支給月の前月に給与の支払いがない場合には、源泉所得税の計算方法が通常とは異なるため、注意が必要です。詳しくみていきましょう。
計算方法
前月に給与が支給されていない場合は、まず以下の計算式によって、賞与にかかる所得税の計算に必要な金額(その月の社会保険料等控除後の給与などの額)を算出します。
その月の社会保険料等控除後の給与などの額=(賞与総支給額-賞与から天引きされる社会保険料)÷賞与の計算期間
賞与の計算期間には、賞与が半年ごとに支給される場合は6を、半年を超える場合は12を代入してください。次に国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使って、先ほど算出した金額と扶養人数を当てはめ、該当する税額を確認します。ここに記載されている税額は1か月分です。半年ごとに賞与が支給される場合は6を、また半年を超えて支給される場合には12を掛けて、賞与に対する所得税額を算出します。
- 参照:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)」
具体的なシミュレーション例は、次のとおりです。
シミュレーション
- ※給与所得者の扶養控除等申告書の提出がある場合
-
- 賞与は半年ごとに支給
- 賞与総支給額:800,000円
- 賞与から天引きする社会保険料:160,000円
- 扶養人数:0人
この場合、1か月分の社会保険料等控除後の給与などの金額は以下のようになります。
(800,000円-160,000円)÷6=106,666円(小数点以下切り捨て)
この金額および扶養人数を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と照合すると、1か月の税額は1,030円です。半年ごとに賞与が支給されるので、賞与から源泉徴収する所得税額は1,030円×6=6,180円となります。
3. 賞与が前月の給与の10倍超の場合の計算方法
前月の給与の金額が少なく、賞与が給与の10倍を超えてしまうようなケースは特例扱いとなり、通常とは計算方法が変わってきます。この場合の計算方法は以下のとおりです。
計算方法
まずは、以下の計算式で、この後の計算に必要な金額(その月の社会保険料等控除後の給与などの金額)を算出します。
その月の社会保険料等控除後の給与などの金額=(賞与総支給額-賞与にかかる社会保険料)÷賞与の計算期間+(前月の給与-前月の社会保険料)
次に「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で、算出した金額と扶養人数とに該当する税額を確認しましょう。税額がわかったら、「税額-前月の給与から源泉徴収された金額」で1か月分の税額を算出して、賞与が半年ごとに支給される場合は6を、半年を超えて支給される場合は12を掛けて計算してください。
具体的なシミュレーション例は次のとおりです。
シミュレーション
- ※扶養控除等申告書の提出がある場合
-
- 賞与は半年ごとに支給
- 賞与:1,000,000円
- 賞与にかかる社会保険料の総額:190,000円
- 前月の給与:90,000円
- 前月の給与にかかる社会保険料:18,000円
- 扶養家族:0名
この例では、その月の社会保険料等控除後の給与などの金額は、以下の形になります。
(1,000,000円-190,000円)÷6+(90,000円-18,000円)=207,000円
この金額および扶養人数(0人)を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と照合すると、税額は5,050円であることがわかります。
次に前月の給与90,000円に対する所得税額を同じく「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で確認しましょう。これに対応する税額は230円です。
さらに、この2つの税額を「税額-前月の給与から源泉徴収された金額」に代入すると、「5,050円-230円=4,820円」で1か月分の所得税額が算出されます。
このシミュレーション例での賞与は6か月分と仮定しているため、賞与から天引きされる最終的な税額は「4,820円×6=28,920円」となります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
賞与から天引きされる社会保険料の計算方法
賞与からは社会保険料も天引きされるため、その算出方法も把握しておく必要があります。賞与から天引き(控除)される社会保険料は原則として、既にご紹介した以下の4種類です。
-
- 健康保険料
- 介護保険料(対象者のみ)
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
このうち、介護保険料に関しては、「40歳以上65歳未満」の従業員が対象になります。賞与から控除される社会保険料の種類を簡単に示すと、以下のとおりです。
-
- 40歳~64歳の場合:健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料
- それ以外の場合:健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料
健康保険料および介護保険料、厚生年金保険料は、以下の計算式で算出します。
厚生年金保険料=標準賞与額×各保険料率×1/2
ここでの「1/2」は、これらの保険料が事業主と従業員で折半されることを意味します。また、標準賞与額とは、源泉所得税を差し引く前の賞与から1,000円未満を切り捨てた賞与額のことです。標準賞与額は、健康保険と介護保険の場合は年間5,730,000円、厚生年金保険の場合は1回の支給につき1,500,000円の上限があり、この金額を超過した分については保険料の対象になりません。
雇用保険に関しては、「賞与総支給額×雇用保険料率」で算出します。雇用保険は労使それぞれで保険料率が異なるのでご注意ください。
以下の一覧表は、賞与に対して控除される社会保険料とその計算方法をまとめたものです。
| 保険料区分 | 計算式 | 主な条件・注意点 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 標準賞与額×健康保険料率×1/2 | ・標準賞与額の年間累計額上限は573万円 |
| ・50銭未満切捨て、51銭以上切上げ | ||
| 介護保険料 | 標準賞与額×介護保険料率×1/2 | ・対象は40歳以上65歳未満の従業員のみ |
| ・標準賞与額の年間累計額上限は573万円 | ||
| ・50銭未満切捨て、51銭以上切上げ | ||
| 厚生年金保険料 | 標準賞与額×厚生年金保険料率×1/2 | ・1回あたりの標準賞与額の上限は150万円 |
| ・50銭未満切捨て、51銭以上切上げ | ||
| 雇用保険料 | 賞与総支給額×雇用保険料率 | ・保険料率は事業の種類により異なる |
| ・50銭未満切捨て、51銭以上切上げ |
賞与から天引きされる社会保険料については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
【支給額別】賞与の手取り額をシミュレーション
賞与から天引きされる具体的な額を知り、従業員に賞与を正しく支給するには、源泉所得税と社会保険料の計算方法を把握することが大切です。以下では、令和7年度(2025年度)における賞与の手取り額のシミュレーション例を紹介します。
- シミュレーションの前提条件
-
- 勤務先:東京都の企業
- 年齢:41歳(介護保険の対象者)
- 前月の社会保険料控除後の給与額:350,000円
- 扶養人数:1人
- 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している(税区分で甲欄を使用)
賞与が50万円の場合
▼所得税
- 所得税:34,530円
▼社会保険料:合計77,250円
- 健康保険料:24,775円
- 介護保険料:3,975円
- 厚生年金保険料:45,750円
- 雇用保険料:2,750円
▼手取り計算
- 500,000円−34,530円(所得税)− 77,250円(社会保険料)= 388,220円
▼賞与の手取り額
- 388,220円
- ※各項目の計算式(保険料率は2025年度のもの)
-
- 所得税:(500,000-77,250)×8.168%
- 健康保険料:500,000×9.91%×1/2
- 介護保険料:500,000×1.59%×1/2
- 厚生年金保険料:500,000×18.3%×1/2
- 雇用保険料:500,000×0.55%
賞与が80万円の場合
▼所得税
- 所得税:55,248円
▼社会保険料:合計123,600円
- 健康保険料:39,640円
- 介護保険料:6,360円
- 厚生年金保険料:73,200円
- 雇用保険料:4,400円
▼手取り計算
- 800,000円–55,248円(所得税)−123,600円(社会保険料) = 621,152円
▼賞与の手取り額
- 621,152円
- ※各項目の計算式(保険料率は2025年度のもの)
-
- 所得税:(800,000-123,600)×8.168%
- 健康保険料:800,000×9.91%×1/2
- 介護保険料:800,000×1.59%×1/2
- 厚生年金保険料:800,000×18.3%×1/2
- 雇用保険料:800,000×0.55%
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
賞与計算時の注意点
賞与の支給にあたっては、税金や社会保険料の計算だけでなく、制度上の取り扱いや届出の手続きについても注意が必要です。特に注意を要するポイントを解説します。
賞与の支給が年4回以上の場合は社会保険料の手続きが異なる
社会保険料の算定に用いられる「標準賞与額」は、原則として支給回数が年に3回までの賞与に適用されます。賞与を年に4回以上支給する場合は、賞与ではなく定期的な報酬とみなされ、通常の給与と同様に「標準報酬月額」を基に保険料が計算されます。
なお、お祝い金や特別手当などの一時金も賞与とみなされることがあるためご注意ください。
退職予定者の賞与計算は保険料控除に注意する
退職間際の従業員に対して賞与を支給する場合は、社会保険料の徴収時期と資格喪失日の関係に注意しなければなりません。健康保険・介護保険・厚生年金保険の場合、被保険者の資格喪失日は退職日翌日となります。
例えば7月31日に退職した場合、資格喪失日は8月1日です。そして、これらの保険は、資格喪失の前月までに支給された賞与分を控除対象とします。したがって、例えば退職日が月末の場合、その月内に支給された賞与については社会保険料が天引きされことになります。そのため、「退職によって被保険者でなくなったので、賞与からは社会保険料が天引きされない」と従業員が考えていたのに、実際にはそうではなかったという事態が起こりえます。
なお、雇用保険料については資格喪失の時期にかかわらず、賞与が支給されるたびに徴収対象となります。
賞与支払届を提出する
賞与を支給した際には、原則として支給日から5日以内に「賞与支払届」を日本年金機構へ提出する必要があります。これは、標準賞与額を確定させ、社会保険料を正しく納付するための手続きです。なお、予定していた賞与を実際には支給しなかった場合は、「賞与支払届」の代わりに「賞与不支給報告書」を提出しなければなりません。
賞与支払届については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
賞与計算でよくある質問
賞与計算に関してよくある質問にお答えします。
賞与の支給額が同じでも所得税が違うのはなぜですか?
賞与から天引きされる所得税は、前月の給与額と扶養親族の人数に応じて決まる税率に基づいて計算されます。そのため、賞与額が同じでも、従業員ごとに所得税の金額に違いが出ることがあります。
賞与支払月に40歳に到達した場合は?
従業員が賞与支払月に40歳の誕生日を迎える場合、その月の賞与から介護保険料が控除されます。介護保険料の対象となるのは、40歳以上65歳未満の健康保険加入者です。誕生日の前日が含まれる月から介護保険料の徴収がスタートするため、誕生月に支給される賞与にも保険料がかかります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
賞与の所得税を正しく求めよう
従業員に正しく賞与を支給するためには、企業は源泉徴収する所得税の税率や社会保険料のしくみ、各項目の計算方法などを正しく理解し、的確に処理をしなければなりません。賞与は金額が大きいため、少しの計算ミスが従業員に大きな不利益をもたらす可能性があります。
賞与の源泉所得税額を正しく計算するためには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は、給与計算業務に必要な機能を網羅し、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しています(ご契約のプランによって利用できる機能は異なります)。ぜひ導入をご検討ください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。