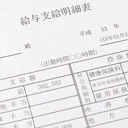住民税決定通知書の概要や見方を解説!再発行できる?どこでもらえる?
更新
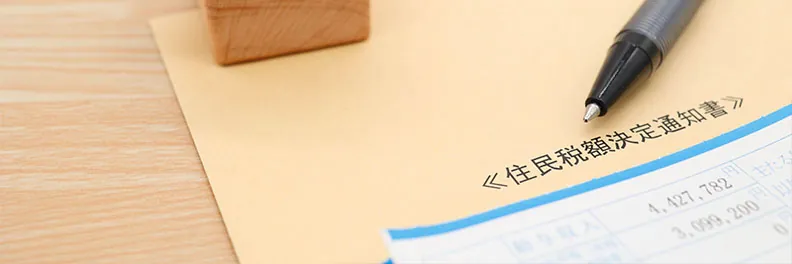
住民税決定通知書は、住民税の金額やその内訳が書かれた重要な書類です。本記事では、知っておきたい基本的な知識から、各項目の詳細な見方までをわかりやすく解説します。また、「再発行はできるのか?」「通知書はどこで手に入るのか?」などの疑問にもお答えします。住民税に関する理解を深めれば、給与計算業務がよりスムーズになるでしょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
そもそも住民税とは
住民税とは、一定以上の所得がある人に課せられる地方税で、地方自治体が運営する公共サービスの財源となる税金です。「道府県民税(東京都では都民税)」「市町村民税(区市町村民税)」を合わせたものを指します。課税主体(課税する側)は、住んでいる地域の都道府県や市町村です。
住民税額は、「所得割」と「均等割」の2つから構成されています。
-
- 所得割:前年の所得に応じて課税されるしくみ。税率は一律10%と定められている。所得が多いほど納める税額も増えるしくみである
- 均等割:同じ自治体に住む住民が一律で負担する金額で、所得に関係なく均等に課される
上記のように、住民税は「所得に応じた負担」と「均等な負担」を組み合わせており、地域の財源としての公平性が重視されています。
納税方法は、「特別徴収」もしくは「普通徴収」です。
-
- 特別徴収:会社員や公務員など、給与所得がある人が対象。毎月の給与から住民税が天引きされ、会社が自治体に代わって納税手続きを行う
- 普通徴収:個人事業主や無職の方などが対象。自治体から送られてくる納付書を使って銀行やコンビニ、オンラインで納税する
住民税は健全な地域社会を維持するための重要な税金で、私たちの生活と深く関わっています。基本的なしくみを理解しておくと、普段の生活や業務などで役立つ場面も多いでしょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税決定通知書とは
住民税決定通知書とは、住民税の金額と、その算出基準となった所得や控除の金額を明示した書類です。納めるべき住民税の金額や、その内訳を納税者に確認してもらうために発行されます。
通知書の正しい名称は、給与所得者とそれ以外の納税者で異なります。
-
- 給与所得者:市民税・県民税特別徴収税額決定通知書
- 個人事業主や給与所得以外の収入がある人:市民税・県民税税額決定通知書
どちらも住民税に関する詳細情報を含む点では同じですが、納税方法や対象者の違いに応じて名称が異なるため注意が必要です。なお後者には納付書が同封されており、一括もしくは4回分割で支払いができます。
住民税決定通知書は、その年の1月1日時点で住んでいた自治体から発行されます。一年の途中で引っ越しをした場合でも、「1月1日に住んでいた自治体がその年の住民税を課税する責任を持つ」しくみです。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税決定通知書はいつ届く?
住民税決定通知書は、特別徴収の場合は毎年5月末までに従業員が居住する自治体から事業主へ送付され、普通徴収の場合は毎年6月頃に納税義務者へ発送されるのが一般的です。ただし、具体的な送付時期や方法は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の公式情報を確認する必要があります。
普通徴収に該当する場合、基本的には納付書と一緒に、納税者の自宅宛に直接送付されます。通知書が届いたら記載内容を確認し、自治体が指定した期限までに銀行やコンビニ、オンライン決済などで住民税を納めるのが基本的な流れです。
特別徴収の場合は、納税者の勤務先を通じて配布されます。普通徴収とは異なり、会社が給与から住民税を天引きし、本人に代わって納付を行うしくみです。納税者本人が直接手続きをする必要はありませんが、受領した場合は記載内容をよく確認しておきましょう。
6月末までに届かない場合は、住んでいる自治体の税務課や窓口に問い合わせ、確認することをおすすめします。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税決定通知書はいつ使う?
住民税決定通知書は、住民税の金額やその内訳を確認するだけでなく、さまざまな場面で必要となる重要な書類です。以下、住民税決定通知書が必要な主なシーンを紹介します。
住宅ローン借り入れ手続き
住民税決定通知書には、前年の所得や税額が記載されています。そのため、借り手の返済能力を確認するための審査資料として機能します。
ただし、すべてのケースで住民税決定通知書が必要なわけではありません。一部の金融機関では、源泉徴収票や確定申告書など、他の所得証明書類を提出することで手続きを進められる場合があります。事前に金融機関に必要書類を確認し、住民税決定通知書が必要かどうかを確認しておくとスムーズに手続きを進められます。
ふるさと納税控除額の確認
ふるさと納税を利用した場合、住民税決定通知書を確認することで、寄附金控除が正しく適用されているかどうかを確認できます。
ふるさと納税をした場合の控除申請方法は、主に「ワンストップ特例の利用」「確定申告」の2種類です。
ワンストップ特例制度を利用した場合、寄付金額から自己負担額の2,000円を差し引いた金額が、住民税から直接控除されます。内容はそのまま通知書に反映されるため、通知書を確認することで、正しく控除されているかどうかを確認できます。
確定申告の場合、控除は住民税と所得税の両方に分けて適用されるのが原則です。通知書に住民税から控除された金額が書かれている一方で、確定申告書には所得税に関する情報が載っていますので、それぞれチェックして計算に間違いがないかを見てください。具体的には、以下の計算式で求められます。
・所得税からの控除額
(寄付金額 - 2,000円)× 所得税の税率
・住民税からの控除額
基本分:(寄付金額 - 2,000円)× 10%
特例分:(寄付金額 - 2,000円)×(90% - 所得税の税率)
これらを合計すると、
(寄付金額 - 2,000円)= 所得税控除額 + 住民税控除額(基本分+特例分)
となり、自己負担額2,000円を除いた全額が控除対象となります。ただし、控除額には上限があり、年収や家族構成などによって異なります。詳細な計算方法や上限額については、総務省の公式サイトをご参照ください。税額控除の内容は、自治体によって特別徴収税額の決定通知書に示されている場合も、示されていない場合もあります。
参照:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税決定通知書が届かない・手元にない場合
住民税決定通知書が届かない・手元にない場合は、市区町村の税務課や住民税を担当する部署に確認しましょう。引っ越しなどしても、住所変更をしていない場合や、勤務先の手続きに問題がある場合、通知書が届かない可能性があります。
特別徴収の場合は、勤務先に確認しましょう。特別徴収であれば、通知書は勤務先を通じて手元に届きます。勤務先が渡し忘れている可能性もあるため、会社の人事部や総務部に確認してください。
紛失した場合、通知書自体の再発行はできません。届いた時点で内容を確認し、大切に保管しましょう。万が一紛失してしまい、今すぐに必要な場合は、市区町村役場で発行してもらえる「住民税課税証明書」を発行してもらい、代用してください。発行手数料は300円ですが、自治体によって若干異なります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税決定通知書を紛失した場合には課税証明書を取得して代用する
住民税決定通知書を紛失した場合、「住民税課税証明書」を取得することで代用できます。住民税決定通知書と同様に、課税額や所得情報が記載されているためです。以下の手順で発行できます。
| 発行方法 | 手順 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 市区町村役場 | 1. 市区町村役場へ行く 2. 窓口で「住民税課税証明書の発行を希望」と伝える 3. 必要書類(備え付けの交付請求書)を提出し、手数料を支払う |
・本人確認書類 ・交付請求書 ・代理人の場合は委任状 |
| オンライン申請 | 1. 自治体などの申請システムにログイン 2. 必要情報を入力して申請を完了 3. 手数料をオンラインで支払う(クレジットカードなど) |
・マイナンバーカード ・インターネット環境 ・クレジットカードなど |
発行手数料は、自治体によって若干の差はありますが、1通当たり300円前後です。
窓口申請の場合は即日発行が可能です。オンライン申請の場合は、申請自体はすぐに終わりますが、証明書が郵送されるのを待つ必要があります。数日〜1週間程度かかるため、なるべく早めに申請するのがおすすめです。
住民税課税証明書と住民税決定通知書の違いは、以下の表のとおりです。
| 項目 | 住民税決定通知書 | 住民税課税証明書 |
|---|---|---|
| 発行元 | 自治体が自動的に発行し送付 | 自治体に申請して発行 |
| 内容 | 課税額、控除額、所得情報など | 住民税決定通知書と同様の情報 |
| 用途 | 納税確認、控除確認、ローン審査など | 紛失時の代用、所得証明、控除確認など |
| 発行の手間 | 手続き不要 | 窓口やオンラインで申請 |
両者の違いをよく整理しておきましょう。
再発行はできる?
住民税決定通知書は、基本的に再発行ができません。前述のように、課税証明書を取得して代用しましょう。
住民税決定通知書の紛失に備え、通知書を受け取った際にそのままコピーを取ることが重要です。また、デジタル形式での保存をして、安全なクラウドサービスやデバイスに保管する方法もあります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税決定通知書の見方
以下では、住民税決定通知書の主な項目や内容の見方について解説します。
「所得」内の項目
住民税決定通知書の「所得欄」には、前年の所得状況を基に、住民税額が計算される際の基本情報を示しています。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 給与収入 | 会社や事業所などから支払われた給与の総額(源泉徴収票の「支払金額」) |
| 給与所得 | 給与収入から所定の給与所得控除を差し引いた後の金額 |
| その他の所得計 | 給与以外の所得 |
| 主たる給与 | 住民税の計算上、主な収入源とされる給与(複数の給与収入がある場合) |
| 所得区分 | 所得を分類した項目で、以下のように分かれている |
| – 事業所得 | 個人事業やフリーランスで得た所得 |
| – 農業所得 | 農業活動による所得 |
| – 不動産所得 | 不動産の賃貸収入などから経費を引いた後の所得 |
| – 配当所得 | 株式や投資信託などから受け取る配当金 |
| – 給与所得 | 給与収入に基づく所得 |
| – 雑所得 | 上記に該当しないその他の所得(年金など) |
給与収入と給与所得の金額は、源泉徴収票の支払金額と給与所得控除後の金額で確認できます。
「所得控除」内の項目
住民税決定通知書の「所得控除欄」には、前年の所得から差し引かれた各種控除の内容と金額が記載されています。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 雑損 | 災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に適用される控除 |
| 医療費 | 1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される控除 |
| 社会保険料 | 健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険などに支払った保険料が対象となる控除 |
| 小規模企業共済 | 小規模企業共済や確定拠出年金(iDeCo)などへの掛金が対象となる控除 |
| 生命保険料 | 生命保険や介護医療保険、個人年金保険などに支払った保険料が対象となる控除 |
| 地震保険料 | 地震保険に加入している場合、その保険料が対象となる控除 |
| 障・寡・勤 | 障害者控除、寡婦控除など特定の場合の控除 |
| 配偶者 | 納税者の配偶者の所得が一定以下の場合に適用される控除 |
| 配偶者特別 | 配偶者の所得が一定額を超えた場合でも適用される特例の控除 |
| 扶養 | 扶養親族がいる場合に適用される控除 |
| 基礎 | すべての納税者に適用される控除 |
「課税標準」内の項目
「課税標準」欄は、住民税を計算する際の課税対象となる所得を示しています。総所得③に以下の表の所得を加算した金額が、住民税の課税対象です。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 総所得③ | 総所得金額から所得控除を差し引いた後の課税対象となる金額 |
| 山林所得 | 山林を売却した際に得た所得 |
| 分離短期譲渡 | 保有期間が5年以下の土地や建物を譲渡した際に得た所得 |
| 分離長期譲渡 | 保有期間が5年を超える土地や建物を譲渡した際に得た所得 |
| 株式等の譲渡 | 株式や投資信託を売却した際に得た所得 |
| 上場株式等の配当 | 上場株式や投資信託などから得た配当金 |
| 先物取引 | 商品先物や金融先物取引で得た所得(差益) |
「税額」内の項目
「税額」欄には、住民税の内訳や計算結果が記載されています。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 税額控除前所得割額④ | 所得控除前の課税標準額に基づき計算された税額 |
| 税額控除額⑤ | 所得税額の控除や住宅借入金等特別控除など、適用される控除額 |
| 所得割額⑥ | 税額控除後の所得割額 |
| 均等割額⑦ | 所得に関係なく一律で課される税額 |
| 特別徴収税額⑧ | 給与天引き(特別徴収)で納付する住民税の金額 |
| 控除不足額⑨ | 特別徴収や予定納税で不足している場合に記載される金額 |
| 既充当額⑩ | 過去に納付した住民税が、既に現在の納税義務に充当されている金額 |
| 既納付額⑪ | 既に納付済みの金額 |
| 差引納付額(⑧-⑪-⑨、⑩) | 実際に納付すべき金額 |
| 変更前税額⑫ | 修正前の税額(修正がある場合のみ) |
| 増減額(⑧-⑫) | 税額の修正や変更があった場合の差額 |
上記のうち、「差引納付額」が、1年かけて納める住民税の金額です。住民税は10%ですが、その内訳は、市町村民税(特別区民税)6%と道府県民税(都民税)4%となります。
「納付」内の項目
「納付」欄には、給与天引き(特別徴収)で毎月納める住民税の金額が記載されています。金額は、年間の住民税額(差引納付額)を12で割った金額です。もし差額が発生した場合は、6月分の徴収で調整されます。
「摘要」内の項目
「摘要」欄は、住民税・所得税に関する控除内容や、特例の適用状況が記載される欄です。主に、ふるさと納税のワンストップ特例の利用や、確定申告のケースで使用されます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
住民税決定通知書の記載内容を確認しよう
住民税決定通知書には、所得額や控除額、課税標準、税額、納付額など住民税を計算する際に必要な情報が記載されています。内容をよく確認することで、課税内容を理解できるだけでなく、トラブルの防止にもつながります。不明点や疑問点がある場合は、市区町村や税理士に早めに相談しましょう。
複雑になりがちな給与計算業務を効率化するには、弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」が便利です。給与支給額を自動計算できるため、手間を大幅に削減するだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。さらに、税金や保険料率の変更にも自動で対応するため、毎回最新の料率や法令を確認する必要がありません。この機会に、導入をぜひご検討ください。
- ※2024年12月時点の情報を基に制作しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。