国民健康保険と社会保険(健康保険)の違いを解説!保障内容や扶養有無は?
更新
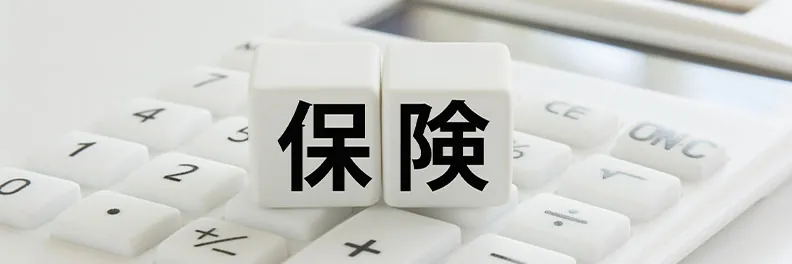
日本には「国民健康保険」と「社会保険(健康保険)」という2つの主要な健康保険制度があり、これらは私たちの生活を支える大切な基盤です。しかし、国民健康保険と社会保険について、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。
2つの保険制度は、それぞれ保障内容や加入条件が異なり、働き方やライフスタイルによって加入する保険が変わります。扶養制度の有無や保険料の計算方法など、正しく理解することが大切です。本記事では、国民健康保険と社会保険の特徴や具体的な違いについて詳しく解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
社会保険とは
社会保険とは、病気やけが、老後の生活、失業といった予測が難しいリスクに備える、公的な強制保険制度です。会社に勤める正規社員や一定の条件を満たした非正規社員に対して、加入が義務付けられています。
この制度は、生活の安定を支え、病気や失業といった場合にも経済的な負担を軽減するしくみです。社会保険には、「健康保険」「雇用保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」の5種類がありますが、狭義にはそのうちの「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つを指す場合もあります。
これらの保険は対象となるリスクごとに異なる目的を持ち、各分野で生活を支える、社会的なセーフティネットです。
社会保険についてこちらの記事で解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
国民健康保険とは
国民健康保険は、社会保険(健康保険)やその他の医療保険に加入していない人を対象とした保険制度です。住民票がある市区町村が原則として保険者(運営主体)となり、地域の住民が必要な医療を受けられる支援をしています。
自営業者やフリーランス、日雇い労働者、無職の人などが主な対象者です。一部には「国民健康保険組合」(例:土建国保)という健康保険組合も存在しますが、本記事では自治体が保険者となる国民健康保険について解説します。
国民健康保険の大きな特徴は、「扶養」という概念がない点です。扶養家族もそれぞれが個別に国民健康保険へ加入し、世帯主が保険料をまとめて支払う必要があります。保険料は所得に応じて決定されるため、高所得者ほど多くの負担を求められます。
この制度は、市区町村全体で医療費を支えるしくみが成り立っており、所得が低い世帯に対しては減免措置が設けられるなど、経済的負担に配慮した設計がなされています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
社会保険と国民健康保険の違い
社会保険と国民健康保険は、その保障内容や加入対象者、保険者の違いなど、さまざまな点で異なります。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 社会保険 | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 保険者 | 全国健康保険協会、健康保険組合 | 市区町村、国民健康保険組合 |
| 加入対象者 | 主に会社員 | 自営業者、無職者など |
| 保険料負担 | 事業主と被保険者で分担 | 被保険者が全額負担 |
| 給付内容 | 労災以外のけがや病気など | けがや病気など |
| その他条件 | 出産手当金、傷病手当金あり | 左記の給付はなし |
保障内容
社会保険と国民健康保険では、保障内容に大きな違いがあります。社会保険の場合、出産手当金や傷病手当金といった生活を支える給付金が用意されます。
これらは、妊娠・出産や病気・けがで働けなくなった場合に支給されるもので、一定の条件を満たせば受け取ることが可能です。
その一方で、国民健康保険にはこれらに該当する給付制度がありません。そのため、国民健康保険の加入者が同様の状況に直面した場合、他の手段で収入を補填する必要があります。ただし、一部の国民健康保険組合では独自に給付制度を設けている場合があります。
保険者
保険者とは、保険制度を運営する母体を指し、加入者から保険料を徴収し、保険事故が発生した際に給付金を支払う責任を負う組織です。
保険者は各保険制度によって異なり、運営方針や対象者、保険料の設定なども異なるため、事前に理解しておきましょう。
社会保険の場合
社会保険の保険者には、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「健康保険組合」「共済組合」の3つがあります。それぞれの保険者には異なる特徴があり、対象者や運営方法も異なります。
- ・全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 協会けんぽは、中小企業の従業員を主な対象として運営されています。全国規模で統一された基準に基づき運営されており、多くの中小企業がこの制度に加入しているのが特徴です。
保険料率は都道府県ごとに異なり、地域経済や医療費の実態に応じて設定されています。加入者が多いことから、制度の運営は安定している一方で、個別のサービス提供には限りがあるのがデメリットです。 - ・健康保険組合
- 健康保険組合は、主に大企業や特定の業界団体が設立して運営しています。協会けんぽと異なり、企業や業界の事情に応じた独自の運営方針を持てるため、保険料率や給付内容に柔軟性があります。
例えば、一部の健康保険組合では、加入者向けに特別な健康増進プログラムや福利厚生サービスを提供している場合があります。このようなサービスが充実している点が、健康保険組合のメリットです。 - ・共済組合
- 共済組合は、公務員や教職員、特殊法人の職員を対象に運営されています。公務員特有の働き方や給与体系を反映した制度設計で、安定した運営基盤が特徴です。
共済組合は医療保険だけでなく、退職後の年金や災害補償なども一体的に取り扱うケースが多く、包括的な保障が受けられるしくみとなります。
国民健康保険の場合
国民健康保険は、主に市区町村が保険者となり、地域ごとの実情に応じた保険制度を運営しています。保険料率や給付内容は自治体ごとに異なり、医療費の実態や住民の所得水準などが考慮されています。また、特定の業種や職業団体向けには「国民健康保険組合」が運営するケースもあります。例えば、建設業向けの「土建国保」や、文芸美術関係者向けの「文美国保」などがあり、業界の特性に応じた給付制度やサービスを提供しています。
加入対象者
加入対象者とは、特定の保険制度に加入する資格を持つ人のことです。社会保険や国民健康保険には、制度ごとに異なる加入条件が設定されています。これらの条件は、保険料負担や給付内容に直結するため、自身がどちらの制度に該当するかを正しく理解することが重要です。
以下では、社会保険と国民健康保険の加入対象者について具体的に解説します。
社会保険の場合
社会保険(健康保険)の加入対象者は、適用事業所で働く労働者です。適用事業所とは、社会保険に加入する義務がある事業所を指し、従業員数や業種にかかわらず、一定の基準を満たす事業所です。適用事業所で働く労働者で、以下の条件を満たす場合は社会保険に加入する必要があります。
ただし、社会保険の加入条件は、事業所の種類(一般の適用事業所と特定適用事業所)によって異なります。
一般の適用事業所
一般の適用事業所とは、以下の要件を満たす事業所です。
- 従業員が常時5人以上の個人事業所(ただし、農林水産業やサービス業の一部は除外)
- 法人事業所(株式会社、合同会社など)は、従業員数に関係なく強制適用
上記の事業所では、原則として正社員は社会保険に加入します。さらに一定の条件を満たすパート・アルバイトも対象となります。一般の適用事業所では、パート・アルバイトは以下のすべてを満たす場合、社会保険の加入義務が発生します。
- 正社員の所定労働時間の4分の3以上および正社員の所定勤務日数の4分の3以上
特定適用事業所
特定適用事業所とは、社会保険の適用拡大が義務付けられた事業所で、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業が該当します(2024年10月から適用範囲が拡大)。特定適用事業所では、一般の適用事業所とは異なり、パート・アルバイトは、以下のすべてを満たす場合、社会保険の加入義務が発生します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(基本給+諸手当)
- 雇用期間が2か月以上(契約更新の可能性があれば対象)
- 学生ではない(夜間・通信制の学生は加入対象)
2024年10月の法改正により、従業員(厚生年金保険の被保険者)51名以上の事業所では、パートタイム労働者やアルバイトも条件を満たせば、社会保険に加入する義務が生じました。これらの条件を満たす場合、企業側と労働者が折半して社会保険料を支払い、健康保険や厚生年金保険の保障を受けることができます。非正規雇用の増加により、パートタイム労働者や契約社員の加入基準も整備され、より多くの労働者が社会保険の対象となっています。
国民健康保険の場合
国民健康保険は、社会保険やその他の医療保険に加入していない人が対象の制度です。これは、全国の市区町村が運営しており、自営業者やフリーランスなど幅広い層が対象です。具体的には、以下のような人が該当します。
-
- 自営業者
フリーランスや個人事業主など、会社に所属せず独立して働く人は、国民健康保険に加入する必要があります。 - 日雇い労働者や短期雇用者
雇用契約が短期間であり、社会保険の加入条件を満たさない人も対象となります。 - 無職の人
退職後や就職活動中など、他の保険制度に加入していない場合、国民健康保険への加入が必要です。 - 適用除外の事業所で働く人
社会保険が適用されない事業所で働いている場合、国民健康保険に加入します。
- 自営業者
なお、国民健康保険には扶養制度が存在しません。そのため、生計を共にする家族であっても、それぞれが個別に被保険者として加入しなければなりません。
保険料の計算方法
保険料の計算方法は、加入する保険制度によって異なります。社会保険と国民健康保険で、それぞれどのように保険料の負担が決定されているかを解説します。
社会保険の場合
社会保険の保険料は、主に加入者の収入を基に計算されます。この計算の基礎となるのが「標準報酬月額」です。標準報酬月額に基づき、健康保険料や厚生年金保険料が決定され、各都道府県や保険組合ごとに定められた保険料率が適用されます。
標準報酬月額の決定方法には、以下のパターンがあります。
- ・定時決定
- 毎年4月から6月の月額報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定する方法です。在職中の被保険者に適用され、7月に報酬月額を届け出て、9月から新しい保険料が適用されます。
- ・随時改定
- 昇給や降給などにより月額報酬が大きく変動した場合に行われる改定です。固定的賃金(基本給、役職手当など)が変動し、その結果、報酬が2等級以上上下し、その状態が3か月以上続いた場合に適用されます。実際の報酬に即した保険料負担を実現します。
- ・資格取得時決定
- 新入社員などが入社した際に、入社時の月額報酬を基に標準報酬月額を決定する方法です。入社直後から適切な保険料を負担できます。
毎年4月から6月の月額報酬の平均額をもとに算出されますが、これが「定時決定」と呼ばれる手続きです。新入社員の場合は、入社時の月額報酬をもとにして標準報酬月額が決定されます。この標準報酬月額に基づき、健康保険料や厚生年金保険料が決定され、各都道府県や保険組合ごとに定められた保険料率が適用されます。
また、満40歳になると健康保険料に介護保険料が加算されます。これは高齢化社会に対応したしくみであり、40歳以上の加入者への負担が増加しますが、介護サービスを受ける社会基盤となります。
社会保険料は、被保険者が全額を負担するのではなく、事業主と折半で負担するしくみです。個人の負担は軽減されており、事業者と労働者が共同で保障の基盤を支えます。
国民健康保険の場合
国民健康保険の保険料は、市区町村が運営するため、地域によって異なります。それぞれの自治体で医療費の状況や財政状況に基づいて保険料率が設定されており、同じ所得でも住む地域によって負担額が変わるしくみです。
また、保険料は世帯単位で計算され、世帯全体の所得を基に保険料が決定されます。このため、家族全員の所得が保険料計算に影響を与えることになります。
ただし、所得が低い世帯に対しては減額制度が設けられています。例えば、所得が一定基準を下回る場合や世帯人数が多い場合など、経済的負担を軽減する配慮がされています。なお、保険料の納付は世帯主が責任を持つ形となるため、家族間での支払管理が重要です。
扶養制度の有無
扶養制度の有無は、社会保険と国民健康保険で大きく異なります。扶養制度は、被保険者に経済的に依存する家族を保険の対象とし、その家族も制度を利用できるしくみですが、制度ごとに対応が異なります。
社会保険の場合
社会保険には、扶養制度が設けられており、被保険者が経済的に支える家族を扶養に入れられます。
扶養に入れる対象は、配偶者や子供、親など、生計を共にする親族です。ただし、扶養に入るには一定の条件があります。主な条件としては、被扶養者の年間収入が130万円未満であること、または被保険者の収入の半分以下であることです。
社会保険の扶養制度は、専業主婦や年金生活者、未成年の子供など、収入が少ない家族にとって重要な支援となります。扶養に入ることで、保険料を負担することなく医療保障を受けられるため、家庭の経済的負担を軽減する効果があり、家族を持つ労働者にとって大きな安心材料となります。
国民健康保険の場合
国民健康保険は扶養という概念がないため、生計を同一にする配偶者や子供であっても、それぞれが保険料を支払う義務があります。保険料は加入者の所得や世帯構成に基づいて計算され、所得が高いほど負担が大きくなるしくみです。その一方で、低所得世帯には減免措置が適用される場合があります。
このように、国民健康保険は加入者の経済状況に配慮した制度設計がなされている点が特徴です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
社会保険の任意継続制度とは
社会保険の任意継続制度とは、退職後でも一定の条件を満たすことで、退職前に加入していた勤務先の健康保険を引き続き利用できる制度です。
この制度は、退職後に新たな雇用先が見つかるまでの間や、健康保険の切り替えがスムーズに行えない場合に、医療保障を継続するための選択肢となります。
任意継続を利用する場合、退職前と同じ健康保険に加入し続けられるため、保険証の変更手続きや新しい制度への適応が不要となります。しかし、労使折半ではなくなり、退職者が全額を負担するため、保険料が高額になる点には注意しましょう。
任意継続制度利用の条件
任意継続制度を利用するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。まず、資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることが必須条件です。
また、退職日の翌日以降、健康保険の資格を喪失した日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しなければなりません。この手続きは、20日という短い期間で行う必要があるため、退職後は早めに必要書類を準備し、手続きを進めることが大切です。
なお、20日目が土日祝日に当たる場合は、翌営業日までが提出期限となります。任意継続制度の加入期間は最長で2年間となっており、この期間が過ぎると任意継続による健康保険は喪失します。
また、任意継続でも2年間の加入期間の上限が設けられているため注意が必要です。
任意継続のメリット
任意継続制度を利用する主なメリットは、健康保険の保障を退職後も継続できる点です。退職後すぐに次の職場での健康保険に加入できなかったり、国民健康保険への切り替えに時間がかかったりする場合、医療保障が途切れるリスクを防げます。
また、任意継続制度を選択すると、保険料を比較的安く抑えられる場合があります。保険料の計算基準は退職前の標準報酬月額に基づくため、国民健康保険の保険料計算で適用される「世帯全体の所得」を基準とした国民健康保険料と比較して、費用負担が軽くなるケースもあります。
任意継続のデメリット
任意継続制度では、保険料を全額自己負担しなければならない点が特徴です。退職前は事業主と被保険者が保険料を折半していましたが、任意継続ではその全額を負担する必要があり、一般的に保険料が大幅に増加する傾向があります。
収入が減少または無収入の状況での保険料の増額は大きな負担となるでしょう。また、任意継続では自己都合での脱退が認められないという制約があります。基本的に、加入期間中の保険料を支払い続ける義務が発生するため、途中で国民健康保険に切り替えたくとも、一般的には自由に解約はできません。メリット・デメリットの両方を理解した選択が重要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
国民健康保険と社会保険の違いを理解しよう
社会保険は、扶養家族も加入できる一方で、国民健康保険は世帯全員が個別に加入する必要があるなど、加入にかかわる条件や保険料の違いを理解しておくことが大切です。会社を辞めた場合、社会保険を継続するのか、国民健康保険に加入すべきか、適切な判断が求められます。
健康保険料の計算や給与計算業務を効率化するためには、給与ソフトの活用もおすすめです。「弥生給与 Next」なら、煩雑な保険料の処理も簡単に行え、業務負担を大幅に軽減できますので、ぜひご活用ください。
- ※2024年12月時点の情報を基に制作しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。








