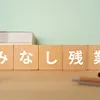固定残業代とは?メリット・デメリットや導入の注意点をわかりやすく解説
更新

固定残業代とは何か、そのメリットや注意点について興味をお持ちの経営者や給与計算の担当者も多いのではないでしょうか。固定残業代制度を正しく理解していれば、制度の導入や運用がスムーズに進み、従業員とのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
本記事では、固定残業代制度の基本的なしくみや計算方法、メリット・デメリット、基本給に含められるかどうかといった実務的な知識を網羅しています。さらに、固定残業代が違法になるケースについても詳しく解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
固定残業代とは
固定残業代とは、残業時間にかかわらず決まった額を毎月支給する残業代のことです。「みなし残業代」とも呼ばれます。固定残業代を導入するには、就業規則や雇用契約書などの書面に記載し、労使双方の合意が望ましいです。固定残業代には、以下の2つのタイプがあります。
基本給組み入れ型:本給に時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含める形式
手当型:手当として一定額を支払う形式
例えば、「固定残業時間は月20時間、固定残業代は5万円」と設定されている場合、月の残業が20時間以内であれば、必ず毎月5万円が支給されるしくみです。20時間を超えた分については、追加の残業代が支給されます。したがって、月に30時間残業した場合は、10時間分の残業代が追加されます。なお、固定残業代は、基本給など通常の賃金と明確に区別されていれば、割増賃金の算定基礎から除外して計算を行います。
固定残業時間の上限
固定残業時間の上限を設定する際には、法定労働時間を超えた時間外労働は、36(サブロク)協定に基づき、原則として1か月45時間、1年間で360時間を参考に設定します。この場合、45時間を超過して勤務することができないためです。
参照:e-Gov「労働基準法」
-
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
事業主には罰則の対象となります。最も重い場合には、労働基準法第119条に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。したがって事業主には、適切な36協定を締結し、上限を守ることが義務づけられています。
引用:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
36協定の特別条項について、こちらの記事で解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
固定残業代制のメリット
固定残業代制には、企業・従業員両者にメリットがあります。業務効率化や従業員の生活・健康面の向上につながり、労働環境改善に役立ちます。
残業代の計算がしやすい
固定残業代制では、残業代が毎月一定額となるため、勤怠の実績から固定残業に残業時間が吸収されれば、給与計算業務の負担が軽減されます。
所得税や社会保険料も、固定残業時間の超過分がなければ一定額となり、計算が容易です。このため、利益計画などを作成する際に、毎月の人件費の見通しが立ちやすくなることから、給与計算担当者だけでなく企業全体にとっても大きなメリットです。人件費は企業の支出に占める割合が大きいため、人件費の支出をある程度予測できることで、資金繰りや経営の計画が立てやすくなります。
業務効率の改善につながる
固定残業代制では、残業がなかった月でも一定の残業代が支給されます。そのため、従業員には「残業を減らした方が得」という意識が生まれる可能性があります。残業を抑える意識から効率的な働き方が促進され、職場全体の業務効率向上や従業員のスキルアップが可能です。また、残業を行う従業員が減ることで、光熱費削減などの間接的な効果も期待できます。
社員の生活が安定しやすい
固定残業代制は、残業時間が少なくても給与が一定のため、比較的安定した収入が得られる点が特徴です。特に、繁忙期と閑散期の差が大きい業種では、このしくみによる収入の安定が大きなメリットです。通常の残業を清算する制度では、閑散期に収入が減りがちですが、固定残業代制であれば年間を通して一定の生活水準を維持できます。また、残業が少なければ、安定した収入を得ながらプライベートを充実させられるため、ライフワークバランスの取れた働き方が期待できます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
固定残業代制のデメリット
固定残業代制にはメリットだけでなくデメリットもあります。導入前によく検討しないと企業に負担がかかるだけでなく、制度を違法に利用してしまう恐れもあるため、注意が必要です。
人件費が上昇する可能性がある
固定残業代制では、一定額の残業代をすべての従業員に毎月支払わなければならないため、人件費が高くなる可能性もあります。特に、残業を行っていない従業員にも固定残業代を支給しなければならない点が課題です。また、固定残業時間を超過した場合には、その分の割増賃金を追加で支払う必要があります。
長時間労働につながる恐れがある
固定残業代制を正しく理解していない場合、管理職や従業員が「固定残業時間分は必ず残業しなければならない」と誤解することがあり、この誤解が長時間労働の原因になる可能性があります。管理者が固定残業制度を正しく理解し適切な指導を行うことが大切です。また、従業員が制度にネガティブな印象を持たないよう、適切な説明の場を設け、固定残業制度の趣旨を十分に周知することが、制度の導入には不可欠です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
固定残業代の計算方法
固定残業代は、通常の残業代と同様に、労働基準法で定められた計算方法に基づき算出されます。特に法定労働時間を超えた場合には、割増賃金率25%が適用される点に注意しましょう。法定労働時間を超えない部分については、割増賃金率は適用されません。計算方法は以下のとおりです。
【基本給組み入れ型】
基本給÷{月の平均所定労働時間+(固定残業時間×1.25)}×固定残業時間×1.25
※月の平均所定労働時間=(365日-年間休日)×1日の所定労働時間÷12か月
従業員への労働条件通知書または雇用契約書には、固定残業代の計算方法や固定残業時間を明記する必要があります。組み入れられている固定残業代と残業時間を記載します。
【手当型】
給与の総額÷月の平均所定労働時間×固定残業時間×1.25
手当型では、基本給と固定残業代を分けて計算します。
固定残業代の計算方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
固定残業代の運用で労務トラブルにつながる例
固定残業代制は企業・従業員ともにメリットがありますが、制度をよく理解しないと思わぬトラブルにつながりかねません。
固定部分を超えた分の未払い
固定残業時間を超えた残業時間については、追加の残業代を支給しなければなりません。例えば、固定残業時間20時間の場合、20時間を超過した分だけ追加の残業代が必要です。一部の企業では「固定残業時間を超えた分は支払わなくてもよい」と誤解している場合があり、超過分の残業代が未払いとなる事例が見受けられますが、こうした運用は労働基準法違反となります。
基本給が最低賃金を下回る
最低賃金法は、正規雇用・非正規雇用を問わず守られるべき法律です。基本給を労働時間で割った結果が最低賃金を下回ることがないよう、固定残業代を含めない基本給や手当の合計額で計算を行う必要があります。
また、法定労働時間を超えた固定残業代も最低賃金に割増賃金率25%以上を適用したうえで設定しなければなりません。特に基本給組み入れ型は注意が必要です。求人では誤解を招かないよう、給与の表記の仕方に注意しましょう。
以下の例では、固定残業代の計上方法により、給与の見せ方が異なります。
-
-
①基本給20万円 残業代別
-
②基本給25万円(固定残業時間30時間)
-
記載上は②の給与が高く見えますが、実際には固定残業代を含んでいるため、1時間当たりの賃金が①よりも低い可能性があります。このように基本給を高く見せかけると、トラブルの原因になり、企業としての信用を失いかねません。特に、1時間当たりの賃金が最低賃金を下回ってしまうと違法なため、基本給や固定残業代の賃金設定は正確に行いましょう。
時間外・休日・深夜労働における割増率を適用していない
固定残業代問わず法定労働時間を超えた分について割増賃金率を適用する必要があり、適用していない場合は違法です。割増賃金率は以下のとおりです。
| 労働時間の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 月60時間以内の時間外労働 | +25% |
| 月60時間を超えた時間外労働 | +50% |
| 法定休日労働 | +35% |
| 深夜労働(22時~5時) | +25% |
割増賃金率は加算して適用されます。例えば、時間外労働が深夜労働に該当する場合、時間外労働の割増賃金率25%と深夜労働の割増賃金率25%を合計した50%の割増率が適用されます。また、休日労働の割増賃金率35%は、法定休日に労働した場合に適用されます。ただし、法定休日以外の休日労働には適用されません。
固定残業代制でも、休日労働や深夜労働に割増率を適用しない場合は違法です。ただし、就業規則・給与規程に明記することで、これらの割増分を固定残業代に含めることは可能です。
参照:東京労働局「しっかりマスター労働基準法割増賃金編」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
固定残業代制導入時の注意点
固定残業代制を導入する際には、制度の理解と、従業員が安心して働けるよう透明性を確保したうえでの運用が欠かせません。
適切な手続きの実施
固定残業代制を導入する場合は、労働基準法に基づく適切な手続きを踏む必要があります。時間外労働や休日労働を行う場合、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。特別条項付き36協定の場合も同様に、労使間での締結が求められます。
また、固定残業代に関する内容を明記するために、就業規則や給与規程を見直します。就業規則を改定する際は、まず36協定の適用範囲を確認し、従業員代表から意見を聴取することが求められます。特に、固定残業代制を導入する場合や基本給を減額する場合など、従業員に不利益が生じる可能性がある場合には、原則として従業員の同意を得る必要があります。変更内容は、労働条件通知書や雇用契約書に明確に記載し、契約を締結することで、後のトラブルを防げます。
参照:e-Gov「労働基準法」
透明性の確保
固定残業時間について労使間で合意した後、その内容を労働条件通知書または雇用契約書に明記し、従業員と雇用契約します。特に労使双方が合意する雇用契約書での明記を推奨します。
また、給与明細には、基本給と固定残業代を分けて記載することが望ましいです。これにより、透明性が向上し、従業員との信頼関係が強化されます。同様に、求人票にも基本給、固定残業時間、固定残業代などの詳細を明記して、透明性を確保してください。
さらに、固定残業代制の導入後は、就業規則にその内容を記載したうえで、従業員全体に周知し管轄の労働基準監督所へ届け出を行うことが求められます(ただし10人未満の事業所の場合は、周知のみでも有効となります)。
長時間労働の防止策
固定残業代制を導入する際は、長時間労働にならないよう防止策を実施しましょう。例えば勤怠管理ソフトは、リアルタイムでの残業時間がわかるため、活用がおすすめです。日々ツールで残業時間を管理すれば、長時間労働を防ぐことが可能です。また、2019年から「客観的な記録による労働時間の把握」が義務化されたため、タイムカードやパソコンのログイン・ログアウト記録を利用し、労働時間を定期的にチェックする必要があります。
参照:東京労働局 労働基準部 健康課「改正労働安全衛生法のポイント」
労働時間の適正な管理は、従業員の健康を守り、ワークライフバランスを向上させるだけでなく、良好な労働環境を維持し、人材流出を防ぐ効果も期待できます。従業員の健康管理を徹底し、企業全体の働きやすさを高めることを意識しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
基本知識を整理して固定残業代制導入を円滑に進めよう
固定残業代を導入すると、人件費の見通しが立てやすくなり、経営計画が効率化するというメリットがあります。また、従業員にとっても業務の効率化や生活・健康面でのプラス効果が期待できます。
固定残業代制度の運用には、制度を正しく理解し、正確な給与計算を行うことが不可欠です。「弥生給与 Next」を活用すれば、煩雑な給与計算作業を自動化し、ミスの不安を軽減できます。固定残業代の導入を検討している方は、ぜひ弥生のクラウド給与サービスを活用し、スムーズな運用を実現してください。
- ※2024年12月時点の情報を基に制作しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。