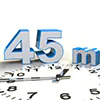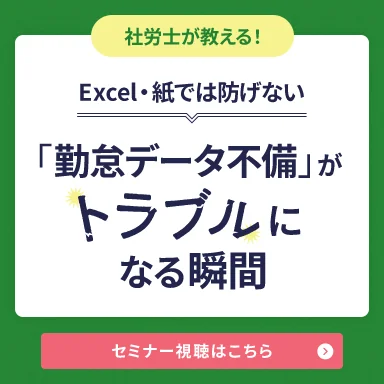休憩時間の法律上の定義やルールを解説!6時間ちょうどはどうなる?
更新

企業の担当者や経営者にとって、休憩時間の適切な付与は重要な課題です。労働基準法に基づく休憩時間のルールを理解し、適切に運用すれば、従業員の健康管理を促進し、働きやすい職場環境を実現できます。これにより、企業と従業員の双方にとって、よりよい関係を築けます。
本記事では、休憩時間の定義から計算方法、付与ルールまでをわかりやすく解説します。併せて、職場や働き方に合わせた休憩時間付与の工夫、押さえておきたい法律上の注意点も取り上げています。企業で実践すべき休憩時間管理のポイントを明確化するためにも、ぜひ目を通してみてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
労働時間と休憩時間の定義
労働時間とは、労働者が雇用主の指揮命令下で働く時間のことを指します。具体的には、オフィスでの業務や現場での作業など、雇用主から指示された業務を遂行している時間です。実際の作業に限らず、その準備や片付けなどを行っている時間もすべて労働時間に含まれます。
その一方で、休憩時間は、労働者が休息として労働から完全解放されることが保障されている時間です。労働者のリフレッシュを目的としており、法定労働時間に基づいて付与されます。休憩時間中、労働者は業務から完全に離れ、自分の時間を自由に使えます。ただし、就業規則などの職場の規律やルールには服するので、注意しなければなりません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
労働基準法における休憩時間のルール
労働基準法第34条では、労働者が長時間労働によって疲労を蓄積し、健康を損なうことを防ぐため、労働時間に応じた休憩時間の付与が義務付けられています。具体的には、以下のとおりです。
- 労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合:少なくとも45分の休憩を付与
- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩を付与
重要なのは「6時間を超える」「8時間を超える」という点で、6時間ちょうどの労働については休憩を付与しなくても法的には問題ありません。ただし、これはあくまでも最低限の基準であり、企業はこれを超える休憩時間を付与することが可能です。
所定労働時間内で残業をせず終業することは少なく、実労働時間が所定労働時間と一致しないケースはよく見られます。多くの企業では、所定労働時間が6時間の場合は45分、8時間の場合は1時間の休憩を設定するケースが一般的です。特に、8時間を1分でも超える場合は、1時間の休憩が必要であることに注意が必要です。労働の実態に応じて、適切な休憩時間を設定し、健康管理を行うようにしましょう。
参照:e-Gov「労働基準法 第34条」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休憩時間の付与対象
休憩時間の付与対象は従業員全員です。正社員だけでなく、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員など、雇用形態に関係なく、すべての従業員に対して休憩時間を付与しなければなりません。例外として、労働基準法第41条および第41条の2では、「管理監督者」とされる者や高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者への休憩時間の付与は必須ではないとされていますが、健康や安全に配慮して、適切な休憩を提供しましょう。
参照:e-Gov「労働基準法 第41条、第41条の2」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休憩時間の計算における3原則
休憩時間の付与、利用には3つの原則があります。
途中付与の原則
休憩時間は、労働時間の途中に付与しなければなりません。これは労働基準法に定められているもので、「途中付与の原則」と呼びます。休憩時間を労働時間の始めや終わりに設定することは認められていません。
例えば、始業時刻を遅らせてその分を休憩時間と見なしたり、終業時刻を早めて早退させる形で休憩時間を与えたりすると労働基準法に反します。この原則の目的は、労働者に労働の途中で適切な休息を取らせて疲労の蓄積を防ぎ、労働効率と安全性を確保することにあります。したがって、使用者は労働時間の途中に適切なタイミングで休憩時間を設定し、労働者が十分な休息を取れるよう配慮する必要があります。
一斉付与の原則
休憩時間は、事業場で従業員全員が一斉に取る必要があります。労働基準法にあるこの定めを、「一斉付与の原則」と呼びます。ただし、労使協定を結んでいる場合や特定の業種に該当する場合には、例外が認められることもあります。
例えば、運輸業や医療・介護業など、法律上の規定により一斉に休憩を取ることが難しい業種では、労使協定労使協定がなくても個別に休憩時間を設定することが可能です。また、シフト制を採用している企業でも、全員が同時に休憩を取ることは現実的ではないため、労使協定により一斉付与の原則が適用されないことがあります。このような場合、労働者が個別に休憩を取れるように調整が必要です。
自由利用の原則
休憩時間には、労働者が完全に労働から解放されていなければなりません。労働基準法に定めがあるこの原則を「自由利用の原則」と呼びます。したがって、休憩時間中に電話当番や来客対応などの業務を任せてはいけません。これらの業務を行った時間は、休憩時間として扱わないことが原則です。労働者が完全に労働から解放されていない限り、その時間は休憩時間に該当しません。ただし、やはりこれにも例外はあります。警察官や児童養護施設の職員など、一定の職務に従事する労働者は、例外的に休憩の自由利用が制限される可能性があります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休憩時間の付与ルールを破った場合の罰則
休憩時間の付与ルールを守らなかった場合、雇用主には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります(労働基準法第34条、第119条)。違反が認められると法的責任を問われるだけでなく、企業は社会的信用を大きく損なうリスクも伴います。
例えば、労働者に休憩時間を取らせずに業務を継続させた場合や、休憩時間中に業務を行わせる指示を出した場合が該当します。また、休憩時間を形式的に設定していても、実際に労働者が業務から完全に離れ、自由に利用できない状況が続く場合は、労働基準法に違反する可能性があります。罰則にとどまらず、休憩時間の適正な管理ができていない企業は、労働基準監督署から是正指導を受けることがあるため、適切な制度運用が求められます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休憩時間付与の柔軟な運用方法
働き方の多様化に伴い、休憩時間の運用にも柔軟さが求められています。例えば、分割休憩を活用した効率的な運用や、一斉休憩を実現しがたい場合の代替方法があげられます。また、シフト制勤務やテレワーク環境では、より慎重に休憩を管理しなければなりません。
分割休憩の運用方法
特に長時間の勤務が必要な職場や変則的な勤務体制だと、分割休憩には労働者の集中力を維持し、疲労を軽減する効果が期待できます。ただし、安全衛生の観点から、1回の休憩時間は最低でも30分程度確保することが望ましいでしょう。また、分割休憩を適用する際には、途中付与の原則に違反しないよう注意しなければなりません。
労働時間が6時間を超える場合、休憩時間の付与が必要です。必ずしも一度にまとめる必要はなく、休憩時間の分割付与も法的に認められています。例えば、6時間以上働く場合には45分の休憩が最低ラインですが、これを分割して与える場合、安全衛生的な観点から、30分程度までを目安とします。これは、あまりに短い休憩時間を何度も与えると、労働者の健康や集中力に悪影響を及ぼす可能性があるためです。また、最初の休憩を業務開始から2時間以内など、適切なタイミングで付与することが求められます。
一斉休憩の代替運用方法
一斉休憩(労働基準法第34条第2項)には、代替運用をする手段もあります。例えば、医療、警備、運輸などの業種では、全員が同時に休憩を取ることが困難なケースも多いためです。
医療機関では、患者の継続的なケアが必要です。全スタッフが同時に休憩を取ることは非現実的であるため、スタッフごとに休憩時間をずらして取得する個別付与が行われています。同様に、警備業や運輸業でも、業務の特性上、個別に休憩を取る運用が一般的です。
こうした例外業種では法律上、一斉休憩の適用が除外されるため、労使協定を締結しなくても、業務に応じた休憩時間を設定できます。一方で、その他の業種で一斉休憩を適用しない場合は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と書面で労使協定を締結する必要があります。
-
- 休憩スケジュールの明確化:各従業員の休憩時間を明確に定め、全員に周知する
- 公平な運用:特定の従業員に負担が偏らないよう、休憩時間を公平に割り当てる
- 労使間の合意:労使協定を締結し、休憩時間の付与方法について労働者の理解と協力を得る
シフト制勤務における休憩管理
シフト制勤務で1日8時間を超える労働が発生する場合、休憩時間を前半と後半に分割して付与する方法があります。例えば、12時間のシフトでは、法定の休憩時間を前半と後半に分割して取ることが考えられます。さらに、業務の合間に適宜追加の休憩を設定することで、従業員の疲労軽減を図ることができます。労働時間が8時間を超える場合には、このような方法で、適切な休憩時間を設定すれば、従業員の健康管理に役立ちます。
また、フレックスタイム制では労働者が始業・終業時刻を柔軟に決められる一方、休憩時間は一斉付与が原則です。コアタイムを設け、そこで休憩時間を確実に取得させる運用が有効です。例えば、10:00~15:00をコアタイムと設定し、この間に60分の休憩を与えるルールを明文化すれば、法令を遵守でき、労働者の権利も保護できます。
従業員ごとの休憩取得状況を漏らさず記録・管理するには、勤怠管理システムの導入が効果的です。システム上で休憩開始・終了時刻を登録させることで、法定休憩時間を取得しているかを確認できます。
テレワーク時の休憩管理の工夫
テレワークでは、自律的な時間管理が求められます。以下に、効果的な休憩管理のための工夫を紹介します。
- ・事前申請と報告の促進
- 自己管理型の業務では、休憩時間の事前申請や報告が効果的です。オンラインツールを利用して休憩予定を共有し、終了時に報告すれば、自己管理を徹底できます。他のメンバーも同僚の休憩時間を把握でき、業務を調整しやすくなります。
- ・アラート設定と通知ツールの活用
- 休憩のタイミングを逃さないために、アラートを自動通知してくれるツールを活用する手法です。例えば、パソコンやスマートフォンのアプリケーションを利用すれば、休憩のリマインダーを定期的に設定できます。
多様な職場環境に合わせた休憩時間の柔軟性
職場環境や業務内容に応じて休憩時間を柔軟に運用すれば、労働者の健康と生産性の向上を図れます。以下に、具体的な方法をいくつか紹介します。
- ・工場やライン作業での調整
- 工場やライン作業では、一定のリズムを保ちながら効率を維持するために、休憩時間を細かく調整することが重要です。通常の休憩時間に加えて、適宜、短時間の休憩を取り入れることで、長時間の連続作業による疲労を軽減し、生産性を保てます。
また、交代制で休憩を取得するしくみを導入すれば、ラインの稼働を維持しながら、従業員が適切に休息を取れる環境を整えられます。具体的には、休憩時間を前半と後半に分けたり、追加の短時間休憩を設定したりすることで、従業員の健康管理と生産性の両立を図れます。 - ・小規模事業所での公平性の確保
- 小規模事業所では少人数で業務を回す必要があるため、休憩時間の公平性は重要です。従業員間で休憩のスケジュールを共有し、互いにカバーし合うことで、公平かつ効率的に休憩を取得できるようになります。また、休憩時間の取得状況を可視化すれば、管理者は偏りなく休憩を与えられます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休憩時間付与において押さえておきたいポイント
休憩時間の付与には、法律に基づいたルールがいくつかあります。企業や労働者による正しい休憩時間の管理には、以下のポイントの適切な理解と実践が欠かせません。
手待ち時間は労働時間
手待ち時間とは、使用者から指示があったときにすぐ作業に入れるよう待機している拘束時間のことを指します。休憩時間中であっても、労働者が電話当番や来客対応などの業務を行う場合は、手待ち時間として労働時間に該当します。手待ち時間中の業務は休憩時間として認められず、適切に管理しなければなりません。
例えば、労働者が休憩中に電話応対する場合は手待ち時間と見なされ、通常の業務時間と同じ扱いになります。休憩を取る時間が実際には労働から一時的に離れる時間ではなく、待機している状態にすぎないため、労働契約に基づく給料支払い義務が生じます。
残業中の休憩時間
残業が発生した場合、休憩時間は実際の労働時間に応じて適切に調整しなければなりません。所定の労働時間を超える場合は、追加の休憩の付与が必要です。例えば、通常の労働時間が7時間で45分の休憩が付与されているとき、残業によって合計労働時間が8時間を超えると、15分以上の追加休憩が必要になります。この場合、確保されるべき休憩時間は合計で1時間以上です。このように、労働時間が長くなる場合には、労働基準法にしたがって適切な休憩を付与することが義務付けられています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
休憩時間のルールを理解しよう
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが企業に義務付けられています。休憩は原則として一斉に付与する必要がありますが、業務上の必要がある場合には、分割して与えることも認められています。
テレワークやフレックスタイム制においても、労働基準法に基づく休憩時間の規定が適用され、労働時間に応じた休憩の確保が求められます。特にテレワークでは、自己管理が重要となり、企業は従業員が適切なタイミングで休憩を取れるようにする工夫が必要です。さらに、休憩時間の適切な付与は、勤怠管理や給与計算の正確性にも影響を及ぼすため、これらを徹底することが重要です。
- ※2024年12月時点の情報を基に制作しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。