給与計算の基礎日数とは?基本の数え方や注意するポイントなどを解説
更新
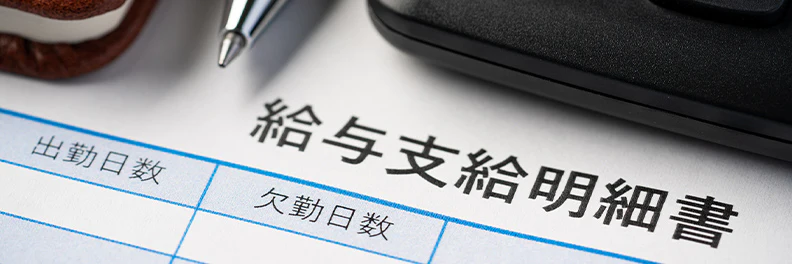
給与計算の基礎日数とは、賃金や報酬の支払い対象となる日数のことです。給与計算の基礎日数は、失業保険(雇用保険の基本手当を算出するための離職票の作成などに用いられる)や、社会保険料の算定にも影響します。従業員の出勤日数とは概念が異なるため、給与計算の基礎日数の正しい数え方を押さえておきましょう。
本記事では、給与計算の基礎日数の意味や給与形態別の数え方のほか、給与計算の基礎日数における注意点などについて解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
給与計算の基礎日数とは、賃金や報酬の支払い対象となる日数のこと
給与計算の基礎日数とは、賃金や報酬の支払い対象となる日数のことで、「賃金支払基礎日数」や「支払基礎日数」ともいいます。
給与計算の基礎日数が必要になるのは、一般的に「失業保険」と呼ばれる雇用保険の基本手当の受給資格を確認するときや、社会保険料を計算するベースとなる標準報酬月額を決めるときです。
賃金の支払い対象になる日数と聞くと、出勤日数と混同する人もいるかもしれませんが、給与計算の基礎日数は出勤日数とは数え方が異なります。そのため、給与計算の基礎日数の数え方について正しく理解しておきましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
支給方法に基づく給与体系の種類
給与体系は支給方法によって、「完全月給制」「日給月給制」「日給制・時給制」に分けられます。それぞれのしくみを見ていきましょう。
完全月給制の場合
完全月給制とは、1か月の賃金が決まっていて、たとえ欠勤しても減額がない給与形態のことです。完全月給制の場合は、休んだ日も含めた暦日数が給与計算の基礎日数となります。
暦日数とは、土日や祝日も含むカレンダーどおりの日数です。例えば、3月26日から4月25日までの期間であれば、31日が給与計算の基礎日数となります。
日給月給制の場合
日給月給制は、1か月の賃金が決まっているものの、欠勤をすれば欠勤日数に応じて減額される給与形態です。日給月給制の給与計算の基礎日数は、就業規則などで定められた給与計算の基礎となる月平均所定労働日数から、欠勤日数を差し引いた日数となります。
例えば、就業規則で定められた月平均所定労働日数が20日だった場合、欠勤がなければ給与計算の基礎日数は20日、欠勤が2日あれば給与計算の基礎日数は18日です。なお、この場合の欠勤とは、賃金が控除される欠勤のことを指します。有給休暇は欠勤には当たりません。
同じ月給制でも、完全月給制と日給月給制では、給与計算の基礎日数の数え方が違うため注意しましょう。
日給制・時給制の場合
日給制や時給制の場合は、出勤した日数がそのまま給与計算の基礎日数となります。有給休暇を取得した日も出勤日と同様に賃金支払いの対象になるため、給与計算の基礎日数に含めて数えます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算の基礎日数で注意するポイント
給与計算の基礎日数の数え方には、間違えやすいいくつかのポイントがあります。給与計算の基礎日数を数えるときには、以下の点に注意しましょう。
公休日の扱い
給与計算の基礎日数を数える際、公休日の扱いは、対象の従業員の給与形態によって異なるため、注意が必要です。
日給制や時給制であれば、「出勤日数=給与計算」の基礎日数ですから、土日祝日に出勤していれば給与計算の基礎日数に含まれますし、働いていなければ含まれません。
それに対して、完全月給制の場合は、公休日に働いたかどうかにかかわらず、暦日数が給与計算の基礎日数となります。また、日給月給制は月平均所定労働日数がベースになるため、やはり公休日かどうかは関係ありません。それぞれの給与形態に沿って、給与計算の基礎日数を正しく数えるようにしましょう。
特別休暇や有給休暇の扱い
給与計算の基礎日数を数える際、特別休暇や有給休暇の扱いにも注意が必要です。労働基準法では、給与形態や雇用形態を問わず、一定の要件を満たした従業員には年次有給休暇を与えなければならないと定められています。
また、企業によっては、慶弔休暇やリフレッシュ休暇などの休暇制度を設けていることもあるでしょう。このような有給休暇や特別休暇は、賃金支払いの対象になりますので、給与計算の基礎日数に含まれます。特に、日給月給制や日給制・時給制の場合、実際に出勤していない場合でも、有給休暇や特別休暇を給与計算の基礎日数から除外しないように注意してください。
休職・産休の扱い
給与計算の基礎日数を数える際、休職の扱いに注意しましょう。業務外の病気やケガなどによって休職した日数は、賃金の支払い対象にならないため、給与計算の基礎日数には含まれません。有給休暇や特別休暇と同じく休んでいる状態ではありますが、賃金の支払いがない期間は給与計算の基礎日数には計上されません。同様に、賃金が支払われない産休(産前産後休業)なども、給与計算の基礎日数の対象外です。
給与計算の基礎日数を数えるときには、賃金の支払いが発生する休みかどうかを確認するようにしましょう。
所定労働時間に満たない場合
雇用保険や社会保険の基礎日数を数える際に、1日の労働時間が所定労働時間に満たない場合も確認が必要です。遅刻や早退などによって、1日の労働時間が短くなり、所定労働時間に満たない場合も、給与計算の基礎日数では「1日」として扱われます。
例えば、「半休を取って0.5日」などと数えるようなことはしません。1時間でも勤務をしていれば、給与計算の基礎日数は1日として計算します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
雇用保険で用いられる給与計算の基礎日数
給与計算の基礎日数は、失業保険(雇用保険の基本手当)の支給要件の基準として用いられます。失業保険を受給するには原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが条件です。
この被保険者期間を算定する際には完全月であり、給与計算の基礎日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
社会保険料の計算で用いられる給与計算の基礎日数
給与計算の基礎日数は、社会保険料を計算するベースとなる「標準報酬月額」の算定にも影響します。なぜなら、標準報酬月額は通常、4~6月の3か月のうち、給与計算の基礎日数が17日以上の月の平均報酬月額を基にして、標準報酬月額保険料額表から算出することができます。
例えば、4~6月の3か月とも給与計算の基礎日数が17日以上なら、平均報酬月額は4~6月に支払った報酬の平均です。また、4月の給与計算の基礎日数が17日未満で、5~6月は17日以上だったとすると、平均報酬月額は5月分と6月分のみで計算されることになります。
社会保険料の計算で標準報酬月額を使用するのは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料になります。各保険料は、標準報酬月額にそれぞれ決められた保険料率を乗じて算出し、企業と従業員で支払う保険料を折半するため、「標準報酬月額×各保険料率÷2」で求めることができます。
短時間就労者の社会保険における取り扱い
短時間就労者の社会保険における取り扱いは、標準報酬月額の算定基準が少し異なります。短時間就労者とは、正社員より短時間の労働条件で勤務する人のことです。毎年1回の定時決定で出される、短時間就労者の標準報酬月額の算出方法を見ていきましょう。
短時間就労者の標準報酬月額の算出方法
- 4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合
該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
- 4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
3か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
- 4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。
- ※日本年金機構「定時決定(算定基礎届)
」
4~6月の3か月とも給与計算の基礎日数が17日以上の場合や、4~6月のうち1か月でも給与計算の基礎日数が17日以上の月がある場合は、短時間就労者も平均報酬月額の計算方法は同じです。
その一方で、4~6月の3か月とも給与計算の基礎日数が17日未満であっても、給与計算の基礎日数が15日以上の月があれば、その月(15日以上17日未満の月)の報酬の平均を平均報酬月額とします。給与計算の基礎日数が3か月とも15日未満である場合は、保険者算定となり、直近で使われていた標準報酬月額がそのまま適用されます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算の基礎日数の数え方を正しく理解しておこう
給与計算の基礎日数は、賃金や報酬の支払い対象となる日数のことで、雇用保険の基本手当の支給要件や、社会保険料の計算のベースになる標準報酬月額の算定にも用いられます。出勤日数とは異なるルールがあるため、給与形態ごとの数え方をしっかりと把握しておかなければなりません。
給与にかかわる業務を効率化するには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は、給与計算や年末調整業務を効率化し、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しています。自社に合ったツールを活用して、業務の効率化を目指しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。








