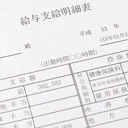給与計算のやり方とは?手順や正しい計算方法、注意点などを解説
更新

従業員を雇用している企業では、毎月の給与計算が欠かせません。給与計算では、勤怠データの集計、各種手当の計算、社会保険料や税金の控除など、複雑な作業を正確に処理することが必要です。
また、給与計算には法的なルールがあり、計算ミスや手続きの不備があると、従業員に影響があるだけでなく、労働基準法違反などに該当し、企業がペナルティを受ける可能性もあります。そのため、正確な知識を身に付け、必要な作業をしっかりと把握し、手順に沿って進めることが大切です。
本記事では、給与計算の流れを紹介すると共に、作業時に知っておきたいポイントや注意点についても解説します。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
給与計算とは、従業員の給与を計算し正しく支払うための業務
給与計算とは、従業員に支払う給与を正しく算出する業務のことです。毎月の勤怠データを基に、総支給額と各種控除額を計算し、最終的な支給額を確定します。給与計算式は次のとおりです。
- 総支給額 – 各種控除額=実際に支給する手取り額(差引支給額)
総支給額には、基本給に加え、残業代や各種手当(通勤手当、役職手当、住宅手当など)も含まれます。その一方で、総支給額から差し引かれる控除には、社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険)や所得税、住民税などが含まれます。
給与計算を誤ってしまうと、従業員に正しく給与を支払えないだけでなく、社会保険料や税金の納付にも支障が生じます。正確な給与計算を行うことは、従業員の不利益を防ぐとともに、信頼を守り、企業のコンプライアンスを維持するためにも重要です。次段では、具体的な給与計算の手順について解説します。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算のやり方
給与計算は、以下の4つの手順で進めます。
-
手順1.勤怠情報を取りまとめる
-
手順2.支給額の計算を行う
-
手順3.控除額の計算を行う
-
手順4.差引支給額を求める
給与計算は、まず各従業員の出勤日数や労働時間などの勤怠情報を集計し、それを基に基本給や各種手当、残業代などの支給額を計算します。
次に、社会保険料や税金などの控除額を算出し、最終的な差引支給額を決定します。給与計算には、勤怠データの収集から支払いまで複数の工程があるため、正確な処理が重要です。特に、時間外労働や深夜労働の割増賃金、住民税の控除額などはミスが発生しやすいため、慎重に確認しましょう。
以下では、各手順の詳細を解説します。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算の手順1. 勤怠情報を取りまとめる
給与計算で最初に行うのが、勤怠情報の収集・整理です。勤怠管理システムやタイムカード、出勤簿を基に、各従業員の勤務状況を確認し、一覧表にまとめましょう。
確認すべき勤怠情報には、勤務日数や有給休暇の取得状況、欠勤日数、遅刻や早退時間、労働時間、残業時間などがあります。具体的な項目は会社規程によっても変わりますが、代表的な項目例と概要は以下のとおりです。
| 所定労働日数 | 給与計算期間(月末締めであれば1日~末日まで、20日締めであれば前月21日~当月20日までなど、給与の計算対象となる期間)中の、従業員が出勤しなければならない日数のことです。同じ勤務形態で働いている従業員の所定労働日数は、基本的に全員同一です。カレンダーを見て、出勤すべき日数が何日あったのか確認しましょう。 |
|---|---|
| 勤務日数 | 所定労働日数のうち、それぞれの従業員が実際に出勤した日数です。休日出勤した日数を勤務日数に含めるかどうかは、企業ごとの定義や就業規則等によって異なる場合があります。 |
| 労働時間 | 給与計算期間中の、従業員の労働時間を分単位で合計します。 |
| 有休取得日数と有休残日数 | 給与計算期間中に取得した有給休暇の日数。有休残日数は、取得済の有給休暇を除いた残りの年次有給休暇の日数です。 有給休暇を使うタイミングや付与されるタイミングは、従業員ごとに異なります。有給休暇の付与には、出勤率が影響してくるため、有給休暇管理簿を作成して、勤怠と合わせて管理することがおすすめです。 |
| 欠勤日数 | 給与計算期間中に、欠勤した日数を確認します。 |
| 遅刻および早退時間 | 給与計算期間中に遅刻や早退をした従業員については、遅刻、早退時間を確認して合計を算出します。 |
| 所定労働時間を超えた時間すべて | 給与計算期間中の、残業時間(深夜労働時間を除く)の合計を算出します。 |
| 深夜労働時間 | 夜22時~朝5時までの残業は「深夜労働時間」として、所定労働時間を超えた時間すべてとは別にまとめます。これは、残業手当の計算方法が異なるためです。 |
| 休日出勤時間 | 休日出勤をした従業員については、休日の勤務時間を確認します。 なお、休日出勤には、法定休日出勤と、所定休日出勤の2種類があります。それぞれ何日出勤しているのかを確認しておきましょう。 休日出勤の種類 ・法定休日出勤:法律で定められた週1回の休日に出勤した場合 ・所定休日出勤:法定休日以外の会社規程による休日に出勤した場合 |
それぞれの項目について、こちらの記事で詳しく解説しています。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算の手順2. 支給額の計算を行う
勤怠情報をまとめたら、次に支給額の計算を行います。支給額には、基本給などの金額が毎月固定されている項目と、割増賃金や一部手当のように勤怠状況に応じて変動する項目があります。そのため、それぞれの項目を正確に計算する必要があります。また、手当には課税と非課税の区分があるため、こちらも正しい取り扱いが大切です。
基本給
基本給とは、従業員に対して必ず支払われる金額で、各種手当を含まない給与のベースとなる部分です。月給制の場合、欠勤がなければ基本的には前月と同じ金額を転記すれば問題ありません。ただし、新入社員の初回給与や、月の途中で入社した従業員の給与は日割り計算が必要になる場合があります。その際、翌月以降も誤って日割り計算を続けないよう注意しましょう。
割増賃金
割増賃金は、時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働を行った場合に支払う追加賃金です。割増賃金は「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」の3つに分けられ、種類ごとに割増率が労働基準法で定められています。従業員の勤怠状況に合わせて割増賃金の有無を確認し、必要な場合は個別に計算して基本給に加算します。割増賃金の種類と割増率は以下のとおりです。
| 割増賃金の種類 | 対象 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を超える労働 | 月60時間まで:25%以上 月60時間超:50%以上 |
| 休日労働 | 「週1日または4週を通じて4日」という法定休日における労働 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 22時~翌5時の深夜の時間帯における労働 | 25%以上 |
割増賃金は、条件が重なると複数の割増率が適用されます。例えば、深夜に時間外労働を行った場合、深夜労働の割増率(25%以上)と時間外労働の割増率(25%以上)の両方が適用され、合計50%以上の割増率になります。割増賃金の計算式は次のとおりです。
- 割増賃金=1時間当たりの基礎賃金×対象の労働時間数×各種割増率
割増賃金を求めるとき、「対象の労働時間数」の部分に、時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの労働時間を入れ、各種割増率を掛けて算出します。月給制の場合、上記計算式における「1時間当たりの基礎賃金」は、給与規程に記載された内容を前提に、次のように求めます。
- 1時間当たりの基礎賃金=月給÷月平均所定労働時間
これはあくまで代表的な計算式の一例です。実際の算出方法は各企業の給与規程によって異なります。
その他、残業をしても割増賃金が発生しないケースもあるため注意しましょう。残業には、「法定内残業」と「法定外残業」の2つがあります。このうち、労働基準法で定めた「法定労働時間(1日8時間、週40時間)」を超えた法定外残業に対しては、上記の割増率で割増賃金を計算する必要があります。
その一方で、所定労働時間を超えていても法定労働時間を超えない残業は法定内残業と扱われ、割増賃金は発生しません。例えば、所定労働時間が7時間の従業員が1時間残業した場合は、法定労働時間(8時間)を超えていないため割増賃金は発生しません。このような場合、会社が決めた割増率で残業代を計算するか、そのような規定がない場合は、残業時間に応じて通常どおりの1.0倍の賃金を支払うことになります。
同様に休日出勤も、「法定休日」の労働に対しては35%以上の割増賃金が適用されます。それ以外の休日(法定外休日)における労働も、労働時間によっては法定時間外労働として扱われ、割増の対象になる場合がありますので注意が必要です。
このように給与計算を行う際には、割増賃金の対象になるものとならないものを正しく把握することが大切です。
割増賃金についてはこちらの記事でも解説しています。
各種手当
賃金規程などで定められた手当がある場合は、それぞれの支給額を計算し、給与に加算します。代表的な手当の例として、以下のようなものがあります。
- 通勤手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 役職手当
- 資格手当
- 皆勤手当
手当には、支給額が固定されているものと、状況に応じて変動するものがあります。例えば、住宅手当や家族手当は、扶養状況や居住形態によって支給額が変わるため、最新の情報を基に計算しましょう。また、手当の中には、一定額までの通勤手当や、要件を満たした出張手当など、非課税となるものもあります。非課税の手当は所得税の計算にも影響するため、課税対象となる手当とは分けて計算しましょう。
手当についてはこちらの記事でも解説しています。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算の手順3. 控除額の計算を行う
支給額の計算が完了したら、給与から控除する金額を計算します。控除額には、法律で定められた社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料)や税金(住民税、源泉所得税)が含まれます。遅刻・早退に応じてまた、遅刻・早退や欠勤に対する控除は、会社の規定に基づいて適用されます。 なお、法改正などにより料率が変更されることがあるため、最新の情報を確認しながら処理しましょう。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、「標準報酬月額」に保険料率を掛け、労使折半して算出します。計算式は以下のとおりです。
- 厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2
標準報酬月額は、「報酬月額」を基に、日本年金機構が公表している「保険料額表」の等級に当てはめて決定されます。社会保険対象賃金の報酬月額は、基本給や残業手当(見込み含む)などの各種手当を合計した1か月の総支給額から算出されます。ただし、臨時的に支払われる手当や、3か月を超える期間ごとに支給される賞与は含まれません。
なお、標準報酬月額は、入社時や毎年7月1日の定時決定、昇給・降給があった場合など、さまざまタイミングで算定されます。2025年2月現在の厚生年金保険料率は18.3%です。保険料は労使折半なので、事業主と従業員が9.15%ずつ負担します。
標準報酬月額についてはこちらの記事で解説しています。
健康保険料および介護保険料
健康保険料および介護保険料は、標準報酬月額にそれぞれの保険料率を掛けて算出します。それぞれの計算式は以下のとおりです。
- 健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率÷2
- 介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率÷2
厚生年金保険とは異なり、健康保険の標準報酬月額は50段階に等級が分かれています。加入している健康保険組合の種類や協会けんぽの適用地域によって保険料率が異なるため、必ず自社の保険料額表を確認したうえで計算しましょう。また、40歳未満の従業員は健康保険料のみですが、40歳以上の従業員は介護保険料も含めて計算する必要があります。
なお、介護保険は、「第1号被保険者(65歳以上)」と、「第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)」に分けられます。第1号被保険者は、理由を問わず要介護・要支援認定を受けると、原則として介護サービスを利用することが可能です。
雇用保険料
雇用保険料は、毎月の給与額に雇用保険料率を乗じて算出します。計算式は以下のとおりです。
- 雇用保険料=月給×雇用保険料率(本人負担分)
給与のうち、雇用保険の算定対象となるものと、対象外のものがあるため、注意が必要です。
- 算定対象になるもの:基本給、賞与、残業手当、通勤手当など。
- 算定対象外のもの:休業補償費、結婚祝金、死亡弔慰金など。
また、雇用保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3つの区分で異なります。事業主負担分と従業員負担分がそれぞれ定められているため、詳しくは厚生労働省の「雇用保険料率について」を確認しましょう。
なお、いずれの業種でも、雇用保険料率は従業員に比べて事業主の負担割合が大きくなっています。厚生年金保険料や健康保険料のように、労使折半ではないので注意が必要です。
住民税
住民税は前年の所得を基に自治体が税額を決定し、毎年5月中旬~下旬ごろに「住民税課税決定通知書」が会社へ送付されます。会社は、各従業員の納税額を確認し、6月から翌年5月までの12か月で分割して給与から控除・納税しなければなりません。
源泉所得税
源泉所得税は、毎月の給与から概算の所得税を計算し、会社が従業員に代わって徴収・納付します。年間の給与の総額が確定したタイミングで年末調整を行い、実際の所得税額との過不足を精算するしくみです。
月々の給与から徴収する源泉所得税は、従業員の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数によって金額が決まります。該当の月の総支給額から、社会保険料と非課税通勤費を差し引いた金額を、国税庁による「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と照合して源泉所得税の金額を算出しましょう。
なお、源泉徴収税額表には甲欄と乙欄があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員は甲欄、提出していない従業員は乙欄を参照します。1か所のみで勤務している従業員は、その会社に扶養控除等(異動)申告書を提出し、甲欄の税額表を適用します。2か所以上の会社で勤務している場合は、そのうち1社にしか扶養控除等(異動)申告書を提出できません。したがって、副業がないことを前提にすると、一般的な従業員は甲欄に該当し、「扶養親族等の数」に応じた源泉徴収税額を確認します。
勤怠状況に応じた控除
従業員が欠勤・遅刻・早退をした場合は、賃金規程で定めた計算方法に基づき控除額を算出します。計算方法は各就業規則によりますが、一般的な計算式は以下のとおりです。
- 欠勤控除額=月給÷月平均所定労働日数(もしくはその月の所定労働日数)×欠勤日数
- 遅刻早退控除額=月給÷月平均所定労働日数×遅刻早退時間
いずれの控除の場合も、「月給」に基本給のみを適用するか、一部手当を含めるかは、事前に賃金規程で定めておく必要があります。社内で統一した基準を適用する必要があり、従業員ごとに異なる控除計算はできないので注意しましょう。
その他の控除額
法律で定められた控除以外に、会社が定める福利厚生関連の控除項目がある場合は、それを「その他の控除額」として計上します。代表的なものは以下のとおりです。
- 共済費
- 労働組合費
- 社宅費、寮費
- 財形貯蓄
- 社内預金
これらの控除を行う際は、事前に労使協定で取り決め、書面で締結する必要があります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算の手順4. 差引支給額を求める
控除額を算出したら、総支給額から差し引き、差引支給額を求めます。計算式は以下のとおりです。
- 差引支給額(手取り額)=総支給額-控除額
この金額が、いわゆる「手取り額」となり、従業員の口座へ振り込む(もしくは手渡す)金額となります。一般的に、手取り額は額面(基本給と各種手当を合わせた金額)の75~85%程度が目安です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算で知っておきたい4つのポイント
給与計算には法的なルールがあり、これを正しく理解していないとトラブルの原因となる可能性があります。労働基準法や最低賃金法などに基づくルールを遵守することが、企業に求められます。給与計算を担当する者は、以下の4つのポイントを理解し、適切に運用する必要があります。
1. 賃金支払の五原則
労働基準法第24条では、賃金の支払方法について、以下の「賃金支払の五原則」が定められています。
-
-
1.通貨で支払う:原則として日本円で支払う必要があります。ただし、労使協定を締結すれば一部現物支給も可能です。
-
2.直接労働者に支払う:代理人への支払いは原則禁止ですが、例外として長期入院時や裁判所による差し押さえ時は認められます。
-
3.全額を支払う:賃未払いや不当な天引きは違法です。ただし、労使協定で合意がある場合や、過払いの調整は認められます。
-
4.毎月1回以上支払う:給与は最低でも月1回以上、決まった期日に支払わなければなりません。
-
5.一定の期日を定めて支払う:事前に決めた支払日に遅延なく支払う必要があります。支払日が休日の場合は前後にずらすことも可能です。(事前の規定作成が必要)。
-
賃金支払の五原則を守らない場合、労働基準法違反となるため、企業は適切に対応する必要があります。
参照:厚生労働省「賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。」
2. 最低賃金制度
労働者の賃金は、最低賃金法に基づき「最低賃金制度」によって保護されています。最低賃金は都道府県ごとに異なり、事業所の所在地によって適用される額が決まります。
出向など、所属する事業所と実際に働く場所が異なる場合は、実際に働く場所を基準に判断します。例えば、東京本社の社員が大阪の支社で勤務する場合、東京の最低賃金が適用されます。また、業種によっては地域別最低賃金とは別に、産業別最低賃金が定められています。産業別最低賃金は、地域別最低賃金より高い水準に設定されることが多く、該当する事業者は注意しましょう。
なお、最低賃金は毎年10月に改定されるため、企業は最新情報を定期的に確認する必要があります。
参照:厚生労働省「最低賃金制度とは」
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
3. 労働時間の端数
労働時間は原則として1分単位で計測し、賃金計算に正確に反映させる必要があります。例えば、30分未満を切り捨てるといった「丸め処理」は認められていません。2024年には厚生労働省からの指導が入り、企業に対して適正な労働時間の把握を求める動きが強まっています。ただし、例外的に端数処理が認められるケースもあります。1か月の合計残業時間を求める場合には、30分未満の端数は切り捨て、30分以上1時間未満の端数は1時間に切り上げることが可能です。
また、時間単位の有給休暇を取得する際には、所定労働時間が7時間30分であれば、1日分の年休時間として8時間として取り扱う必要があります。この処理は企業の任意判断ではなく、労働基準法施行規則に基づいて定められている法定のルールです。
参照:厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
4. 賃金の小数点以下の端数
賃金計算においては、労働者に不利益となるような端数処理は認められていません。特に、賃金額を切り捨てることによって本来支払われるべき金額が不足するような方法は違反です。
割増賃金に関する端数処理では、1時間当たりの賃金に端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げることが可能です。また、1か月の割増賃金総額についても、1円未満の端数が発生した場合は同様に処理できます。これらの処理は、常に労働者に不利となるものでなく、事務簡便を目的としたものと認められ、労働基準法第24条および同法第37条違反としては取り扱われません。具体的には、以下の方法が認められています。
-
-
1.1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
-
2.1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
-
3.1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が発生した場合も、2と同様に処理すること
-
参照:厚生労働省「賃⾦計算の端数の取扱い」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算を行うときの注意点
給与計算におけるミスは、大きなトラブルにつながる可能性があります。場合によっては労働基準法違反や所得税法違反となり、企業がペナルティを受けることもあるため、細心の注意が必要です。以下では、特に重要なポイントを紹介するので、給与計算を行う際の参考にしてください。
情報漏えいに注意すること
給与額などの情報は、従業員にとって重要な個人情報であり、慎重な管理が求められます。外部の第三者はもちろん、社内の関係者に対しても情報が漏れないよう、徹底した対策を講じる必要があります。情報漏えいを防ぐ具体的な対策として、以下のような方法が有効です。
- 給与計算システムへのアクセス権限を制限する
- 経理担当者と秘密保持誓約書を取り交わす
- 紙の給与明細を廃止し、電子明細に切り替える
- 外部への持ち出しを禁止し、セキュリティ対策を徹底する
給与情報の適切な管理体制を構築し、情報漏えいのリスクを最小限に抑えましょう。
計算ミス・転記ミスに注意すること
給与計算では、計算ミスや転記ミスが起こりやすいため、常に細心の注意を払う必要があります。給与の誤計算は、社会保険料や税金の計算にも影響を及ぼし、後から修正が必要です。特に、徴収額が不足していた場合、追加徴収や修正申告が必要となり、企業側の手間が増えるだけでなく、従業員にも負担をかけることになります。
また、給与が正しく支払われないと従業員に不利益を与えてしまうだけでなく、不信感を招き、仕事へのモチベーション低下や離職につながる恐れもあります。こうしたトラブルを防ぐために、給与計算ソフトを導入するなど、ミスを未然に防ぐしくみを構築しましょう。
余裕を持ったスケジュールを立てること
給与計算は毎月決まった時期に行わなければならない業務であり、スケジュール管理が大切です。給与の支払いが遅れてしまうと、従業員が家賃や生活費などの支払いに影響を受け、信頼関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
給与計算のスケジュールでは、給与計算の対象期間を決める「締め日」と、実際に給与を支払う「支払日」が重要なポイントです。締め日と支払日の間に十分な作業時間を確保し、給与計算の手順を明確にしたうえで、計算ミスの発生や担当者の急病といった突発的なトラブルにも対応できるよう、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
給与計算の記録は保存すること
給与計算の記録は、労働基準法により賃金台帳に記載し、保存することが義務付けられています。
保存期間は原則5年間ですが、現在は経過措置として3年間とされています。ただし、今後正式に5年間へ移行することが予想されるため、早めに対応できるようにしておくと安心です。また、源泉徴収簿を兼ねる場合は保存期間が7年間となるため、適切に管理する必要があります。
保存した記録は、年末調整や各種手続きの際に使用するほか、税務調査などの場面でも重要な証拠となるため、適正に保管し、紛失や改ざんを防ぐよう注意しましょう。
源泉徴収簿についてはこちらの記事で解説しています。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算は計画的に正しい手順で行うことが大切
給与計算や給与明細の作成、給与支給などの一連の手続きは、煩雑で時間がかかる業務です。正しい知識を持ち、適切に処理しなければ、労働基準法違反に問われる恐れがあるだけでなく、従業員のモチベーション低下や生活への影響にもつながるため、細心の注意が必要です。
給与計算には明確なルールがあり、それに沿って進めることが求められます。ギリギリになってから手続きを行うと、計算ミスや給与支給の遅延につながるリスクがあるため、スケジュールを立て、余裕を持って取り組みましょう。
なお、複雑な給与計算を正確かつ迅速に行うには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は、だれでも簡単・スムーズに給与計算業務ができ、給与明細や源泉徴収票などのWeb配信も可能です。自社に合った給与計算ソフトを活用して、業務を効率よく進めましょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。