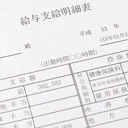給与明細書の電子化とは?メリット・デメリット、方法を解説
更新

かつては紙で作成していた給与明細書について、近年では電子化を進める企業が増えてきました。しかし、給与明細書を紙からデジタルに切り替えようと思っても、「どうやって電子化すればいいかわからない」「Web給与明細書にデメリットはないのだろうか」などと、戸惑う企業も多いかもしれません。
本記事では、給与明細書の電子化による企業側と従業員側、双方にとってのメリット・デメリット、法律で認められる電子交付の方法、給与明細書を電子化する方法とその際の注意点やおすすめのWebでの給与明細書作成ソフトなどについて解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
給与明細書をパソコンやスマートフォンで見ることが可能に
給与支払に関連する法律のうち労働基準法では、従業員への給与明細書の交付は義務付けられていません。しかし、所得税法において、給与を支払う者(企業)は支払いを受ける者(従業員)に支払明細書を交付しなければならないと定められています。
また、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料を給与から天引き(控除)した場合は、その控除額を従業員に通知することが、これらの法律によって義務付けられています。そのため、給与明細書は従業員に給与を支払う際に、必ず交付すべきものです。
そのような給与明細書を近年では、電子化する企業が増えてきています。給与明細書の電子化とは、従来は紙で従業員に渡していた給与明細書を、インターネット上で確認できるようにすることです。電子化された給与明細書(Web給与明細書)は、従業員が自分のパソコンやスマホを使って手軽にアクセスして閲覧できるようになります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
法律で認められている電子交付の方法
給与明細書の電子交付は、法律的にも認められています(所得税法231条第2項)。ただし、どのような方法でも良いわけではなく、所定の方法や手続きに従うことが求められます。国税庁が認める電子交付の方法は以下の3つです。
-
(1)電子メールで送信する方法
電子メールに給与明細書のファイルを添付し、従業員のパソコンやスマートフォン、または従業員が契約しているデータセンターなどにデータを送信する方法です。
-
(2)社内LAN・WANやインターネットを利用して閲覧を可能にする方法
企業が保有・契約するサーバーに保管された給与明細書のデータに、社内ネットワークやインターネットなどを介して従業員にアクセスしてもらう方法を指します。自社専用のポータルサイトやクラウドサービスの活用が一般的です。
-
(3)CD-ROMなどの媒体に記録して交付する方法
CD-ROMなどの記録媒体に給与明細書データを保存し、それを従業員に提供する方法です。この方法では、提供する記録媒体と従業員が所持するデバイスに互換性があるかを確認する必要があります。
一般的に採用されることが多いのは、(1)のメール送信か、(2)のネットワークを利用する方法です。特に近年では、クラウドサービスを活用する企業が増加しています。交付方法を決定する際は、自社の担当者の業務負担や従業員のデバイスの保有状況などに配慮することが大切です。
また、詳しくは後述しますが、電子交付には従業員の同意を得ることが前提になります。さらに、交付する電子データは紙に出力(印刷)できる形式であることも条件として定められています。
参照:国税庁「1. 基本的な事項」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与明細書を電子化するメリット
給与明細書を電子化すると、会社にも従業員にもさまざまなメリットがあります。どのようなメリットがあるのか、詳しく解説します。
会社側のメリット
会社側の大きなメリットは、給与明細書作成にかかわるコストと業務負担を、大幅に軽減できることです。
コスト削減
電子化によって、紙の給与明細書を作成する必要がなくなるため、ペーパーレス化が実現できます。用紙代や印刷代、封筒代なども不要になるため、コスト削減も期待できます。印刷や封入、配付にかかる作業も不要になるため、人件費の削減にもつながるでしょう。
また、複数の拠点を持っている場合や、従業員がリモートワークをしている場合、紙の給与明細書を郵送しているケースも少なくありません。Web給与明細書の場合、インターネット環境があれば離れた場所へも簡単に交付が可能です。郵送の手間やコストも不要になります。
さらに、紙の給与明細書の場合、保管スペースの確保が必要なうえ、ファイリングなどの手間も発生します。しかし、Web給与明細書ならそのような心配も不要です。従業員からの再交付依頼や過去の給与明細書の確認作業も、適切にデータ管理をしていれば迅速に対応できます。
ミスの防止
紙での給与明細書配付は手作業がメインのため、送り先の間違いや漏れ、遅れといったヒューマンエラーがどうしても発生しやすくなります。特に、別の従業員に誤って給与明細書を交付してしまうと、プライバシー保護の観点から大きな問題になりかねません。
しかし、給与明細書を電子化することで、これらのリスクを大幅に軽減できます。特に、設定した日時にデータを自動的に配信・交付できるシステムを活用すれば、給与明細書の送り忘れや遅延を防ぐことが可能です。また、配付前に複数の担当者が内容を確認・承認するワークフロー機能を活用すれば、誤記載や誤配付も未然に防げます。ミスによる手戻りの手間が減ることは、業務効率のさらなる向上につながります。
従業員側のメリット
給与明細書の電子化は、従業員にとってもさまざまなメリットをもたらします。
時間・場所を選ばず確認できる
紙の給与明細書は手元にないと確認できませんが、電子化されていれば、インターネット環境さえあればどこからでも自分の好きなタイミングで閲覧できます。出張や在宅勤務など社外で活動している従業員も、パソコンやスマートフォンを使って簡単に給与明細書を確認することができます。
管理が簡単
紙の給与明細書は毎月溜まっていくため、収納や管理の手間が発生します。しかし、Web給与明細書ならインターネット上でいつでも確認できるため、従業員が管理に気を配る必要がありません。過去の明細データも、検索機能などを活用してすぐに見つけることが可能です。
紛失リスクの低減
紙の給与明細書には、紛失や棄損のリスクがあります。紛失したり、紙が破れたりするたびに会社に再発行を依頼するのは大きな手間です。その点、オンライン上で管理するWeb給与明細書なら、紛失などの心配はありません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与明細書を電子化するデメリット
給与明細書の電子化には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。会社側、従業員側で分けて見てみましょう。
会社側のデメリット
給与明細書の電子化によって考えられる会社側のデメリットには、以下のようなものがあります。
社員への対応依頼
給与明細書を電子化するには、メール配信やWeb閲覧といった具体的な交付方法やファイルの記録方法などを伝え、あらかじめ従業員の同意を得なければなりません。特に従業員が多い企業の場合、同意を得る作業には予想外に多くの時間や労力がかかることも多いため注意が必要です。
紙と電子情報の混在
給与明細書を電子化しても、従業員から要望があった際は紙面で交付しなければなりません。そのため、データと紙の給与明細書が社内に混在することがあります。その場合、データと紙、それぞれの給与明細書の交付・管理をすることになり、担当者の手間が増えてしまう恐れがあります。
情報漏洩・データ改ざんのリスク
給与明細書をデータで管理する以上、情報の漏えいや改ざんなどを防止するために、十分な配慮が必要になります。給与明細書は従業員の個人情報です。不正アクセスなどへの技術的な対策の他、社内の管理ルールをきちんと整備し、周知徹底することが求められます。
システム導入に伴うコスト
Web給与明細書のシステムを導入するためには、初期費用やシステム利用料が発生します。また、データの管理方法やシステムの運用方法なども含め、従業員教育コストも発生します。システム導入を検討する際は、業務効率化などによるコスト削減効果と、システム導入に伴って発生するコストのバランスを意識しましょう。
従業員側のデメリット
従業員側にとっては、給与明細書の電子化にどのようなデメリットがあるのでしょうか。
閲覧用の端末が必要
Web給与明細書はインターネット上で確認するため、閲覧にはパソコンやホといった端末機器が必要です。Web給与明細書に対応可能なデバイスを持っていない閲覧者は、社内の端末機器で閲覧するか、紙に印刷することになり、かえって不便になります。端末機器自体は所持していても、従業員によっては、Webでの閲覧の仕方が分からないなどで、Webでの給与明細書に不安や抵抗感を抱く場合があります。
紙面で欲しいときは印刷が必要
例えば、住宅や車をローン契約で購入するケースなどでは、給与明細書が紙面で必要になることがあります。このような場合、収入証明書類として給与明細書の提出が要求され、該当する月の給与明細書を、会社(担当者)に依頼して印刷してもらう必要があります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与明細書を電子化するには?
給与明細書を電子化するには、システムの導入が効率的です。Web給与システムは、大きく次の3種類に分類されます。
専用型システム
手作業や別のシステムで作成した給与明細書データを取り込んで電子化し、従業員に交付するシステムです。機能がシンプルで扱いやすい一方で、給与計算自体は手作業や別のシステムで別途行わなければなりません。既になんらかの給与計算システムを導入しており、「Webによる給与明細書交付だけできればいい」という場合におすすめです。
なお、給与計算には勤怠管理、給与振り込み、税金・保険料の納付などの業務も含まれますが、以下では「支給額の計算」「明細作成」の両業務を指します。
給与計算一体型システム
給与計算から給与明細書のWeb交付までを一貫して行えるシステムです。給与明細書の作成・交付にかかる手間も削減できるため、業務効率化に役立ちます。ただし、現在使用中の給与計算システムがある場合は、新システムの導入に伴いデータなどの移行作業が発生します。
労務管理一体型システム
Web給与明細書にとどまらず、入退者手続きや社会保険の管理、年末調整にかかわる業務など、労務管理全般を一括して行えるシステムです。労務管理と給与明細書など、必要な機能のカスタマイズができ、バックオフィス業務全体の効率化に役立ちますが、多機能な分取り扱いが難しく、導入費用も高額になりがちです。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与明細書を電子化する際の注意点
給与明細書を電子化する際には、次のような点に注意が必要です。メリットを最大限活かすためにも、しっかり確認しておきましょう。
システム導入体制の整備
まずは、システム導入に対応する担当者を決めましょう。その後、既存業務の洗い出しなどを通して、導入するシステムにどのような機能が必要か、機能要件を整理します。また、システム導入が過度な負担とならないよう、予算を事前に設定しておくことも必要です。この際は、初期費用だけでなくランニングコストも考慮することが求められます。さらに、システム導入に必要なPCや端末機器の準備も忘れないようにしましょう。
機能要件の明確化は、自社に最適なシステムを導入するために重要です。必要な機能が不足している場合はもちろん、必要以上に多機能であっても費用対効果が悪くなります。過不足なく自社に必要な機能を備えており、だれでも簡単に使えるシステムを選定するのが理想です。
必ず従業員の同意をとる
前述したように、給与明細書の電子化には従業員の同意が必要です。同意を得る際は口頭のみではなく、書面や電磁的方法できちんと記録を取る必要があります。
また、電子化にあたっては、必ず事前に従業員の閲覧環境を確認しましょう。パソコンやスマホといった端末がなく、Web給与明細書を受け取れない従業員に対しては、環境整備などのサポートが必要です。
弥生では、給与明細書書電子化の同意書の無料エクセルテンプレートをダウンロードできます。ご利用いただく場合は、事前に従業員へ説明し、意思確認を行い、同意書を提出してもらうようにしましょう。無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。
セキュリティ対策の確保
給与明細書の電子化には、適切なセキュリティ対策が不可欠です。Web給与明細書システムに求められるセキュリティ機能としては、ネットワーク間の通信を暗号化するSSL暗号化通信や、IPアドレス制限などが挙げられます。
ただし、従業員のリテラシーが低いと、いくら技術的な対策を講じてもセキュリティリスクが高まることは避けられません。そのため、社内における管理ルールの策定や従業員のセキュリティ意識を高める教育も重要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与明細書の電子化の進め方
給与明細書を電子化する際は、法的な要件や自社のシステム環境、従業員の意向などに配慮しながら施策を進めることが大切です。以下の手順に沿って、計画的に取り組みましょう。
1. どこまで電子化するか範囲を決める
給与明細書の電子化を進める際には、まず電子化する範囲を明確にすることが重要です。例えば、毎月の給与明細書だけを電子化するのか、源泉徴収票の発行や勤怠管理システムから作成できる勤怠表等も電子化の範囲に含めるのかなどを検討します。なお、源泉徴収票の電子化に際しても、給与明細書と同様に従業員の承諾を得ることが必要です。
基本的に電子化は書類や業務ごとに個別対応するのではなく、1つのシステムにまとめた方が導入コスト削減につながります。運用上も、システムは可能な限り一本化していた方が効率的です。電子化の範囲にしたがって、先に紹介した「専用型システム」「給与計算一体型システム」「労務管理一体型システム」のどのタイプが適しているか検討しましょう。
また、対象範囲とともに電子交付の方法も決定しておくとスムーズです。メール配信は特別なソフトウェアがなくても手軽に導入しやすいですが、個別にファイル送信する手間がかかります。従業員数が少数であればメール配信で対応するのも良いですが、そうでない場合はシステムを導入し、Web/クラウドで閲覧する方法を採用するのがおすすめです。
2. 従業員の同意を得る
従業員からの同意は所得税法第231条第2項で定められています。具体的には、従業員に対して電子交付する書類の名称や方法、交付予定日などの詳細を通知し、書面または電磁的方法で承諾の記録を取る方式です。従業員には、電子化によって従業員がどのようなメリットを得られるかも永寧に説明しましょう。会社側の都合を一方的に押し付け、電子化を強制してはなりません。
同意を得る際には書面や社内メールを活用し、「電子交付について承諾する旨」「承諾日」「従業員の氏名」などを含む同意書を提出してもらいます。システムによっては、この同意書の提示・取得をする機能が搭載されていることもあります。もしも同意が得られなかった場合、該当の従業員には引き続き紙の給与明細書を交付するなどの対応策を用意しておきましょう。
3. 給与明細書電子化システムを選定・導入する
給与明細書を電子化する際は、自社に最適なシステムを選んで導入することが重要です。電子化に対応したシステムはさまざまな形式があるため、自社に最適なものを選べるよう、複数のシステムを慎重に比較検討することが求められます。主な比較基準は、機能、使いやすさ、既存システムとの連携性、料金、セキュリティ対策、サポートの充実度などです。既存の給与計算における業務フローとの兼ね合いや電子化したい範囲、自社が要求するセキュリティレベルなどに応じて適切なサービスを検討しましょう。
また、現在自社で使用しているシステム(給与計算システムなど)と連携可能か確認することが重要です。既存システムと互換性がない場合、余計なコストが発生したり、業務フローに無駄な手間が生じたりする恐れがあります。また、従業員が直感的に操作できる使いやすさも重要なポイントです。ITが苦手な従業員でも簡単に利用できるシステムを選ぶことで、スムーズな導入・運用が期待できます。もしも無償のトライアル期間などを提供しているシステムがあれば、本格導入前に実際に操作方法を確認しておくのがおすすめです。
さらに、料金体系の確認も欠かせません。特にクラウドサービスの場合、従業員数に応じた月額課金制や、実際に給与明細書を発行した人数に応じた課金制など、さまざまな料金体系があります。自社にとって最もコスト効率が優れたプランを選びましょう。自社でシステムの導入・運用をするのが不慣れな場合は、サポートの充実度も優先度が高い項目になります。
4. 給与明細書を配信・交付する
給与明細書の電子化システムを導入した後は、事前に従業員へ通達した方法に基づき、給与明細書を配信・交付します。メール配信、クラウド上での閲覧、専用ポータルの利用など、選択した方法に従い、予定日に合わせて確実に配信・交付できるように準備しましょう。
スムーズに運用を開始するには、システムや給与処理の担当者側の実務的な作業を進めるだけでなく、システムを利用する従業員に不明点がないか等のフォローをすることも大切です。具体的な施策としては、従業員が戸惑うことなくシステムにアクセスし、給与明細書を閲覧できるように、事前に説明会を開催したり、操作マニュアルを作って周知したりすることが挙げられます。
配信・交付の手間を減らすという意味では、クラウド給与ソフトを活用するのが便利です。この方法であれば、従業員が個別にサービスへアクセスして確認できるようになるため、担当者側の負担を大幅に軽減できます。特に「弥生給与 Next」はだれでも簡単に使えるクラウド給与計算ソフトとしておすすめです。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与明細書の電子化には給与計算ソフトの導入がおすすめ
給与明細書の電子化は、コストの削減や業務効率化、管理の簡便化などにつながる効果的な施策です。そのため、給与明細書を紙から電子に切り替えることは、会社と従業員双方にとって大きなメリットがあります。電子交付を導入するには従業員の同意が必要ですが、このメリットをていねいに説明し、従業員が前向きな気持ちでシステム導入を迎えられるようにしましょう。
電子化をスムーズに進めるコツは、自社に合ったシステムを導入することです。特に、Web給与明細書を初めて導入する企業には、給与計算から給与明細書のWeb交付まで一貫してできる給与計算ソフトがおすすめです。
「弥生給与Next」は、初めて給与計算ソフトを導入する方でも簡単に使えるクラウド給与計算ソフトです。機能はシンプルでわかりやすく、専門的な知識がなくてもかんたんに設定作業を行えます。勤怠情報を入力すれば残業代や給与支給額などは自動計算で、給与明細書の作成はラクラク。また作成した給与明細書は、Web配信で従業員のスマホ・パソコンに配布できます。さらに年末調整に必要な各種控除申告書の回収、法定調書の作成、源泉徴収票の従業員への配付もオンラインでスムーズです。便利な給与計算ソフトを活用して、給与計算と給与明細書にかかわる業務を効率化しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。