給与明細書をもらえない場合はどうする?手続きなど対処法を紹介
更新
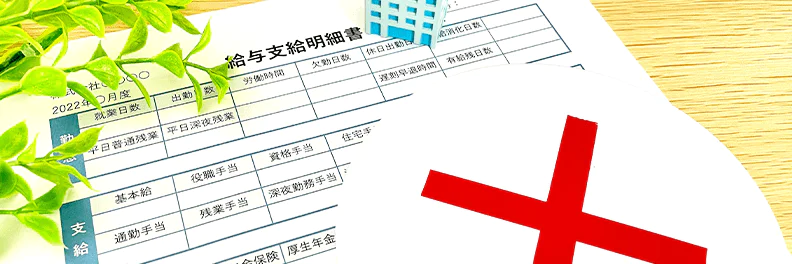
会社は、従業員に給与を支払う際に給与明細書を作成して交付します。しかし、「会社から給与明細書をもらえない」という声が聞かれることがあります。給与明細書をもらえなかった場合、どうすればいいのでしょうか。
本記事では、会社から給与明細書をもらえなかった場合の対処法について解説します。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
給与明細書の交付は会社の義務
従業員に給与明細書を交付することは、雇い主である会社の義務であり、給与明細書をもらえないことは違法です。所得税法においては、給与を支払う者(会社)は支払いを受ける者(従業員)に対して、金額など必要な事項を記載した支払明細書を交付しなければならないと定められています。
また、所得税法施行規則により、支払明細書は給与の支払いの際に交付することが定められています。給与明細書は、この支払明細書に該当する書類です。例えば、給与の支払日が10日なら、毎月10日に給与明細書の交付が必要です。
さらに、健康保険法などの法律によって、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料を給与から天引き(控除)した場合は、その控除額を従業員に通知することが義務付けられています。
雇用形態にかかわらずすべての従業員に給与明細書の交付が必要
給与明細書は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、給与を支払うすべての従業員に交付しなければなりません。「正社員には給与明細書を交付するが、パートやアルバイトには交付しない」というようなことは、法律上認められないため注意しましょう。
会社が給与明細書を交付しなかった場合は罰則がある
給与明細書の交付は、雇い主である会社の義務のため、従業員に給与明細書を交付しなかった場合は所得税法違反となり、罰則の対象となります。
給与明細書を交付しなかったり、給与明細書に虚偽の記載をしたりした場合は、所得税法により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
給与明細書についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与明細書をもらえない場合の対処法
給与明細書の発行は法律で義務付けられているため、会社などで働くほとんどの人は、給料日に給与明細書を受け取っているはずです。しかし、中には給与明細書をもらえないケースがあるかもしれません。給与明細書をもらえなかった場合は、次のような対処法があります。
会社に給与明細書の発行を請求する
給与明細書をもらえなかったとき、まず取るべき対処法は、会社に給与明細書の発行を請求することです。手違いによって給与明細書をもらえていなかった場合、上司や人事部門に問い合わせればすぐに交付されるはずです。発行が遅れている場合は、遅延の理由を確認しましょう。
労働基準監督署に相談する
会社に請求しても給与明細書が発行されない場合、労働基準監督署への相談も検討しましょう。会社が給与明細書の交付を拒む背景には、賃金未払いを隠したいなどの理由があるかもしれません。労働基準監督署に相談することで、問題を解決するための支援を受けられます。また場合によっては、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法が遵守されているか確認するために臨検などが行われる場合があります。
弁護士に相談する
労働基準監督署に相談しても問題が解決しない場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談するのも1つの方法です。弁護士に依頼すると、給与明細書の交付や未払い賃金の支払いなどについて、会社に直接請求できます。所得税法や労働基準法などの法令に基づき、より具体的な解決策を探すことができるでしょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与明細書の交付方法は2種類ある
給与明細書の交付方法には「紙」と「電子データ」の2種類があります。従来は紙での交付が一般的でしたが、近年では、電子データで給与明細書を交付する企業も増えています。
紙の場合
紙の場合は、印刷した給与明細書を書面で従業員に交付します。以前から一般的に行われてきた交付方法ですが、印刷、封入、郵送の手間とコストがかかります。また、給与明細書を作成する部署と離れた場所に店舗や事務所があったり、在宅勤務やテレワークを導入していたりする場合は、給与の支払日までに確実に従業員の手元に届くようにしなければなりません。
電子データの場合
電子データの場合は、電子メールでの送信、社内ネットワークやインターネットなどを通して、給与明細書のデータを交付します。2006年に行われた税法改正により、2007年1月1日から、電子データによる給与明細書の交付が認められるようになりました。人件費やコスト削減、紛失などのリスク軽減の観点から、給与明細書を電子化する会社は増えています。ただし、給与明細書を電子データで交付するには、従業員の同意が必要です。また、従業員から請求があった場合は、紙の給与明細書を交付しなければなりません。
給与明細書の電子データ化についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与明細書に記載されている内容
給与明細書の記載内容は、企業によって多少異なる場合もありますが、基本的には「勤怠」「支給」「控除」の3つの欄で構成されています。なお、給与明細書の書式については、法律などによる定めはありません。勤怠欄、支給欄、控除欄には、主に以下のような内容が記載されます。
勤怠欄
勤怠欄には、従業員の出勤日数や欠勤日数、労働時間、残業時間など、給与計算の根拠になる勤怠情報が記載されます。就業規則や労働契約で定められた就業日数と、実際に出勤した日数、残業時間がそれぞれ記載されているので、給与明細書を受け取ったら、タイムカードなどと照らし合わせて誤りがないかを確認しましょう。
支給欄
支給欄には、基本給をはじめ、残業手当や通勤手当、資格手当といった各種手当など、会社から支給される金額が記載されます。実際の残業どおりに残業手当が支給されているか、その他の手当に間違いはないかなどを確認することが大切です。
残業代の計算方法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
手当についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
控除欄
控除欄には、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)や雇用保険料、労災保険料、所得税、住民税など、給与から差し引かれる金額が記載されます。社会保険料や税金は、控除額の計算方法がそれぞれ定められています。
社会保険料の計算方法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
所得税の計算方法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
会社に給与明細書の保管義務はない
法律では、会社に対して給与明細書の保管義務は定められていません。ただし、給与計算の根拠になる書類や給与明細書の記載項目をまとめた書類は、一定期間の保管が義務付けられています。
5年の保管義務が定められている書類の一例
以下の書類は、労働基準法において5年間の保管が義務付けられています。以前は保管期間が3年でしたが、労働基準法の改正により2020年4月から5年に延長されました(法改正の経過措置として当分の間は3年)。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 労働者名簿 | 従業員の氏名、生年月日、住所、性別などの情報を記載した書類。会社の規模にかかわらず、従業員を1人でも雇い入れている場合は必ず作成しなければならない法定帳簿の1つ |
| 賃金台帳 | 従業員の氏名や労働日数、賃金の計算期間など、給与の支払い状況を記載した書類。労働者名簿と同じく法定帳簿の1つ |
| 雇い入れに関する書類 | 雇入決定関係書類、雇用契約書、労働条件通知書、履歴書など雇い入れに関する書類 |
| 解雇に関する書類 | 解雇決定関係書類や解雇予告除外認定関係書類など解雇に関する書類 |
| 災害補償に関する書類 | 労災(労働災害)に当たるケガや病気の診断書のほか、補償の支払いに関する書類、領収関係書類などを指す |
| 賃金に関する書類 | 賃金決定関係書類、昇給・減給関係書類など賃金に関する書類 |
| 労働関係に関する重要な書類 | 出勤簿、タイムカードの記録など。出勤簿は、従業員の出勤日や労働日数、出社・退社時刻などを記載した帳簿で、労働者名簿、賃金台帳と並ぶ法定帳簿の1つ |
その他、労使協定の協定書、各種許認可書、退職関係書類、休職・出向関係書類なども5年間の保管が必要でしょう。
7年の保管義務が定められている書類の一例
給与に関係する書類のうち、下記は国税通則法により7年の保管が義務付けられています。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 所得税の扶養控除などを受けるために従業員が提出する書類。給与所得のある従業員は、アルバイトやパートを含め提出が必要 |
| 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書の4つを1つにまとめた書類。年末調整で保険料控除や配偶者控除(配偶者特別控除)を受けるため、従業員は申告書を提出する必要がある |
給与明細書の保管についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算ソフトを使って給与明細書の発行・交付を円滑に
給与明細書の発行・交付は会社の義務のため、従業員に給与を支払う際には、必ず発行しなければなりません。また、給与明細書を作成するには、給与計算を正しく行うことが前提となります。しかし、支給額や控除額の計算を手作業で行っていると、ミスが起こりがちです。給与明細書を間違いなく、スピーディーに作成するには、給与計算ソフトの活用がおすすめです。
「弥生給与 Next」は、給与支給額の自動計算はもちろん、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しており、給与計算や年末調整業務の効率化に役立ちます。自社に合った給与計算ソフトを活用して、業務の効率化を目指しましょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。


