年末調整時の定額減税(年調減税)とは? 書き方やチェックすべきポイント
監修者: 高崎 文秀(税理士)
更新
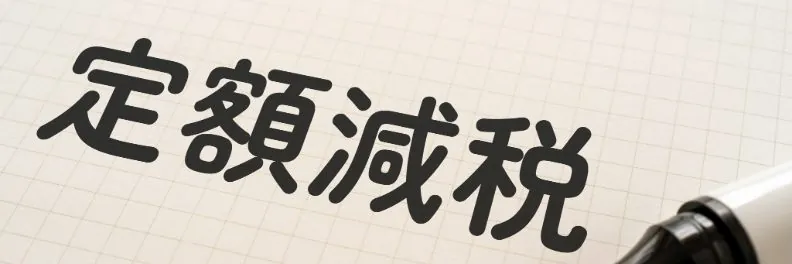
2024年(令和6年)6月に定額減税が施行されました。給与計算業務を担当する方は、定額減税が年末調整業務におよぼす影響や、対象者の確認方法など、さまざまな疑問を抱いているかもしれません。
定額減税には、毎月処理する「月次減税」と年末調整時の「年調減税」の2つがあります。本記事では、年末調整における税額の清算方法である年調減税に焦点をあて、定額減税の概要や年調減税事務の手順、給与計算で注意すべきポイントのほか、源泉徴収票への記載方法を解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
年末調整時の定額減税(年調減税)とは
定額減税とは、2024年(令和6年)6月に施行された制度であり、納税者本人、配偶者、および扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除される2024年(年度)限定の措置のことです。
定額減税は、正社員やパート・アルバイトなどで雇用されている方や、自営業者、年金受給者などを含めた所得税・住民税を納めている方が対象です。これにより、従業員に対して給与を支払う会社側は、定額減税額を差し引いて個々の給与や納税額を計算しなければなりません。
定額減税額を差し引く処理は、6月1日以降の最初の給与もしくは賞与の計算時に行う「月次減税」と、年末調整時に行う「年調減税」の2種類があり、給与担当者はこれらを正しく理解する必要があります。
定額減税の対象となる従業員に対して、会社は原則として月次減税による処理を行います。ただし、月次減税の対象にならないなどのやむを得ないケースでは、年末調整時に年調減税の処理を行うことも可能です。
定額減税について詳しくはこちらをご覧ください。
定額減税の対象となる人
定額減税の対象となるのは、以下の条件を満たした方です。
-
- 国内に住所を有する方、もしくは現在まで1年以上国内に居住している方
- 2024年(令和6年)分の所得税および令和6年度分の住民税の納税者
- 2024年(令和6年)分における、給与や給与外のものも含む合計所得金額が1,805万円以下(収入が給与のみの場合は所得が2,000万円以下)の方
定額減税は、所得税を納める方が対象となっています。小学生や中学生など無収入の子どもについては、親の扶養親族として一人当たり30,000円が、親の控除として適用されます。
定額減税の金額
定額減税では、すべての対象者が一律の金額で所得税と住民税の減税を受けます。減税金額は次のとおりです。
-
- 納税者本人:所得税30,000円、個人住民税所得割10,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族 :1人につき所得税30,000円、個人住民税所得割10,000円
定額減税においては、納税者本人のみならず、同一生計配偶者や扶養親族も対象に含まれます。そのため、人数分を合計した額が納税者本人の所得税や住民税から控除されます。
例えば、Aさんに配偶者と扶養親族が2人いる場合、Aさんの所得税から差し引ける定額減税額は30,000円×4人=120,000円、住民税の定額減税額は4人×10,000円=40,000円です。
定額減税の4万円について詳しくはこちらをご覧ください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
年調減税事務の手順
年調減税に関する詳細については、最新情報を国税庁のホームページ内に設置されている「年末調整がよくわかるページ」で確認できます。年末調整業務を実施する前に、必ず最新の情報を確認し、適切な手続きを行いましょう。
-
参照:国税庁「源泉徴収義務者の方-年末調整に関する情報
」
参照:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
1.対象者を確認する
年調減税事務では、定額減税額に基づいて年末調整時に所得税額の計算を行います。計算するうえで、まず対象者を確認しましょう。
基本的には、年末調整の対象者が定額減税の対象者です。なお、年末調整の対象者であっても、給与所得以外の所得を合計した⾦額が1,805万円を超える場合は対象外です。基礎控除申告書を確認し、該当する場合は年調減税額を控除せず、例年どおりの年末調整を⾏います。また、給与収入のみで2,000万円を超える場合は年末調整そのものが対象外となり、従業員本人による確定申告が必要です。
2.年調減税額を計算する
次に、年調減税額の計算を行います。定額減税を受ける同一生計配偶者の有無、扶養親族の人数を正しく把握したうえで計算しましょう。「扶養控除等申告書」あるいは「配偶者控除等申告書」を用いて人数を確認し、30,000円×人数の計算式で所得税の合計減税額を算出します。
例えば、本人と同一生計配偶者のみの世帯では所得税の定額減税額は30,000円×2人=60,000円です。本人と同一生計配偶者に加え、扶養親族が3人いる場合は30,000円×5人=150,000円です。
3.年調減税額の控除を行う
年調減税額および年調所得税額を算出したのちに、年調減税額を控除します。計算を行う際は、定額減税に対応した給与計算ツールを用いるほか、国税庁の「年末調整計算シート」あるいは「令和6年源泉徴収簿」を活用しましょう。
年調所得税額から年調減税額を差し引き、102.1%を乗じると復興特別所得税(所得税×2.1%)が含まれた所得税額を算出できます。その後は、通常の年末調整の手順に沿って最終的な税額を算出してください。
【計算式】(合計所得税額-年調減税額)×102.1%=所得税額(復興特別所得税を含む)
なお、扶養親族の数が多いなどの理由で年調所得税額から引ききれないケースも考えられます。このようなケースでは、年末調整計算シートや源泉徴収簿に記載しなければなりません。年末調整計算シートは「控除外額」の欄に、源泉徴収簿の場合は「年調所得税額」の欄に控除しきれなかった差額を記入しましょう。
-
参照:国税庁「年末調整計算シート(令和6年用)
」
参照:国税庁「令和6年分源泉徴収簿」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
年調減税の源泉徴収票への書き方
年末調整の際に定額減税を処理する年調減税では、定額減税で控除された額を源泉徴収票に記載しなければなりません。源泉徴収票への書き方は次のとおりです。
年調減税を行った場合
給与収入2,000万円以下に該当し、年末調整の必要がある源泉徴収票には、年調減税額を記入します。具体的には、源泉徴収票下部にある(摘要)の欄に「控除した合計の年調減税額」と併せて「控除外額」を記載します。仮に定額減税額が30,000円だった場合、適用欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額30,000円 控除外額0円」と書き記しましょう。
もし、源泉徴収した所得税から定額減税額の全額を差し引けなかった場合には、その金額を「控除額〇円」と記載します。例えば、Aさんの給与から源泉徴収されている所得税の合計が100,000円、定額減税の額が120,000円の場合には、控除しきれない20,000円が残ります。この場合「源泉徴収時所得税減税控除済額100,000円 控除外額20,000円」と記載し、控除されていない残りの額を示さなければなりません。
年調減税を行わなかった場合
給与収入が2,000万円を超えている方は、年末調整および年調減税の対象外です。このように、年調減税を行わなかった場合、源泉徴収票の摘要欄へ定額減税に関する記載は必要ありません。例年どおりに「源泉徴収税額」の欄へ、実際に源泉徴収した合計の税額を記載しましょう。既に月次減税している場合は、月次減税で控除した額を加味して源泉徴収の合計額を記載してください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
詳しい手続きは国税庁の公式ホームページで確認を
年調減税に関する詳細については、最新情報を国税庁のホームページ内に設置されている「年末調整がよくわかるページ」で確認できます。年末調整業務を実施する前に、必ず最新の情報を確認し、適切な手続きを行いましょう。
-
参照:国税庁「源泉徴収義務者の方-年末調整に関する情報
」
参照:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
年末調整時の定額減税についての注意点
年末調整や控除額の計算には、従業員の所得が深くかかわります。そのため、対象者や計算に間違いがないように十分注意しましょう。
従業員に給与以外で所得があるか確認する
合計した所得金額が1,805万円を上回る(給与収入のみの場合は2,000万円を超える)場合、年末調整時の定額減税は対象外です。そのため、副業収入や不動産所得など、給与以外の所得があるかどうか確認しなければなりません。
なお、上のように定額減税の対象外となる場合でも、月次減税では、いったん対象者として計算します。しかし、定額減税そのものが対象外であるため、月次減税をしたのちの年末調整もしくは確定申告により再調整を行います。
新しく従業員が加わる場合は入社日を確認する
新入社員の月次減税ができるかどうかは入社日によって判断されます。2024年(令和6年)6月1日時点で在籍している従業員が月次減税の対象になるため、6月2日以降に入社した場合、6月分の給与支払いが発生したとしても月次減税の対象外です。
このようなケースでは、月次減税ではなく、年調減税を適用して対応するようにしましょう。年末調整時に、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書を提出してもらい、定額減税額を計算します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算ソフトで年調減税をスムーズに進めよう
定額減税は、期間が限定された特別措置となるため、普段とは異なる計算や事務手続きに戸惑う給与担当者も少なくないでしょう。また、年末調整業務そのものも、多くの企業にとって負担となりがちな業務の1つです。
定額減税にかかわる業務の効率化には、給与計算ソフトの導入がおすすめです。 「弥生給与 Next」は給与計算や年末調整、給与・賞与明細書の作成と配付を効率化するクラウド給与ソフトです。
「弥生給与 Next」では、2024年(令和6年)度の税制改正で実施されている定額減税に対応しています。不慣れな月次減税時の税額計算を自動で行えるほか、税務署や自治体へ提出する法定調書の作成にも対応しています。条件や計算が複雑になるケースもある定額減税ですが「弥生給与 Next」を活用すれば、だれでも簡単に給与計算を行えます。また、計算ミスや記載ミスといった不備を大幅に軽減できるため、業務の負担や作業に対するプレッシャーを軽減できるのも大きなメリットです。自社に合わせた給与計算ソフトで年末調整業務の効率化を目指しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者高崎 文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。






