年収の壁とは?4つの壁と税制改正での変更点について解説
更新
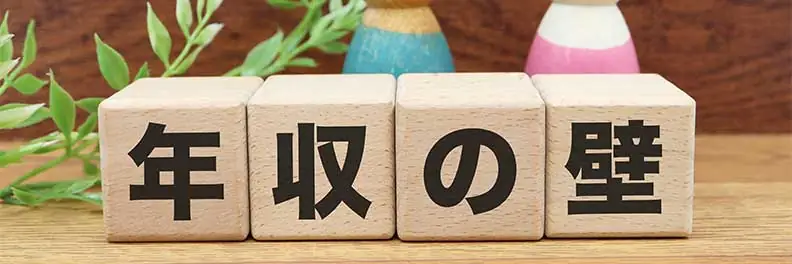
年収の壁とは、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が発生する境界線を指します。特にパート・アルバイトをしている方やその家族、給与計算担当者にとって非常に重要なポイントです。
2025年度の税制改正では、年収の壁を意識せずに働きやすくするため、「103万円の壁」が160万円まで引き上げられるなど、さまざまな変更点があります。本記事では、年収の壁の種類や税制改正の変更点について詳しく解説します。
※本記事は2025年3月28日時点の情報を基に制作しており、今後変更される可能性があります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
年収の壁とは税や社会保険の負担が発生する境界線
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する境界線を指します。収入が一定額を超えると、それぞれ住民税・所得税の課税や社会保険料の負担が発生もしくは増加し、手取り収入に影響を及ぼします。額面年収が増えても、手取り収入が減少する場合があるため、特にパートやアルバイトで働く人にとっては注意が必要です。
年収の壁は、税金に関する「100万円の壁」「103万円(令和7年度税制改正で160万円へ引き上げ)の壁」と、社会保険に関する「106万円の壁」「130万円の壁」の4つに分けられます。
税金に関する壁では、年収が一定額を超えると住民税や所得税が発生します。その一方で、社会保険に関する壁では、年収が基準を超えると扶養から外れ、厚生年金や健康保険への加入が義務付けられるため、保険料が引かれて手取り収入が減少します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
4つの年収の壁について詳細を解説
ここでは、「100万円」「103万円(令和7年度税制改正で160万円へ引き上げ)」「106万円」「130万円」の4つの壁について詳しく解説します。
100万円の壁を超えると住民税が発生する
パートやアルバイトなどで得た年収が約100万円を超えると、住民税の課税対象となります。住民税は居住地の自治体が徴収するもので、課税基準は自治体によって異なるため、「約100万円」という表現が使われます。
年収が100万円以下であれば住民税は課されず、収入が増えた分だけ手取りも増加します。しかし、100万円を超えると住民税の負担が発生し、収入が増えてもその分が手取りに反映されにくくなります。
住民税の計算方法や納税方法などについて、こちらの記事で解説しています。
103万円(160万円へ引き上げ)の壁を超えると所得税が発生する
年間の給与収入が103万円を超えると所得税の課税対象となっていました。改正前は基礎控除額(48万円)と給与所得控除額(55万円)を合計した金額が103万円であったことに基づいています。
2025年度の税制改正により、労働力不足や物価上昇への対応のため、課税最低ラインが引き上げられました。
具体的には、基礎控除が48万円から58万円へ、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ拡大され、課税最低ラインは123万円になります。さらに、年収200万円以下の人には基礎控除がさらに37万円上乗せされ95万円となることで、課税最低ラインが160万円に引き上げられます。
税制改正による年収の壁に関する変更点について、詳しくは後述します。
所得税の計算方法はこちらの記事もご覧ください。
106万円の壁とは社会保険に関係する1つめの壁
年収が106万円以上になると、一定の要件を満たす場合に社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。その結果、保険料負担が発生するため、106万円の壁と呼ばれています。具体的には以下の要件をすべて満たすと、社会保険への加入が必要になります。
-
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 学生ではない
- 従業員51人以上の企業で働いている
年収106万円を超える場合、所得税や社会保険料の負担増により手取り額が減少するケースがあるため、この金額を意識して、労働時間を調整する動きが見られることがあります。
そのため、厚生労働省は、いわゆる「106万円の壁」への対策を進めています。2023年には、年収106万円を超えたことで手取りが減少するパート・アルバイトなどの短時間労働者を支援するため、企業に対し一人あたり最大50万円を支給する「年収の壁・支援強化パッケージ」を導入しました。
また、現在の「年収106万円以上」という社会保険加入の賃金要件の撤廃が検討されており、週20時間以上働くすべての労働者が、賃金額に関係なく社会保険に加入する方向で調整が進められています。ただし、制度の具体的な内容や開始時期については、今後の検討状況によって変更される可能性があります。
参照:厚労省「社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について」
130万円の壁とは社会保険に関係する2つめの壁
年間の収入が130万円以上になると、社会保険の扶養対象から外れ、自分で国民年金や国民健康保険に加入しなければなりません。この境界線が130万円の壁と呼ばれます。保険料を負担することによって、手取り収入が減少する場合があり、年収が130万円を超えないよう労働時間を調整する働き方を選ぶ人も少なくありません。
保険料は居住地や年齢によって異なりますが、月額約2万~3万円程度の負担が生じる場合があります。その結果、年収が130万円をわずかに超えても、手取りが減る「逆転現象」が発生することがあります。ただし、わずかに超える程度であれば、事業主の証明により社会保険への加入を免除される救済措置が適用されることがあります。
年収を130万円未満に抑えるための目安は、月収換算で約10万8,333円です。また、繁忙期の一時的な収入増で130万円を超えた場合は、事業主による証明をもとに、引き続き扶養認定が可能となるしくみが設けられています。ただし、最終的な扶養認定の判断は保険者(健康保険組合や協会けんぽ等)が行うため、事業主が証明した場合でも、扶養として認定されないことがあります。このしくみを活用すれば、労働者の手取り減少を抑えられます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
年収の壁の問題点
「年収の壁」の最大の問題は、収入が一定額を超えると税や社会保険料の負担が発生し、手取り収入が相対的に減少してしまう点です。多く働いたにもかかわらず手取りが減ってしまうケースもあり、家計への影響は小さくありません。
このような「年収の壁」を意識することで、「壁を超えない範囲で働く」といった“働き控え”の行動が見られることも課題です。例えば、パートタイマーやアルバイトの方が年収の壁を超えないように勤務時間を調整することで、結果的に収入が頭打ちとなり、労働意欲の低下や社会全体の労働力供給の減少につながる恐れがあります。
さらに近年では、最低賃金が上昇し時給が増加している一方で、年収の壁自体は据え置かれているため、働ける時間を短くし、収入を抑えるような働き方を選択する方もいるでしょう。その結果、実質的な年収の増加が見込めず、家計の改善にもつながりにくい状況が続いています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「令和7年度税制改正大綱」および税制関連法案修正可決による年収の壁の変更点
2024年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が公表され、その後、与野党の協議を経て、2025年度予算案および税制関連法案の修正案が衆議院で可決されました。今回の改正では、特に「年収の壁」に関する見直しが盛り込まれています。
所得税の課税最低ラインが103万円から160万円に引き上げ
「令和7年度税制改正大綱」により、これまでの103万円の壁が160万円に拡大されます。従来は、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円が課税ボーダーラインでしたが、改正により基礎控除と給与所得控除が引き上げられます。
-
- 従来:基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円
- 当初予定(「令和7年度税制改正大綱」公表時):基礎控除58万円+給与所得控除65万円=123万円
- 衆院可決後(2025年3月時点):基礎控除が年収に応じて変動し、最大160万円まで課税ボーダーラインが拡大
| 年収(給与所得者) | 基礎控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 95万円 |
| 200万円超~475万円 | 88万円 |
| 475万円超~665万円 | 68万円 |
| 665万円超~850万円以下 | 63万円 |
年収200万円以下の給与所得者は基礎控除が95万円まで引き上げられ、給与所得控除65万円とあわせて160万円まで所得税が生じません。年収が上がるにつれて基礎控除額は段階的に減少します。
ただし、年収200万円超~850万円以下の給与所得者に対する基礎控除の上乗せは、政府が「賃金上昇が物価上昇に追いつくまでの措置」と説明しており、2025年と2026年の2年間限定です。その一方で、年収200万円以下の場合は恒久的な措置とされています。
今回の改正により、年収103万円以下に抑えるための働き控えが緩和される可能性があります。しかし、基礎控除の変動や2年間限定措置には注意が必要です。
参照:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
配偶者特別控除における控除額減少の開始年収が150万円から160万円に変更
2025年度税制改正により、配偶者特別控除にかかわる年収要件が150万円から160万円に変更されました。主にパートなどで働く配偶者を扶養する納税者の税負担を軽減することを目的としており、103万円の壁の引き上げに連動して適用範囲が拡大しています。変更内容は以下のとおりです。
-
- 控除額の満額38万円は従来どおりで、配偶者の年収が160万円以下の場合に適用される
- 配偶者の年収が160万円を超えると控除額が段階的に減少し、201万円を超えると控除が受けられなくなる(通称201万円の壁は変更なし)
従来は、配偶者の年収が150万円を超えると控除額の逓減が開始されていましたが、変更後は、逓減の開始額が160万円になります。世帯全体の手取り収入が増える可能性が広がり、特に扶養内で働いている配偶者の収入増加が家計にプラスの影響を与えることや、150万円の壁を気にした働き控えの行動を緩和する効果が期待されています。
特定扶養控除の拡充と特定親族特別控除の導入
令和7年度税制改正により、大学生年代の子どもを扶養する親向けの「特定扶養控除」が拡充され、新たに「特定親族特別控除」が導入されました。扶養家族の収入増加による控除額の急激な減少を緩和し、世帯全体の手取りを安定させることを目的としています。
- ・特定扶養控除の拡充
従来、特定扶養控除は子どもの年収が103万円を超えると適用外となり、親は63万円の控除を受けられませんでした。しかし、今回の改正により、年収要件が150万円に引き上げられました。子どもの収入が増えても控除を受けられる範囲が広がり、親の税負担が軽減されます。
- ・特定親族特別控除の導入
さらに、特定親族特別控除が新設され、子どもの年収が150万円を超えても控除額が段階的に減るしくみが導入されます。
| 子の年収 | 親の控除額 |
|---|---|
| 150万円 | 63万円 |
| 160万円 | 51万円 |
| 170万円 | 31万円 |
| 188万円超 | 0円 |
このしくみにより、子どもの収入増による急激な控除喪失を避けられます。
- ・制度変更の背景と効果
この改正は、少子高齢化による労働力不足への対応策として実施されます。これまで学生は扶養控除を維持するために労働時間を調整していましたが、要件が緩和されたことにより、学生の就労時間や収入の増加が期待されます。結果として、学生自身の手取り額アップと企業の人手不足解消につながる可能性があります。
参照:財務省「令和7年度税制改正の大綱の概要」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
【早見表】年収の壁の一覧
年収の壁は、手取り収入や扶養控除などにかかわる重要な境界線であり、それぞれが異なる税制や社会保険制度に関連しています。年収ごとにどの壁が影響を与えるのかは、以下の表のとおりです。
なお、「令和7年度税制改正大綱」により、103万円の壁と150万円の壁の上限が引き上げられています。詳しくは上述のとおりです。
| 年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円以下 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | ー |
| 100万円 | 対象 | ー | |||
| 103万円 | 対象 | 対象外 | 対象 | ||
| 106万円 | 要件を満たせば加入義務あり | ||||
| 130万円 | 加入義務あり | ||||
| 150万円 | 対象外 | ||||
| 201万円以上 |
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算・年末調整業務の負担は給与計算ソフトで軽減しよう
年収の壁は、一定の収入を超えると税負担や社会保険料が発生し、かえって手取りが減少する境界線です。これまで100万円、103万円、106万円、130万円の壁がありましたが、令和7年度税制改正により、所得税の課税最低ラインが最大160万円に引き上げられるなど、大きな変更が行われます。
税制改正による各壁の見直しは、働き控えの解消を目指した重要な一歩です。所得税課税最低ラインの引き上げや控除範囲の拡大は、世帯全体の手取りを改善し、働きやすい環境づくりに寄与することが期待されています。
税制改正に伴う変更により、給与計算や年末調整の業務負担が増すと考えられます。そこで活用したいのが「弥生給与 Next」です。複雑な税制変更にも自動で対応するため、業務を効率的に進めることができ、企業にとって大きな負担軽減につながります。自社に合ったツールを活用して、業務の効率化を目指しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。








