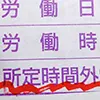就業規則とは?作成義務が生じる条件や記載事項などを解説
更新
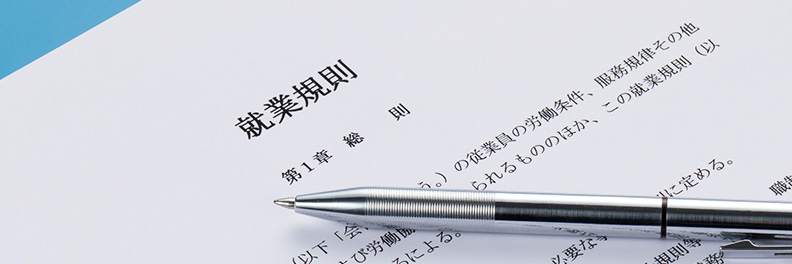
就業規則を作成しようとしても、どのように作成すればいいのか、頭を悩ませる企業経営者や担当者も多いかと思います。就業規則の作成は法律で義務付けられているため、対象となる企業は必ず整備しなければなりません。従業員が安心して働ける環境を提供するためにも、企業は適切な就業規則を整備する必要があります。ただし、就業規則の作成や見直しは、正しい知識と手順で進めることが重要です。
本記事では、就業規則の基礎知識から記載が必須の事項、作成の流れなどをまとめました。また、就業規則の作成や見直しにおける注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
就業規則とは労働条件や職場内でのルールを明記した規則集
一定の条件を満たす企業は労働基準法により必ず就業規則を作成しなければならないと定められています。職場で守るべきルールが定められていない場合、さまざまなトラブルを招きかねません。社内の風紀を乱すだけでなく、組織に不利益をもたらすリスクも考えられます。明確な就業規則を定め、従業員がそれを守ることで労使間トラブルの回避につながり、安心して働ける職場環境が実現します。
なお、就業規則を新たに作成したり、内容の変更をしたりするときは、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。その際、組合または従業員の過半数代表者からの意見書を添付する必要があります。この意見書は、労働者の代表から聴取した意見を記載した文書であり、法律で提出が義務付けられています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
就業規則の作成義務が生じる条件
パートやアルバイトを含め、常時10人以上の労働者を雇用する事業場は、就業規則を作成・届出する義務があります。
全社で10人以上ではなく、事業場ごとに10人以上という決まりがあります。そのため、10人未満の事業場が複数ある企業では、該当の事業場では就業規則を作成・届出する義務はありません。ただし、昨今は労務トラブルが増加傾向にあるため、10人未満の事業場であっても就業規則の作成が推奨されています。
なお、就業規則の作成は労働基準法第89条で定められています。対象となる企業は就業規則の作成が必要です。作成を怠った場合、同法第120条第1号の規定に則り、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
参照:e-GOV「労働基準法第89条」
参照:e-GOV「労働基準法第120条」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
就業規則に記載する事項
就業規則の記載内容は、「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」「任意的記載事項」の3項目に分けられます。記載すべき内容が網羅されているかどうか、改めて確認してみましょう。
絶対的必要記載事項
絶対的記載事項とは、就業規則に必ず記載しなければならない事項で、就業規則を作成するすべての企業が明記しなければなりません。記載すべき項目は以下のとおりです。
- (1)労働時間および休日、休暇に関する事項
- 始業および終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇(年次有給休暇を含む)
- 交替制の場合の就業時転換に関する事項
- (2)賃金に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払の方法
- 賃金の締切りおよび支払の時期
- 昇給に関する事項
- (3)退職、解雇に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらは、労働基準法第89条に基づき、就業規則に明記することが求められています。
労働時間および休日、休暇に関する事項
始業時間や終業時間が何時なのか、休憩時間が何時から何時なのかといった労働時間に関する事項を、就業規則に明記します。所定労働時間や、始業時間と終業時間の定義も必要に応じて記載しましょう。また、法定休日および法定外休日(所定休日)も明記が必要です。年末年始休暇やお盆休みなどがある場合も記載しなければなりません。有給休暇も同様に、付与条件と日数、付与されるタイミング、取得する方法、有効期限などを記載します。
工場などのように、常に誰かが稼働し続けなければならない施設を持つ企業では、従業員が交代で勤務するケースが一般的です。このような場合、変形労働時間制の該当の有無や、それぞれのシフトの始業時間と終業時間、休憩時間、シフトの確定時期などを明記しなければなりません。
賃金に関する事項
賃金をどのように決定しているのかも就業規則に明記が必要です。賃金の内訳、手当の種類、割増賃金の詳細、控除する金額、計算方法、支払方法(現金支給、振込支給)などを詳しく記載します。また、賃金の計算期間や締め日、いつ支払われるのかも記載しましょう。賃金については項目が多岐に渡るため、別紙として賃金規程を作成することもあります。
退職、解雇に関する事項
従業員がどのような場合に退職、解雇となるのかを、ケース別に就業規則に記載します。問題のある従業員に対し、制裁(ペナルティ)などの就業規則に基づいた対応をとるために、しっかりと記載しておきましょう。
相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、以下のような就業規則を定める事業場において「ルールを設けるのであれば、必ず記載しなければならない事項」のことです。
| 退職手当や臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項 | 退職金が支払われる場合、就業規則に退職金の算出方法や支払い対象者、支払い時期などの記載が必要です。また、賞与などの臨時賃金の支払いを行う場合や、最低賃金額を定める場合、決まりを明記しましょう。 |
|---|---|
| 食費、作業用品などの負担に関する事項 | 業務上で、従業員が食費や作業用品などを自己負担しなければいけない場合、負担額や負担方法などを就業規則に明記します。 |
| 安全衛生に関する事項 | 従業員が労働安全衛生法に定められた安全衛生を守るべき場合も、就業規則に記載が必要です。 |
| 職業訓練に関する事項 | 従業員に職業訓練を義務付ける場合は、研修制度の詳細などの職業訓練を行う際の決まりを就業規則に明記します。 |
| 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 | 災害時や業務外で病気やケガをした際の手当を用意している場合は、就業規則に対応方法や補償などの明記が必要です。 |
| 表彰、制裁に関する事項 | 表彰や制裁などを行う場合、就業規則に対象者や表彰方法の他、制裁制度の種類や内容などを明記します。 |
| その他全労働者に適用される事項 | 上記以外にもルールを設けている場合は、就業規則に記載する必要があります。例えば、休職や出向、出張規定など、全労働者に影響する決まりがある場合は明記しましょう。 |
任意的記載事項
任意的記載事項は、就業規則に記載するかどうかを企業の判断で決められる事項です。法的に記載が義務付けられているものではありません。ただし、記載することで従業員や企業にとってメリットがある場合は、積極的に活用しましょう。具体的には、企業理念や社訓、人事に関する規程などが該当します。ただし、独自の休暇制度、住宅手当の支給、人間ドック受診の補助など、法定を上回る福利厚生(法定外福利厚生)などを導入しており、のちに廃止する場合、従業員にとって不利益変更となるため注意が必要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
就業規則を作成する際の流れ
就業規則は、企業経営の実態に応じて整備する必要があります。それを踏まえ、ここでは就業規則作成時における流れを紹介します。
-
1.就業規則の原案を作成する
-
2.従業員に原案の内容を周知し、連絡する
-
3.従業員代表者を選任する
-
4.従業員代表から意見聴取する
-
5.従業員代表の意見書をまとめて所轄の労働基準監督署に届け出る
-
6.就業規則を従業員に周知する
スムーズに就業規則を作成できるよう、上記の流れで取り組んでみましょう。
1. 就業規則の原案を作成する
まずは、就業規則の原案を作成します。就業規則には必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、定めがある場合に記載が義務付けられている相対的必要記載事項があります。漏れがないよう注意しましょう。厚生労働省が提供している無料のテンプレート、「モデル就業規則」を参考にすると、法的に記載が義務付けられている内容を網羅しやすくなります。
自社での作成が難しい場合や、法律に詳しい人材がいない場合は、社会保険労務士をはじめとする専門家に相談・作成依頼するのがおすすめです。
2. 従業員代表から意見聴取する
作成した就業規則原案を、全社的に公開し周知した後に、専任された従業員代表へ確認してもらい、意見を聴取します。従業員代表とは、従業員の過半数で組織される労働組合です。労働組合がない場合は、従業員の過半数を代表する者を指します。この代表者は、投票や挙手など民主的な方法で選出する必要があり、企業側が指定することはできません。
3. 従業員代表の意見書をまとめて所轄の労働基準監督署に届け出る
従業員代表は、企業の代表取締役宛ての意見書を作成します。意見書には、意見聴取が行われた日付、就業規則に対する従業員代表の意見、従業員代表の氏名または労働組合の名称、従業員代表の選出方法を記載します。意見書のフォーマットに決まりはありませんが、厚生労働省のホームページからフォーマットをダウンロードすることも可能です。
参照:厚生労働省「様式集」
企業は作成した就業規則に意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出ます。就業規則に対する反対意見が意見書に記載されていても、届出は受理されます。ただし、反対意見が記載されている場合は、後のトラブルを防ぐためにも精査し、必要に応じて規則の見直しを行うことをおすすめします。また、労働条件の不利益変更となるような内容が含まれる場合は、労働基準法上の制限や、個別の労働契約との関係に注意が必要です。労働条件の不利益変更については、原則として労働者の同意が必要となります。
4. 就業規則を従業員に周知する
就業規則は、従業員がいつでも確認できるような体制を整える必要があります。周知の方法として、社内掲示板に掲示したり、データとして社内システムで閲覧可能にしたりする方法があります。
就業規則の周知が徹底されていない場合、「周知義務違反」とみなされることがあります。この場合、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けるだけでなく、場合によっては罰金が科されることもあるため、注意が必要です。従業員がどこで就業規則を確認できるかを明確に伝え、周知徹底を図りましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
就業規則の作成費用の相場
就業規則の作成は、専門家へ依頼できます。特に社会保険労務士(社労士)に依頼するケースが多く、費用は一般的に15~50万円程度が相場とされています。ただし、規定内容が多岐にわたる場合や特別な事情がある場合、費用が50万円以上になることもあります。費用は依頼先や規則の内容によって大きく異なるため、事前に見積もりをとることが重要です。また、追加費用の可能性や修正対応の有無も確認しておくと安心です。
社労士などの専門家への依頼は、法的に適合した就業規則を効率的に作成できるというメリットがあります。また、自社で作成する場合に比べ、大幅な時間と労力を削減できる点も魅力的です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
就業規則の作成・見直しでの際の注意点
就業規則の作成・見直しにおいては、次の点に十分注意する必要があります。
- 各種法令を遵守する
- 従業員への公平性を確保する
- 時代や自社に合った内容にする
これらの注意点を踏まえずに就業規則の作成・見直しを進めると、就業規則が適切に機能しないばかりか、法律違反のリスクが生じる可能性があります。
就業規則の変更について、こちらの記事で解説しています。
各種法令を遵守する
法令に違反するような就業規則では、企業組織としての信頼を失いかねません。後に大きなトラブルに発展する可能性がある他、就業規則そのものが無効とみなされるケースもあるため注意が必要です。
就業規則の作成・見直しにおいては、最新の法改正を正確に把握することが欠かせません。法改正を見逃したまま進めると、法令違反につながる就業規則を作ってしまうことになりかねません。例えば、2019年からは年5日の有給休暇取得が企業に義務付けられました。また、残業時間の上限規制や最低賃金の変更なども行われています。2019年以前の就業規則にはこれらの内容は含まれていないため、定期的な見直しとアップデートが必要です。
法令遵守の判断は専門的で難しい場合もあります。そのため、自分で就業規則の作成・見直しを進めるのが不安困難な場合、社労士などの専門家に相談しつつ取り組みましょう。
従業員への公平性を確保する
就業規則を作成する際に重要なポイントの1つが公平性です。特定の従業員が不利益を被るような規則を盛り込むのは避けましょう。例えば、女性よりも男性従業員の給与をあからさまに高く設定する、派遣社員よりも正規従業員を手厚く優遇するなど、性別や雇用形態による待遇差にも注意が必要です。社会的信頼の失墜や採用力の低下、従業員の離職などにつながるリスクもあります。公平な就業規則を作成し、健全な職場環境を維持しましょう。
時代や自社に合った内容にする
働き方は時代によって変化します。近年では、コロナ禍や働き方改革などの影響もあり、テレワークやフレックスタイム制の導入に踏み切る企業も増えました。ただし、これらの働き方が適しているかどうかは、企業の業務形態や組織の特性によるため、単に働き方の変化に対応するだけでなく、組織全体や業務プロセスの見直しも重要です。就業規則の見直しに際しては、企業の実態に即した柔軟な対応が求められます。
また、働き方だけでなく、時代によって価値観や考え方なども変わります。就業規則が時代や自社の実態に即していない場合、適切に運用できないことになるため注意しましょう。なお、就業規則を見直す際には、企業側だけで進めるのではなく労使間で十分検討することが重要です。
従業員への周知を徹底する
就業規則を作成・見直しの際は、労働基準監督署への届出だけでなく、従業員への周知を徹底することが必要です。従業員の働き方や待遇などに大きく影響を及ぼす規則であるため、全従業員への徹底した周知が求められます。「就業規則を変更した」とただ伝えるだけでは不十分です。説明会を実施するなどして、具体的な変更箇所やその意図を明確に説明することが求められます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
就業規則の作成でのポイント
就業規則を作成する際には、以下のポイントを重視しましょう。
- 企業の価値観を共有する
- ルールを定めトラブルを事前に防止する
- 従業員の労働条件を明示する
これにより、従業員との信頼関係を築き、企業運営をより円滑に進めることが可能です。
企業の価値観を共有する
就業規則に企業の価値観を示すことで、従業員全員と目指すべき方向を共有できます。企業理念や目標は、事業を行う上での軸となる重要な指針です。法的な記載義務はありませんが、就業規則に明記して、従業員に企業の思いを伝えることが肝心です。企業が目指しているゴールやミッションなどを就業規則へ盛り込み、全従業員で共有することで、一体感が生まれます。全従業員が同じ目標、ゴールに向かって前進できれば、組織全体の生産性が高まり利益の最大化にもつながります。
ルールを定めトラブルを事前に防止する
就業規則は、企業と従業員双方が守るべきルールを示すものです。ルールが定まっていないと、従業員側と企業側で意見が折り合わずにトラブルにつながる可能性があります。例えば、従業員が副業をしたいと申し出た際、就業規則に副業のルールが明記されていれば、それに則った対応が可能です。このように、さまざまな事態を想定し、あらかじめ対処法を明記しておけば、労使双方のトラブルを回避しスムーズな対応が行えます。
また、ルールを定める際、あいまいな表現を避けることも重要です。記載内容があいまいだと、読み手によって解釈が異なる場合があり、就業規則の適切な運用ができません。明確で具体的なルールを定めることで、トラブルを事前に防止でき、企業の信頼性を高められます。
従業員の労働条件を明示する
就業規則には、従業員の労働条件や賃金規定について明記する必要があります。可視化することで、従業員は自身の労働環境に対する理解が深まり、安心して働けるようになります。
ただし、就業規則は一般的なルールを示すものであり、個別の労働条件や雇用契約は従業員ごとに異なることがあります。企業にとっても、昇給ルールや賃金計算方法を明確に定めておくことで、公平性を保ちながら一定のルールに基づく運用ができます。このように、労働条件を明示することで、労使関係を円滑にし、組織の安定的な運営に寄与します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
就業規則は時代や自社の実態に合わせて作成しよう
労働条件や職場でのルールを明記した就業規則は、従業員の働き方や賃金などに大きな影響を与える重要な規則です。守るべきルールや労働条件などを明確に定めることで、労使間におけるトラブルを回避でき、従業員も安心して働けます。
就業規則を適切に運用するために、時代や自社の状況に合わせた内容の作成・見直しが必要です。本記事で解説したポイントや注意点を参考に、就業規則の作成・見直しに取り組みましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。