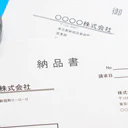信書とは?該当する・しない文書、送り方をわかりやすく紹介
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
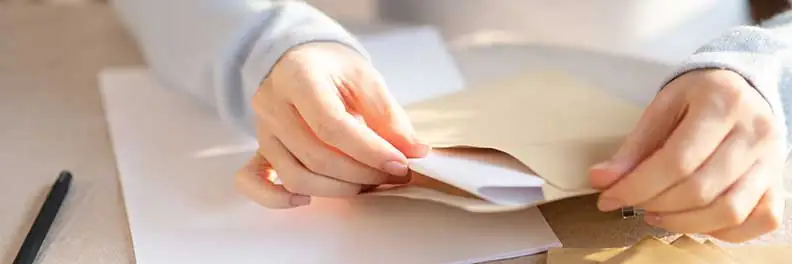
業務上、請求書やダイレクトメール、カタログなどさまざまな書類をやり取りする場面があります。その中で、この書類は信書に該当するのか、どのように送付すべきかについて迷うことがあるかもしれません。信書を規定どおりに送付しなければ法律違反となり、罰則を受ける可能性があるだけでなく、送り先の方からの信用を損ねる場合があるため注意が必要です。
本記事では、信書とはどのような文書なのかをわかりやすく解説し、信書に該当する文書と該当しない文書、正しい送り方などを紹介します。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
信書とは、特定の受取人に差出人の意思を表示したり事実を通知したりする文書のこと
信書は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法および信書便法に規定されており、正しい方法で送らなければなりません。そのために、まずは「特定の受取人」「意思を表示し、又は事実を通知する」「文書」とはそれぞれ何を意味するか、正しく理解する必要があります。
- ・「特定の受取人」
- 郵便法によれば、特定の受取人は「差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者」です。特定の受取人には個人の他、法人、組合、団体なども含まれます。文書中の「◯◯様」や「◯◯社御中」などの記載が、特定の受取人です。
- ・「意思を表示し、又は事実を通知する」
- 総務省のガイドラインでは、「意思を表示し、又は事実を通知する」を「差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えること」と説明しています。例えば、「当社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます」という文章は、意思の表示に当たります。また、「◯◯さまが当社サービスに入会されて1年が経ちました」という文章は、事実の通知です。
- ・「文書」
- 文書は、人の知覚で認識可能な文字や記号、符号などが記載された紙または有体物のことです。USBやCD、DVDなどの電子データは、内容を人の知覚で直接認識できないため、文書に含まれません。
引用:総務省「信書のガイドライン」
引用:e-gov法令検索「郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)」第4条2項
信書と手紙の違い
手紙は信書の1つです。信書には広い意味があり、手紙以外にもさまざまな文書が信書に当たります。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
信書に該当する文書
信書に該当する文書には、次のようなものがあります。
- 書状
- 請求書の類
納品書、領収書、見積書、願書、申請書など - 会議招集通知の類
結婚式の招待状、業務報告文書など - 許可証の類
免許証、表彰状、認定書など - 証明書の類
納税証明書、戸籍謄本、住民票の写しなど - ダイレクトメール(一部)
文書自体に受取人が記載されているダイレクトメールは、信書に該当します。また、商品購入などの利用関係や契約関係など、特定の受取人に差し出すことが明らかな文言が記載されているダイレクトメールも信書です。
参照:総務省「信書のガイドライン」
納品書が信書に該当するかどうかについては、以下の記事を参考にしてください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
信書に該当しない文書
信書に該当しない文書には、次のようなものがあります。
- 書類の類
新聞、雑誌、会報、カレンダー、ポスターなど - カタログ
- 小切手の類
手形、株券など - プリペイドカードの類
商品券、図書券など - 乗車券の類
航空券、定期券、入場券など - クレジットカードの類
キャッシュカード、ローンカードなど - 会員カードの類
入会証、ポイントカードなど - ダイレクトメール(一部)
新聞折り込みや街頭での配布、店頭での配布などを想定して作られたチラシのようなダイレクトメールは、信書に該当しません。 - その他
説明書の類(取扱説明書、仕様書、約款)、求人票、名刺。振込用紙など
参照:総務省「信書のガイドライン」
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
信書の送り方
信書は送付方法が郵便法で定められています。規定以外の方法で信書を送ると、懲役または罰金が科せられる可能性もあるため、注意が必要です。
参照:e-gov法令検索「郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)」第76条
郵便で送付する
信書は郵便で送るのが一般的です。信書を送付できる郵便サービスは、定形郵便と定形外郵便、レターパック、スマートレターとなります。
- ・定形郵便・定形外郵便
- 定形郵便は、最大縦23.5cm、横12cm、厚さ1cm、重さ50gまでなら送付可能で、料金は110円です。
定形外郵便には規格内と規格外があり、規格内の場合、縦34cm、横25cm、厚さ3cm、重さ1kgがサイズの上限です。規格外の場合、長辺60cm、3辺の合計90cm、重さ4kgが上限です。定形外の料金は重さによって細かく決められており、規格内は140円~750円、規格外は260円~1,750円です。参照:日本郵便株式会社「第一種郵便物 手紙
」
- ・レターパック
- レターパックは、A4サイズ、重さ4kgまでの荷物を送れるサービスです。レターパックプラスとレターパックライトがあり、配達方法が異なります。レターパックプラスは対面での配達となり、受領印または署名が必要で、料金は600円です。後者は郵便受けへの配達となり、厚さ3cmまでのサイズ規定があり、料金は430円です。
レターパックには追跡サービスがあり、土・日・祝日を含め毎日配達している点がメリットです。なお、送付には郵便局やコンビニエンスストアで購入できる、専用の封筒を利用しなければなりません。発送はポスト投函または郵便窓口から行います。参照:日本郵便株式会社「レターパック
」
- ・スマートレター
- スマートレターはA5サイズ、厚さ2cmまで、重さ1kgまで全国一律料金で送付できるサービスです。郵便局やコンビニエンスストアで専用の封筒を購入し、信書などを封入してポスト投函するか、郵便窓口から発送します。土・日・祝日の配達や追跡サービスはなく、郵便受けに配達されます。料金は210円です。
参照:日本郵便株式会社「スマートレター
」
信書を送付できない郵便サービス
日本郵便のサービスのうち、ゆうパックとゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは信書を送れません。送付物が信書に当たるかわからない場合、見本を持って郵便局で相談しましょう。
もし、ゆうメールやゆうパケットなどで送付しようとしていたものが、信書に当たると判明した場合、宛名などの表記方法を変更したり、箱などを入れ替えたりする必要が生じることがあります。大量の送付物がある場合、早めに確認しておかないと予定どおりに発送できなくなるおそれもあるため、注意が必要です。
信書便事業者を使って送る
日本郵便のサービス以外にも、総務省の認可を受けている信書便事業者を利用して信書を送ることができます。総務省の認可を受けている信書便事業者は、2024年11月25日時点で618社です。認可を受けている信書便事業者の中には、佐川急便や日本通運などがあります。なお、利用可能地域やサービス内容がそれぞれ異なるため、利用の際は確認が必要です。
参照:総務省「信書便事業者一覧(令和6年11月25日現在)」
参照:総務省「特定信書便事業者 一覧表」
佐川急便の信書を送れるサービスは「飛脚特定信書便」です。飛脚特定信書便は、長さ、幅、厚さの合計160cm以内、重量30kg以内の荷物を送れます。また、「飛脚特定信書航空便」を利用すれば、北海道から沖縄まで信書を翌日に届けることも可能です。
参照:佐川急便「飛脚特定信書便」
日本通運の信書送付サービスは「ビーエスピー」と呼ばれています。長さ、幅、厚さの合計170cm以内、重さ30kgまでの荷物に対応しており、WEBサイトから荷物の追跡も可能です。
参照:日本通運「特定信書便輸送」
納品物と一緒に宅配便で送る
信書であっても、封をしていない状態の送り状または添え状ならば、送付物に同梱して宅配便で送っても問題ありません。例えば、あいさつ状や納品書、請求書などは無封なら同封できます。これは郵便法第4条に、貨物に添付する無封の添え状または送り状は認める旨の記載があることが根拠となっています。
参照:e-gov法令検索「郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)」第4条3項
納品書や請求書を送付物と一緒に宅配便で送る際は、「納品書(請求書)在中」と記載した封筒に入れるのが一般的です。封筒は封をせず、箱の内側または外側に貼り付けると受取人が見つけやすくなります。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
信書は発送方法に注意しよう
手紙や納品書、領収書、見積書などさまざまなものが信書に当たりますが、中には信書かどうかわかりにくいものもあります。特にダイレクトメールは、特定の受取人に差し出すことがわかる文言があれば信書に当たるため注意が必要です。
信書は日本郵便の定形郵便と定形外郵便、レターパック、スマートレターで送れます。他には、総務省の認可を受けている信書便事業者を利用して送ることも可能です。また、封をしていない送り状や添え状なら、信書に当たる請求書なども送付物に同梱して宅配便で送れます。本記事の内容を参考にして、信書を適切に送付しましょう。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。