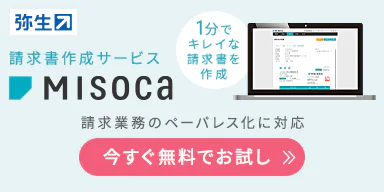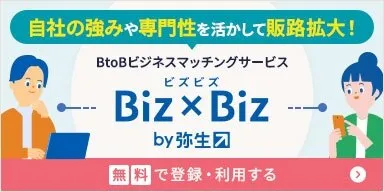諸経費とは?目安となる相場や含まれる内訳、計算方法を簡単に解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新

諸経費は、工事などにかかる見積書に欠かせない項目です。諸経費には、現場で直接発生する「現場経費」と会社全体の運営にかかわる「一般管理費」の2種類があり、それぞれ異なる役割があります。本記事では、諸経費の種類や内訳、経費との違い、正確な見積書作成のポイントを解説します。見積書に諸経費をどう記載すべきか悩んでいる担当者の参考にしてください。
諸経費とは?現場経費と一般管理費の2種類がある
工事の見積書における諸経費とは、直接工事費以外に発生する費用を指す重要な項目です。諸経費は、工事現場で直接発生する「現場経費」と、企業全体の運営にかかわる「一般管理費」に大別され、役割が異なります。以下では、それぞれの概要と具体的な内訳について詳しく解説します。
諸経費に含まれる現場経費とは
現場経費は、建築工事などの作業現場で発生する費用です。作業員の賃金、作業着や保護具の費用、現場で使用する事務用品の購入費などが該当します。加えて、作業用発電機などの機器レンタル費、作業で消耗した道具を交換する際に発生する機材損料なども現場経費の一部です。さらに、作業現場で使う携帯電話の通信費、移動にかかるガソリン代や駐車料などの交通費、不測の事故に備えた保険の保険料など、現場の業務に関連して発生するさまざまな費用が該当します。
諸経費に含まれる一般管理費とは
一般管理費には、会社全体の運営におけるさまざまな費用が該当します。主な費用には、本社や支社のオフィスの賃料や、従業員の賃金、事務用品費、電話代・通信代・交通費などの通信交通費、電気・水道・ガスなどの水道光熱費などです。さらに、会社が保有する不動産や車両などにかかる固定資産税や自動車税などの租税公課、新規顧客獲得を目的とした広告宣伝費も一般管理費の一部です。
諸経費と経費の違い
諸経費に似た言葉に「経費」があります。諸経費とは、工事などのプロジェクト全体を完遂するために必要となる費用であり、見積書で示される直接工事費以外の費用です。
その一方で、経費とは、事業活動全般に必要な費用で、「経営費用」を略したものです。経費には、事業活動やプロジェクトに関連して発生するさまざまな費用が含まれます。例えば、従業員の出張にかかる交通費や宿泊費、取引先との会食などにかかる交際費、会社の備品購入費などが該当します。
また、従業員が交通費や備品購入費などの経費を一時的に立て替えた場合には、後からその金額を精算しなければなりません。通常、会社の収支の流れを適切に管理するため、経費精算は毎月月末までに行います。
「経費で落とす」の経費とは
事業活動で発生した費用は、損金として税務処理できる経費に分類して計上するため、よく「経費で落とす」という表現を使用します。損金とは、会社の法人税を計算する際に収益から差し引いて計算できる費用のことです。法人税の計算は、会社の収益(益金)から損金を差し引いた所得金額を基にするため、損金の金額が多いほど所得金額が低くなり、法人税額も抑えられます。経費計上した費用は、基本的に税制上の損金としての処理が可能です。ただし、すべての経費が損金として認められるわけではなく、経費で落とせないものもあります。
経費として計上できないのは、事業活動とは無関係の支出です。例えば、従業員が仕事と関係のない人との飲食費や、個人的に使用する道具購入費などは、会社の経費には認められません。また、事務用品などを大量に購入した場合は、経費計上が可能でも、使用分のみが損金として計上でき、残りは資産として扱われる場合があります。さらに、役員報酬のうち事前届出がない賞与など、一定額を超える交際費、寄付金、法人税、法人住民税、経営者個人の税金などは、損金に計上できない損金不算入の経費として処理しなければなりません。
このように、損金と損金不算入の経費は分けて考えることが大切です。見積書や請求書に記載する諸経費も、必要に応じて違いがわかるように記載する必要があります。次に、あいまいになりがちな諸経費について解説していきます。
スムーズな取引のために諸経費は見積書に正しく記載する
見積書に記載する諸経費は、業界によってそれぞれ項目が異なり、かかる金額にも幅があります。諸経費を記載する場合、顧客に納得してもらうために、適切な項目と金額設定が重要です。
諸経費を記載すべき項目は業界によって違う
諸経費の内訳の基本的な項目には、材料費や、労務費、外注費などがあります。見積書に各内訳を明確に記載すると、諸経費のイメージがしやすくなり、顧客に不信感を持たれにくくなります。業界や取引内容によって内訳項目が異なるため、それぞれに応じた項目を選定することが重要です。
例えば、建設工事の見積書の場合、「作業員の労務管理費」「作業車両のガソリン代」「事務用品代」「事務所の家賃」などを諸経費として書き込みます。不動産販売業の見積書の場合、「仲介手数料」「住宅ローンの借入手数料」「司法書士報酬」「登記費用」「火災・地震保険料」などです。清掃業の見積書の場合、「洗剤代」「掃除用具代」「ごみ袋代」などを記載します。電気工事業の見積書の場合、「電線代」「コネクタ代」「絶縁材」などが主な項目です。
諸経費の相場は工事全体にかかる費用の5~20%以内を意識する
諸経費には相場があるため、相場を意識して金額を設定することが重要です。一般的に工事全体にかかる費用の5~10%程度が目安ですが、会社の規模の大きさに比例して諸経費も増加し、20%程度になることもあります。また、諸経費の金額は、工事の規模や種類、地域差、環境保護への取り組みなども金額に影響するため、これらを踏まえた設定が大切です。特に大規模な工事や都市部での作業では、諸経費が高くなる傾向があります。
諸経費を削りすぎるとクオリティの低下につながる
諸経費は詳しい内容が見えにくいため、顧客から高額だと思われがちです。しかし、諸経費は品質維持や工事の安全性に必要不可欠な費用です。諸経費を削りすぎると作業中のトラブルやクオリティの低下が起きやすくなり、結果的に顧客満足度が下がることもあるため、適切な金額設定が必要です。
諸経費の内訳がわかりやすい記載例を参考にする
見積書には明確な書式が定められていないため、内訳が記載されていない見積書もあります。しかし、内訳が不明な場合、顧客が疑問を抱きやすく、質問への回答が不十分だと信頼を損ねる可能性があります。そのため、見積書に諸経費の内訳を記載しない場合でも、内訳を詳細に把握しておくことが必要です。
見積書に諸経費の内訳を記載することで、顧客が詳細まで確認できるため、納得を得やすいというメリットがあります。そのため、諸経費は内訳がわかる書き方で作成するのがおすすめです。見積書作成の際に、わかりやすい記載例を参考にすることで、顧客が理解しやすい見積書の作成が可能です。諸経費として書き出される基本的な項目には、「人件費」「保険料」「税金」「手数料」などがあります。
諸経費の2つの計算方法
諸経費の計算方法には、2種類あります。1つは、直接工事費の総額を基に一定の割合で計算する方法、もう1つは内訳を明細として記載する方法です。以下では、それぞれの方法について詳しく解説します。
1.一定の割合で設定する
業界によっては、直接工事費に一定の割合を掛けて諸経費を設定する方法が用いられています。この場合、諸経費は直接工事費の5%〜20%を目安に、工事の種類や会社の規模、地域性などを考慮して設定します。例えば、直接工事費が10万円、諸経費割合を10%と設定した場合、諸経費は1万円(10万円×10%)です。一定の割合で設定する際、見積書に諸経費の内訳は記載しないことが一般的です。しかし、顧客から内訳について質問があった場合に備えて、回答できるよう準備しておくことが重要です。
2.内訳に明細を記載する
諸経費の内訳を明記する方法では、諸経費の項目を詳細に分け、それぞれの金額を積み上げて合計額を算出します。内訳には労務費、交通費、事務用品費などが含まれ、それぞれの費用を過去の実績や基準額を基に計算することが重要です。これにより、各費用を適切に算出し、精度の高い金額設定が可能になります。特に内訳を重視する顧客には、透明性の高い見積書を提示できるメリットがあり、諸経費の内訳や計算の根拠についても説明しやすい計算方法です。
諸経費は相場と内訳の把握が大切
諸経費には、作業現場で発生する現場経費と、会社の事業活動全般にかかる一般管理費があります。見積書に諸経費を記載する際は、顧客の納得を得るためにも相場に見合った金額を設定し、内訳をきちんと把握しておくことが大切です。
見積書を適切に作成するには、専用ツールの導入がおすすめです。弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」は、見積書・納品書・請求書・領収書を簡単に作成でき、発行・送付の自動化にも対応しているツールです。電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しているため、さまざまな書類の作成・管理業務の効率化が図れます。ぜひ導入を検討してみてください。
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。