傷病手当金は確定申告が必要?退職後のケースや医療費控除との関係
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新
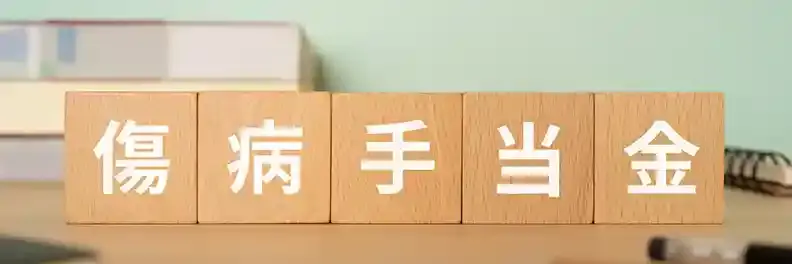
会社などに雇用されて働いている方がケガや病気で働けなくなると、健康保険組合から傷病手当金が支給されます。傷病手当金は給与ではないため、源泉徴収票などに記載されることはありません。
傷病手当金を受け取った場合、基本的に確定申告の必要はありませんが、状況によっては確定申告が必要になる場合があります。
ここでは、傷病手当金を受け取っている方や、これから受け取る方に向けて、制度の内容や確定申告の要否、退職後に確定申告が必要となるケース、医療費控除との関係などについて解説します。
なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしております。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。
ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

傷病手当金とは、ケガや病気で働けない会社員などへの給付金
傷病手当金は、ケガや病気で働けなくなった会社員や公務員などに対して、健康保険組合などから支払われる給付金です。健康保険組合などに加入している被保険者が、同じケガや病気を理由に4日以上休業したときに受け取れます。ケガや病気の種類に制限はなく、入院か自宅療養かも問いません。うつ病のような精神疾患も対象です。
ただし、対象者は会社員などが加入する健康保険組合の被保険者のみです。国民健康保険に傷病手当金の制度はありません。また、健康保険組合の被保険者の扶養になっている家族も対象外です。
例えば、配偶者の扶養内でパートをしていて健康保険組合などに加入していない方が、ケガや病気で働けなくなったとしても、傷病手当金の対象にはなりません。
また、傷病手当金の対象者に関する保険加入期間の定めはなく、入社直後であっても、健康保険組合などに加入していれば対象になります。
なお、休業中に傷病手当金の支給を受けている場合でも、健康保険料と厚生年金保険料は免除になりません。支払方法については、勤務先に振り込みなどで別途支払う方法や、一時的に勤務先が立て替えて復帰後に支払う方法などが考えられます。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
傷病手当金の支給期間と支給額
傷病手当金の支給期間は、支給開始から通算1年6か月です。職場に復帰後、再度同じケガや病気が原因で休職した場合でも、合計の休業期間が1年6か月に到達するまでは手当金が支給されます。
支給額は、以下の計算によって算出します。
傷病手当金の支給額の計算式
1日当たりの傷病手当金支給額=支給日前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
大まかに、休業前の給与額の3分の2程度の金額と考えていいでしょう。休業前の社会保険加入期間が12か月に満たないときは、「加入してからの平均額」と「健康保険組合の被保険者全体の平均額」のいずれか低い方が標準報酬月額の基準となります。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
傷病手当金の確定申告は原則として不要
傷病手当金は非課税であるため、傷病手当金の収入があったことについて確定申告を行う必要はありません。所得税を源泉徴収されることもなく、支給額をそのまま受け取れます。傷病手当金は、住民税も非課税です。
ただし、傷病手当金を受け取ったこと以外の理由で、確定申告をした方がいい場合もあります。詳しくは次の項目で解説します。
確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
傷病手当金を受け取った場合に確定申告が必要なケース
傷病手当金についての確定申告は不要ですが、それ以外に確定申告が必要な理由がある方は申告をしましょう。傷病手当金を受け取った方が確定申告を行う主なケースとしては、医療費控除の適用を受けたい場合と、傷病手当金の申請後に退職した場合があげられます。
医療費控除の適用を受けたい場合
傷病手当金を受け取れるのはケガまたは病気で療養中の方であるため、確定申告をすれば医療費控除の適用を受けられる可能性があります。医療費控除は年末調整では申告できないため、適用を受けたい場合は確定申告が必要です。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までにかかった医療費が10万円を超える方(総所得金額等が200万円以上の場合)が利用できる所得控除制度を指します。医療費とは、病院などに診療した際に支払った診療費や調剤された医薬品、薬局で購入した医薬品の代金などです。
総所得金額等が200万円以下の場合は、10万円ではなく、総所得金額等の5%が基準となります。この基準額を超えた金額を、所得税の課税対象となる所得金額から控除できるため、節税につながります。
ケガや病気を理由に民間の生命保険会社から保険金などを受け取ったケースでは、受け取った金額を控除する医療費から差し引かなければなりません。ただし、傷病手当金や出産手当金のような「働けない間の生活費」として支払われる金額については、差し引くことは不要です。
なお、ドラッグストアなどで特定の医薬品を購入した場合、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例を利用できる可能性がありますが、セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか一方しか利用できないため、有利な方を選択してください。
医療費控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
傷病手当金の申請後に退職して年末調整を受けない場合
傷病手当金を受け取った後または受け取っている間に退職して、年末調整を受けていない方は、確定申告を検討しましょう。所得税の還付を受けられる可能性があります。
会社員は、給与から概算の所得税額を源泉徴収されていて、源泉徴収時には個人ごとの状況に応じて適用できる所得控除などが考慮されていません。そのため、源泉徴収された税額の方が、所得控除などを適用した正しい所得税額よりも高額になっていて、所得税の納めすぎになっているケースがあります。
通常、勤務先で行う年末調整でその差額を精算しますが、退職した場合は、払いすぎた所得税の還付を受けるために確定申告が必要です。また、確定申告をすることで住民税の申告も不要になります。
ただし、退職した年に再就職した方は、転職先で前職の状況を踏まえて年末調整をしてもらえるため、確定申告は不要です。前職の源泉徴収票を現在の勤務先に提出してください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
確定申告のやり方
確定申告は、以下の4つのステップで進めます。確定申告期間は、例年2月16日から3月15日まで(土日祝日に重なった場合は翌平日)ですが、納税が発生せず還付を受けるために申告する場合は、申告したい所得があった年の翌年1月1日から5年間いつでも申告できます。間に合うように準備を進めましょう。
確定申告の流れ
-
1.必要書類を用意する
-
2.確定申告書類を作成する
-
3.確定申告書と必要な添付書類を提出する
-
4.税金の還付を受ける
必要書類は、申告内容によって変わります。傷病手当金を受け取っていて医療費控除の適用を受ける方であれば、主に以下のような書類が必要です。
医療費控除の適用を受ける場合の主な必要書類
- 確定申告書
- 申告する年の給与所得の源泉徴収票(勤務先から交付)
- 医療費控除の明細書(領収書の情報を基にExcelなどで作成)
- マイナンバーカード、または、本人確認書類(マイナンバーがわかる書類と身元確認確認書類)
なお、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用するのであれば、パソコンやスマートフォン上で確定申告書を作成できるため、申告書の書式の用意は不要です。また、源泉徴収票は、添付書類として提出する必要はありませんが、申告書に収入金額や所得金額などを記載する際に参考にします。
確定申告のやり方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
傷病手当金の支給要件
傷病手当金は、勤務先の健康保険に加入している人のうち、以下の4つの支給要件をすべて満たす人が受け取れます。ケガや病気で仕事を休んでいたとしても、満たしていない支給要件があると受け取れません。
傷病手当金の支給要件
- 仕事とは無関係なケガや病気の療養のために休業すること
- 今まで従事していた仕事ができないこと
- 連続して3日間仕事を休んでから、4日目以降に仕事ができなかった日があること(3日連続の休業後に1日出勤してから休んだ場合などを含む)
- 休んだ期間に給与が支払われないこと
- ※全国健康保険協会「傷病手当金について | よくあるご質問
」
仕事を原因としたケガや病気で休業する場合は、労働保険から休業補償給付が支給されるため、健康保険の傷病手当金は支給されません。また、ケガや病気があっても、今まで従事していた仕事ができる状態の方は対象から除外されています。就業不能かどうかは、医師の意見を基に健康保険組合などが判断します。
休業期間中に、有給休暇などで休業日分の給与が満額支払われていた場合も、傷病手当金の対象外です。給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金が減額されます。
なお、傷病手当金の対象者は原則として勤務先の健康保険に加入している労働者です。しかし、在職中に傷病手当金を受け取っていた方がそのまま退職した場合、継続して手当を受け取れる可能性があります。退職しても傷病手当金を受け取るための主な要件としては、以下の3点があげられます。
資格喪失後の継続支給の要件
- 資格を喪失した日の前日までに、1年以上の継続した被保険者期間(任意継続の期間を除く)があること
- 退職後も傷病手当金を受ける条件を満たしていること
- 退職日も休んでいること
- ※全国健康保険協会「傷病手当金について | よくあるご質問
」
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
傷病手当金と扶養との関係
ケガや病気で休業した場合、収入が下がることから、配偶者などの扶養に入れる可能性があります。扶養には、以下のように扶養控除・配偶者控除といった税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。傷病手当金の収入が、扶養の判定の際に被扶養者の所得や収入に含まれるかどうかはそれぞれで異なるため、正しく判定できるようにしておきましょう。
扶養控除・配偶者控除との関係
傷病手当金は、扶養控除や配偶者控除の対象になるかどうかを判断する際の所得金額には含まれません。
所得金額が一定額を下回っていると、親などの扶養に入る場合は扶養控除、配偶者の扶養に入る場合は配偶者控除の適用を受けられる可能性があります。
どちらの制度も、被扶養者の所得金額が58万円(2024年分までは48万円)以下、給与所得のみであれば年収123万円(2024年分までは103万円)以下の場合に適用できますが、傷病手当金は非課税であるため、この所得金額の計算には傷病手当金の金額を含めなくてもいいこととされています。
なお、配偶者控除については、所得金額が58万円(2024年分までは48万円)を超えていても、133万円以下であれば、配偶者特別控除という控除制度の利用が可能です。
扶養控除や配偶者控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
社会保険の扶養との関係
社会保険の扶養とは、健康保険や厚生年金における扶養制度のことですが、社会保険の扶養の判定では、傷病手当金も収入と見なされます。
社会保険の扶養では、年収130万円未満の場合に親や配偶者などの扶養に入ることができ、追加の保険料の負担がなくても保険給付を受けることが可能です。傷病手当金を受け取っていた場合、年収の判定には受け取った傷病手当金の金額も含まれるため、注意してください。
また、傷病手当金の受給期間中に扶養に入りたい場合は、受給額の日額に関する要件もあります。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
傷病手当金を受け取って所得税の還付が受けられそうなら、確定申告しよう
傷病手当金については、確定申告をする必要はありません。しかし、多額の治療費がかかったり、勤務先を退職して再就職していなかったりする場合は、確定申告をするのがおすすめです。還付金として払いすぎた税金が戻ってくるうえに、会社を辞めていた場合に必要な住民税の申告も不要になります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、パソコンやスマートフォンで確定申告をすることもできるため、うまく活用して効率的に申告書の作成を進めましょう。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。









