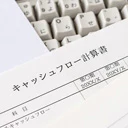長期借入金とは?短期借入金との違いや仕訳方法などを解説
更新

事業者にとって、資金の確保は事業を安定的に運営するうえで非常に重要な要素の1つです。資金を確保する手段としては、金融機関などからの借入を行うケースもあり、長期借入金とは、このうち決算日の翌日から起算して返済期限が1年を超える借入金を指します。
本記事では、長期借入金に該当するものや短期借入金との違い、借入金の種類、仕訳方法について解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
長期借入金とは、決算日の翌日から起算して返済期限が1年を超える借入金のこと
長期借入金とは、金融機関などからの融資のうち、決算日の翌日から起算して返済期限が1年を超える借入金を指します。主に設備投資など多額の資金が必要な場合に利用されますが、返済期間が長期にわたることから、企業にとっては返済負担が大きくなる傾向があります。また、貸主である金融機関等にとっても、返済までの期間が長いことで、景気変動や企業業績の悪化などによって貸倒れが発生するリスクが高いため、審査基準が厳しいケースが少なくありません。そのため、融資審査に際して担保の提供や、詳細な事業計画書の提出を求められることがあります。
借入金については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
長期借入金に該当するもの
長期借入金に該当する主な借入金は、以下のとおりです。
長期借入金に該当する借入金
- 銀行などの金融機関からの借入金
- 関係会社からの借入金
- 役員や従業員からの借入金
- 個人からの借入金
- 親会社などからの借入金
社内関係者からの借入については、決算関係書類において「関係会社長期借入金」「役員長期借入金」などと注記し、社外からの借入と区別する必要があります。
貸借対照表では「固定負債の部」に区分される
貸借対照表の「負債の部」には、将来支払うべき債務が表示されます。このうち、返済期限が決算日の翌日から起算して1年以内のものを「流動負債」、1年を超えるものを「固定負債」として区分するのが基本的なルールです。長期借入金は、返済期限が1年を超える借入金であることから、「固定負債の部」に区分されます。
流動負債と固定負債の区分には、「正常営業循環基準」と「1年基準(ワン・イヤー・ルール)」の2つの基準があります。正常営業循環基準とは、通常の事業活動に伴って発生する買掛金や支払手形といった負債のことです。貸借対照表を作成する際には、まず正常営業循環基準に則って流動負債を決定したのち、ここに含まれていないものを1年基準(ワン・イヤー・ルール)に基づいて区分するのが通常の手順となります。
貸借対照表については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
「1年以内返済予定長期借入金」の取り扱い
長期借入金は、分割返済が一般的です。決算日の翌日から起算して1年以内に返済期日が到来する金額は、「1年以内返済予定長期借入金」として、流動負債の部に計上されます。
帳簿上では、まず長期借入金の全額を記載し、貸借対照表の作成時に、1年以内の返済予定分を1年以内返済予定長期借入金として流動負債へ振り替えます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
長期借入金と短期借入金の違い
長期借入金は、決算日の翌日から起算して返済期限が1年を超える借入金を指すのに対して、短期借入金は返済期限が1年以内の借入金を指します。貸借対照表では、短期借入金は流動負債の部、長期借入金は固定負債の部に表示される点が大きな違いです。
短期借入金は、主に短期の資金繰りや特定のプロジェクトのための資金として借り入れるケースが多いことから、回収した売掛金がプロジェクトが生み出すキャッシュが返済の原資として用いられます。それに対して、長期借入金は、設備投資のための借入であれば、返済の原資は主に取得資産が生み出すキャッシュフローです。
また、短期借入金は比較的短い期間での返済が予定されており、貸し付ける金融機関にとっては資金の回収が早く、貸倒れのリスクが少ないと判断され、一般的に金利が低く設定される傾向があります。さらに、短期借入金の主な目的は運転資金の補填であるため、売掛金の範囲内で借入金を調整すれば赤字であっても融資を受けられるケースも少なくありません。それに対して、長期借入金の主な目的は設備投資であり、融資する金額も大きくなりやすいことから、担保の提供や綿密な事業計画の提出を求められる場合があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
借入金の種類
金融機関からの借入金には、「証書貸付」「手形貸付」「手形割引」「当座繰越」の4種類があります。借入金の各種類について、詳しく解説します。
証書貸付
証書貸付とは、金銭消費貸借契約書を取り交わし、その内容に基づいて借り入れを行う方法です。
一般的に借入金という場合、証書貸付のことを指します。金銭消費貸借契約書とは、借入条件や返済方法などを記載した契約書です。
一般的に、企業が借入をする際には、金融機関との間で金銭消費貸借契約が交わされ、これを基に借用証書が作成されます。金銭消費貸借契約書には借入額や利率のほか、返済期日、返済方法といった貸付の条件が記載されており、借手である企業は契約書の内容に沿って返済していくことになります。状況によっては、貸付金の担保として、抵当権などが設定されることもあります
手形貸付
手形貸付とは、借用証書の代わりに、企業が自ら振出人となって受取人を金融機関とする約束手形を振り出す方法のことです。
担保を設定せず、比較的短期間の資金を調達する際に用いられることが多い方法といえます。手形貸付の場合、手形に記載された金額から利息を差し引いた金額が企業に貸し付けられます。手形の満期が到来した際には、借入額を返済しなければなりません。
なお、紙の手形および小切手は2026年度末までに廃止される予定であり、代替手段として、電子記録債権を活用する方法があります。今後は、手形貸付による借入を行う場合、電子記録債権の活用が推奨されます。
紙の手形・小切手の廃止については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
手形割引
手形割引は、他者が振り出した期日到来前の手形を金融機関に買い取ってもらうことにより、融資を受ける方法です。
期日前の手形を買い取ってもらう際、額面金額から期日までの手数料や利息が差し引かれた金額を受け取ることになります。手形を現金化することで、早期に資金を調達できる一方、手形が不渡りになれば買い戻しの義務が生じます。買い戻しが発生した場合、資金繰りに悪影響を及ぼすリスクがある点に注意しましょう。
当座繰越
当座繰越は、金融機関と当座繰越契約を結び、当座預金残高を超える金額の小切手を発行することで、資金を借り入れる方法です。
あらかじめ設定された融資限度額までであれば、融資や返済が自由に行える一方で、金融機関による審査は厳しくなる場合があるため注意しましょう。また、当座繰越は、将来的に不測の事態が生じた際の運転資金を確保するために、あらかじめ契約するケースが多く見られます。
借入金については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
長期借入金の適正範囲を見る指標
前述のとおり、長期借入金は主に設備投資など比較的大規模な資金準備に際して活用されるケースが多いことから、借入金の金額も大きくなる傾向があります。借入金の金額が大きくなるほど返済の負担も重くなるため、借入の健全性を保つためには、長期借入金の適正範囲を見極める必要があります。その際、指標として用いられるのが「自己資本比率」「固定比率」「固定負債比率」の3つです。
自己資本比率
自己資本とは、企業が調達したり、稼いだりした資本のうち、返済の必要がない部分を指します。総資本(自己資本と負債を合わせた額)に占める自己資本の割合を示したものが「自己資本比率」です。これに対して、金融機関からの借入金や社債のように、株主以外から調達した資本のことを他人資本といいます。
自己資本比率が高い状態は、返済の必要がない資本の割合が大きいことを示しています。企業としての安定性や独立性が実現できている状態であり、倒産リスクが低い状態といえるでしょう。自己資本比率は、以下の計算式で求められます。
自己資本比率の計算方法
自己資本比率=自己資本÷総資本×100
自己資本と総資本のいずれも、貸借対照表から確認できます。よって、貸借対照表を参照すれば自己資本比率の算出が可能です。なお、望ましい自己資本比率の目安は業種によって異なります。企業ごとの状況を踏まえ、適切な自己資本比率を見極めることが大切です。
自己資本比率については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
固定比率
固定比率とは、自己資本に対する固定資産の割合を示す財務指標です。
企業が所有する資産は、固定資産と流動資産に大きく分けられます。このうち流動資産は現金化しやすいことから、企業の短期的な支払能力を見極める際に参照されるケースが少なくありません。それに対して、固定資産は土地・建物・設備のように、一般的には一度購入したら年単位で使用するものがほとんどです。したがって、固定資産はできる限り返済義務のない資金で工面するのが望ましいといえますが、業種によっては設備投資の資金を金融機関からの借入によって調達するケースも多く見られます。固定比率の計算式は以下のとおりです。
固定比率の計算方法
固定比率=固定資産÷自己資本
固定比率が100%未満であれば、固定資産をすべて自己資本で賄っていることを意味します。よって、長期的な支払能力が高い状態と判断できるでしょう。反対に、固定比率が100%を超える場合は、借入金などの他人資本によって固定資産が賄われていると判断できます。
固定比率については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
固定負債比率
固定負債とは、長期間支払義務が発生しない負債のことを指します。
具体的には、企業が抱えている負債のうち、決算日の翌日から起算して支払期限が1年以上のものです。負債のうち、固定負債が占める割合を固定負債比率といいます。固定負債比率の計算式は以下のとおりです。
固定負債比率の計算方法
固定負債比率=固定負債÷自己資本×100
借入金が事業規模に見合っていないと、返済が困難になる可能性があります。したがって、固定負債比率が高いようであれば、資本構造を見直していく必要があるでしょう。
固定負債については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
長期借入金の仕訳方法
長期借入金の仕訳方法を、ケース別に紹介します。長期借入金を返済する場合、諸経費が差し引かれて入金される場合、短期借入金に振り替える場合のそれぞれのケースにおける仕訳方法を確認しておきましょう。
長期借入金を返済した場合の仕訳例
設備の購入費用として1,000万円を借り入れ、企業の銀行口座に振り込まれた場合、以下のように仕訳を行います。
仕訳例:借入を行ったとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000,000円 | 長期借入金 | 10,000,000円 |
この借入金について、元金50万円と利息1万円が預金口座から引き落とされた際の仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:元金と利息が引き落とされたとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 500,000円 | 普通預金 | 510,000円 |
| 支払利息 | 10,000円 | ||
長期借入金として諸経費を差し引かれた金額が振り込まれた場合の仕訳例
金融機関から融資を受けた際に、利息、印紙税、信用保証料などが差し引かれて振り込まれる場合があります。金融機関から600万円を借り入れ、諸経費が差し引かれた金額が振り込まれた際の仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:諸経費が差し引かれた金額が振り込まれたとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 5,475,200円 | 長期借入金 | 6,000,000円 |
| 支払利息 | 4,000円 | ||
| 租税公課 | 10,000円 | ||
| 長期前払費用 | 500,000円 | ||
| 支払手数料 | 10,800円 | ||
この借入金について、返済期日が到来した50万円と利息5,000円が預金口座から引き落とされた場合、以下のように仕訳をします。
仕訳例:元金と利息が引き落とされたとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 500,000円 | 普通預金 | 505,000円 |
| 支払利息 | 5,000円 | ||
返済期限1年を切った長期借入金を短期借入金へと振り替える場合の仕訳例
返済期限が1年を切った長期借入金は、短期借入金へ振り替える必要があります。長期借入金300万円を短期借入金に振り替える際の仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:長期借入金を短期借入金に振り替えるとき
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 3,000,000円 | 短期借入金 | 3,000,000円 |
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
長期借入金の元本と利息を適切に管理しよう
長期借入金とは、返済期限が1年を超える借入金のことを指します。主に設備投資などの長期的な資金需要にあてられるため金額が大きく、返済期間も長くなる傾向があります。そのため、借入企業にとっては返済負担が重くなりやすいのが特徴です。また、貸主である金融機関等にとっても返済までの期間が長いことで、景気変動や企業業績の悪化といった要因により、貸倒れが発生するリスクが大きいとされています。こうした理由から、審査が厳しくなるケースも少なくありません。
長期借入金の仕訳については、借入時、返済時、短期借入金への振替時にそれぞれに応じた仕訳が求められます。長期借入金の元本と利息を適切に管理するためにも、会計ソフトを活用し、正確かつ効率的に仕訳処理を行うことが大切です。本記事で紹介したポイントや仕訳例を参考に、長期借入金を適切に管理していきましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。